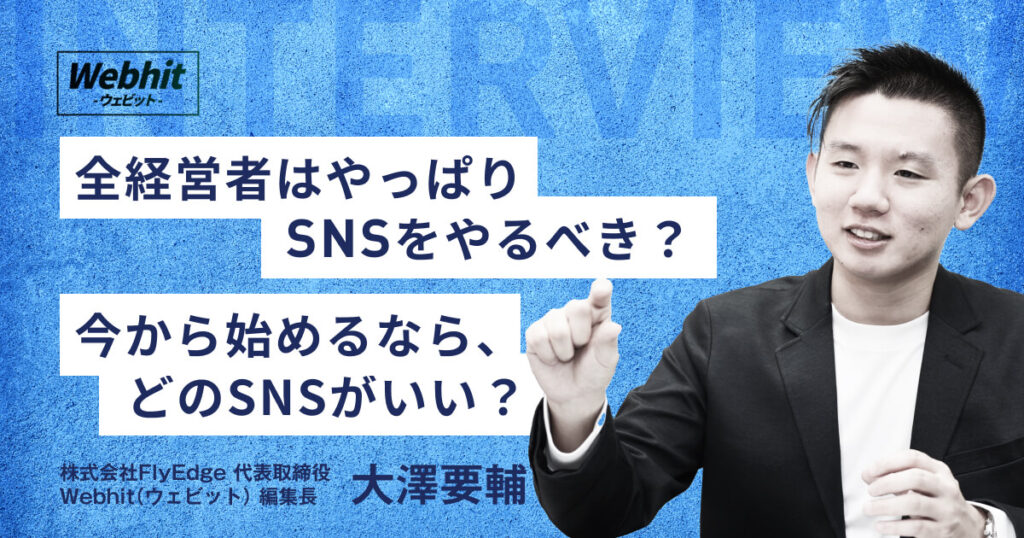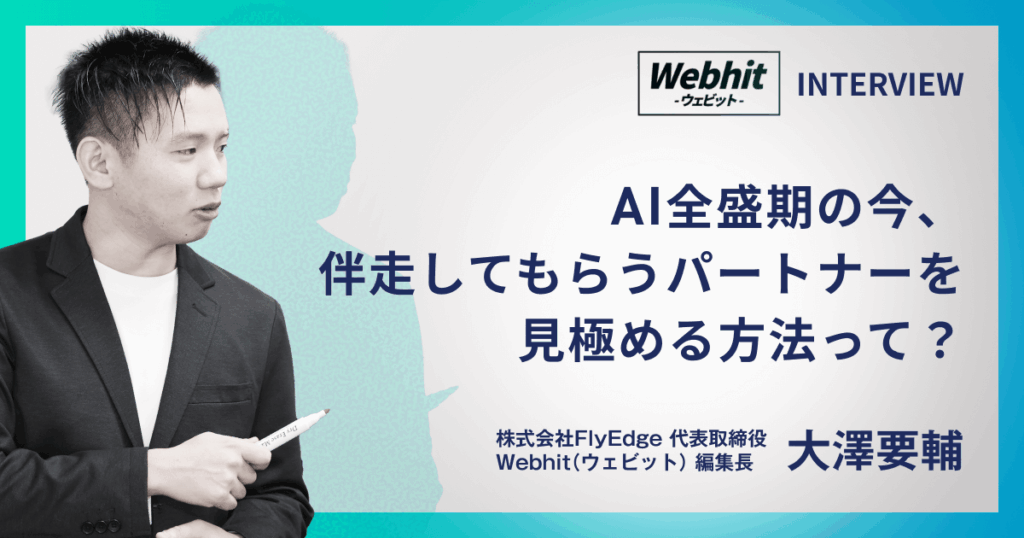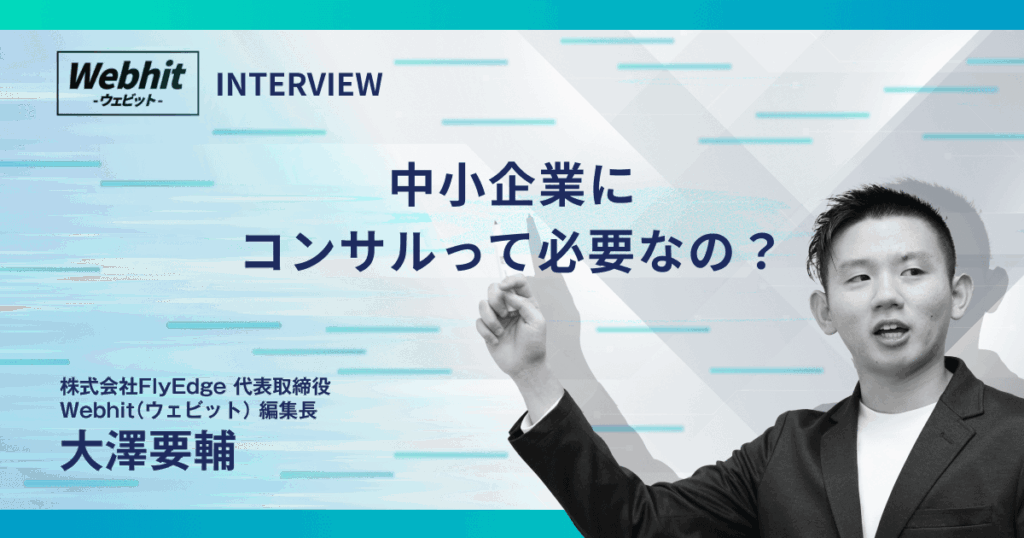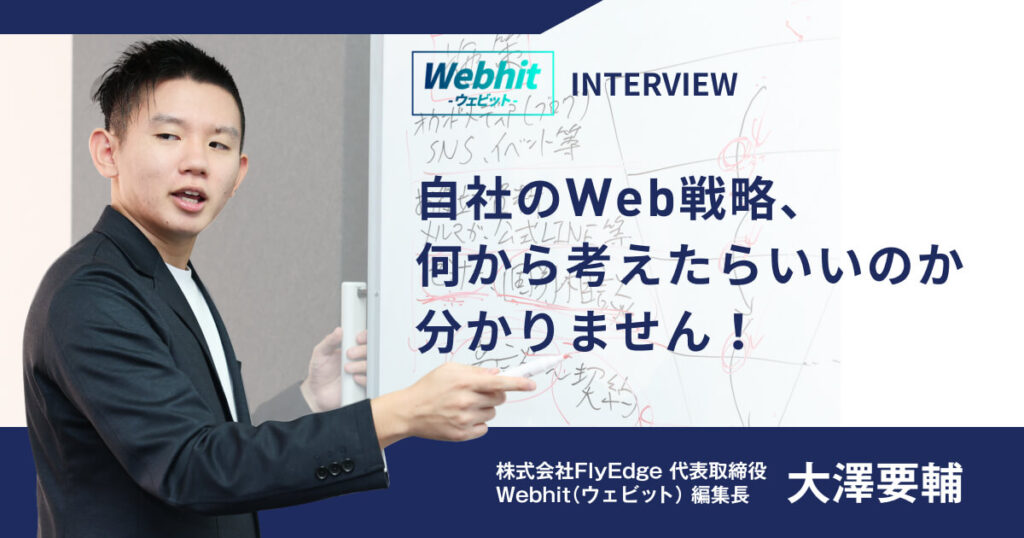Webhit 編集部
Webhit 編集部今回は「Meta広告のクリエイティブを改善するためのA/Bテストとは?」というテーマについてお話しいただきたいと思います。
よろしくお願いします。



はい、お願いします。



結論として、「Meta広告のクリエイティブを改善するためのA/Bテスト」とは何ですか?



はい、Meta広告のクリエイティブを改善するためのA/Bテストとは、
1つの要素ずつ変更する、かつ大量のテストを行うことです。



ありがとうございます。
非常に短くまとまって、中身が集約されているように感じました。
「1つの要素ずつ」とはどんな感じなのでしょうか?



例えばA、B、Cのパターンが全く違うものを作って、うまくいかなかった場合、次に、全く違うDパターンを作ってテストする。



これは多くの人がやっているメディア広告のクリエイティブ改善の例なのですが、A/Bテストにはなっておらず、全く意味がありません。
ちなみにこれはなぜだと思いますか?



なぜなんでしょう……?
A/Bテストというのはボタンの色だけ変えるなどしてテストしていくことだと思っていたのですが、そうではないのですか?



はい。Meta広告のクリエイティブになるため、画像についてです。



画像で言うと、少しわかりませんね……。



なぜ、これが意味がないかという話ですが、そもそもA、B、Cが色も
原稿も違う、使われてる写真や要素も全然違うクリエイティブであった場合、そのものがなぜ良くて、なぜ悪かったのかというファクトデータが取れないからです。



たしかに、1サンプルずつが集まったみたいな感じですよね?



はい。3つの物全てが別物です。



例えばAパターン、Bパターンと 全然違う物が2つあって、これを比較したとします。原稿も色も違うし、写真も違う。
その中でその仕様に訴求されてる言葉も違うという状態でやると、変数が多すぎるんです。
変数が多すぎるとファクトが取りづらくなります。



Aパターン、Bパターンの原稿だけ違って他の色や写真などの要素が
全部一緒な場合、比較してBの原稿の方が良かったというファクトが
取れます。



そもそもA/Bテストはなぜやるのかというと、基本的にうまくいく勝ちパターンを作りたいからです。勝ちパターンというのは、ある程度再現性がある勝ち筋を作りたいということです。



・どういう色が入っているといいのか
・どういう原稿でキーワードやフレーズが入っているといいのか
・写真 、イラスト、または全然別の物がいいのか、ない方がいいのか
とかですね。



特にどこを大きく訴求をすると、効果が出るのかがわからないと勝ち筋はわかりません。
つまり、これらがわからないようなA/Bテストには、あまり意味がないということです。
目的が達成できない状態になるため、1要素ずつやる必要があります。



なるほど。



はい。例えば原稿もそのベースの色も一緒で、写真の部分だけイラストに変える。または、写真もベースの色も一種だけど、原稿だけ違う。



原稿の中でも、この1行だけのターゲットコピーだけが違うといったように、1ヶ所だけ変えたテストをやるのが一番A/Bテストとしては結果が出やすいです。



AとBで原稿のターゲットコピーだけ切り替えたときに「Bのターゲットコピーの方がクリック率が高く、CPAも低かった」ということがわかれば、Bのターゲットコピーを使って、Cのクリエイティブを新しく作って、他の部分をまた変えて試せます。



つまり、AとBの戦いで勝ったBと、新しく作ったCの戦いをすることとなります。



このようにやっていくと、各変数となる要素が一つひとつ、これの方がいいというのが決まってきます。



それを積み重ねて掛け合わせていくと、より勝ち筋として再現性のあるクリエイティブを作ってくことが可能です。
A/Bテストの本来の目的に沿ったやり方ができるということになります。



この話が出るということは、3パターンを全然全く違うクリエイティブで出してる会社が多いということですか?



そうですね。そういう会社は結構多いと思います。



マーケティングの主体を握ってる制作側がこの話を理解してると、1要素だけ変えたものを作ってくれるケースもあります。
しかし、理解していないと「前のやつと似たような感じじゃん?」と言ってテストをしないこともあります。



似ていても入っているものによって全然効果が違うので、そこの要素は一つひとつ分解して、地道なテストを大量に回すというのが、結果的に一番効果が出るA/Bテストです。



ありがとうございます。今おっしゃっていたものを大量にやるという
ことでしたが、大量というのはどれぐらいなのでしょうか?



これについては、必要なだけですね。これもよく聞かれる質問ですね。「1週間に1回ぐらいクリエイティブを変えた方がいいんですか」とか「何日に1回ですか?」とか聞かれますが、予算がいくらであろうと、日数が経ってなかろうと効果が出ないものは止めます。



もちろん効果が出る、出ないという判断基準を作る必要はありますが、その判断基準において効果が出ないものは止めて、次のクリエイティブを入れます。



ここでメタ広告で効果改善ができないような会社は、ほとんどの場合「クリエイティブを新しく作るコストがかかるため嫌です」と言って
作らないんですね。これは非常にもったいない状態です。



「運用で何とかしてください」という人もいますが、誰でもそうだと
思いますが、ある商品を何回見せられても買わない人は、その商品は
もう買いませんよね?
「なんか前に見たけど、いらないな」というふうになるわけですから。



そういう人ばかりになっていくので、同じものがずっと出てくれば、
次第に飽きます。
そのため、クリエイティブを作るのをやめた会社が、基本的にMeta広告でうまくいくのは見たことがないです。



コストや時間をかけてクリエイティブをどんどん回している会社が、
結果的に一番数字が良くなっています。
A/Bテストの精度やスピードに差はあれど、結果的にA/Bテストが一歩
でも前に進んでいるため、結果的に効果があります。



なるほど。
例えば上司が「いや、もう変えずに回してくれ」と言ったら、担当の
人も「でもA/Bテストをやっていきたいんです」と双方の考えの違いに
悩む場合も多いのではと感じました。
そう言った場合、社内でどのようにすると良いのでしょうか?



それはもう、上層部に考えを改めていただくしかないですね。



「コストをかけたくない、何か広告費だけかければ成果が出るのでは?」と思ってる人が非常に多いのですが、広告をかけているということは、当然ながらその付随するコストもかかります。



ランディングページ(LP)を作る必要があれば、大なり小なり、コストも時間かかります。広告バナーを作るのもそうです。運用を外注する
のであれば、外注コストもかかります。



そのため、純粋な広告費以外にはコストはかからないと思い、高をくくっている人たちが非常に多いのですが、その考えを改めないのはもったいないです。
本当に結果を出したいのであれば、改善のための費用を惜しんではいけません。



例えば、その改善の提案に対して納得ができないのであれば、もちろんお金を出す必要はありません。
しかし、「提案には納得できても、お金を出したくない」ということで
あれば、絶対に結果は出ないですね。



Meta広告の効果を出すためのポイントは、どういったところになるのでしょうか?



はい、これはクリエイティブをまず、1つずつ変えるということです。
1週間に1回、2週間に1回など、定期的なやり方をするよりも、効果が悪くなったのは止めるし、効果があるうちは出しておくという効果ベースでのクリエイティブ判断という基準を持つことが重要ですね。



なるほど。
数値も大事なのはわかっていても、クリエイティブを作って出したということに満足している会社が多いのでは?と思ったのですが、やはり
多いですか?



さすがに、広告を出して満足したという会社は、そんなに多くないと思います。
しかし、「広告の製作にお金がかかるのは最初だけでしょ」と、クリエイティブの制作などにお金をかけないという判断をする会社は結構あり
ます。



なるほど。
「最初だけしかお金がかからない」と思っていること自体が、もう失敗の始まりという感じでしょうか?



そうですね、はい。



わかりました。ありがとうございます!
まとめ



では、今日の記事のまとめと、記事を読んでくださっている方に一言
お願いします。



はい。まず、Mete広告のクリエイティブを改善する上で行う、A/Bテストの目的は、再現性のある勝ち筋を作りに行くことです。
そのため、目的を達成できるやり方をしないと、A/Bテストをやってもほぼ意味がありません。



デザインも原稿も全然違うパターンを多く作って、とりあえずたくさん回すみたいな方法でテストをしても、変数が多すぎるため、効果のあったものは何なのかがわからなくなります。



そうなってしまうと、なにが原因で勝ったのか、負けたのかということがわからなくなります。
A/Bテストをしているようで、実際にはA/Bテストになっていないということが、中小企業の9割ぐらいで起こっていると思います。



そのため、Meta広告のクリエイティブ改善の前に、A/Bテストは原則
として1要素ずつやることが肝心です。



そもそもMeta広告で効果が出ないというのは、会社がクリエイティブ自体に対してお金をかけないという判断をするケースです。



このような会社はクリエイティブを作って、駄目なものは駄目で辞める、新しいのが必要ならどんどん作るという改善行動ができません。
そのため、どんなに素晴らしいデザイナーやライター、運用者がいても、上手くいかないことがほとんどです。



Meta広告において一番重要なクリエイティブの改善行動がそもそもできないため、そういう会社である限り、ずっとMeta広告では成果が出ません。
反対に言えば、成果が出る会社は、多少の先行投資があっても、クリエイティブ改善のためにコストを投じることができます。



もちろん会社の経営判断もありますが、クリエイティブの改善のためには一定のコストがかかるということを含んだ上で、改善に取り組んでいただければと思います。



ありがとうございます。