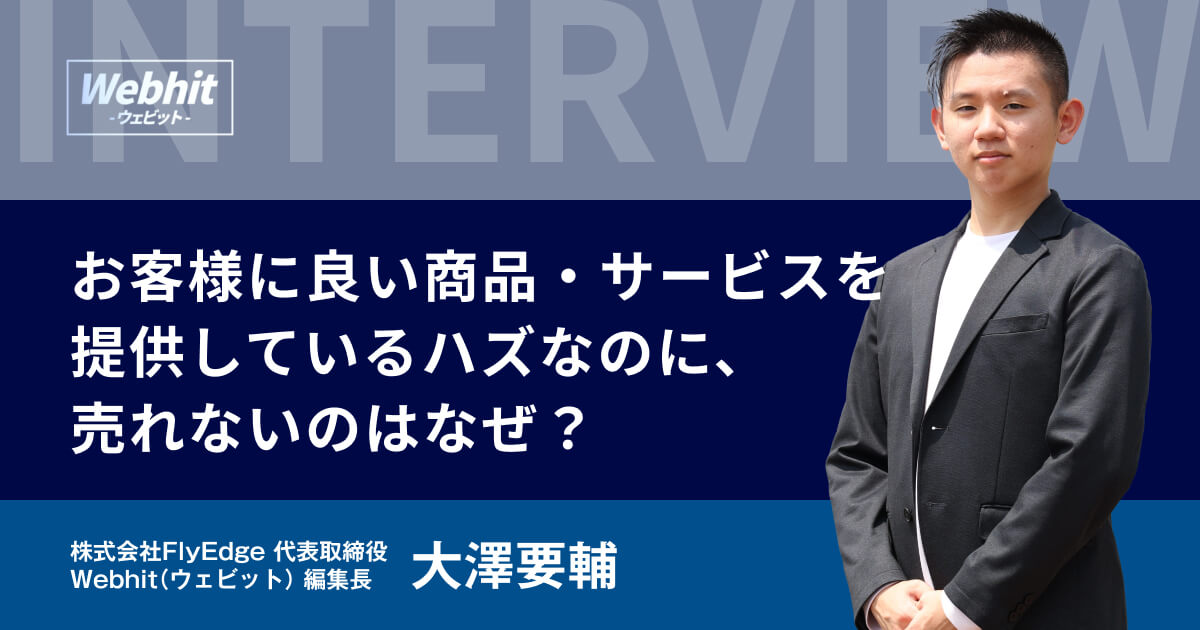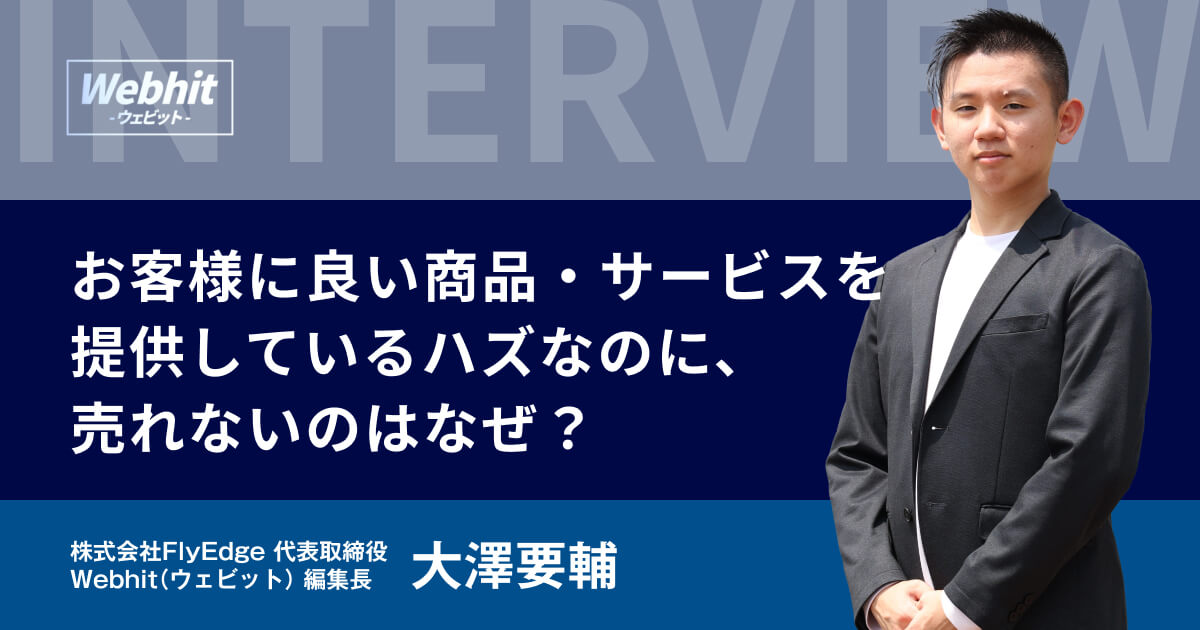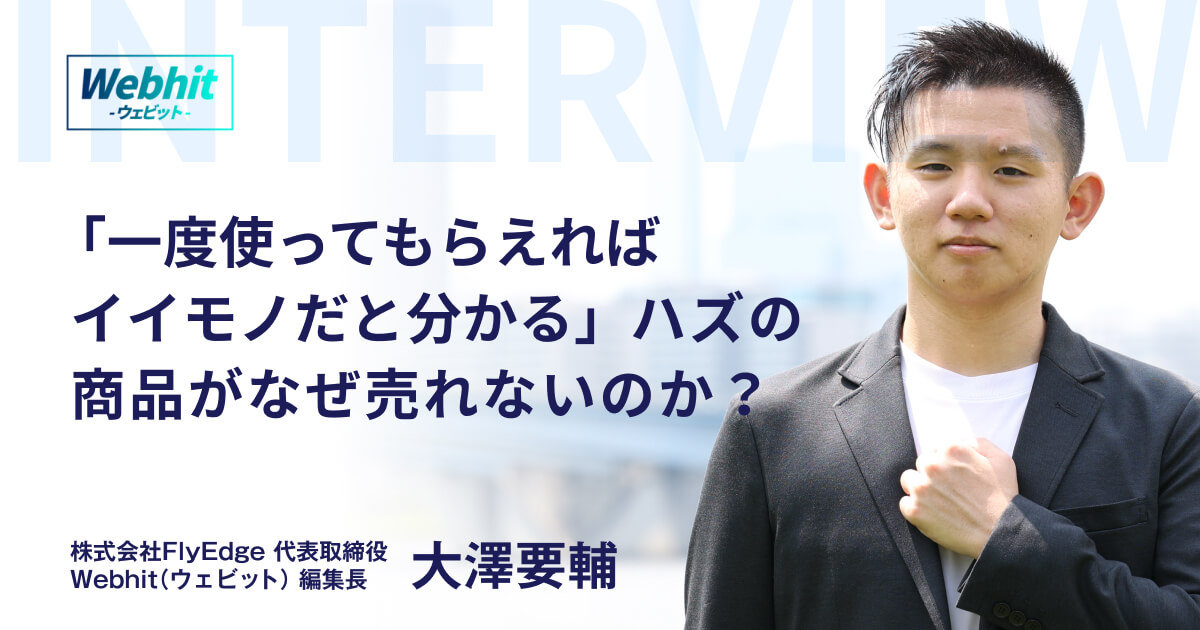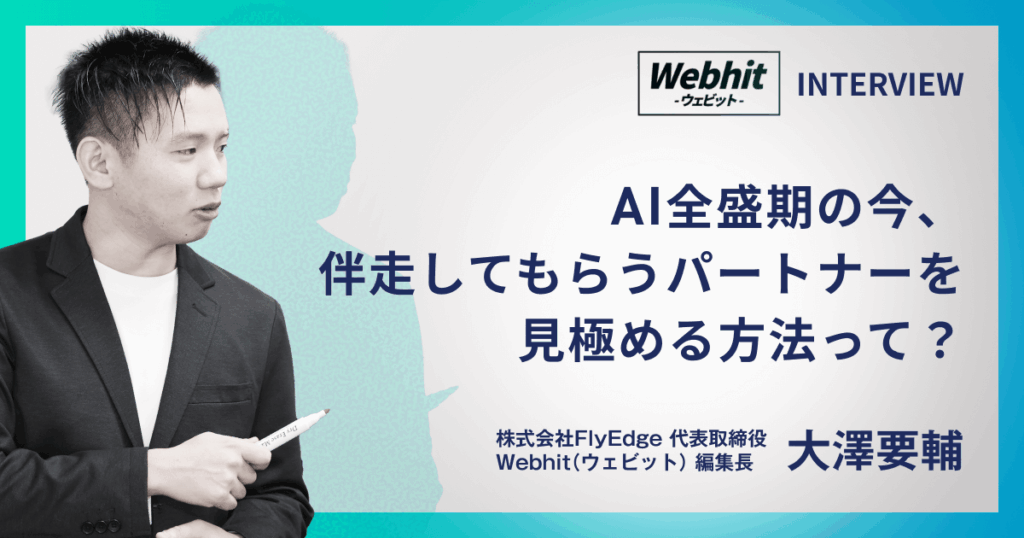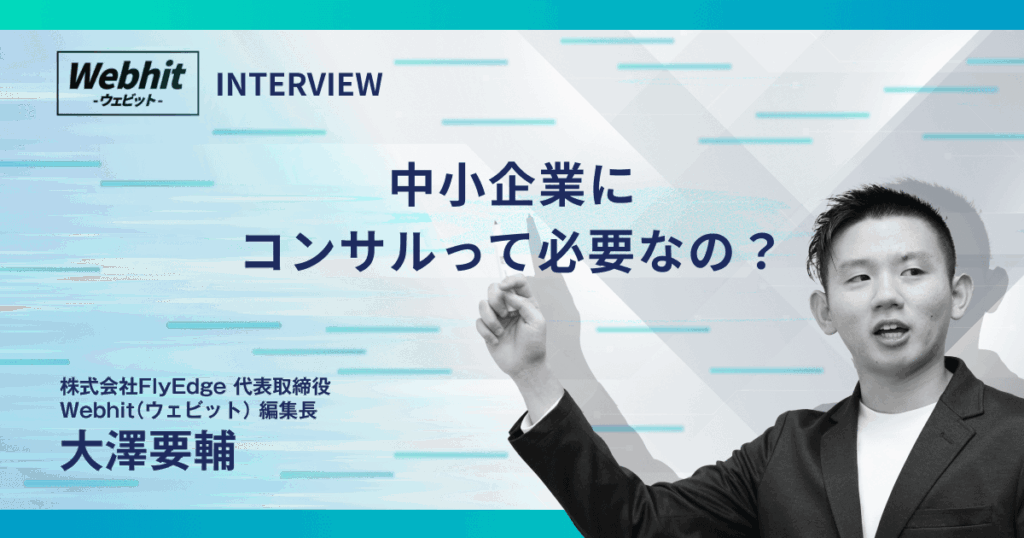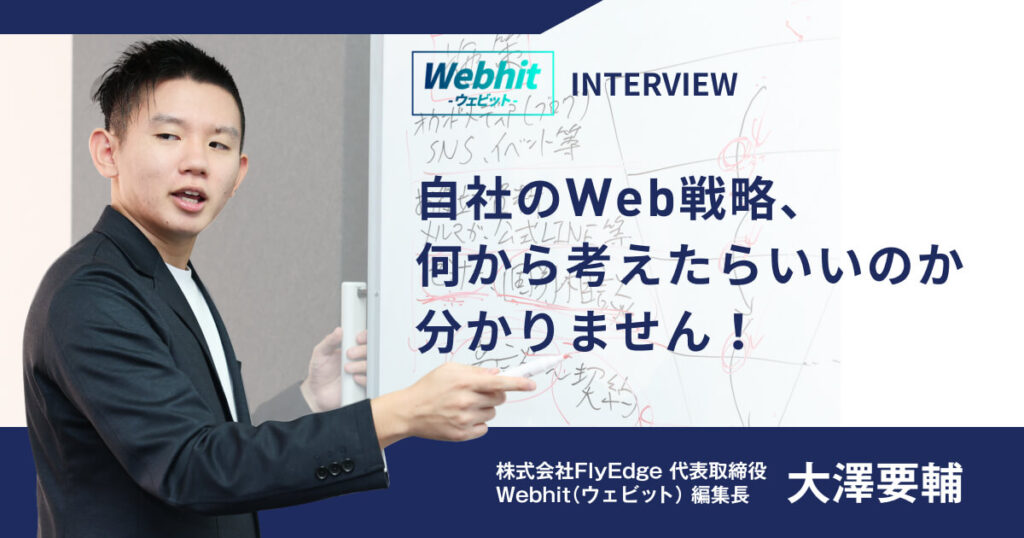Webhit 編集部
Webhit 編集部お客様に一度使ってもらえたら、必ず「良いもの」だとわかってもらえるほどの良い商品を扱っているのに、「なぜ売れないのか」というお話が結構あると思うんですけど…。
実際、何が原因で売れないのでしょうか?



そうなんですよね…これ、よくあるんですよ。
中小企業であればあるほど、めちゃめちゃあります。
「うちの商品を1回使ってもらえたら、1回触ってもらえたら、1回体験してもらえたら良いものだとわかります。どうして売れないのかわからないです」と言う会社がたくさんあるんです。



そんなにあるんですね…!



本当によくありますね。
確かに良い商品、良いサービスは作れているのですけど、一方で「良さそうに見える商品・サービス」にはなっていないんですよ。
一言で言えば、それが原因なんですよね…。



なるほど。
では、良い商品があったとして、それがお客様に伝わっていない・良さそうに見えていないことが原因で売れないんですか?



おっしゃる通りです。
物が良くても、ぱっと見たときに良さそうに見えなかったら、お客様からすれば別に興味は沸かないんですよね。



なるほど…。
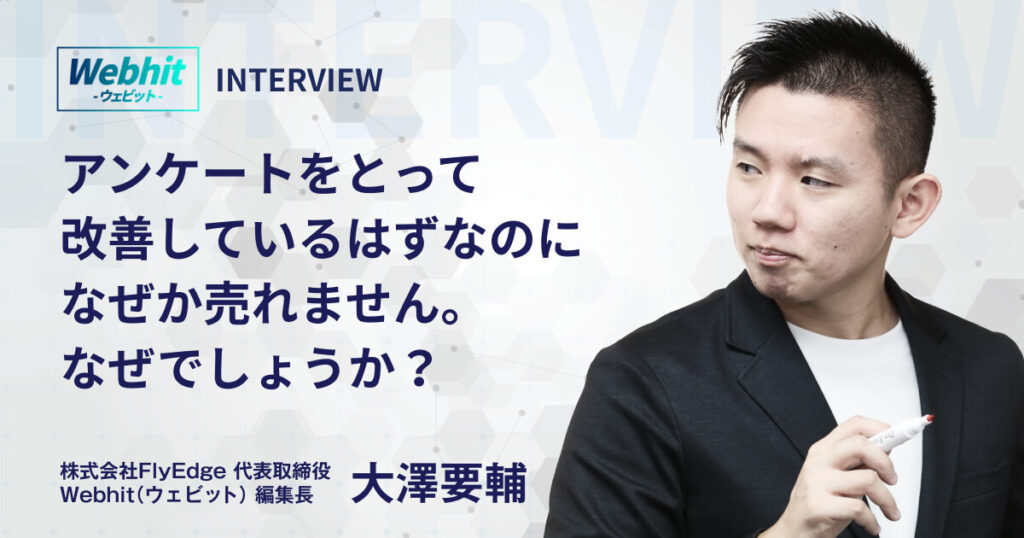
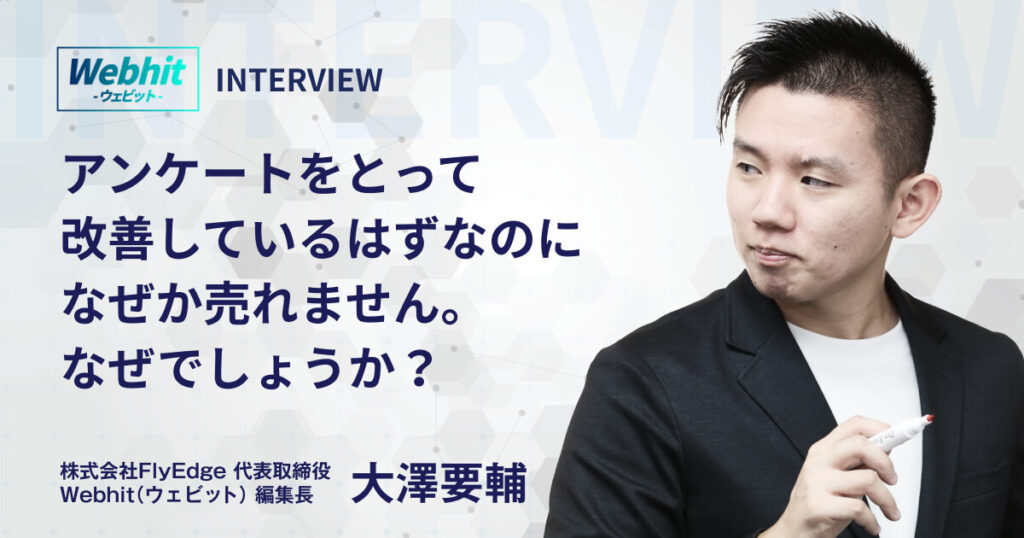



例えば、ここに水がありますが、これが普通の何でもないペットボトルに入っていて、ラベルも一切ついていなくて、何の説明もなかったら、ペットボトルに入っているだけの水じゃないですか。



でも、実はその水は、
・飲んだらたちどころに病気が治る水
・飲むことによって、体の中のデトックスができる水
のように、非常に良い商品の可能性もありますよね。



要は、お客さんがそれを知るのは、その商品なりサービスなりを使った後なんです。
買った後、つまり、そこに対してお金を払った後にそれを使うことになるので、「一度使ってもらえればわかるのになんで売れないのか」という命題そのものが間違っているんですよ。



そもそも、「使ってもらえればわかる、わかったら買う」という順番だとすると、そもそも買う前にわかることができないんです。



確かに!



なので、「この水は300円です」と言って出しても、「いや、でもこの水は300円には見えないね、良さそうではないよね…」と思われた瞬間に
300円は払ってもらえず、その水を手に取られることはないんですよ。
そうなると、良い商品であることはわかってもらえないので、売れないですよね。



やらなくてはいけないことは、
・良さそうだと思ってもらえるようなペットボトルの容器に入れる
・良さそうだと思ってもらえるようなラベルにする
・お客様にとって良いと思われる部分をテキストで書いて出してあげる
・成分を正確に記入する
などですね。



例えばこれには、「信州安曇野天然水」と書いてありますね。
信州といえば水が綺麗なイメージがあります。「安曇野って、多分お水の産地だ」と、聞いたことがある人もいるんですよ。



また、「天然水」っていうワード自体が好きな人もいますよね。
なので、それだけで良さそうに聞こえるんですよ。
このラベル自体も、明るい青の半透明なので、少し清潔感がある感じ。



また、ここに水の波紋のようなデザインが入っていて、瑞々しさのようなものを感じやすく、「これはすごく綺麗な水なんだな、安心できる」
「澄んだような水なんだな」というイメージを持って、これなら買おうと思うわけです。



なるほど。



だって、無味無臭で、色も付いていないんですよ。
水が並んでいるだけであれば、どれを選ぶかと言っても、基本的にそれしかないんです。
以前飲んだことがあって知っているので買うというケースもありますけど、初めての人の場合は、また少し違いますよね。



確かにそうですね。
「どれだけその一瞬で惹きつけられるか」みたいなところが大事になってくるんですね。



そうですね。
オレンジジュースの場合も同じです。
例えば、「オレンジジュース」って書いてあるだけのペットボトルと、瑞々しいオレンジの写真を使ってデザインされているオレンジジュースがあって金額が同じであれば、中身が別物だったとしても、絶対に瑞々しい方を選びます。
そこに「温州みかん使用」なんて書いてあったら、もう確実に買いますよね。



絶対に買いますね!



でも、文字しか書いていない方は、実はもしかしたら世界でも数%しか
採れない、非常に希少なオレンジを使っている可能性があるんですよ。



しかし、そのようなことは、初めて買う人にとっては知ったことではないわけです。
買う人からすれば、「それが良さそうかどうか」でしか買わないので、
わからないですよね。



そうですね…!



良いものを売っているのだとしたら、まずどうやったらお客様に手に取ってもらえるかを第一に考えないといけないのですね。
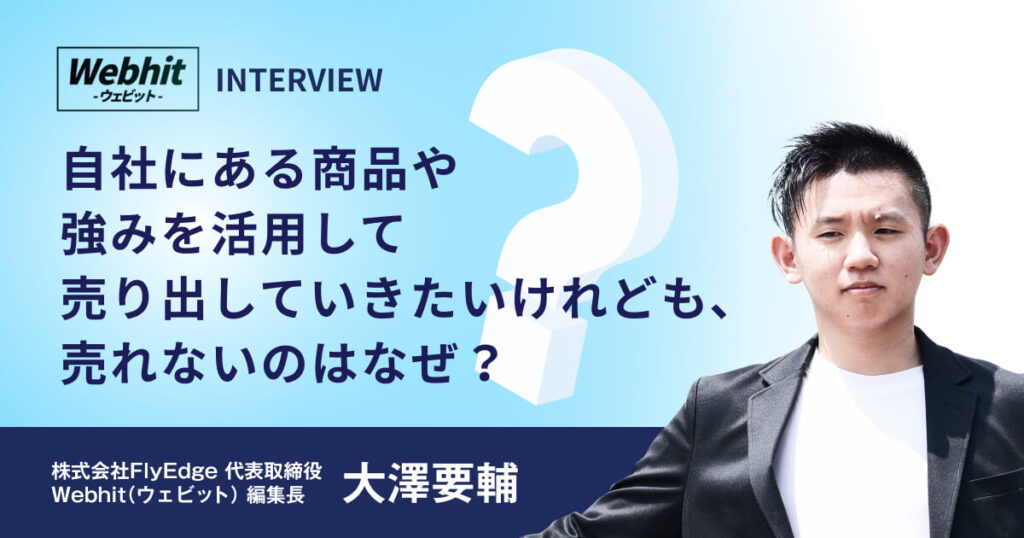
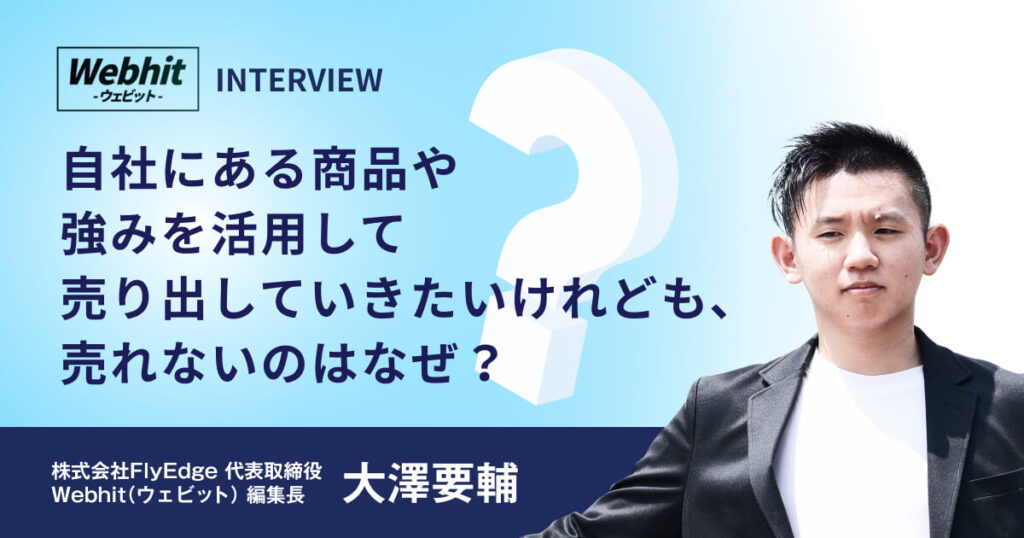
関連性と価値の提示でユーザーの心を掴む



店頭で並んでいたら、パッケージで目を引くことなどができると思うのですが、このWebという世界の中では、どうやったら流れてきた広告に目を留め、注目してもらうことができるのでしょうか?



ユーザーに「関係がある」と思われれば目を止めてもらえますよ。
例えば、有形ではない無形のサービス、Adobeなどのツールの場合を
考えてみましょう。



当然ながらAdobeのツール、AdobeCreativeCloudなどの場合は、基本的にはクリエイターやデザイナーなど、デザイン制作をするクリエイターにとって必要なツールですよね。



そのツールを、旅館で働いて常にお客様対応している人など、デザインともクリエイティブとも一切関係ない人に向けて広告を出したところで、特に刺さることはありません。



そのような場合は、どんなデザインを用いようが、どんなキャッチコピーを使おうが、自分に関係ないことなので刺さらないですよね。



でも、それをしっかり作って、クリエイターやデザイナーに見せていけばいいんですけど、ここには次の問題もあります。
「他のものよりも良い」ということをわかってもらわないくてはいけません。
例えばCanvaやFigma、その他にもいろいろなツールがありますよね。
そういった色々なものがある中で、「なぜAdobeでないといけないのか」ということをしっかり出していかなくてはいけないわけです。



要は、前提として、まず「自分に関係がある」と思わせれば興味を
引けます。
プラス、今その人の頭の中にあるものよりも良いものであること。
お客さんにとって、何かと比較して良いものだということがわかる、
または良さそうだと思ってもらえると共鳴するんです。



例えば無料プランの場合、よくある他の無料ツールには機能制限があるところ、「このツールなら無料です、かつ無料の場合でも機能制限がありません」のような触れ込みができれば、デザイナーやクリエイターの
興味や関心がある部分を見せることができていますよね。



ターゲットがしっかり合っている前提で、他とは違ってこちらも良さそうであるということが伝われば、基本的には刺さります。つまり、そこに対して売りやすくなってくるという感じですね。



なるほど。
「無料で使えます」という文言で思い出しましたが、「1ヶ月無料で使えます」などの売り文句があって、その後サブスクみたいにお金がかかるものが結構あると思います。
使ってもらえればいいものだとわかるなら、そのように「1ヶ月無料で使えます、サンプルであげます」などの戦略も効果的ですか?



おっしゃる通りです。
例えば、「1回使ってもらえたら、もうこれから離れられない」みたいなものの場合は、無料で出しちゃった方がいいですよ。



最初は無料でバーンと出して使ってもらう。



そうそう。
業務をダイレクトに便利にしてくれたり、時間を削減してくれるツールって、いっぱいあるじゃないですか。
有名なものではChatworkなど、いろいろありますね。
そして、大体は全て無料プランを作っていますよね。



そうですね、確かに。



マインドマップツールなどもそうです。
「これがあったらぶっちぎりで良くなる」という感じですね。



「業務効率が上がって、良さが圧倒的にわかる、伝わる」ようなものの場合は、一定期間無料で出したとしても、または機能を制限して無料にしてあったとしても、「それ以上の機能が欲しい」「その期間が終わっても、有料化してでも使いたい」というニーズを作りやすいので、そういうプロダクトの場合は無料で出した方がよいという話がありますね。



なるほど、そういうことですね。
入口を広げておいて1回使ってもらって、もう離れられなくするという
ことですね。



今のは売れる商品であることが前提だと思うのですが、逆に企業側が
少し勘違いをしていて、そもそもの商品の売り出し方が微妙なのに、
「これ、使ってもらえたら良いと思ってもらえるはずなんだよね」と
言っている場合もあるんですか?



ありますね。



そのパターンでよくあるのは、「こだわっているからいいものになっています」っていうパターンなんですけど、そのこだわりがお客さんにとって特に良いこだわりになっていない場合ですね。



「ここにはこういう技術を使っています」「ここにはこういう理論があって…」のようなことを言うんですが、それはお客さんからすればどうでもいいよねというケースがあります。



確かに。
アピールする部分が違っているのが要因なんですね。



そうですね。勘違いを生んでいる元凶といいますか…。



大体そういうときは、お客様にテスト的に触ってもらって感想をもらうようなことをしていないケースが多いです。
自分たちの思い込みだけで作っているというか。



なるほど、なるほど。



ただ、
・お客様にしっかり試してもらう
・使ってもらってインタビューしてみる
などのことをしていれば、そういうことにはなりにくいんですけどね。



そういった開発段階でユーザーテストをするなど、確実にマッチする
お客さんがいるとわかった状態できちんと売り出さないと、失敗する
可能性があるんですね。



ものを売り出す順序としては、そもそもの開発段階で自分たちが、
「ここをこうしたい」などではなく、お客様にテストしてもらったり
感想をもらうことで、お客さんの本当に欲しい物や意見を取り入れた
商品を作り、その口コミや感想をもとに売り出していくのが正しい
やり方なのですか?



企業側でとりあえず作って、「使ってもらえれば良いものだとわかるのに、全然売れないよ」というのは、そもそも前提からして間違っているということでしょうか?



そうですね。
お客さんのことが抜けているので、そのこと自体良くないですね。
ただ少し難しいのは、お客様の声を聞けば必ずいいものができるというわけでもないんです。



お客様が意見を出したり口コミを出したりするときは、かなり主観で話をするんですよ。
自身の経験や知識によって偏りが出るので、「こんな声をもらったから
その通りに直しました、その通りに作りました」といっても、「それって本当にみんな思っていることなんだっけ?」ということはあまり検証
できていないので。



もちろん、お客様の声から示唆が得られることはたくさんあります。
ですが、それに全て従うというのはまた違うことです。
あくまでも、その意見の中から、
・自分たちにできること
・自分たちがやるべきこと
・その商品名なりサービスなりの果たすべきこと
などを見極めるのは、自分たちでやらなくてはいけないんです。



お客様の気持ちに寄り添うけれども、お客さんの声に振り回されずに
きちんと信念を持つことが大事なのですね。


顧客の意見を適切に反映させる方法と新商品開発時の視点



お客様の声を鵜呑みにしてはいけないです。
寄り添いはするものの、鵜呑みにはしない。



例えば、オーガニックなサラダ専門店があるとします。
そこでお客様にアンケートをお願いしました。
たくさんの答えが返ってきて、「今のサラダが美味しいです」みたいな
ものもあれば、「少しこうしてほしいです」みたいな意見もありました。
その中に、「サラダは確かに美味しいんですけど、たまにガッツリしたものも食べたいなと思うので、ガッツリ系のメニューをたくさん準備してほしいです」みたいな声があったとします。



ここで、もし鵜呑みにするとどうなるか。
サラダの専門店なのに、ガッツリ系のメニューがたくさんできる。
例えば唐揚げや、天ぷらみたいなものをどんどん付け足すんです。
そうなると、「サラダ専門店」であることにこだわっているところが
良くて来ていた人たちが、今度は離れていきますよね。



確かに。



結局何屋さんかわからなくなってしまって、そういう人が離れていくということもあるので、それではその意見を無視するのかというと、それはそれでまた違うんです。それはそれで受け止めなきゃいけない。
例えば「サラダの上にトッピングできるようにしてはどうか」みたいな形でアイディアを求めるなどですね。



なるほど。



例えば、あくまでもトッピングメニューとして小さい唐揚げを作って
準備しておく。
「ややガッツリ食べられるけれども、オーガニックサラダ専門店という
お店のコンセプトも崩さないように、トッピング程度にするのはどうか」など…。



「サラダ専門店なのはわかっているんですけど、やはりどうしてもお昼ご飯にお米を食べたい時があるんです」という話が出たときに、「サラダの比率が非常に少ない定食のようなものをいきなり作るのかというと、それはそれで違うよね」と。



そうなったら、オーガニックサラダの文脈で何かできないかということを考えてみます。
例えば、ハワイ発祥のポキ丼っていうのがあるんですよね。
海鮮系で作られたサラダのようなものを丼にして食べるというスタイルも存在するんですよ。



・サラダベースにするのか、違うスタイルにするのか
・ご飯と合わせる場合は白米ではなく、十六穀米や玄米という形で、
オーガニックサラダでさっぱり食べられるという文脈を崩さないようにやってみようか
など、ベースの選択肢を増やしてあげるんです。



要は、きちんと受け止めはするし寄り添いもするし、そういうご意見があることは受け入れるけれども、それに振り回されて、自分たちのコンセプトが崩れることや、今満足してくれている他のお客様に悪影響を
与えることがあってはいけないという話ですね。



そういうことですね。
既にある自分たちのコンセプトを崩さずに、お客様の意見をどう反映させるかというところをしっかりやっていかないと、今までのお客さんが離れていくということですね。



リピーターさんも、何かしらの意味があってリピートしてくれている
わけじゃないですか。



確かに。
逆にリピーターの方の気持ちをないがしろにすることになってしまう
ということですね。



例えば、上島珈琲店を知っていますか?



はい、知っています!



黒糖ミルク珈琲というコーヒーが有名ですね。
僕はすごく好きなんですけど、例えばあそこがキャラメルマキアート
だけのお店なら行かないです。
上にクリームが乗っていたり、よくわからないチップみたいなものを
パッとかけたり、チョコレートとか何とか言い出したら、絶対に
行かないです。



全く違う、別物ですもんね。



そうそう。
やっぱりそこの名物は黒糖ミルク珈琲なんですよ。



そこを崩したら、そこに行く意味がなくなってしまいますよね。



他にも、わかりやすい例として挙げると、ドトールなどの客層は、30代から50代の男性会社員、サラリーマンが中心となっています。



結局、彼らが提供するのは「落ち着く空間」です。
スタバなどと違って、ドトールって、どの店舗を見てもかなり落ち着いた色調が多いんですよ。



確かに!



内装がすごく落ち着いていて、白や、薄い茶色などが多いんですよね。
装飾も控えめです。



メニューなども含めて、スタバのフラペチーノみたいに、「生クリームが乗っていて、ソースがかかっているのを美味しそうに撮る」ようなこともしないんですよね。



多分彼らは、実直にコスパよく美味しいコーヒーを出し、それとともに食べられる簡単な軽食を出すという以上のことをやらないんですよ。



もしも彼らが、「スタバでジュースが売れているから」と考えたり、
たまたま来た20代の男女の声に、「ここはなぜチョコ味のものがないんですか」「なぜ生クリームをトッピングできないんですか」のような意見があり、それを真っすぐ受けとめたとしたら、多分今の30代から50代の
男性サラリーマンは、みんなどこか別のところに行きますね。



そういうことですね。確かにそうですね…!



もちろんそういう意見はあるんだな、そこを比較されるんだなという
のは、事実の認識としては必要です。
しかし、だからといって何でも取り入れればいいわけではなく、自分
たちの既存のお客様や、自分たちのコンセプトを勘案した上で、入れるかどうかを考えなくてはいけないということですね。
もし入れるなら適切な入れ方を考えないと、お客様が離脱してしまうというケースにつながります。
「良さそう」が「買いたい」に繋がる



「商品・サービスの認知度が低い」とは、「何かしらの施策をしている
けれども売れていない」状態ですね。
良い物のはずでも、まずはお客さんにとって良さそうに見えないと意味がないんですよね。



お客さんにとって良さそうに見えていないと売れません。
BtoCについて考えると、例えば、脱出ゲームがありますね。
あれを何のコンセプトも無く、「今から店の中に閉じ込めるので、何分
以内に脱出してください」ということだけがポスターに書かれていても、行くと思いますか?



怖いですね。行かないですね。



行かないですよね。
白い画面に黒いゴシックフォントで、それだけ書かれていても
行きませんよね。



怖すぎますね。



はい。「多分、何かの事件に巻き込まれるだろうな」と思ってしまい
ますよね。



絶対に行かない。



でも結局、リアル脱出ゲームも、例えば
「アニメとコラボで、〇〇からの脱出、〇〇迷宮からの脱出」
「ホラーと掛け合わせて、こんな館から脱出」
のようなコンセプトがあるから、
「それなら参加してみたいよね、みんな行ってみたいよね」
となるわけですよね。



なるほど。
お客さんから見て、どうやったら目に留まるかを考えて、その一つの
例として、なにかとコラボさせるなどの方法もあるんですね。



はい、いいと思います。
結局、会社として売り上げを継続的に上げるという話とは少し違います。まず、「良いはずなのに売れないのはどうして」という命題に関しては、良さそうであれば売れるんですよ。
まず集客ができるので、本当に良いものであれば売れるんですよ、
いっぱい集客できてしまえば。



なるほど。



一定の割合で売れるんです。



そこから伸ばしていくなどはまた別の話で、はじめは良さそうに見えることが第一。



前提として、それがないと集められません。



例えば、それこそAmazonなどにあるものもそうですね。
似たような商品ばかりがいろいろあるじゃないですか。
ですが、同じくらいの金額であれば、もう「良さそうなもの」を
選ぶしかないですよね。



確かに、口コミなどを見たり…。



そうですね。
口コミも同じです。結局、口コミを使った人が言っているけど、
良さそうかどうかしかわからなくて、「良い」かどうかはわからない
ですよね。



その次には、「試着できるものや、試しに使えるものはどうか」という
話があります。
例えば、靴などは試着できますよね。
試着できて、その時はいいなと思っても、少し歩き続けると違ったり
するじゃないですか。
結局、その時は「良い」と思って買っているけど、実際には「良さそう」で買っているはずなんです。
日常生活と同じ使い方をしているわけではないので。



そうか、ユーザーの買う理由に、「なんだか良さそう」があるかどうか
ということですね。



逆に言えば、それ以外で買うのは難しいと思います。
「過去にも買ったことがある」とか、「その界隈についてすごく詳しい」とか、そういうことであれば違いますけど、あくまで一般的な人が一般的な購入の仕方をする、初めてこれを購入するというのなら、基本的にはほとんどが「良さそう」で買うしかないと思います。



ボールペンなどもそうです。試し書きができますよね。
でも、「サラサラして良さそうだな」と思っても、実際に長時間使うと、手が疲れてきたり、グリップなどが気に食わなくなってきたりすることがあります。



はい、ありますね。



他に、知識差が激しいもので言えば、一眼レフカメラがあります。
例えば、
・センサーの規格
・画素数
・特定のモードがある / ない
・特定のレンズが使える / 使えない
など、いろいろあるのですが、それらを知っている人間からすれば、
その物を買わなくても、ある程度いいものかどうかという判断がつくのですが、詳しくない人からすれば、
・持ったときに軽いか
・バッグに入りそうか
・画質がよさそうか
・細かい設定をしなくてもオートモードで撮れるか
・スマートフォンと連携できるか
程度のポイントを見て、「良さそうだ」と思って買うしかないんです。



ああ、確かに!



でも、実際1時間ぐらいカバンに突っ込んで持ち運んでみたら重たくなってくるかもしれません。
それは、買う前にはわからないことですよね。
「良さそう」に見せるマーケティングテクニック



「良さそう」だと思ってもらうために、自分たちが考えるターゲット層に対して、どうすればそう思ってもらえるかということを考えないと
いけない。
・「良さそう」だと思ってもらうための考え方
・「良さそう」だと思う気持ちをどうやって引っ張り出せばよいか
このことについて教えてください。



基本的には、ターゲットとな人たちが、何を基準に「良さそう」と
判断しているかを、まず知らなければいけません。
例えば、スマートフォンです。
我々と同年代の20代後半の人たちをメインターゲットとしてスマート
フォンを作りたい場合、「20代後半って、どういう基準でスマートフォン
を選んでいるんだっけ?」ということを考えます。



まず、20代後半にもなると、いろいろなスマートフォンを使った経験がありますよね。
例えばiPhoneでずっと来ている人もいれば、AndroidとiPhoneを行ったり来たりする人もいる。



ですから、「20代後半って何を基準で選んでいるのかな」ということから、さらにペルソナで「こういう悩みを持っている」「普段はこういう生活スタイルをしている」というものがあると、さらに細かい選定基準が出てきます。



そのような人たちにインタビューをした時に、例えば、
・スマホを触っている時間が長い
・とにかく軽いスマホがほしい
・割れにくい画面がよい
・SNSで共有することが多いため、写真の画素数が高いことや、液晶が綺麗に写ることが大切
などの選定基準が出てきたとします。
そうなると、その選定基準に当てはまるものを、要素として打ち出す
しかないんですよね。



・1日にスマートフォンを10時間ぐらい使うヘビーユーザーが、移動中に使っていても手が疲れない
・画面の大きいスマートフォンが主流の中、片手にすっぽり収まり、
重量も150gしかない
・画素数も、今の一般的なものが2000から4000万画素ぐらいなのに
対して、8000万画素ある
などですね。



良さそう!



そうなんです。そう思ってもらったら勝ちなんですよ。
なので、例えば20代後半の女性でも扱いやすいように、
・手が小さい方でも片手で扱えて指が疲れにくい
・幅が少なくて少し縦の長さがある形で、小さなカバンにも入る
・カメラの状態が良くて、落下にも強い米軍仕様
のようなスペックの要素ではありますが、彼らがこの選定基準で判断
しているのなら、そういうものを出さなくてはいけないですよね。



今一度ペルソナをはっきりさせて、その人が何をもって選ぶのか
というところですね。



ペルソナによって選定基準が違うので、その選定基準に合わせて、
・どのようなメリットがあるのか
・その商品やサービスがあると、その人がどのような姿を描けるのか、実現できるのか
のようなことですね。



ですから、そういう生活において、
・一日長時間スマホを触っても全く疲れない毎日になる
・SNSなどでも画質の良いものを共有できる
など、「日常生活やSNSにもフィットした形で、ストレスなくスマート
フォンを使う日々を送れますよ」と。



同時に、特に20代後半の、手が小さくてスマホが重いことに疲れて困っている女性の皆様に、「ストレスがない生活ができますよ」のような、
いわゆるベネフィットと呼ばれるものを伝えていくことも必要です。



そのベネフィットをお客さんが想像できたら勝ちということですね。



想像させくてはいけません。
想像できないのであれば、要素が間違っているか、要素が弱いかの
どちらかですね。
まとめ



今日はお話いただきありがとうございます。
最後に今日のまとめと、この記事を見てくださっている方に一言お願いできればと思います。



今回のテーマ「一度使ってもらえれば良いものだとわかるはずの商品が、なぜ売れないのか」について。
基本的には良いものだと自分たちは思っているけれど、お客様が良さそうだと思ってくれていないことが基本的に売れない原因だという話ですね。



「良さそう」だと思ってもらうのって、そんなに簡単ではなくて、結構難しいんですよ。
ペルソナ像として、どういう人たちがターゲットなのか、そのターゲットが持つ考え方や意思決定基準や、価値観のようなことをしっかり把握すること。
また、彼らに合わせたメリットの提示、メリットの先にあるベネフィットの提案ができていて、それがお客様にしっかり刺さっていること。
これで初めて「良さそう」だと思ってもらえるんですよ。



ですから、結構変数が多いんです。
変数というのは、お客さんによって変わる部分のことを言います。
そういう変数が多くなるため、非常に難しいことではあります。



ただ、「良さそう」だと思ってもらえない限り、基本的にお客様は、
料金を払うのが先か、または料金を払うことを確定するのが先か。
例えば飲食店の場合では、食べた後に料金を判断することになりますが、料金を払うことは注文時に確定しています。
いずれにしても、料金を払うことが先に確定している、または先に料金を支払ってからそれを使用するため、「買ってもらえば良いものだとわかる」ということが、そもそもあまり成立し得ないですよね。



唯一成立するとすれば、いわゆるフリーニューモデルです。
「全機能を無料で一定期間開放します」「一定の制限をつけた機能を無料で開放します」のようなものです。
使ったら、それが圧倒的にいいものだとわかるものなのであれば、
そこから有料化するので成立するよねとも言えますが、ただ、それが
できるのは無形商材であったり、インターネットで販売を完結するものであったりと、限られてくる部分もあるので少し難しいですよね。



そのため、基本的には、無料のものであっても、「良さそう」だと思われなければ無料でも使ってもらえないんですよ。
その「良さそう」だと思わせるものを作らなくてはいけないので、他の何かの施策よりもどんどん圧倒的に先にやらなくてはいけないことかなと思います。
これが、僕からの全体のまとめです。



一言お伝えすることがあるとしたら、自分たちの今売ろうとしている、または売っている商品やサービスを、「自分たちが良いものだと思っている」だけで売っていませんか?
「お客様に、良さそうだなと思ってもらえる仕掛けを施していますか?」ということを聞きたいですね。