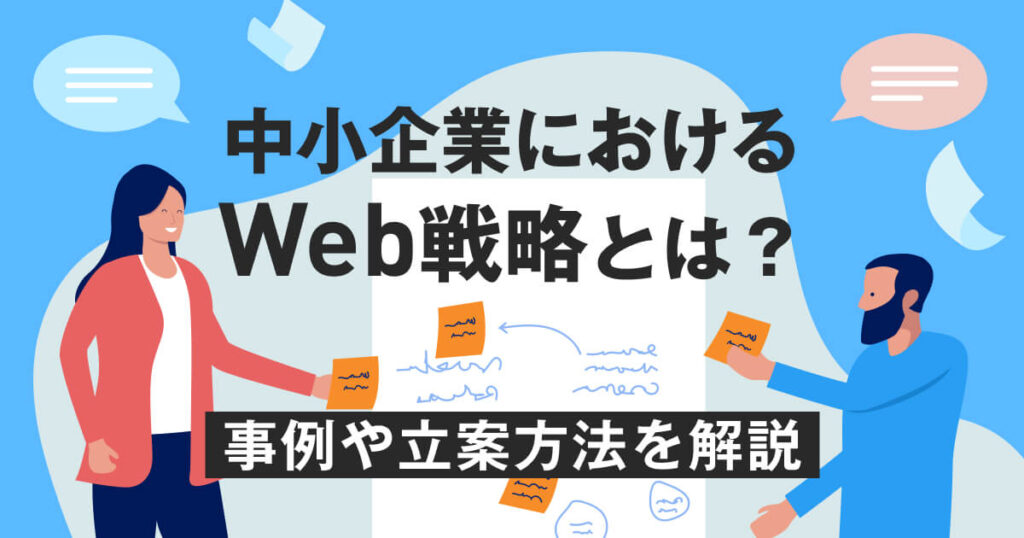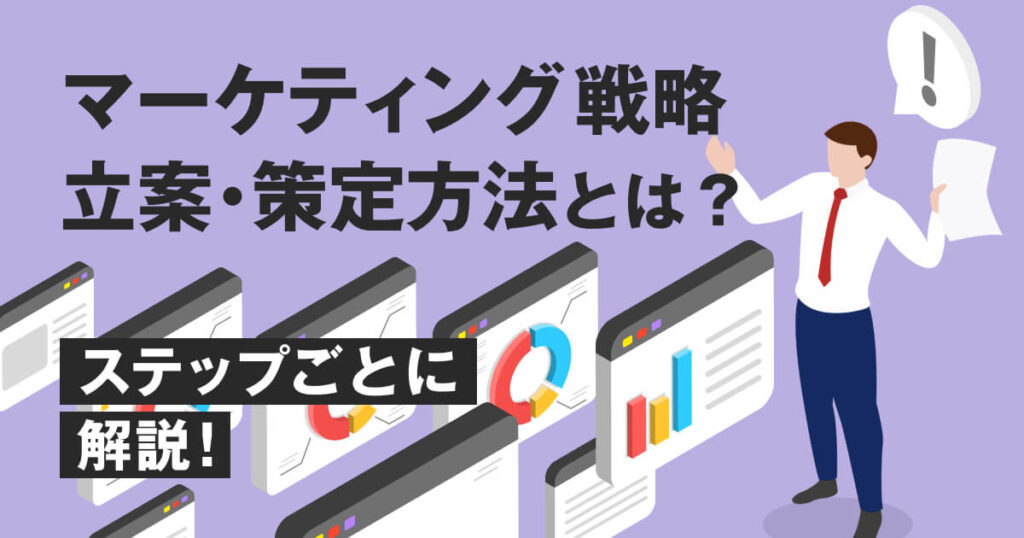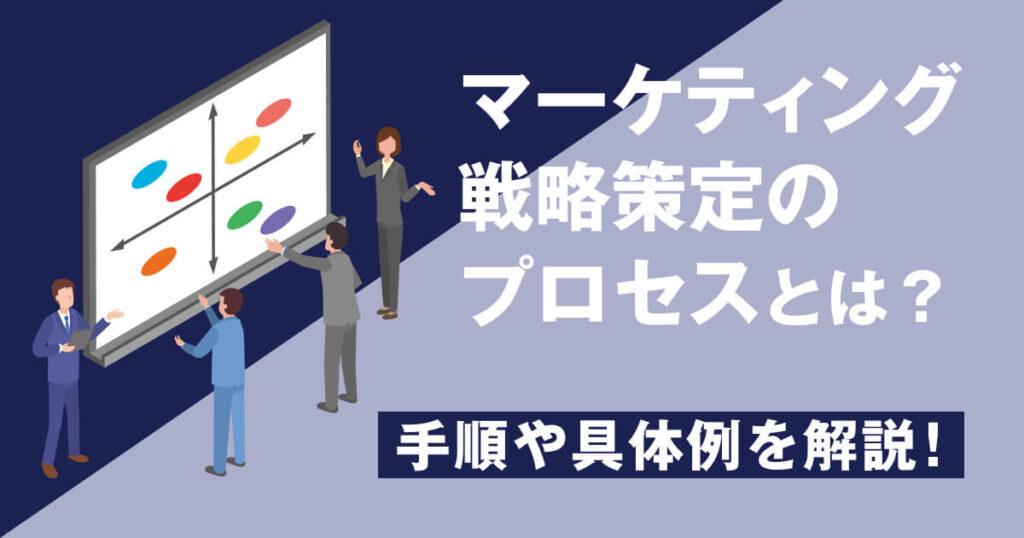「サイトリニューアル、何から手をつければいいか分からない…」
サイトリニューアルの成否は、実は始まる前にもう決まっています。土台となるのは「要件定義」です。
本記事では、サイトリニューアルを成功に導く要件定義の進め方を徹底解説します。さらに、要件定義書に盛り込む必須項目から、抜け漏れを防ぐテンプレート活用術、発注先との円滑な進め方まで網羅しました。
もし「失敗しない要件定義書の作り方が知りたい」と悩んでいるなら株式会社FlyEdgeにご相談ください。多くのリニューアルを成功させてきた実績で、貴社のプロジェクト計画を支援します。
サイトリニューアルは要件定義で決まる
サイトリニューアルの成功は、プロジェクトの土台となる要件定義で決まります。要件定義とは、リニューアルの目的や必要な機能を明確にする作業です。
この工程を丁寧に行うことで、関係者の認識を統一し、手戻りのないスムーズなプロジェクト進行が期待できます。この記事では、要件定義の基本的な知識から、担当者に求められるスキルやツールまでを分かりやすく説明します。まずは基礎をしっかり理解しておきましょう。
リニューアルの定義・目的・効果
サイトリニューアルにおける要件定義とは、プロジェクトの目的や必要な機能を具体的に定める作業です。
なぜなら、関係者間の認識をひとつにまとめ、プロジェクトが目指す方向性を固めるためです。この作業が曖昧だと、完成したサイトが期待したものと違うという事態になりかねません。例えば、「売上を1.2倍にする」という目的を立てます。そのために「問い合わせフォームを使いやすくする」「商品の検索機能を強化する」といった具体的な要件を洗い出すのです。これにより、開発会社とのやり取りがスムーズに進み、手戻りを防ぐ効果があります。
リニューアルを成功に導くには、まず要件定義でプロジェクトの設計図の明確化が重要です。
いつ実施するか
サイトリニューアルの要件定義は、プロジェクトの最も初期段階で実施します。
具体的なデザイン制作やシステム開発に着手する前に行うことが鉄則です。先に要件を固めなければ、必要な機能やデザインの方向性が定まりません。
後から仕様の変更が出ると、追加の時間や費用が発生してしまいます。まず現状のサイトが持つ課題を調べます。そしてリニューアル後の理想の姿を描き、関係者と合意を形成した後に要件定義を開始するのが一般的な流れです。例えば「スマートフォンで見にくい」という課題に対し、それを解決するための設計図をまとめる段階が要件定義にあたります。
プロジェクトの成否は初期段階で決まるため、計画の最初に要件定義の時間を確保することが大切です。
必要な担当者スキル・ツール
要件定義の担当者には、コミュニケーション能力や課題を発見する力など、幅広いスキルが求められます。
なぜなら経営層から現場の担当者まで、様々な立場の人の意見を聞き、要望を整理する必要があるからです。現状のサイトや業務が抱える問題点を見つけ、解決策を考える力も欠かせません。具体的には、相手の話を聞く力、物事を筋道立てて考える力、内容を分かりやすく資料にまとめる力がポイントです。
ツールとしては、課題管理にJiraやBacklog、情報共有にConfluenceやGoogleドキュメント、図の作成にはCacooやMiroなどが使いやすいです。専門的な知識だけでなく、関係者とスムーズに話し合い、プロジェクトを前に進める力が必要です。
サイトリニューアルの手順
要件定義の全体フロー 要件定義は、決まった手順に沿って進めることがポイントです。
手順を踏むことで、情報の抜け漏れを防ぎ、関係者との合意を確実に取れるからです。結果として、精度の高い要件定義書を作成できます。主なフローは、現状分析、コンセプト設計、合意形成、そして要件定義書ドラフト作成の4つのステップです。
この流れに沿ってひとつずつ丁寧に進めれば、プロジェクトが迷走するリスクを減らし、成功の確率を高められます。
ステップ1|現状分析
要件定義の最初のステップは、現在のウェブサイトが抱える課題を正しく知る現状分析です。
どこに問題があるのかを理解しなければ、的確な改善策を立てることはできません。思い込みで判断するのではなく、客観的なデータに基づいて分析することが求められます。例えば、アクセス解析ツールを使い、どのページの閲覧が少ないか、ユーザーがどの段階でサイトを離れているかを調べます。
また社内の担当者や顧客に話を聞き、サイトの使い勝手に関する意見を集めることもおすすめです。集めた情報から「問い合わせが増えない原因は、入力フォームが複雑なことかもしれない」といった仮説を立てていきます。
現状を正確に把握し、効果的にリニューアルを進めていきましょう。
ステップ2|コンセプト設計
現状分析で課題が見えたら、次はリニューアル後のサイトの方向性を決めるコンセプト設計に進みます。
コンセプトがはっきりしていないと、デザインやコンテンツに一貫性がなくなり、誰に何を伝えたいサイトなのかが曖昧になります。プロジェクト関係者の目線を合わせる意味でも大切な工程です。まず「誰に(ターゲット)」、「何を伝え(提供価値)」、「どのようなサイトを目指すか(ゴール)」を具体的に定義します。
例えば「20代の若手社員に、ITの基礎知識を分かりやすく提供し、研修への申し込みにつなげる」といった形です。このコンセプトが、後のデザインや機能を決める際の判断の軸として使えます。
ぶれないコンセプトを最初に固めることで、プロジェクトがスムーズに進みます。
ステップ3|合意形成
コンセプトが固まったら、プロジェクト関係者の間で合意形成を行うことが大切です。
関係者の間で認識にズレがあると、後の工程で「こんなはずではなかった」という意見が出て、大きな手戻りやトラブルの原因になるからです。経営層や事業部長、現場の担当者など、それぞれの立場から出る意見や要望を丁寧に聞きます。そして設計したコンセプトやリニューアルの目的、期待できる効果を分かりやすく説明し、全員の納得を得るのです。
この段階で認識を合わせておくと、その後の判断が速やかに進みます。疑問や心配な点は、この時点で全て解消しておく必要があります。時間をかけてでも丁寧に関係者の合意を得ることが、プロジェクトをスムーズに進めるポイントです。
ステップ4|要件定義書ドラフト作成
関係者との合意が取れたら、これまでの決定事項をまとめた要件定義書のドラフト(下書き)を作ります。
要件定義書は、リニューアルの目的や仕様を開発会社などに正確に伝えるための、いわば設計図です。口頭でのやり取りだけでは、認識の違いや情報の抜け漏れが起こる可能性があります。まず、プロジェクトの背景や目的、目標とする数値を書きます。
次に、サイトの構成案(サイトマップ)やデザインの方向性、必要な機能(例:会員登録、商品検索)などを具体的に書き出します。このドラフトを元にして、関係者や開発会社とさらに詳細を詰め、内容を完成させていくのです。
この文書がプロジェクトの土台となるため、誰が読んでも分かるようにまとめることが求められます。
要件定義に盛り込む必須項目
要件定義書には、リニューアルの全体像を正確に伝えるため、必ず記載すべき必須項目があります。
これから紹介する項目が抜けていると、開発会社との認識にずれが生まれ、見積もりが不正確になることや、プロジェクトが迷走する原因にもなり得ます。ビジネス上の目標から公開後の運用方針まで、具体的に何を記載すべきかを理解することがポイントです。
抜け漏れなく項目を網羅し、プロジェクト成功のための精度の高い設計図を完成させましょう。
ビジネス目標(背景・KGI/KPI)
要件定義書には、なぜサイトをリニューアルするのかという背景と、ビジネス上の目標を具体的に記載します。プロジェクトの目的を関係者全員で共有し、同じゴールを目指して進むためです。目的が明確であれば、開発会社からもより的確な提案を引き出すことができます。
例えば「既存サイトのシステムが古く、更新作業に手間がかかっている」といった背景を説明します。その上で、最終目標であるKGI(例:サイト経由の売上30%増)と、中間目標のKPI(例:月間問い合わせ数100件)を数値で設定します。具体的な数値を設定することで、リニューアルの成果を客観的に評価できるようになるのです。ビジネス目標を明確にすることが、成果の出るサイトリニューアルにつながります。
サイト構成とデザイン
サイトリニューアルの要件定義では、サイト全体の構造とデザインの方向性を明確にする必要があります。ユーザーが必要な情報へたどり着きやすく、かつ企業のブランドイメージを正しく伝えるためです。全体構造と方向性が曖昧な状態だと、使いにくく魅力のないサイトになってしまいます。
サイト構成では、どのようなページが必要で、それらをどう配置するかを示すサイトマップを作ります。デザイン面では、ターゲットユーザーに合わせた雰囲気や色使い、レイアウトの方向性を言葉にしたり、参考サイトを提示したりします。例えば「信頼感を重視し、青を基調としたシンプルなデザイン」のように具体的に示すのです。ユーザー目線の分かりやすい構成と、コンセプトに合ったデザインを定義することがサイトの価値を高めます。
サイトマップ作成手順
サイトマップは、サイト全体のページ構成を地図のように見せるもので、論理的な手順で作成します。抜け漏れなく必要なページを洗い出し、ユーザーや検索エンジンに分かりやすい構造を作るためです。
いきなり作り始めると、構成が複雑になりがちなので注意しましょう。
まず、サイトに載せるべき情報を全てリストアップします。次にそれらの情報を関連性の高いもの同士でグループ分けし、階層構造に整理していくのです。例えば「会社情報」という大項目の中に「代表挨拶」「沿革」「アクセス」といった小項目を配置します。ツールを使い、樹形図のような形で視覚的に表現すると、関係者とも認識を合わせやすくなります。
ユーザーの動きを考えながらページを整理し、分かりやすいサイトマップを作成しましょう。
UI/UX要件
UI/UX要件では、ユーザーが快適にサイトを使えるための操作性や体験を定義します。サイトの使いやすさはユーザーの満足度に直接結びつき、サイトから離れてしまう割合にも大きく影響するためです。
見た目のデザインが良いだけでは、ビジネスの成果にはつながりません。UI(見た目の使いやすさ)では、「ボタンは大きく押しやすい形にする」「入力フォームの項目は少なくする」といったことを定めます。UX(体験価値)では、「スマートフォンでもストレスなく見られる」「ページの表示を速くする」など、ユーザーが目的を達成するまでの体験全体を設計することが必要です。
ユーザーが直感的に操作でき、心地よいと感じる体験を提供するための要件を定めることが求められます。
機能・システム要件
機能・システム要件では、リニューアルで実現したい具体的な機能や、その裏で動くシステムの仕様をはっきりとさせます。
開発会社が正確な作業量や費用を見積もるために、なくてはならない情報だからです。要件が曖昧だと、希望した通りの機能が作られなかったり、後から追加の費用がかかったりします。
例えば「ブログ記事を社内で簡単に更新できる機能(CMS)」「キーワードでサイト内を検索できる機能」「問い合わせ内容を保存する機能」などを具体的に洗い出します。また、現在使っている他のシステムと連携が必要な場合は、その仕様も明確に記載しなくてはなりません。
「何ができるようにしたいか」をできるだけ詳しく書き出すことがポイントです。
CMS/検索/フォーム
機能要件の中でも、CMS、サイト内検索、フォームは、多くのサイトで基本となる特に重要な機能です。
なぜならCMSは情報発信の効率を、検索は情報の見つけやすさを、フォームはユーザーとの接点を左右する、サイトの心臓部と言える部分だからです。
CMSでは「見出しや画像の挿入が簡単にできるか」「公開する日時を予約できるか」といった点を定義します。検索機能では「複数のキーワードで絞り込み検索ができるようにしたい」など、具体的な仕様を決めなくてはなりません。フォームについては「入力内容の間違いをその場で表示する」「郵便番号から住所を自動で入力する」といった使いやすさをアップさせる要件が考えられます。
主要機能の要件を具体的に詰めることで、サイトの利便性と運用効率が大きくアップします。
インフラ・セキュリティ要件
サイトを安定して安全に動かすため、サーバーなどのインフラや、セキュリティに関する要件を定めます。
サイトへのアクセスが集中してサーバーが停止することや、外部からの攻撃で情報が漏れることを防ぐためです。見過ごされがちですが、事業の継続に直接関わるポイントです。インフラ要件では、予想されるアクセス数に耐えられるサーバーの性能や、データのバックアップ方法などを決めます。
セキュリティ要件では、個人情報などを守るためのSSL化(通信の暗号化)や、不正なアクセスを防ぐ仕組みの導入、定期的な安全性の診断実施などをはっきりと書きます。
サイト公開後の安定した稼働とユーザーの信頼を守るためにも、インフラとセキュリティの要件は必ず盛り込みましょう。
プロジェクト体制・スケジュール・予算
プロジェクトをスムーズに進めるために、誰が何を担当するかの体制、いつまでに何を行うかの日程、そして全体の予算を明確にします。
体制が不明確だと責任の所在が曖昧になり、日程や予算がなければ計画的な進行ができません。関係者全員が同じ認識を持つことが重要です。プロジェクト体制では、自社の責任者や担当者、開発会社の担当者などを図で示すと分かりやすいです。日程は、要件定義から設計、開発、テスト、公開までの各工程の開始日と終了日を具体的に設定します。
予算については、開発費用だけでなく、サーバー代や公開後の保守費用なども含めた総額を記載し、支払い条件なども決めておくことが望ましいです。
運用・保守方針
サイトを公開した後の運用や保守についての方針を、要件定義の段階で決めておくことが大切です。
サイトの公開はゴールではなくスタートです。誰がどのようにサイトを更新し、問題が起きた時にどう対応するかを事前に決めておかないと、サイトが放置されてしまうからです。運用方針では、コンテンツを更新する頻度や担当部署、アクセス状況の分析ルールなどを定めます。保守方針では、システムやサーバーの監視、障害が起きた時の対応窓口や対応時間、セキュリティ対策の実施体制などを明確にします。
運用・保守業務を自社で行うか、開発会社に任せるかも決めておく必要があります。将来にわたってサイトの価値をアップさせるため、公開後の体制まで考えた計画を立てることが求められます。
サイトリニューアルで押さえたいSEO・アクセス対策
サイトリニューアルでは、デザインや機能の刷新と同時に、検索エンジンからの評価をアップさせるSEO対策が重要です。
SEOの視点を忘れると、リニューアル後に検索順位が下がり、アクセス数が激減する危険があります。URLの変更に伴う転送設定や、ページの表示速度の改善などを、要件定義の段階で必ず盛り込みましょう。事前のSEO要件定義が、リニューアルの失敗を防ぐポイントです。
URL設計とリダイレクト
サイトリニューアルでページのURLが変わるなら、古いURLから新しいURLへ自動で転送するリダイレクト設定が不可欠です。
設定を怠ると、ユーザーがブックマークからアクセスできなくなります。また、検索エンジンがそれまで蓄積してきたページの評価が失われる可能性もあります。要件定義では、まず新しいサイトのURL構造を分かりやすく設計します。
次に旧URLと新URLの一覧を作り、どのページからどこへ転送するかを明確に定めるのです。「301リダイレクト」という方法で、恒久的な移転だと検索エンジンに伝えることが一般的です。
リニューアルによるアクセス数減少を防ぐため、URL設計とリダイレクト設定は要件定義に必ず入れておきます。
メタ情報/構造化データ
検索エンジンにページの内容を正しく伝えるため、メタ情報や構造化データの要件を定義します。
この情報が適切に設定されていると、検索結果でユーザーの目を引き、クリックされやすくなる効果が期待できるからです。メタ情報とは、ページのタイトルや要約文のことです。リニューアルを機に、各ページの内容に合った、より魅力的な文言に見直す計画を立てます。構造化データは、ページの内容をさらに詳しく検索エンジンに伝える情報です。
例えば、商品ページに価格や在庫情報を、イベントページに日時や場所の情報を設定すると、検索結果で特別な表示がされることがあります。検索結果での見え方まで考えた要件定義が、集客の成功につながります。
コアウェブバイタル・表示速度最適化
ユーザーの満足度を示す指標であるコアウェブバイタル、特にページの表示速度の改善を要件定義に含めることが重要です。
ページの表示が遅いと、ユーザーは待たずにサイトを離れてしまうからです。また、表示速度は検索エンジンの評価にも影響します。要件定義では、「ページの表示を2秒以内に終える」といった具体的な目標数値を設定が必要です。
目標を達成するため、画像のファイルサイズを軽くすることや、不要なプログラムを減らすことなどを、開発会社への要件として伝えます。Googleの無料ツールなどで現状の速度を調べておくと、改善の計画が立てやすくなります。
快適な閲覧環境の提供は、ユーザー満足度とSEO評価の両方を高める上で欠かせません。
要件定義からRFP作成までの手順
要件定義書が固まったら、次はその内容をもとにRFP(提案依頼書)を作成します。
RFPとは、開発会社に具体的な提案と見積もりを依頼するための公式な文書です。精度の高いRFPを作ることで、各社から質の高い提案を引き出し、プロジェクトに最適な発注先を選ぶことができます。要件定義からRFP作成への流れを理解し、最高のパートナー選びにつなげることが重要です。
RFPに盛り込む要素
RFP(提案依頼書)には、要件定義書の内容に加えて、発注先を選ぶために必要な情報を盛り込みます。
開発会社が提案内容や見積もりを具体的に考えるためには、プロジェクトの全体像を正確に伝える必要があるからです。情報が足りないと、的確な提案は期待できません。まずリニューアルの目的や背景、予算の上限、希望する納期をはっきりと書きます。次に、作成した要件定義書を付け、サイトの機能やデザインに関する要望を伝えます。
加えて、提案してほしい範囲(例:デザインのみか、開発までか)、会社を選ぶ基準、提案の提出期限なども記載します。会社の紹介資料を添付してもらうよう依頼することもおすすめです。依頼したい内容を十分に記載したRFPの作成が、良い提案を受けるためには必須です。
発注先から良質提案を得るコツ
複数の開発会社から質の高い提案を引き出すためには、いくつかのコツがあります。
良い提案は、ただ待っているだけでは集まりません。依頼する側が少し工夫をすることで、開発会社の意欲を高め、よりプロジェクトに合った提案を受けられる可能性が高まるからです。
ひとつのコツは、RFPを送る前に、候補となる会社へ事前に話をしておくことです。また、質問を受け付ける期間を設け、丁寧に対応することで、相手の理解が深まります。複数の会社に同じ条件で依頼し、比較して選ぶ姿勢を見せることも大切です。ただし、あまりに多くの会社に依頼すると対応が大変になるため、3社から5社程度に絞るのが現実的でしょう。
丁寧で誠実なやり取りを心がけることが、最終的に良いパートナーシップを築くことにつながります。
要件定義を成功させるポイントと注意点
これまでに説明した手順や項目に加えて、要件定義を成功に導くためには、押さえておくべきポイントと注意点があります。
技術的な要件だけでなく、人とのやり取りやお金の管理といった面も、プロジェクトの成否に大きく影響するためです。社内外でのコミュニケーションの取り方や、現実的な予算管理の方法などを紹介します。
社内外コミュニケーション術
サイトリニューアルの要件定義では、社内外の関係者とスムーズに話し合うことが重要です。
プロジェクトには様々な立場の人が関わるため、認識のズレや情報共有の不足が、後々のトラブルや手戻りの原因になりやすいからです。社内では、経営層には「投資で得られる効果」を、現場担当者には「業務がどう楽になるか」など、相手の関心に合わせた説明を心がけます。定期的に進捗を共有する会議を開くこともおすすめです。社外の開発会社に対しては、専門用語に頼らず、実現したいことを分かりやすく伝える努力が必要です。
疑問点はそのままにせず、その都度確認し合う姿勢が、信頼関係を築きます。丁寧な対話を重ねることが、プロジェクトを成功に導くための確実な方法です。
予算・工数の現実的管理
サイトリニューアルでは、設定した予算や工数(作業時間)を現実的に管理することが求められます。
「あれもこれも」と要望を詰め込みすぎると、予算を超えてしまったり、納期に間に合わなくなったりするからです。これは、プロジェクトが失敗する大きな原因のひとつです。まず、実装したい機能に優先順位をつけます。「絶対に必要」なものと「できれば欲しい」ものを分けておくのです。開発会社からの見積もりが出たら、予算内に収まるかを確認します。必要であれば、優先順位の低い機能を見直すことも検討してください。
予期せぬ追加作業に備え、予算やスケジュールに少し余裕を持たせておくことも、賢明な管理方法と言えます。理想を追い求めるだけでなく、限られた資源の中で最大の効果を出す視点が大切です。
外注先との情報共有・レビュー方法
開発を外注する場合、外注先とのこまめな情報共有と、作られたものに対する的確なレビューが成功のポイントです。
「作ってもらって終わり」という姿勢では、意図したものと違うサイトが出来上がってしまう可能性があります。プロジェクトの進行中も、積極的に関わっていく必要があるのです。情報共有には、定期的な打ち合わせのほか、チャットツールなどを活用し、日頃から連絡を取り合える体制を作ると良いでしょう。
外注先からデザイン案や試作品が出てきた際には、複数人で確認します。その際は「もっとかっこよく」といった曖昧な伝え方ではなく、「このボタンの色を青に変えてほしい」など、具体的に修正してほしい点を伝えることが重要です。
協力し合う姿勢で、密な連携を心がけることが、質の高いサイト制作につながります。
まとめ|サイトリニューアル
サイトリニューアルの要件定義は、プロジェクトの成功を左右する「設計図」です。デザインや機能の前にビジネスの目的を明確にし、関係者の認識を合わせることで、手戻りや失敗のリスクをなくします。
この記事では、要件定義の基本的な流れから必須項目、さらにはテンプレートの活用法まで、成功に必要な知識を解説しました。紹介したフレームワークやチェックリストを活用すれば、あなたもプロジェクトの軸となる、精度の高い要件定義書を作成できます。
しかし、多くの関係者の意見をまとめ、専門的な要件を抜け漏れなく作り上げるのは、決して簡単な作業ではありません。そんな時は、プロジェクト成功の確率を上げるための戦略として、専門家の力を借りるのも賢明な選択です。株式会社FlyEdgeでは100社以上の支援経験と自社の実戦経験をもとにした、施策の支援を受けたい方はぜひお問い合わせください。