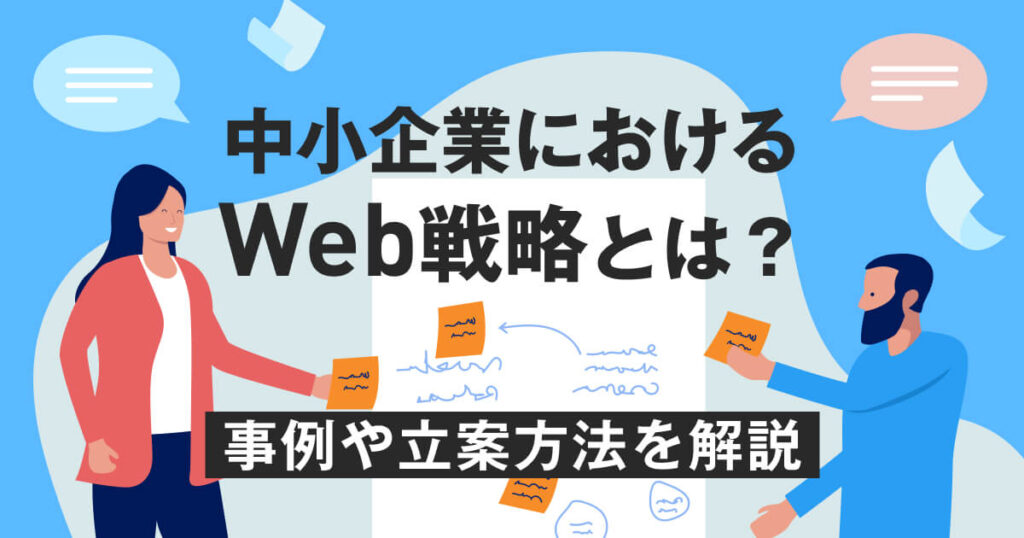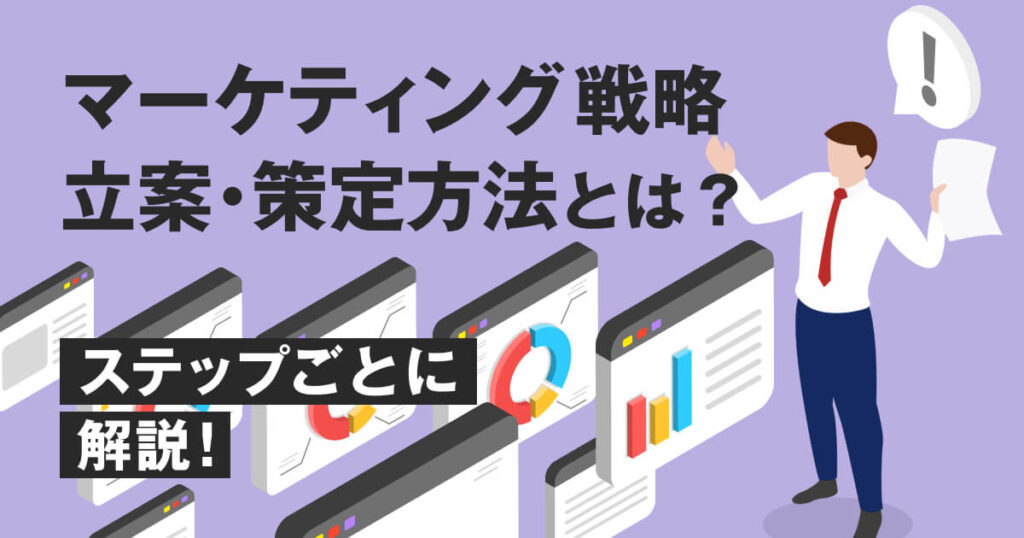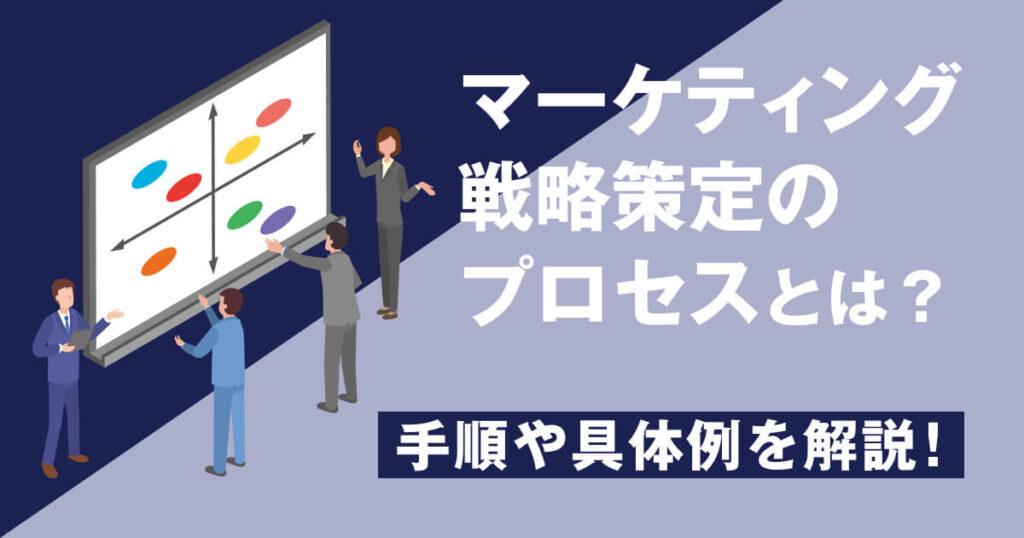多くの企業が憧れるディズニーのマーケティング戦略。なぜディズニーは、これほどまでに人々を魅了し、高い顧客満足度とリピート率を誇るのでしょうか。その秘密は、徹底して「体験価値」を追求する姿勢にあります。
本記事では、ディズニーの成功を支えるマーケティング戦略の全体像を、具体的なフレームワークを用いて分かりやすく解き明かします。7PやSTPといった基本的な考え方から、自社のビジネスに応用するためのヒントまで、詳しく見ていきましょう。
株式会社FlyEdgeでは、マーケティング関連にお悩みの方のお手伝いをしております。3,000回以上のコンサルティングで構築した、中小企業の勝ちパターンを活用したい方はぜひお問い合わせください。
ディズニーのマーケティング戦略とは(経営戦略と体験価値の関係)
定義と狙い
ディズニーのマーケティング戦略は、単なる商品販売や宣伝活動ではありません。すべての活動が「ハピネスの提供」という一貫した目的のために設計されています。ゲストがパークで過ごす時間や、映画・グッズに触れるすべての瞬間で、最高の体験価値を感じてもらうことが狙いです。感動的な体験が口コミを生み、再訪につながるという好循環を作り出す。これがディズニー戦略の核心部分といえます。
この戦略を支える基本的な考え方は、以下の通りです。
- 世界観の徹底: 現実を忘れさせるほど作り込まれた世界観で、ゲストを物語の主人公にします。
- 人材(キャスト)の役割: キャストは単なる従業員ではなく、世界観を体現し、ゲストの体験を豊かにする重要な存在です。
- 体験の拡張: パークだけでなく、映画、音楽、グッズ、オンラインなど、あらゆる接点で一貫した体験を提供します。
ディズニーの経営戦略
ディズニーの経営戦略は、マーケティング戦略と密接に結びついています。ただ楽しませるだけでなく、ビジネスとして成立させるための仕組みが考え抜かれています。特に重要な「世界観」「人材」「体験拡張」の3要素が相互に作用することで、他社には真似できない強力なブランドを築いています。長期的な視点でブランド価値を高め、安定した収益を生み出すことを目指しています。
経営戦略の要点を、以下の表に整理します。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 世界観 | 独自の物語やキャラクターを創造し、すべての事業で一貫した世界観を保ちます。これにより、強力なIP(知的財産)を育んでいます。 |
| 人材 | 「キャスト」と呼ばれる従業員への徹底した教育を行い、マニュアルを超えたおもてなし(ホスピタリティ)を実現。これが顧客満足度を高めます。 |
| 体験拡張 | パーク事業を中核としながら、メディア、スタジオ、商品ライセンスなど多角的に事業を展開。ファンとの接点を増やし、ブランドへの愛着を深めます。 |
ディズニー事例の俯瞰
ディズニーの事例を大まかに見ると、パーク体験が中心にあることが分かります。しかし、その体験はパーク内だけで完結するわけではありません。映画を見てキャラクターを好きになり、パークを訪れてその世界に浸る。
そしてお土産のグッズを家に持ち帰り、日常でもディズニーの世界観に触れる。複数の事業が連携して顧客との関係を深めていくのが特徴です。オンラインでの情報発信や、季節ごとのイベントも、顧客の期待感を高める重要な役割を担います。
自社転用のためのポイント
ディズニーの戦略を自社に活かすには、「顧客にどのような感情を抱いてほしいか」を明確にすることが重要です。高価な設備がなくても、顧客体験を高める工夫はできます。例えば、従業員の接客態度を見直したり、商品の梱包にひと工夫加えたりすることです。
大切なのは、自社ならではの「世界観」や「価値」を定義し、すべての企業活動で一貫性を持たせること。顧客とのあらゆる接点で、その価値を伝え続ける姿勢が、ファンを生み出します。
ディズニーのマーケティング戦略を理解する基本フレーム(3C/STP/4P・7P)
3C(市場・競合・自社)で前提を固める
3C分析は、マーケティング戦略を立てる上での基礎となる考え方です。市場(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの視点から現状を分析します。ディズニーはこの分析を徹底し、自社の立ち位置を明確にしています。
市場のニーズを正確に捉え、競合にはない独自の強みを把握する。そして、その強みを最大限に活かせる戦略を描くことで、エンターテイメント業界での圧倒的な地位を確立しました。
自社で3C分析を行う際の確認観点は、以下の通りです。
| 分析対象 | 主な確認観点 |
|---|---|
| 市場(Customer) | 顧客は誰か?市場の規模や成長性はどうか?顧客が本当に求めている価値は何か? |
| 競合(Competitor) | 競合はどこか?競合の強み・弱みは何か?競合が提供している価値は何か? |
| 自社(Company) | 自社の強み・弱みは何か?独自の技術やブランド力はあるか?経営資源は十分か? |
定義・狙い
3C分析の狙いは、外部環境(市場・競合)と内部環境(自社)を客観的に把握し、成功する可能性の高い事業領域を見つけ出すことです。市場にどのようなニーズがあり、競合がどのように動いているかを知る。
その上で、自社の強みを活かせる場所はどこかを探ります。この分析を通じて、戦略の方向性を定めるための土台を固めることが可能です。思い込みや感覚だけに頼らず、事実に基づいた意思決定をするために、3C分析は欠かせない工程です。
自社での確認観点
自社で3C分析を行う際は、具体的な情報を集めることが大切です。顧客アンケートや市場調査データから市場のニーズを調べます。競合のウェブサイトや商品・サービスを利用して、その特徴を分析するのもおすすめな手段です。
自社の強みについては、従業員へのヒアリングや顧客からのフィードバックが参考になります。調査で得られた情報を整理し、自社が「誰に」「何を」「どのように」提供すれば成功できるのか、その仮説を立てることが、次の手順につながっていきます。
STP(セグメンテーション/ターゲティング/ポジショニング)
STP分析は、市場を細分化し(Segmentation)、狙うべき市場を定め(Targeting)、その市場における自社の立ち位置を明確にする(Positioning)手法です。ディズニーは、このSTP分析を用いて、多様な顧客層に対して的確なアプローチを行っています。
「すべての人」を対象にするのではなく、特定のグループに狙いを定める。そして、そのグループにとって最も魅力的な存在になるための戦略を立てることで、効果的なマーケティングを実現しています。
セグメンテーション(市場細分化)を行う際の、代表的な設計の型は以下の通りです。
- 地理的変数: 国、地域、都市、気候などで市場を分ける考え方です。(例:国内ゲスト/海外ゲスト)
- 人口動態変数: 年齢、性別、家族構成、職業、所得などで分ける方法です。(例:ファミリー層/カップル層/学生グループ)
- 心理的変数: ライフスタイル、価値観、パーソナリティなどで分ける考え方です。(例:キャラクターの熱狂的なファン/雰囲気を楽しみたい層)
- 行動変数: 利用頻度、求めるベネフィット(便益)などで分ける方法です。(例:年に何度も来園するリピーター/初めて来園するゲスト)
セグメント設計の型
セグメントを設計する際には、いくつかの切り口を組み合わせて、より具体的な顧客像を描き出すことが重要です。例えば、「小さな子どもがいる30代のファミリー層(人口動態)」で、かつ「キャラクターとの触れ合いを重視している(行動変数)」といった形です。
市場を細かく分けることで、それぞれのグループのニーズに合わせた商品開発やコミュニケーションが可能です。自社の強みが、どのセグメントに最も響くのかを見極めること重要です。
ポジショニング仮説の立て方
ターゲットとするセグメントを決めたら、次にポジショニングの仮説を立てます。「競合と比べて、顧客の頭の中でどのような独自の立ち位置を築くか」を考える工程です。例えば、「価格」と「品質」の2軸でマップを作り、競合他社と自社の位置を書き出してみます。
ディズニーの場合、「価格は高いが、最高の体験品質を提供する」という明確なポジションを確立しています。自社のポジションを定めることで、伝えるべきメッセージやブランドイメージが明確になっていきます。
4P・7Pの全体像と役割分担
4Pとは、マーケティング戦略の具体的な実行計画である「マーケティングミックス」の代表的な要素です。Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販促)の4つの頭文字を取ったものです。ディズニーは、4つのPを巧みに組み合わせ、顧客に一貫したメッセージを届けています。
さらに、サービス業では、Personnel(人)、Process(プロセス)、Physical Evidence(物的証拠)の3つを加えた「7P」の考え方が重要です。
4Pから7Pへ拡張する意義は、以下の点にあります。
- サービスの品質向上: 従業員の質(Personnel)やサービスの提供手順(Process)が、顧客満足度に直結するためです。
- 無形の価値の可視化: サービスは形がないため、店舗の雰囲気や設備(Physical Evidence)が、その価値を伝える重要な手がかりとなります。
- 体験全体の設計: 7Pの視点を持つことで、顧客がサービスを認知し、利用し、終了するまでの一連の体験を設計できます。
4P→7P拡張の意義
形のある「モノ」を売る場合、4P(製品・価格・流通・販促)を中心に戦略を考えます。しかし、ディズニーランドのような「コト(体験)」を提供するサービス業では、それだけでは不十分です。サービスの品質は、提供する「人(Personnel)」のスキルや態度に大きく左右されます。
また、チケット購入からアトラクション体験までの「プロセス(Process)」がスムーズかどうかも満足度を決めます。そして、パークの景観や音楽といった「物的証拠(Physical Evidence)」が、世界観への没入感を高めます。7Pは体験価値を構成するすべての要素を網羅しているのです。
7Pとサービス体験の関係
7Pの各要素は、それぞれが独立しているのではなく、相互に連携して1つの優れたサービス体験を作り上げています。例えば、素晴らしいアトラクション(Product)があっても、キャスト(Personnel)の対応が悪ければ、ゲストの満足度は下がってしまうでしょう。
また、パーク内の美しい景観(Physical Evidence)は、長い待ち時間(Process)のストレスを和らげる効果があります。7Pのすべての要素に気を配り、一貫性を持たせることが、ディズニーのような感動的な体験を生み出す秘訣です。
ディズニーのマーケティング戦略のSTP
ターゲット層と体験設計の考え方
ディズニーは「すべての世代に夢と魔法を」という普遍的なテーマを掲げつつ、STP分析に基づいた緻密なターゲット設定を行っています。中心的なターゲットは子ども連れのファミリー層ですが、それ以外にもカップル、友人グループ、熱心なファンなど、多様な層を想定しています。
そしてそれぞれのターゲットが何を期待してパークを訪れるのかを深く理解し、その期待を超える体験を設計しています。これが、幅広い層から支持される理由です。
ターゲットごとのペルソナ(具体的な顧客像)と期待価値の例を、以下に示します。
- ペルソナ例1: 小さな子どもを持つ30代の夫婦
- 期待価値: 子どもの笑顔が見たい、家族の思い出を作りたい、日常を忘れてリフレッシュしたい。
- ペルソナ例2: 記念日を祝う20代のカップル
- 期待価値: ロマンチックな雰囲気の中で特別な時間を過ごしたい、SNS映えする写真を撮りたい。
- ペルソナ例3: キャラクターが好きな20代の女性グループ
- 期待価値: 大好きなキャラクターに会いたい、限定グッズを購入したい、友人と世界観に浸りたい。
ペルソナ例と期待価値
ペルソナを設定することで、顧客の解像度が高まります。例えば「30代の母親、田中さん」という具体的な人物像を思い描く。すると「ベビーカーでの移動はしやすいか」「授乳室はどこにあるか」といった、より細やかなニーズが見えてきます。
ディズニーは具体的なペルソナの視点に立ち、パーク内の施設やサービスを設計しています。レストランのメニュー構成からパレードのルートまで、すべてがターゲットの期待価値を最大化するために考え抜かれているのです。
価値提案マップの作り方
価値提案マップとは、顧客が何を望んでいるか(顧客の課題・欲求)と、自社が提供できる価値(製品・サービス)を整理し、両者を結びつけるためのツールです。はじめにターゲットとなるペルソナが「得たいこと」と「解決したい課題」を書き出します。
次に自社の製品やサービスが、どのようにしてそれらを実現できるかを考えます。このマップを作ることで、顧客のニーズと自社の強みが合致するポイント、つまり「独自の価値提案」が明確になります。
セグメント別の価値提案
ディズニーは、細分化したセグメント(顧客グループ)ごとに、異なる価値提案を行っています。例えば、ファミリー層にはキャラクターとのグリーティングや子ども向けのアトラクションをアピールします。
一方で大人だけのグループには、季節限定の食事やアルコールドリンク、夜のショーなど、落ち着いた楽しみ方を提案します。ターゲットに合わせて見せ方や体験の内容を調整することで、多様なニーズに応え、満足度を高めています。
各セグメントへの価値提案の方向性を、以下の表に整理します。
| セグメント | 価値提案の方向性 | 具体例 |
|---|---|---|
| ファミリー層 | 家族全員で楽しめる、安全・安心な空間 | ベビーカーのレンタル、身長制限の少ないアトラクション、キャラクターグリーティング |
| カップル層 | 非日常的でロマンチックな体験 | パーク内の高級レストラン、夜景が綺麗なスポット、記念日向けのサービス |
| ファン層 | より深く世界観に没入できる体験 | 季節ごとのイベント、キャラクターの背景を知れるショー、限定グッズの販売 |
ファミリー/カップル/ファン層などの方向性
ファミリー層が最も重視するのは「子どもの笑顔」です。そのため、ディズニーは子どもが主役になれるような体験を数多く用意しています。カップル層には、2人の特別な思い出作りをサポートするロマンチックな演出が響きます。
そして熱心なファン層に対しては、彼らの知識欲やコレクション欲を満たすような、よりマニアックな情報や商品を提供します。相手によって「響く言葉」や「嬉しい体験」は異なります。それぞれのセグメントに寄り添ったアプローチが重要です。
自社への転用ポイント
自社の顧客を、いくつかのセグメントに分けて考えてみましょう。「よく購入してくれる優良顧客」「新規の顧客」「しばらく離れている休眠顧客」など、様々な切り口があります。それぞれのセグメントが、自社の商品やサービスに何を期待しているかを分析します。
そしてセグメントごとにメールマガジンの内容を変えたり、特別なキャンペーンを案内したりするなど、アプローチを工夫することで、顧客との関係をより深めることができるはずです。
ディズニーのマーケティング戦略における7P実践(パーク/コンテンツ/ライセンス)
Product(商品・サービス)
ディズニーの「商品」は多岐にわたります。中核となるのはテーマパークでの体験ですが、それだけではありません。映画やアニメーションといった映像コンテンツ、キャラクターの権利を他社に貸し出すライセンス事業も大きな柱です。別々の事業に見えて、実は密接に連携しています。
映画のヒットがパークへの来場者を増やし、パークでの体験がグッズの購買意欲を高める。複数の商品が相乗効果を生み出し、ディズニー全体のブランド価値を高めているのです。
ディズニーの主な商品を、以下の3つに分けて整理します。
- パーク: 東京ディズニーランドやディズニーシーなど、テーマパークで提供される非日常的な体験そのものが商品です。
- コンテンツ: ミッキーマウスなどのキャラクター、アナと雪の女王といった映画やアニメ作品、音楽などが含まれます。
- ライセンス: キャラクターや作品を使用する権利を他社に提供し、食品、玩具、アパレルなど、様々な商品が作られます。
パーク/コンテンツ/ライセンスの切り分け
「パーク」は、ディズニーの世界観を五感で体験できる最も重要な場所です。ここで得られる感動が、ブランドへの強い愛着を育みます。「コンテンツ」は、物語を通じてキャラクターに命を吹き込み、ファンを創造する役割を担います。
そして「ライセンス」は、ディズニーブランドとの接点を日常生活の中にまで広げます。スーパーマーケットでキャラクターのパッケージを見ることで、パークや映画を思い出す。異なる事業が連携し、顧客との関係を常に保ち続けているのです。
キャラクターマーケティングの成功要点
ディズニーのキャラクターマーケティングが成功している理由は、キャラクターにしっかりとした「物語」と「個性」があるからです。ミッキーマウスには、いつも前向きで友達思いという性格があります。こうした個性が、人々に共感や親近感を抱かせます。
またキャラクターを大切に扱い、イメージを損なうような使い方を決して許可しません。この一貫したブランド管理が、キャラクターの価値を長期的に維持し、世代を超えて愛される存在にしているのです。
自社に転用する手順
自社の商品やサービスに、何か「物語」を付加できないか考えてみましょう。例えば、商品の開発秘話や、創業者の想いなどを顧客に伝えることです。また会社のロゴやマスコットキャラクターに、一貫した個性やストーリーを持たせるのもおすすめです。
ただのモノとして売るのではなく、背景にある物語や想いを伝えることで、顧客は感情的なつながりを感じ、ファンになってくれる可能性が高まります。ブランドに個性を与えることが、他社との差別化につながります。
Price(価格)
ディズニーの価格戦略は、単にコストを積み上げて決めているわけではありません。提供する「体験価値」に見合った価格設定が基本です。パークチケットは決して安くありませんが、多くの人がその価格に納得して支払います。
それは、価格以上の特別な体験ができると期待しているからです。また、季節や曜日によって価格を変動させる「ダイナミックプライシング」を導入し、需要の平準化を図っています。これにより、混雑を緩和し、ゲスト1人ひとりの満足度を高める狙いがあります。
ディズニーの価格設計における考え方を、以下にまとめます。
- 価値に基づいた価格設定: 提供する独自の体験価値を基準に、自信を持った価格を設定します。
- 需要に応じた変動価格: 混雑が予想される日は価格を高く、閑散期は安くすることで、来場者数をコントロールします。
- 多様な選択肢の提供: パークチケット以外にも、食事やグッズ、有料の体験プログラムなど、ゲストが予算に応じて楽しめる選択肢を用意しています。
価格設計の考え方と段階設計
ディズニーの価格は、周到に設計されています。例えば、1デーパスポートだけでなく、複数日利用できるチケットや、夕方から入園できるチケットも用意されています。これにより、ゲストは自身の滞在時間や予算に合わせて、最適な選択ができます。
またパーク内のレストランも、手軽なカウンターサービスから、特別な日に利用したい高級レストランまで様々です。このように、価格帯に幅を持たせることで、より多くの顧客層を取り込むことが可能です。
需要変動とバンドルの考え方
「バンドル」とは、複数の商品やサービスを組み合わせて、セットで販売する手法です。ディズニーでは、ホテル宿泊とパークチケット、オリジナルグッズなどを組み合わせた「バケーションパッケージ」がこれにあたります。
セットにすることで、1つひとつを個別に購入するよりもお得感が出たり、特別な体験ができたりといった付加価値が生まれます。こうしたパッケージ商品は、顧客単価の向上に貢献するだけでなく、顧客に滞在全体の計画を提案し、満足度を高める効果も期待できます。
Place(流通・提供チャネル)
ディズニーにおける「Place」とは、ゲストがディズニーの世界観に触れるすべての場所や機会を指します。最も重要なチャネルは、もちろんテーマパークそのものです。しかし、それだけではありません。
公式ウェブサイトやアプリ、ディズニーストア、さらにはテレビCMやSNSも、ゲストをパークへと誘う重要な導線です。ディズニーは、複数のチャネルを通じて一貫したメッセージを発信し、ゲストの期待感を高めています。パーク内においても、ゲストが快適に過ごせるよう、導線が工夫されています。
ディズニーの主な提供チャネルについて、以下にまとめます。
- テーマパーク: ディズニー体験の中核となる物理的な場所です。
- 公式ウェブサイト/アプリ: チケット購入、情報収集、パーク体験の補助など、来園前から来園後までゲストをサポートします。
- ディズニーストア: パーク外でディズニーの世界観に触れ、グッズを購入できるリアル店舗です。
- オンラインメディア: SNSや動画サイトを通じて、最新情報や魅力を発信し、ファンとのコミュニケーションを図ります。
来園導線と購買導線
来園導線とは、ゲストがパークを訪れるまでの一連の流れです。ディズニーは、テレビCMで興味を惹き、ウェブサイトで詳細情報を提供し、アプリで簡単にチケットを購入できるようにするなど、スムーズな来園を促す仕組みを整えています。
一方、購買導線は、パーク内でゲストがグッズや食事を購入するまでの流れを指します。アトラクションの出口にグッズショップを配置したり、魅力的なポップコーンバケットを販売したりと、自然に購買意欲が湧くような工夫が随所に見られます。
オンライン接点の活用
近年、オンラインでの接点はますます重要になっています。ディズニーの公式アプリは、単なるチケット購入ツールではありません。パークのマップ機能、アトラクションの待ち時間表示、ショーの抽選申し込みなど、パーク内での体験をより豊かにする機能が満載です。
これによりゲストはスマートフォンを片手に、効率よくパークを楽しむことができます。またSNSでは、パークの美しい写真や動画を積極的に発信し、ゲストによる投稿(UGC)を促すことで、魅力を拡散させています。
Promotion(販売促進)
ディズニーのプロモーション戦略は、大規模な広告キャンペーンだけでなく、ゲスト自身が「伝えたい」と思えるような仕組み作りに長けています。季節ごとのスペシャルイベントや新しいアトラクションのオープンは、大きな話題を呼び、メディアにも頻繁に取り上げられます。
さらにSNSでの「写真映え」を意識したフードメニューやフォトスポットを用意することで、ゲストによる情報発信を促します。こうした口コミの連鎖が、何よりの宣伝効果を生んでいるのです。
プロモーションにおける主な手法を、以下にまとめます。
- イベントの活用: ハロウィーンやクリスマスなど、季節感あふれるイベントでリピーターを惹きつけます。
- メディアミックス: 映画、テレビ、雑誌、ウェブなど、複数のメディアを連動させて、情報を多角的に届けます。
- UGC(ユーザー生成コンテンツ)の促進: ゲストが自ら発信したくなるような体験や仕掛けを用意し、口コミを広げます。
話題化の仕組みとUGC連動
ディズニーが新しいイベントを始めると、多くのゲストがその様子をSNSに投稿します。これは、偶然起きているわけではありません。限定のフードメニューや、キャラクターがデザインされたカチューシャなど、思わず写真に撮って誰かに見せたくなるような要素が計画的に用意されています。
ゲストが投稿した楽しそうな写真や感想(UGC)は、それを見た他の人の「行ってみたい」という気持ちを刺激します。企業からの宣伝よりも、友人や知人の口コミの方が信頼されやすいという点を巧みに活用しているのです。
メディアミックスの整理
メディアミックスとは、1つのコンテンツ(例えば新作映画)を、様々なメディアで展開していく手法です。映画が公開されると、関連するテレビ番組が放送され、キャラクターグッズが販売され、テーマパークではスペシャルイベントが開催されます。
複数のメディアで同時に情報を発信することで、社会全体での認知度を一気に高め、大きなムーブメントを創り出します。それぞれのメディアの特性を活かし、連携させることで、相乗効果を最大化しているのがディズニーの強みです。
Personnel(人・要員)
ディズニーの魔法を支えているのは、精巧なアトラクションや美しい景観だけではありません。「キャスト」と呼ばれる従業員の存在が不可欠です。彼らは、清掃係であれ、アトラクションの案内係であれ、全員が「ハピネスを提供する」という共通の目的を持っています。
徹底された研修により、ディズニーの世界観を深く理解し、マニュアル通りの対応だけでなく、ゲスト1人ひとりに合わせたおもてなしを実践します。このキャストの力が、忘れられない感動的な体験を生み出しているのです。
人材育成と体験の標準化に関する要点は、以下の通りです。
- 行動規準「SCSE」: 安全(Safety)、礼儀(Courtesy)、ショー(Show)、効率(Efficiency)という優先順位が全キャストに共有されています。
- 徹底した研修: ディズニーの理念や歴史、行動基準を学ぶ研修を通じて、キャストとしての誇りと使命感を育みます。
- 権限移譲: 現場のキャストにある程度の裁量権が与えられており、マニュアルにない状況でも、ゲストのために最善の判断を下すことが奨励されます。
人材育成と現場体験の標準化
ディズニーでは、すべてのキャストが「SCSE」という行動基準を徹底して学びます。これは、Safety(安全)、Courtesy(礼儀正しさ)、Show(ショー)、Efficiency(効率)の頭文字を取ったもので、行動する際の優先順位を示しています。
何よりもゲストの安全を確保し、次に丁寧な対応を心がける。そして自らもショーの一部であるという意識を持ち、最後に効率を考える。この共通の価値観があるからこそ、どのキャストに接しても、一定水準以上の質の高いサービスが提供されるのです。
Process(提供プロセス)
ディズニーは、ゲストがパークで過ごす体験の「プロセス」全体を設計しています。その目的は、ゲストがストレスを感じる要因を可能な限り取り除き、楽しい時間に集中できるようにすることです。特に注力しているのが、混雑や待ち時間の緩和です。
アトラクションの待ち時間をアプリでリアルタイムに確認できるようにしたり、予約システムを導入したりすることで、限られた時間を有効に使えるようサポートしています。快適な体験プロセスが、高い顧客満足度につながっています。
待ち時間を最小化するための設計について、以下にまとめます。
- 待ち時間表示: 公式アプリやパーク内の掲示板で、各アトラクションの待ち時間をリアルタイムに提供します。
- スタンバイパス/プライオリティパス: 人気アトラクションの体験時間を予約できるシステムを導入し、長時間の行列を避ける選択肢を用意します。
- キューライン(待機列)の工夫: ただ並ぶだけでなく、物語に関連する装飾や映像を用意し、待ち時間そのものを楽しめるように演出しています。
混雑・待ち時間の最小化設計
テーマパークの大きな課題である「待ち時間」。ディズニーは、この課題を解決するために様々な工夫を凝らしています。待ち時間を事前に予測し、運営体制を調整するのはもちろんのこと、ゲストが待っている間も退屈しないような演出を加えています。
例えば人気アトラクションの待機列(キューライン)は、物語の世界観に浸れるような装飾が施されています。これにより、長い待ち時間もアトラクションの一部として楽しむことができ、体感的なストレスを軽減する効果があります。
Physical Evidence(物的証拠)
Physical Evidence(物的証拠)とは、サービスの品質を形として示す、目に見えるすべての要素を指します。ディズニーランドでは、パークに足を踏み入れた瞬間から、この物的証拠に圧倒されます。
シンデレラ城のような象徴的な建物、手入れの行き届いた草花、ゴミ1つ落ちていない清潔な道、そして流れる音楽など、すべてが現実世界とは異なる「夢と魔法の王国」という世界観を支えています。ゲストは、様々な物的証拠に囲まれることで、物語の中にいるかのような没入感を味わうことができます。
世界観を支える主な要素は、以下の通りです。
- 建築物・景観: パーク内の建物や装飾は、細部に至るまでテーマに沿って作り込まれています。
- 清掃・メンテナンス: 常に清潔で美しい環境を保つことで、非日常的な空間の質を維持します。
- グッズ・フード: パーク内で販売される商品も、世界観を構成する重要な一部であり、体験の記念品となります。
- キャストのコスチューム: キャストが身に着ける衣装も、それぞれのエリアの雰囲気に合わせてデザインされています。
世界観を支える環境・演出・グッズ
ディズニーの世界観は、細部へのこだわりによって支えられています。例えば、エリアごとにゴミ箱のデザインが異なったり、BGMが変わったりします。これは、それぞれのエリアのテーマに合わせた演出です。また、パーク内で販売されているグッズも、ただのお土産ではありません。
キャラクターのカチューシャを身に着ければ、ゲスト自身がパークの景観の一部となります。ポップコーンバケットは、食べ終わった後も記念品として持ち帰れます。このように、すべてのモノが体験を豊かにするための小道具として機能しているのです。
ディズニーのカスタマージャーニーとコミュニケーション
認知→興味→来園→体験→共有の設計
ディズニーは、ゲストがパークの存在を知り(認知)、興味を持ち、実際に訪れ(来園)、パークで楽しみ(体験)、その感動を誰かと分かち合う(共有)までの一連の流れ(カスタマージャーニー)を設計しています。各段階で、ゲストの気持ちに寄り添った最適なコミュニケーションを行います。
テレビCMやSNSで「楽しそう」という興味を喚起し、公式ウェブサイトで詳しい情報を提供します。来園後は、感動的な体験を通じて「また来たい」「誰かに伝えたい」という気持ちを育むのです。
カスタマージャーニーの各段階でのタッチポイント(顧客接点)を、以下の表に整理します。
| 段階 | 主なタッチポイント(顧客接点) |
|---|---|
| 認知 | テレビCM、映画、雑誌広告 |
| 興味・関心 | 公式ウェブサイト、SNSアカウント、情報番組の特集 |
| 来園(検討・購入) | 公式アプリ、旅行代理店、ディズニーストア |
| 体験 | パーク内のアトラクション、ショー、キャストとの交流 |
| 共有 | SNSへの投稿、友人や家族との会話、口コミサイトへの書き込み |
タッチポイント整理
タッチポイントとは、顧客が企業やブランドと接する機会のことです。ディズニーは、オンラインからオフラインまで、多くのタッチポイントを持っています。重要なのは、どのタッチポイントにおいても「ディズニーらしい」一貫した世界観や価値観が伝わるように管理されていることです。
例えば公式ウェブサイトのデザインや言葉遣いも、パークの世界観を壊さないように配慮されています。これにより、ゲストはどの接点でも安心してディズニーの世界に浸ることができるのです。
メッセージ設計の原則
ディズニーが発信するメッセージは、常にポジティブで、夢や希望を感じさせるものです。「ハピネスの提供」という企業理念が、すべてのコミュニケーションの根底にあります。広告では、単にアトラクションのスペックを伝えるのではなく、ゲストが楽しんでいる笑顔や感動の瞬間を切り取って見せます。
これにより、視聴者は「自分もあんな体験をしてみたい」という感情的な共感を覚えるのです。事実を伝えるだけでなく、感情に訴えかけるメッセージ設計が、人々の心を動かします。
UGC・口コミ・コミュニティの活用
UGC(User Generated Content)とは、一般のユーザーによって作られたコンテンツのことで、SNSへの投稿や口コミサイトのレビューなどがこれにあたります。ディズニーは、このUGCが強力な宣伝効果を持つことを理解しています。
そのためゲストが思わず写真や動画を撮り、SNSで共有したくなるような仕掛けをパークの随所に用意しています。友人や知人からの「楽しかった」という口コミは、どんな広告よりも信頼性が高く、新たな来園のきっかけとなります。
UGCを促進するための施策とガイドラインには、以下のようなものがあります。
- フォトジェニックな仕掛け: SNS映えするフードメニュー、美しい景色、キャラクターとの写真撮影機会などを提供します。
- ハッシュタグの活用: 公式のハッシュタグを用意し、ゲストが投稿する際に利用するよう促します。これにより、関連する投稿をまとめやすくなります。
- コミュニティの育成: 熱心なファンが集うオンラインコミュニティなどを通じて、ブランドへの愛着を深め、情報交換を活発化させます。
促進施策とガイドライン
ディズニーは、UGCを増やすために、積極的にゲストの投稿を後押ししています。例えば、公式SNSアカウントが、ゲストの素敵な投稿を紹介することがあります。自分の写真が公式に認められることは、ファンにとって大きな喜びであり、さらなる投稿の動機付けになります。
一方でキャラクターのイメージを損なうような不適切な投稿や、他のゲストの迷惑になるような撮影行為に対しては、ルールを設けるなど、ブランドイメージを守るためのガイドラインも重要です。
ディズニーのロイヤルティ設計とKPI
リピートを生む仕組み(CRM/会員施策)
一度訪れたゲストに、なぜ「また来たい」と思わせることができるのでしょうか。その秘密は、感動的な体験そのものに加えて、顧客との継続的な関係を築く仕組み(CRM: Customer Relationship Management)にあります。
ディズニーは、会員プログラムや公式アプリを通じて顧客情報を管理し、1人ひとりに合わせた情報を提供しています。例えば過去の来園履歴や好みに合わせて、おすすめのイベント情報を配信する。こうした細やかなアプローチが、顧客の「特別感」を高め、再来園へとつなげています。
会員プログラムを設計する際の主な要素を、以下の表にまとめます。
| 設計要素 | 内容 |
|---|---|
| 会員ランク | 利用頻度や購入金額に応じてランクを設定し、上位ランクには特別な特典を用意します。 |
| ポイントプログラム | 利用金額に応じてポイントが貯まり、景品交換や割引に使える仕組みです。 |
| 限定コンテンツ | 会員だけが閲覧できる特別な情報や、先行予約などの権利を提供します。 |
| パーソナライズ | 誕生日メッセージの配信や、興味に合わせた情報の提供など、個別のアプローチを行います。 |
会員プログラムの設計要素
優れた会員プログラムは、単なる値引きサービスではありません。顧客が「会員でいてよかった」と感じられるような、特別な価値を提供することが重要です。
ディズニーのファンクラブ「ファンダフル・ディズニー」では、会員限定のグッズ販売や、パークチケットの割引、会報誌の発行など、ファン心理をくすぐる様々な特典が用意されています。こうした施策を通じて、ブランドへの愛着(ロイヤルティ)を育み、長期的なファンを育成しているのです。
満足度・推奨指標(NPS/CSAT等)の使い方
ディズニーは、ゲストの満足度を重視しています。その満足度を測るために、NPS(Net Promoter Score)やCSAT(Customer Satisfaction Score)といった指標を用いています。NPSは「このパークを友人や知人にどの程度すすめたいですか?」という質問を通じて、顧客のロイヤルティを測る指標です。
CSATは、特定のアトラクションやレストランなど、個別のサービスに対する満足度を尋ねるものです。NPSやCSATを定期的に計測し、改善点を見つけ出すことで、サービスの質を常に高いレベルに保っています。
目標設定と改善サイクルの要点は、以下の通りです。
- 定期的な計測: アンケートなどを通じて、定期的かつ継続的に顧客満足度をデータとして収集します。
- 目標値の設定: 収集したデータに基づき、達成すべき具体的な目標値を設定します。(例:NPSを前期比で5ポイント向上させる)
- 課題の分析と改善: 目標を達成できなかった場合、その原因を分析し、具体的な改善策を立案・実行します。
- 効果測定: 実施した改善策が、満足度の向上につながったかを再度計測し、評価します。このサイクルを繰り返します。
目標設定と改善サイクル
ただ数値を測るだけでは意味がありません。大切なのは、その数値をもとに具体的な改善活動につなげることです。例えば、あるレストランのCSATが低いという結果が出たとします。その原因が「料理の味」なのか、「提供スピード」なのか、「キャストの接客態度」なのかをさらに詳しく調べます。
そして原因に応じた改善策(メニューの見直しや、オペレーションの改善など)を実行します。この「計測→分析→改善→再計測」というサイクルを回し続けることが、サービス品質の継続的な向上につながります。
ディズニーのビジネスモデル(収益構造と指標)
体験価値と収益化の関係
ディズニーのビジネスモデルの根幹は、「優れた体験価値が収益を生む」という考え方です。ゲストがパークで過ごす時間に心から満足すれば、自然とグッズを購入したり、レストランで食事をしたりします。また、「楽しかった」という思い出は、「また来たい」という再来園の意欲につながります。
つまり目先の利益を追うのではなく、まずは最高の体験を提供することに全力を注ぐ。その結果として、長期的に安定した収益がもたらされるという好循環が生まれているのです。
体験価値と収益化の関係について、主なポイントは以下の通りです。
- 顧客満足度の向上: 高い満足度は、滞在時間の延長や消費金額の増加につながります。
- リピート率の向上: 感動的な体験は、再来園の最も強い動機となります。
- 口コミによる新規顧客獲得: 満足した顧客が良い口コミを広めることで、広告費をかけずに新しい顧客を呼び込めます。
- ブランド価値の向上: 優れた体験はブランドイメージを高め、ライセンス事業など他の収益源にも良い影響を与えます。
客単価・稼働率の考え方
テーマパークの収益を考える上で重要な指標が「客単価」と「稼働率(入場者数)」です。ディズニーは、この両方を高めるための戦略を巧みに実行しています。客単価を高めるためには、魅力的なグッズやフードメニューを開発し、購買意欲を刺激します。
一方、稼働率を高めるためには、季節ごとのイベントでリピーターを惹きつけたり、変動価格制で需要を平準化したりします。客単価と稼働率をバランス良く追求することが、収益の最大化につながります。
周辺収益(グッズ・飲食・ライセンス・配信)
ディズニーの収益源は、パークの入場料だけではありません。グッズ販売や飲食、ホテル事業といった「周辺収益」が大きな割合を占めています。パーク内でしか手に入らない限定グッズは、来園の動機にもなります。
また映画やキャラクターの権利を他社に提供する「ライセンス事業」や、公式動画配信サービス「ディズニープラス」も、安定した収益を生み出す重要な柱です。このように、多様な収益源を持つことで、安定した経営基盤を築いています。
複数の事業が相互に利益をもたらす「交差収益」の仕組みを、以下の表に整理します。
| 中心となる事業 | 周辺収益を生み出す事業 | 仕組み |
|---|---|---|
| 映画コンテンツ | パーク事業、グッズ販売 | 映画がヒットすると、関連するアトラクションやグッズへの関心が高まり、売上が増加します。 |
| パーク事業 | ホテル事業、飲食事業 | パークへの来園者が、併設されたホテルに宿泊したり、レストランで食事をしたりします。 |
| キャラクター(IP) | ライセンス事業、ゲーム事業 | 人気キャラクターの使用権を他社に提供し、ロイヤリティ収入を得ます。 |
交差収益の仕組み
交差収益(クロスセル)とは、ある商品やサービスをきっかけに、別の商品やサービスの購入を促す仕組みです。ディズニーは、この仕組み作りが巧みです。例えば、映画『アナと雪の女王』がヒットすれば、パークに映画の世界を再現したエリアが作られ、多くのファンが訪れます。
そしてそのエリアでは限定グッズが販売され、さらなる収益を生みます。このように、1つのコンテンツが様々な事業に波及し、グループ全体の利益を押し上げる構造になっているのです。
事業ポートフォリオの整理
ディズニーは、テーマパーク事業を中心にしながらも、メディア・ネットワーク(テレビ局など)、スタジオ・エンターテイメント(映画製作)、ダイレクト・トゥ・コンシューマ&インターナショナル(動画配信など)といった、複数の事業の柱を持っています。この事業の多角化を「事業ポートフォリオ」と呼びます。特定の事業が不調な時でも、他の事業が好調であれば、会社全体としてのリスクを分散させることができます。バランスの取れたポートフォリオを組むことが、長期的な安定成長には不可欠です。
事業ポートフォリオにおける主な考え方は、以下の通りです。
- リスク分散: 特定の市場や事業への依存度を下げ、経営環境の変化に対応しやすくします。
- 相乗効果(シナジー): 異なる事業が連携することで、1+1が2以上になるような新たな価値や収益機会を創出します。
- 資源の最適配分: 各事業の成長性や収益性を見極め、経営資源(ヒト・モノ・カネ)を効果的に投資します。
リスク分散と投資配分の考え方
すべての事業が常に好調とは限りません。例えば、社会情勢の変化によって、テーマパークへの来場者数が一時的に減少するリスクがあります。そのような時でも、動画配信サービスのような在宅で楽しめる事業が成長していれば、会社全体の収益の落ち込みをカバーできます。
ディズニーは各事業の将来性や市場環境を常に分析し、どの事業に重点的に投資すべきかを判断しています。成長が見込まれる分野には積極的に投資し、成熟した分野では安定した収益を確保するなど、メリハリのある投資配分を行っています。
ディズニーの強み・弱みと差別化戦略
強み(世界観・人材・プロセス・IP運用)
ディズニーの最大の強みは、他社が容易に模倣できない独自の価値を持っている点です。その源泉となっているのが、長年にわたって築き上げてきた強力なブランド力です。
ディズニーの主な強みは、以下の通りです。
- 圧倒的な世界観: 細部までこだわり抜いて作られた、非日常的な空間を創出する力。
- 優れた人材(キャスト): 高いホスピタリティ精神を持ち、世界観を体現する従業員。
- 洗練された運営プロセス: ゲストのストレスを最小限にし、快適な体験を提供するノウハウ。
- 強力なIP(知的財産): ミッキーマウスをはじめとする、世代を超えて愛される数多くのキャラクターや物語。
弱み・リスク(課題になり得る論点)
圧倒的な強さを誇るディズニーですが、事業を続ける上での課題やリスクも存在します。常に最高の体験を提供し続けるためには、莫大なコストがかかります。
考えられる弱みやリスクは、以下の通りです。
- 高いコスト構造: 世界観の維持や高いサービス水準の確保には、多額の投資と人件費が必要です。これが価格に反映され、高価格化につながる可能性があります。
- 外部環境への依存: 景気の変動や自然災害、国際情勢など、自社でコントロールできない外部の要因によって、来場者数が大きく影響を受けるリスクがあります。
- ブランドイメージ維持の難しさ: 従業員の不祥事や事故など、1つの問題が大きなブランドイメージの低下につながる可能性があります。
持続的差別化の要点
ディズニーの強みは、1つの要素だけが優れているのではなく、複数の要素が複雑に絡み合って成り立っている点にあります。だからこそ、競合他社が簡単に真似をすることができません。
持続的に差別化を図るための要点は、以下の通りです。
- 文化の醸成: 「ハピネスの提供」という理念が、組織の末端まで浸透している企業文化そのものが強みです。
- 継続的な投資: 新しいアトラクションやコンテンツの開発に常に投資し、ゲストを飽きさせない努力を続けています。
- ブランドへの一貫性: どの事業、どのサービスにおいても、ディズニーブランドとしての品質と世界観が一貫して保たれています。
ディズニーのマーケティング戦略から学ぶ実務への落とし込み手順
3C/STP→7Pへのブリッジ
ディズニーの戦略を自社に応用するには、学んだフレームワークを順番に実践していくのがおすすめです。はじめに、3C分析で自社の現状を客観的に把握します。次に、STP分析で「誰に」「どのような価値を」提供するのか、事業の方向性を定めます。
そしてその方向性を実現するための具体的な実行計画として、7Pの各要素を設計していきます。この一連の流れを意識することで、戦略に一貫性が生まれ、成功の確率が高まります。
自社の現状を診断するためのワークシート項目を、以下の表に例示します。
| フレームワーク | 主な診断項目 |
|---|---|
| 3C分析 | ・私たちの顧客は誰で、何を求めているか?<br>・競合他社の強みと弱みは何か?<br>・私たち独自の強みは何か? |
| STP分析 | ・市場をどのように分類できるか?<br>・最も魅力的なターゲット顧客はどこか?<br>・競合と比べて、どのような立ち位置を目指すか? |
| 7P分析 | ・私たちの商品(Product)は顧客の課題を解決しているか?<br>・価格(Price)は提供価値に見合っているか?<br>・顧客との接点(Place)は最適か? など |
自社診断のワークシート
はじめに、自社の状況を整理するための簡単なワークシートを作ってみましょう。項目は「市場・顧客」「競合」「自社」の3つです。それぞれの項目について、現在分かっていることや課題だと感じていることを書き出します。
例えば「顧客からは価格が高いと言われることが多い」「競合はウェブサイトでの情報発信が上手い」「自社の強みは、地域に密着した丁寧なサポートだ」といった形です。この作業を通じて、自社の立ち位置を客観的に見つめ直すことら始めましょう。
設計図の作成(体験価値→収益モデル)
次に、自社が提供したい「体験価値」と、それをどう「収益」につなげるかの設計図を描きます。理想の顧客体験とはどのようなものか、顧客が自社の商品やサービスに触れる前から、利用した後までの一連の流れを想像してみます。
そしてその体験のどの部分で、どのように対価をいただくのかを考えます。例えば、無料のサンプルで商品の良さを体験してもらい、その後の本製品購入につなげる、といったモデルです。顧客の満足と事業の収益が両立する仕組みを作ることが重要です。
設計図を作成する際の要点は、以下の通りです。
- 理想の顧客体験の言語化: 顧客に「こう感じてほしい」という感情や状態を、具体的な言葉で定義します。
- 収益ポイントの明確化: どこで、どのようにして売上を上げるのか、その仕組みを具体的に設計します。
- 重要業績評価指標(KPI)の設定: 設計したモデルが上手くいっているかを判断するための、具体的な数値目標を設定します。
- 行動計画(ロードマップ)の策定: 目標達成のために、「いつまでに」「誰が」「何を」実行するのかを計画します。
重要KPIとロードマップ
設計図が描けたら、それを具体的な目標と計画に落とし込みます。KPI(重要業績評価指標)とは、目標の達成度合いを測るための「ものさし」です。例えば、「ウェブサイトからの問い合わせ件数を月20件にする」といった、具体的な数値目標を設定します。
そしてそのKPIを達成するための行動計画(ロードマップ)を作成します。「第1週はウェブサイトのデザインを改善する」「第2週はブログ記事を3本公開する」など、具体的なタスクと期限を決めることで、計画の実行力が高まります。
実行と改善(小さく試す→拡張)
完璧な計画を立ててからでないと動けない、と考えてしまうと、いつまでたっても実行できません。まずは「小さく試してみる」という姿勢が大切です。例えば、新しいサービスを始める際に、いきなり大規模な投資をするのではなく、一部の顧客に限定して提供してみる。
そこで得られた意見や反応をもとに改善を加え、少しずつ提供範囲を広げていくのです。この「実行→検証→改善」のサイクル(PDCAサイクル)を素早く回していくことが、変化の速い時代で成功するために必要です。
実行と改善のサイクルを進めるための要点は、以下の通りです。
- テストマーケティング: 本格展開の前に、小規模な市場や限定した顧客層で、商品やサービスの反応を試します。
- 顧客からのフィードバック収集: アンケートやインタビューなどを通じて、顧客の生の声を積極的に集めます。
- データに基づいた意思決定: 感覚だけでなく、売上データやウェブサイトのアクセス解析などの客観的なデータをもとに、次の行動を判断します。
ディズニーのマーケティング戦略に関するFAQ
価格戦略は他社に転用できるか
ディズニーの価格戦略の根底にあるのは、「提供する価値に見合った価格」という考え方です。この本質的な部分は、どのような業種の企業でも参考にできます。
転用する際のポイントは、以下の通りです。
- 自社の提供価値を明確にする: 自社の商品やサービスが顧客にどのような独自の価値を提供しているのかを、自信を持って説明できるようにします。
- 価値を顧客に伝える努力: なぜその価格なのか、理由を丁寧に説明することが重要です。品質へのこだわりや、他社にはないサポート体制などを伝え、価格への納得感を高めます。
- 価格帯の多様化: すべての顧客に同じ価格を提示するのではなく、松竹梅のように複数の価格プランを用意することで、より多くの顧客層にアプローチできます。
中小企業が真似すべき最小セットは何か
ディズニーの戦略すべてを真似することは、規模の観点から現実的ではありません。しかし、その考え方のエッセンスを取り入れることは可能です。
中小企業が取り組むべきことは、以下の通りです。
- 顧客理解の徹底: 自社にとって最も大切な顧客は誰なのかを定義し、その顧客が本当に求めていることを深く理解することから始めます。
- 独自の「世界観」作り: 企業理念や商品への想いを、一貫したメッセージとして顧客に伝え続けることです。ウェブサイトのデザインや、従業員の言葉遣いなど、できるところから統一感を持たせます。
- 従業員満足度の向上: 従業員が自社の仕事に誇りを持ち、楽しく働ける環境を作ることが、結果的に顧客への良いサービスにつながります。
KPIは何から追うべきか
KPI(重要業績評価指標)は、事業の目的によって設定すべきものが異なります。しかし、多くのビジネスで共通して重要となる基本的な指標から始めるのが良いでしょう。
最初に追うべきKPIの例は、以下の通りです。
- 売上: ビジネスの基本であり、最も重要な指標です。
- 顧客数・客単価: 売上を分解した指標です。売上が伸び悩んでいる時、顧客数が足りないのか、客単価が低いのか、原因を分析できます。
- リピート率: 既存の顧客が、どれだけ再購入してくれているかを示す指標です。リピート率の高さは、顧客満足度の高さと事業の安定性につながります。まずはこの指標を計測し、改善することから始めるのがおすすめです。
まとめ
ディズニーのマーケティング戦略の核心は、徹底した顧客目線と、それに基づいた「体験価値」の創造にあります。3CやSTP、7Pといったフレームワークは、その戦略を支えるための強力な道具です。
しかし最も重要なのは、企業として「顧客にどうなってほしいのか」という揺るぎない理念を持つことかもしれません。本記事で紹介した考え方や手法をヒントに、ぜひ自社のマーケティング戦略を見つめ直し、顧客に愛されるビジネスを築くきっかけにしてみてください。
もしマーケティング関連でお悩みなら、株式会社FlyEdgeにお問い合わせください。3,000回以上のコンサルティングで構築した、中小企業の勝ちパターンを活用してお手伝いいたします。