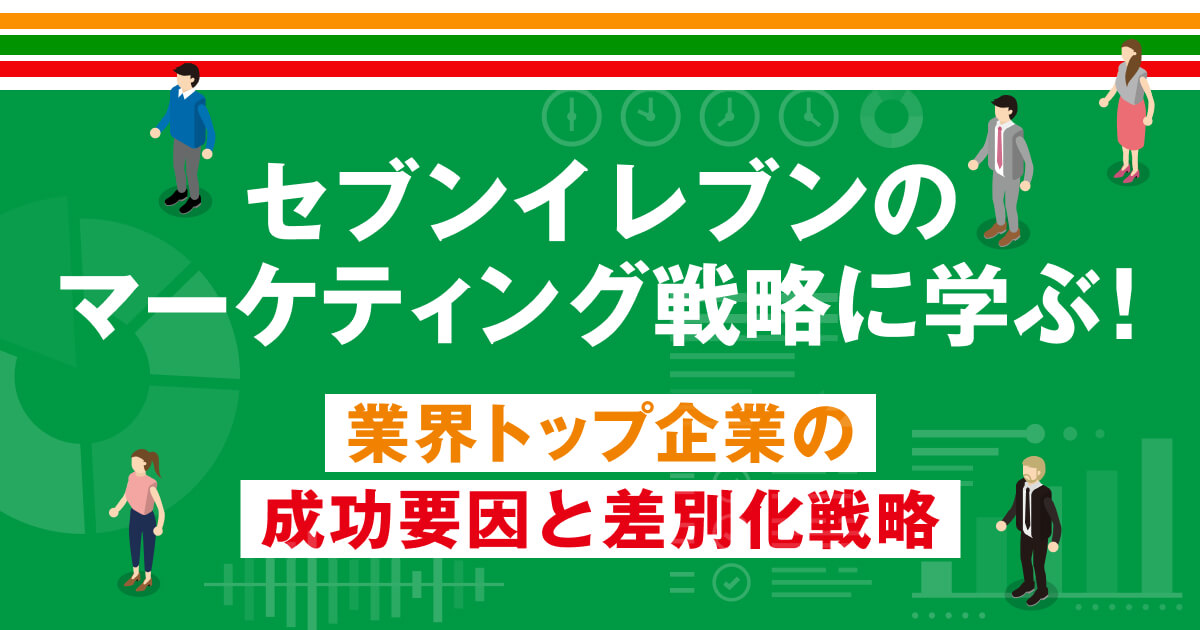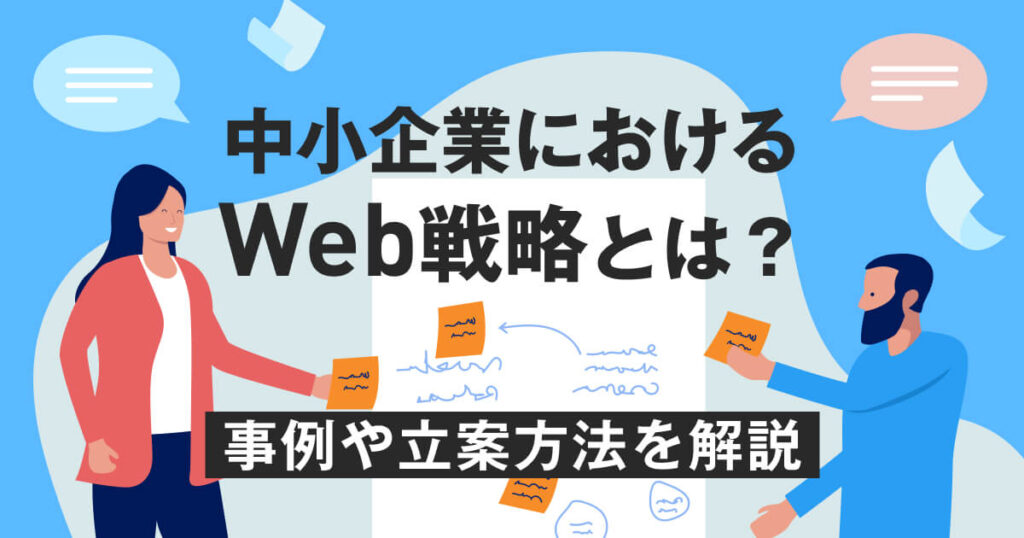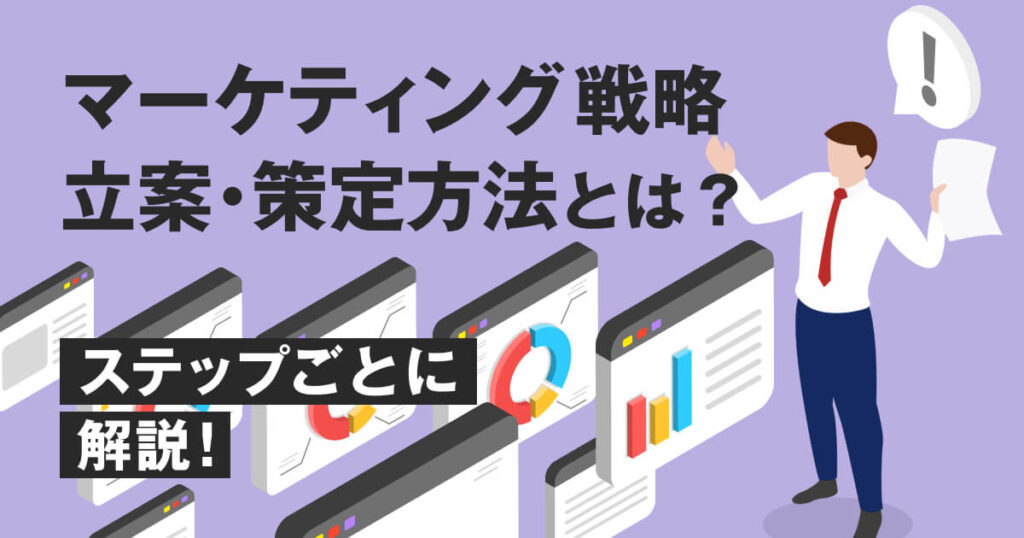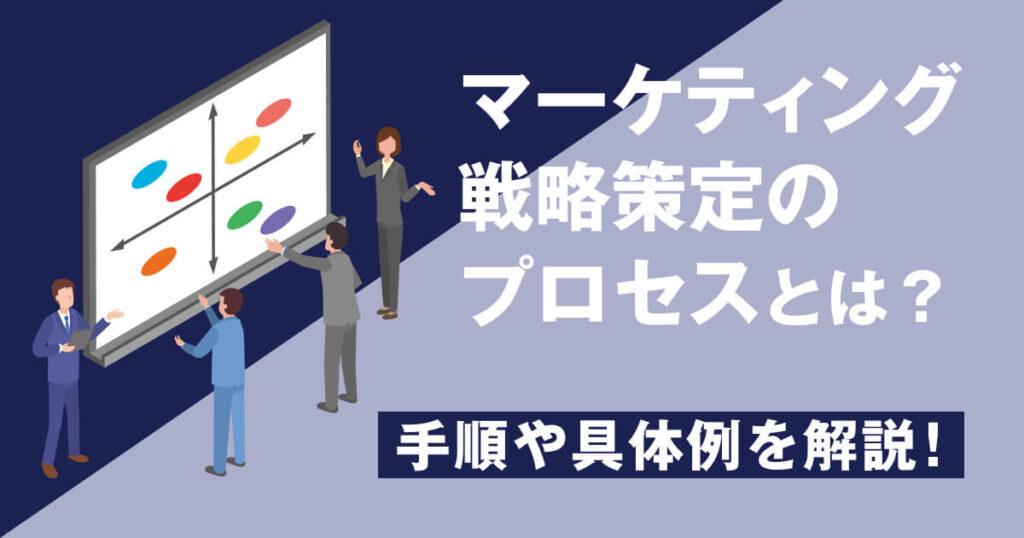セブンイレブンの店舗展開から商品開発に至るまでの徹底した戦略と顧客志向に、多くの企業が注目しています。なぜセブンイレブンは、コンビニ業界で圧倒的トップに立ち続けられるのでしょうか。
この記事では、業界トップ企業であるセブンイレブンのマーケティング戦略の全体像を解説します。
ドミナント戦略(地域集中出店)の狙いや効果、プライベートブランド商品の差別化ポイント、競合他社との戦略比較、さらに3C分析・4P分析といったフレームワークでの分析を通じて、セブンイレブン成功の要因を読み解きます。
もしマーケティング関連でお悩みなら、株式会社FlyEdgeにご相談ください。3,000回以上のコンサルティングで構築した、中小企業の勝ちパターンを活用したい方はぜひお問い合わせください。
業界トップに立つセブンイレブンのマーケティング戦略とは?成功要因の全体像
市場をリードする店舗網とブランド力
セブンイレブンは全国に約2万店以上を展開し、チェーン全店の売上高は5兆円超に達しています。多くの店舗があることによって築かれた高いブランド力がセブンイレブンの強みであり、顧客からの信頼と安心感につながり、地域内での圧倒的な存在感を確立しました。
店舗網の拡大にあたっては、一地域に集中的に出店する「ドミナント戦略」を採用しています。地域でセブンイレブンの看板を頻繁に目にする環境は、自然とブランドの知名度向上と集客アップにつながっているのです。
以下に、高密度な店舗展開による効果を挙げます。
- 戦略の効果 (顧客側)
- 「どこにでもあるセブンイレブン」という安心感が生まれる。
- 生活インフラとして機能し、強いブランド力を築き上げる。
- 戦略の効果 (企業側)
- 多店舗展開により、配送センターからの効率的な小口多頻度配送ができる。商品の鮮度管理や在庫補充が迅速に行える。
- 店舗数増加によるスケールメリットで仕入れコストが削減され、経営効率が高まる。
- 地域で看板を頻繁に目にする環境が、自然とブランドの知名度アップと集客アップにつながる。
商品開発力とデータ活用で顧客ニーズに迅速対応!
セブンイレブンは、顧客が何を求めているかを素早く察知し、商品として形にする開発力に優れています。なぜならば販売データを徹底的に分析し、顧客の隠れたニーズや変化を読み取る仕組みがあるからです。
近年では、SNS上の消費者の声を分析するために生成AIを導入し、商品企画の期間を大幅に短縮する取り組みも始めています。
新しい商品を生み出す背景には、日々蓄積される販売データと現場からのフィードバックをもとに、スピーディーに商品企画へ反映する体制が整っていることがセブンイレブンの競争力の源泉といえるでしょう。
以下にデータ活用の例を挙げます。
- 早期からのデータ活用に注力
- 各店舗のPOS・売上データを本部に集約
- 数分で在庫・販売トレンドを把握できる仕組み
- データに基づく即応オペレーション
- 好調商品:即時の追加発注・配送
- 不振商品:早期の棚替え・入替
- 新商品投入の高速サイクル
- 毎週レベルで新商品・季節限定品を投入
- 「ここでしか買えない」限定性・期間限定CPが来店動機
フランチャイズモデルとパートナーシップ戦略の強み
セブンイレブンの店舗運営は、加盟店オーナーと本部が対等なパートナーとして行う共同事業です。明確な役割分担のもと、双方が協力し合う仕組みのフランチャイズモデルによって支えられています。
現場と本部の密なコミュニケーションにより、お互いの強みを活かして協働することで質の高い店舗運営を可能にし、セブンイレブンの成功に大きく貢献しているといえます。
またフランチャイズモデルを採用することで、本部は比較的少ない自己資本で急速な店舗拡大ができます。一方でオーナー側は本部のノウハウと商品力を活かして独立開業できるメリットがあります。
加盟店オーナーと本部の役割を以下に挙げます。
| 主体 | 主な役割 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 加盟店オーナー | 店舗運営 | 商品の発注・売場管理に専念する。 |
| 人的管理 | スタッフの採用・育成を行う。 | |
| 経営管理 | 経営数値の管理を行う。 | |
| 本部 | システム・物流 | 発注システムや物流網を提供する。 |
| 商品・企画 | 商品開発、販促企画などを行う。 | |
| 経営支援 | オペレーション・フィールド・カウンセラー(OFC)を定期的に派遣し、経営や運営面の相談に乗る。 |
セブンイレブンのドミナント戦略の狙いと効果
ドミナント戦略とは何か?
ドミナント戦略とは、特定の地域に店舗を集中して出店し、地域密着型の店舗展開を行う戦略です。セブンイレブンはこの手法を用いることで、その地域での存在感を一気に高め、お客様にとって「いつでも近くにある便利な存在」となることを目指しました。
以下に、ドミナント戦略の概要と目的や効果を整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 特定の地域に経営資源を集中させ、集中的に多店舗出店することでそのエリア内シェアを支配的に高める戦略 |
| 戦略の本質 | 地域市場における優勢なポジション(Dominantな地位)を築くこと |
| 起源・背景 | 1970年代後半に日本の小売市場が「売り手市場」から「買い手市場」へ移行し、規模の小さい企業が大手に勝つためのモデルとして注目された |
| 推進者 | セブンイレブンが国内で本格的に推進した先駆者 |
| 目的 | 一つの地域での圧倒的な利便性と知名度の確保 |
| 効果 | ・消費者に「少し歩けば必ず店舗がある」という安心感を与える ・店舗間距離が近くなることで、物流や店舗指導の効率がアップする ・チェーン全体の運営効率が高まる |
ドミナント戦略がもたらすメリット
セブンイレブンがドミナント戦略を推進したことで、様々なメリットと効果が生まれました。ただし、ドミナント戦略には注意点もあります。それは、特定地域への過度な集中は、災害や市場変化リスクに弱いことです。
セブンイレブンは、細かな地域市場調査を行いながら出店戦略を調整することで、大きなデメリットを回避しつつドミナント戦略の恩恵を最大限享受してきました。
以下に、ドミナント戦略のメリットを挙げます。
- 物流効率化とコスト削減
- 配送トラック1台で複数店舗にまとめて商品を届けられ、配送頻度を上げてもコスト増を抑制できる。
- 店舗数増加によるスケールメリットが働き、商品の一括仕入れ交渉力が増して原価が下がる。
- チェーン全体の収益性アップにつながる。
- ブランド認知度
- 同一ブランドの店舗が密集することで、日常生活で看板を目にする回数が増え、ブランド認知度がアップする。
- 「あの地域といえばセブンイレブン」というイメージが定着し、地元顧客の囲い込みが容易になる。
- 地域限定のキャンペーンや広告宣伝(折込チラシなど)を効率的に展開でき、広告効果を最大化できる。
- 競合参入障壁の構築
- 新規出店によって競合他社の参入障壁を高める防御効果がある。
- 後発の競合が入り込みにくい市場環境を作り出す。
ドミナント戦略の成功事例
セブンイレブンは1974年の東京1号店出店以来、45年かけて2019年についに全47都道府県への出店を達成しました。
ドミナント戦略の下で築かれた「街のいたる所にあるセブン」という存在感が、最終的には顧客の信頼とロイヤリティを生み、セブンイレブンを業界トップに押し上げています。
以下に、沖縄進出におけるドミナント戦略の成功例を挙げます。
- 沖縄県への進出(2019年)
- 全47都道府県達成の「最後のピース」として、初日から14店舗を同時オープンする大胆なドミナント出店を実行
- 競合チェーンが存在する中、話題性と利便性を一気に確保し、進出直後から高いシェアを獲得
- 短期間で主要チェーンの一角を占めることに成功
セブンイレブンのプライベートブランドと商品戦略の特徴
プライベートブランドの差別化ポイント
セブンイレブンは、「セブンでしか買えない高品質商品」を揃えています。一方で、プライベートブランド商品を高価格帯・中価格帯・低価格帯の三層構造へ再編し、高品質な商品から手頃な価格の商品まで、幅広い層のニーズに応えられるラインナップを実現しました。
これによって、他社にはない強力なブランドイメージを築き、差別化に大きく寄与しています。
以下に、セブンイレブンのプライベートブランド戦略の経緯を挙げます。
| 経年 | 内容 |
|---|---|
| 2007年「セブンプレミアム」誕生 | 低価格より「品質向上」を優先 |
| 国内有名メーカーと共同開発で高品質を量産 | |
| 2010年「セブンプレミアムゴールド」発売 | 一流メーカーの技術を取り入れた贅沢志向の商品 |
| 下手なナショナルブランドを凌ぐクオリティ | |
| 2022年「セブン・ザ・プライス」を投入 | 低価格帯の新プライベートブランド |
新商品投入で顧客を飽きさせない工夫
セブンイレブンの商品戦略の特徴は、絶え間ない商品刷新により日常利用客にも“新鮮な驚き”を提供し、顧客を飽きさせない工夫です。
とりわけ若年層の顧客はコンビニエンスストアを「新商品や限定企画に出会えるエンターテインメントの場」と捉える傾向が強く、セブンイレブンはこの期待に応えるべく品揃えの新陳代謝を図っています。
絶え間ない商品刷新の取り組みにより、セブンイレブンは日常利用するお客様にも常に新鮮な驚きを提供し、飽きられない店舗として選ばれているのです。
顧客を飽きさせない工夫を、以下に挙げます。
- 毎週の「今週の新商品」リストを公式サイトや店頭POPで告知・訴求
- スイーツ・惣菜等で期間限定フレーバーやご当地素材を展開
- 「今だけ・ここだけ」を演出
- 味・食感の改良やパッケージ刷新で常に新鮮さを維持
顧客満足度向上の徹底
顧客満足度を高めるために、セブンイレブンは細部にわたる徹底した工夫と改善を重ねています。根底にあるのは、「お客様にとって本当に便利で快適な店舗とは何か」を追求する姿勢です。
常にお客様にとってのベストを考え抜く姿勢が、セブンイレブン全店で均一かつ高水準の顧客満足度を実現しているのです。
以下に、セブンイレブンが顧客満足度を高めるための取り組みを挙げます。
| 分野 | 項目 | 詳細な内容 |
|---|---|---|
| 商品面:品質・健康 | 美味しさ・品質の追求 | おにぎりやサンドイッチなど日配食品は1日複数回の配送で鮮度を保ち、できたてに近い美味しさを提供 |
| 健康志向への対応 | 総菜やお弁当で野菜の種類を増やす、塩分・糖質控えめの商品を開発するなど、健康に配慮した商品展開 | |
| サービス面:店舗環境 | 快適な買い物環境 | 店内を常に清潔に保つ。明るい挨拶や丁寧な接客を徹底 |
| 接客・人材育成 | 定期的な店舗スタッフ向けの研修を実施し、お客様目線での気配り・心配りを再確認し、サービス品質を底上げ | |
| サービス面:利便性 | 決済の効率化 | レジの省力化、電子マネー「nanaco」導入による決済スピードアップなど、お客様を待たせない工夫 |
| ワンストップサービスの提供 | マルチコピー機設置、宅配便受付、公共料金支払い対応、ATM設置など、多様なサービスをまとめて提供 |
顧客信頼の確保する方法
セブンイレブンが長年にわたり築いてきた盤石なブランドへの信頼は、一朝一夕に成し遂げられたものではありません。
セブンイレブンは企業活動のあらゆる側面で信頼と誠実さを重んじ、それを実践し続けることで顧客からの揺るぎない信頼を確保しています。「お客様に信頼される誠実な企業でありたい」という企業理念が日々の事業活動に反映されているのです。
以下が、セブンイレブンが顧客からの信頼を確保するための取り組みです。
| 分野 | 内容 |
|---|---|
| 商品面の信頼 | 1979年に大手食品メーカーと「デリカ食品共同組合」を設立し、製造工場の衛生管理・品質チェック体制を強化 |
| 厳選された原材料の使用や食品添加物の低減など、安心して口にできる商品作りを推進 | |
| 商品に問題が発生した場合は、迅速に公表・回収を行い、透明性を持った対応 | |
| 地域社会との信頼 | 単なる小売店ではなく、地域のインフラとして機能 |
| 災害発生時に被災地への物資供給や募金活動を行い、地域のライフラインとして貢献 | |
| 高齢者見守りサービスや宅配サービスを導入した買い物弱者の支援への取り組み | |
| 「地域になくてはならない店」を目指す姿勢がブランドロイヤルティを高めること | |
| 人的な信頼関係 | 店員一人ひとりが誠実で親切な応対を心掛け、「セブンイレブンなら安心だ」という顧客心理を醸成 |
| フランチャイズ本部と加盟店オーナーの信頼関係を構築し、共に成長するパートナーとして歩む企業文化を根付かせること |
競合他社(ファミリーマート・ローソン)との比較
ファミリーマートのマーケティング戦略との違い
コンビニ業界第2位のファミリーマートは、総店舗数約1万6千店とセブンに次ぐ規模です。新しいアイデアとブランディング戦略で差別化を図り、自社ファンの獲得に努めている点がセブンイレブンとの大きな違いと言えます。
ファミリーマートのイメージは「常に挑戦するコンビニ」とも評され、近年では異業種への大胆な進出策が注目を集めました。
以下に、ファミリーマートのマーケティング戦略の実例を挙げます。
- 異業種進出の象徴:アパレル「コンビニエンスウェア」(2021年)
- 世界的デザイナー監修のスタイリッシュな衣料品プライベートブランドを展開
- 「ついで買い」発想を超え、ファッション目的の来店を創出
- 発売直後から品切れ続出、SNS・海外メディアで話題となり、ブランド認知拡大
- プライベートブランド再編:「ファミマル」への統一(2020年以降)
- 「ファミリーマートコレクション」「お母さん食堂」を刷新・統合
- パッケージデザインも統一し、プライベートブランドの存在感とブランドイメージを強化
- 定番商品の強みとプロモーション
- ホットスナック(例:ファミチキ)の根強い人気
- 「ファミマの日」セールやキャラクターコラボなど独自キャンペーンで若年層を獲得
ローソンのマーケティング戦略との違い
ローソンは業界第3位ですが、他社と一線を画す健康志向とユニーク路線のマーケティング戦略で存在感を示しています。
ローソンが早くから手掛けてきたのが「ナチュラルローソン」というヘルシー志向ブランド店舗です。健康と遊び心という両軸で他社との差別化を図っている点が、セブンイレブンとの大きな違いとして挙げられるでしょう。
以下に、ローソンのマーケティング戦略の実例を挙げます。
- ヘルシー業態「ナチュラルローソン」
- 2001年開始、都市部中心に134店舗展開
- 無添加弁当/低糖質スイーツ/高タンパク総菜などで固定ファンを獲得
- ヒットは通常店舗にも展開→チェーン全体の「健康」イメージを強化
- “遊び心”の商品開発
- からあげクン(1986年~):多彩フレーバーで飽きさせず、累計42億食超の大ヒット(地域限定・キャラコラボ多数)
- ウチカフェ プレミアムロールケーキ(2009年):発売5日で100万個、コンビニスイーツブームの火付け役
- 接客・体験の付加価値
- アプリでの割引クーポン配布
- MACHI caféのこだわりコーヒーの提供
大手3社のブランド戦略・ターゲット層の比較
セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの大手コンビニ3社は、似たような商品やサービスを提供していますが、そのブランド戦略や主なターゲット層には違いが見られます。一方、近年は各社とも互いの強みを取り入れる動きもみられます。
それぞれのブランドらしさが顧客の支持に直結しており、自社のポジションを明確にしたマーケティング戦略が大手3社の競争を支えていると言えるでしょう。
以下に3社の違いを挙げます。
| 項目 | セブンイレブン | ファミリーマート | ローソン |
|---|---|---|---|
| ブランドイメージ | 信頼と安心のブランド、街のインフラ | チャレンジ精神あふれるブランド、エンタメ性 | ヘルシー志向&女性志向のブランド、お洒落・健康 |
| 主なターゲット層 | オールマイティ/幅広い層(ビジネスパーソン、主婦、高齢者など) | 若年層・ファミリー層(10~20代、流行に敏感な層) | 20~40代の女性客、健康志向の大人、子育て世帯 |
| 戦略の軸・強み | 圧倒的な店舗網と高品質プライベートブランド(セブンプレミアム)による王道戦略 | ユニークな店内施策やエンタメ性で若年層の支持を集める | 健康イメージ(ナチュラルローソンのノウハウ)とスイーツ開発の巧みさ |
| 高品質デリ・惣菜で30代以上の支持が厚い | アパレルプライベートブランド(コンビニエンスウェア)など異業種進出に積極的 | 地域密着の姿勢(地産品の活用、自治体連携など) | |
| 代表的な施策 | 高品質プライベートブランドの充実 | 「ファミチキ」などの人気ホットスナック | 女性比率が他社より高い傾向 |
| 最近は低価格帯商品も取り入れ、幅広くカバー | キャラクターキャンペーン、伊藤忠商事のネットワークを活かしたコラボ | 「体に良いもの」が手に入るイメージ |
セブンイレブンのマーケティング戦略を読み解く(3C分析/4P分析)
3C分析で読み解く
セブンイレブンの戦略を理解するために、マーケティングの基本フレームワークである3C分析の観点から整理してみましょう。
3C分析とは、Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点で事業環境を分析する手法です。「顧客が求めているものは何か」「競合と比べた自社の強みは何か」が明確になり、勝つための戦略を立てることです。
顧客(Customer)
セブンイレブンは、顧客の変化し続ける多様なニーズに対して、幅広い商品やサービスを提供することで応えています。常に意識しているのは、「お客様の日常生活の中で何が求められているか」を先読みし、その期待に応える商品・サービスを提供することです。
顧客がコンビニに求めるものは、単なる商品の購入から生活全般の利便性へと広がっています。24時間営業による利便性、幅広い商品とサービス展開、常に新しい驚きを提供することで顧客から厚い支持を得ています。
セブンイレブンは様々な取り組みを行っています。
| 分野 | 項目 | 詳細な内容 |
|---|---|---|
| 商品戦略 | 多様性 | オフィスワーカー向けの手軽でおいしいランチ学生向けのおやつ・スイーツ高齢者向けの総菜 |
| 地域対応 | 地域ごとの嗜好に合わせご当地メニューを開発食文化に合わせた品揃え | |
| 高齢者対応 | 柔らか食の導入や栄養バランスを考えた惣菜セットを展開 | |
| 単身者対応 | 一人暮らしの需要に合わせた少量サイズの惣菜の提供 | |
| プライベートブランド戦略 | セブンプレミアム」で、節約志向と「少し良いものが欲しい」という気持ちの両方に応える商品展開 | |
| サービス戦略 | 利便性 | 24時間営業、公共料金の支払い、ATM設置など、生活に欠かせない利便性の高いサービスを充実 |
| 特定層対応 | 高齢者向けの食事宅配サービス「セブンミール」を展開 |
競合(Competitor)
セブンイレブンにとって同業のコンビニチェーン各社(ファミリーマート、ローソンなど)は競合相手ですが、広く小売業全体が競合相手とも言えます。
以下に、コンビニ以外を競合と捉える理由を挙げます。
- スーパー/ドラッグ:低価格・品揃えを強みにする
- 深夜外食・自販機:特定ニーズで代替する
- EC・フードデリバリー:購買チャネルの多様化を促す
自社(Company)
セブンイレブンは「商品力」「現場力」「ブランド力」という3つの軸が高い次元でバランスしています。自社の強みを的確に理解し磨き続けることで、業界トップの座を維持する努力をしています。
以下に、セブンイレブンの強みと弱みを整理します。
| 分類 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 強み | 商品開発力・供給力 | 全国の物流ネットワークと情報システムにより、鮮度の高い商品を安定的に供給できる体制(他社が容易に真似できない) |
| ブランド力とマーケティング力 | ・セブンプレミアムを筆頭とする高品質なプライベートブランド商品群・豊富なデータに裏付けられたマーケティング力 | |
| 無形資産 | 長年培った「セブンイレブン=信頼できるコンビニ」というブランドロイヤルティ(競合他社の攻勢に対しファン層が流出しにくい) | |
| 弱み・課題 | 運営・コスト面 | 店舗網拡大に伴う運営コストの増加 |
| 人材・社会課題 | 24時間営業維持に対する社会の目や人手不足問題 | |
| 内部関係 | フランチャイズオーナーとの関係課題 | |
| 商品面のリスク | プライベートブランド重視による一部商品の品質低下 |
4P分析で読み解く
次に、マーケティングの4要素である4P(Product, Price, Place, Promotion)の視点から、それぞれの商品戦略・価格戦略・流通戦略・販促戦略がどのようになっているか、セブンイレブンの戦略を分析します。
製品戦略(Product)
セブンイレブンの製品戦略は、商品そのものの魅力度アップと高品質かつ幅広い品揃えで顧客のあらゆるニーズに応え、「近くて便利」の実現を徹底することです。
以下に、製品戦略の具体例を挙げます。
- 中食(なかしょく)商品
- 業界最高水準の品質を追求:おにぎり・お弁当・サンドイッチ
- 自社専用工場と共同で開発:惣菜や調理パン
- プライベートブランド商品
- セブンプレミアム:スイーツ、冷凍食品、生活雑貨など
- 数千アイテムを展開
- 「コンビニプライベートブランド=高品質」のイメージを定着
- 商品開発力
- 新商品・季節商品を次々と投入
- 店内の新鮮さを保ち、リピーター客の来店動機を創出
- サービス面
- 宅配ロッカーやコピー機、ATMなどの付加サービスを充実
- 店舗一箇所で多くの用事が済む便利さを提供
価格戦略(Price)
コンビニエンスストアの価格は一般にスーパーマーケット等よりやや高めと言われます。
しかし、セブンイレブンは単純な低価格競争には踏み込まず、品質に見合った価格設定で「高くても納得できる商品」を目指し、適正価格で高い価値を提供することを重視しています。
総じてセブンイレブンは、「安さ」よりも「納得感」を重視した価格戦略であり、顧客に長期的なロイヤルティを抱いてもらうことを狙っているのです。
以下に、セブンイレブンの価格戦略を挙げます。
- 価格帯の幅
- 100円前後のおにぎりから500円台のお弁当まで、幅広い価格帯の商品を取り揃え
- それぞれの価格に対して期待以上の満足が得られるよう工夫
- プライベートブランドによる対応
- 物価高や節約志向への対応として、2022年に廉価版PB「セブン・ザ・プライス」**を導入
- プライベートブランドにも低価格帯を設け、節約志向の顧客にもアプローチ
- プロモーション
- 販売期限間近の食品に対する割引シール貼付や、アプリ会員向けのクーポン配布などで適度なプロモーション価格を提供
- 価格以外の価値提供
- 電子マネー「nanaco」やポイントカードによるポイント還元で実質的な値引き
- イントサービスやキャンペーンなど、価格以外の価値提供を通じてお得感を演出
流通戦略(Place)
セブンイレブンの流通戦略は、「近くて便利」な店舗網と高度な物流システムです。ドミナント戦略により、日本全国のあらゆる地域に店舗を張り巡らせ、顧客から見て最も身近な買い物スポットとして機能しています。
徹底した流通戦略が、セブンイレブンの「欲しい時にすぐ手に入る」価値を生み出しています。
| 戦略 | 内容 |
|---|---|
| 店舗運営 | 基本は24時間年中無休とし、深夜・早朝でも必要なものが買える生活インフラとしての役割 |
| 物流システム | セブンイレブン独自の配送網を構築 |
| 日配食品やお弁当類は1日3回以上の配送を行うなど、高頻度少量配送の仕組みを業界に先駆けて確立 | |
| 常にできたての商品補充が可能となり、鮮度維持と品切れ防止を両立 | |
| 物流拠点(センター)を各地域に配置し、天候不順や災害時にも商品供給を途切れさせない強靭なサプライチェーンを構築 | |
| 店舗立地戦略 | 都市部:オフィス街、駅周辺、住宅街の入口など人の動線上に出店 |
| 地方:主要幹線道路沿いや学校・病院周辺などニーズの高い地点に出店 | |
| チャネル多様化 | ネット注文商品の店舗受取りサービスや、自宅・職場へのデリバリー(出前館との提携)など、チャネルの多様化を推進 |
販促戦略(Promotion)
セブンイレブンの販促戦略は、大規模な広告よりも現場での着実なプロモーションに重きがあります。
テレビCMや新聞広告などマス広告も展開はしていますが、頻度は抑えめで、その分店頭販促や会員向け施策に力を注いでいます。
以下に、販促戦略の例を挙げます。
| 戦略 | 内容 |
|---|---|
| 店内・店頭販促 | 新商品告知:店内ポスター、POP、公式SNSを活用し、「今週の新商品」を積極的に告知する |
| 会員向け施策 | アプリ会員特典:新商品引換券や割引クーポンを配布し、試しやすい環境を作る |
| 限定企画 | キャラクタータイアップ:一定金額購入でのオリジナルグッズ(クリアファイル等)配布する |
| 懸賞・景品:対象商品購入で景品が当たる懸賞を実施し、来店を動機づける | |
| ポイントプログラム | リピート促進:電子マネーnanacoにポイント機能があり、利用額に応じてポイントを付与する |
| ポイントキャンペーン:定期的なポイント○倍キャンペーンやボーナスポイント付与でリピートを促す | |
| 地域密着 | コミュニティとの繋がり:地域密着イベントへの協賛や、店舗独自の感謝セールなど、地域ごとのプロモーションも展開する |
セブンイレブンのマーケティング戦略から学ぶポイント
戦略立案と市場環境分析
セブンイレブンの事例から学べるのは、的確な戦略立案のための市場環境分析の重要性です。
自社の置かれた環境を客観視し、適切なフレームワーク(例えば3C分析や4P分析など)を用いて強み・弱みや機会・脅威を見極め、中長期的な成長戦略を描いています。
| カテゴリ | セブンイレブンの事例に見る具体的な教訓 |
|---|---|
| 市場環境分析 | 時代の変化の把握:1970年代の消費市場の変化を的確に捉え、「近くて便利」という新しいコンビニエンスの価値を発見した。 |
| 競合とトレンドの注視:人口動態の変化や競合状況を注視し続けた。 | |
| 客観的な自己理解:3C分析やSWOT分析などの適切なフレームワークを用いて、強み・弱みや機会・脅威を客観的に見極めた。 | |
| 戦略立案 | 戦略の一貫性:ドミナント戦略によるエリア展開や、PB戦略による差別化など、一貫して時代の流れを読んだ戦略を打ち出した。 |
| 勝ち筋の明確化:市場や競合の分析結果に基づき、「どの領域で勝つか」「何を武器に戦うか」を明確にした中長期的な成長戦略を描いた。 | |
| 価値の創出:変化する消費者ニーズに応え続けることで、新しい価値(利便性、高品質など)を提供し続けた。 |
徹底した顧客目線に立った商品・サービス改善の追求
セブンイレブンの成功要因は、徹底した顧客目線があります。常に「お客様が本当に求めているものは何か?」を自問し、その期待を上回る商品・サービスを提供してきました。
顧客の声やデータを積極的に収集・分析し、小さなニーズにも応えていく姿勢が、長期的な顧客満足とロイヤルティにつながります。
自社のマーケティングでも、顧客本位の発想で絶えず商品の質を高め、サービスを磨き続け、ターゲット顧客の視点に立って検討していきましょう。
| カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| 潜在ニーズの汲み取り | 「手軽に美味しいコーヒーを飲みたい」という潜在ニーズを汲み取った結果、淹れたてコーヒーを提供するセブンカフェを導入した。 |
| 環境変化への対応 | 社会環境の変化を踏まえて顧客目線で考え抜いた結果、高齢者向けの配食サービスや健康志向商品を拡充した。 |
| 情報収集と活用 | ・顧客の小さなニーズにも応えていくために、顧客の声やデータを積極的に収集・分析する。・ターゲット顧客の視点に立って検討し、商品開発やサービス改善につなげる。 |
| 信頼構築 | SNS上の批判(弁当の容量減への不満など)といったネガティブなフィードバックも真摯に受け止め、誠実な改良を重ねる。 |
| 成果 | 顧客本位の発想で絶えず商品の質を高め、サービスを磨き続ける姿勢が、長期的な顧客満足とロイヤルティにつながる。 |
地域密着や自社の強みを活かした独自戦略の構築
セブンイレブンのマーケティングから得られるもう一つの教訓は、自社の強みを活かし、地域や分野に密着した独自戦略を構築することです。
セブンイレブンはドミナント戦略によって「地域密着」を実現し、その地域特性に合わせた商品展開やサービス提供で他社との差別化を図りました。また自社の強みである物流・ITシステムを背景に、高頻度配送や在庫最適化といった他社にないサービス水準を実現してきました。
以下に、自社に活かすセブンイレブンの独自戦略のポイントを挙げます。
- 自社固有のリソースを最大活用し、戦略に織り込むこと
- 他社にない強み(ニッチ技術・地元知名度・人脈 等)を起点に、「自社だから提供できる価値」を定義すること
- 小商圏なら徹底的な地元ニーズ対応、特定カテゴリで強いならその分野で圧倒的No.1を狙うこと
- 規模の大小に関わらず、戦略立案では、自社の「武器」と地域の特徴を冷静に分析し、最適に組み合わせること
まとめ
セブンイレブンのマーケティング戦略を振り返ると、業界トップに立つべくして立った理由が見えてきます。
高密度出店による圧倒的な店舗網とブランド力、データを駆使した商品開発力と迅速な市場対応、加盟店との強固なパートナーシップ、そして高品質なプライベートブランド商品の展開など、あらゆる経営資源を巧みに組み合わせた総合力が成功を支えていました。
また競合他社も各々独自の戦略で追い上げていますが、セブンイレブンは顧客志向と革新性において一歩先を走っています。
環境変化への対応力、顧客中心主義、パートナーとの共創、継続的なイノベーションを体現した同社の取り組みから、大いにヒントを得て、自社のマーケティング戦略に活かしていきましょう。
もしマーケティング関連でお悩みなら、株式会社FlyEdgeにご相談ください。3,000回以上のコンサルティングで構築した、中小企業の勝ちパターンを活用したい方はぜひお問い合わせください。