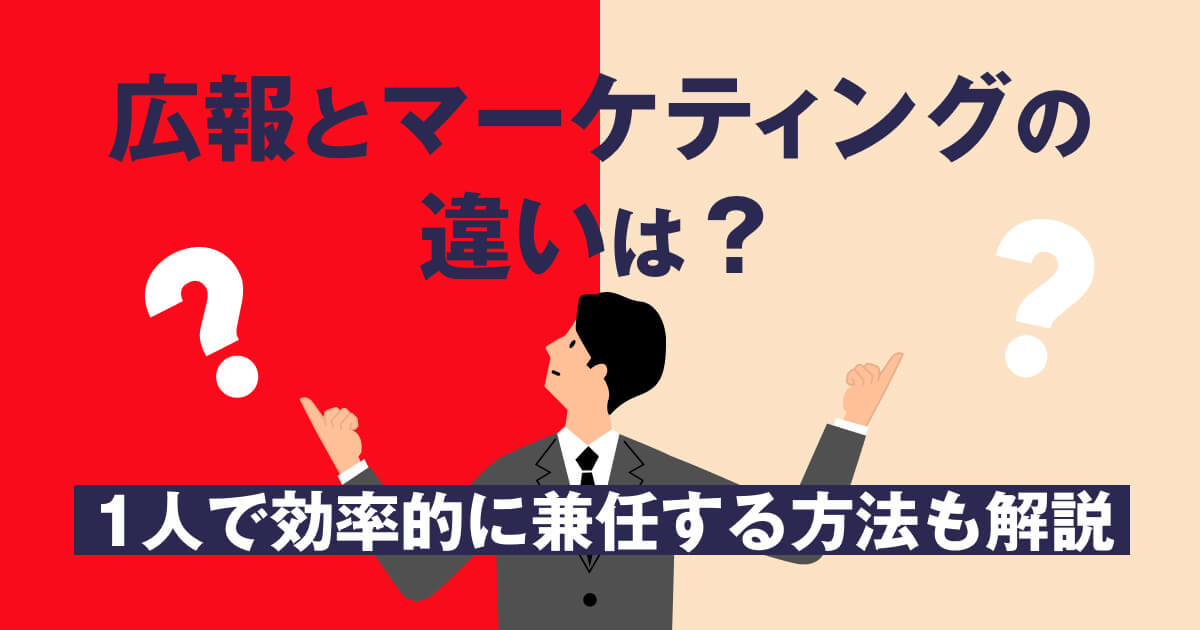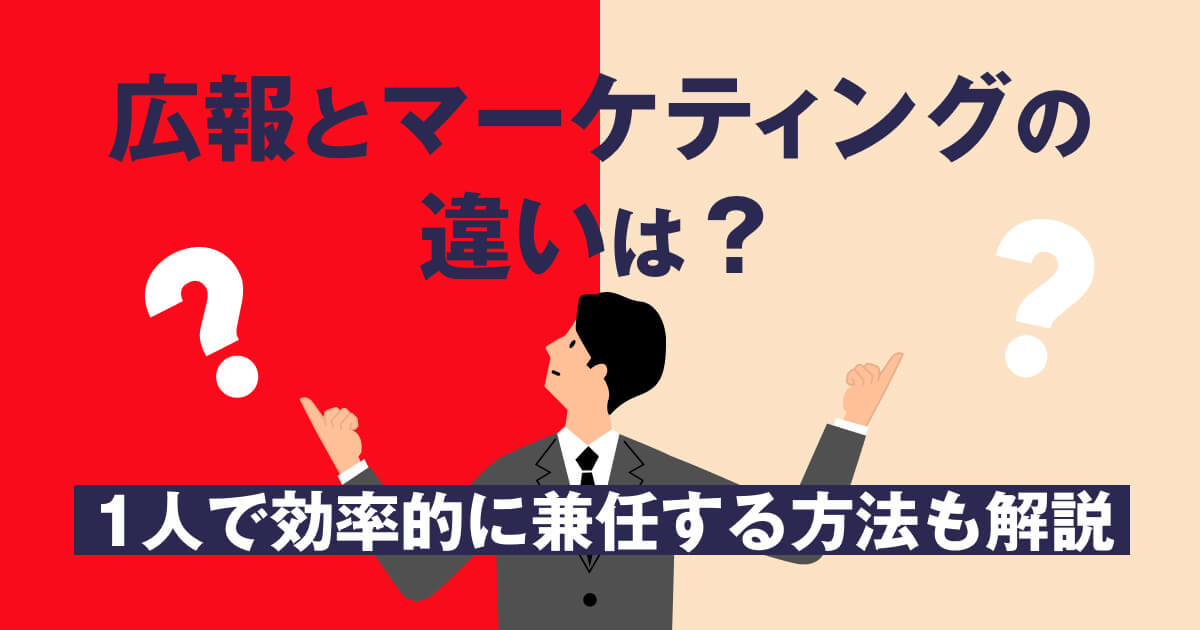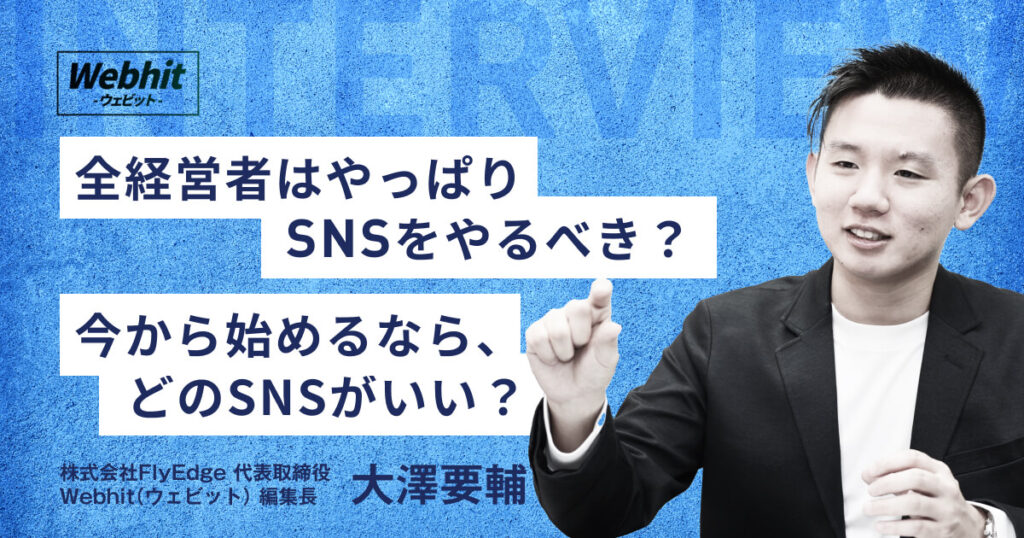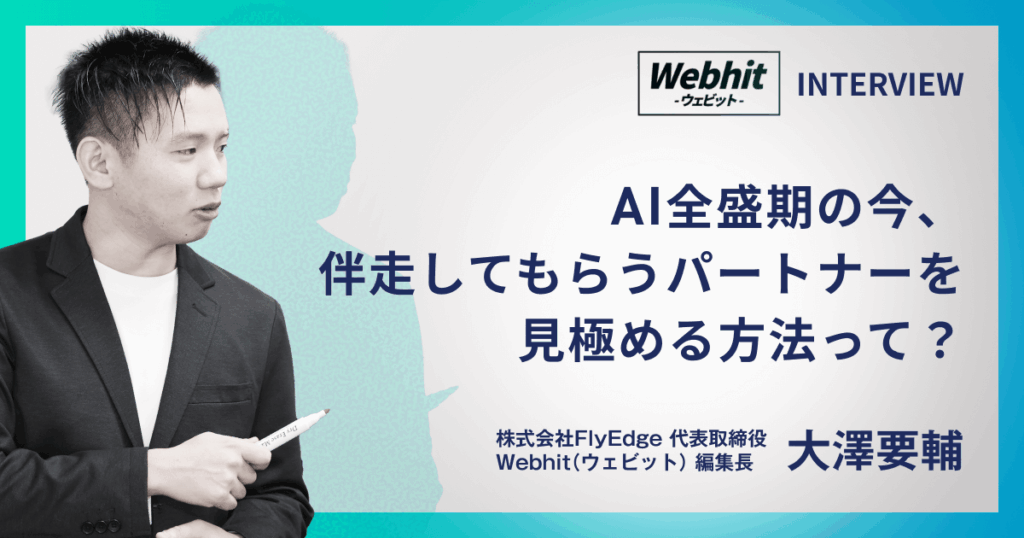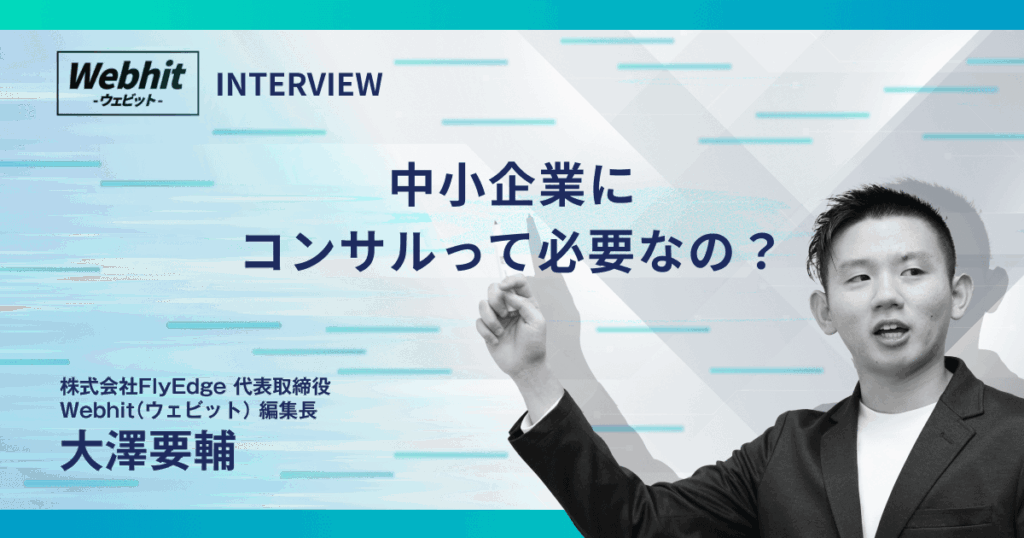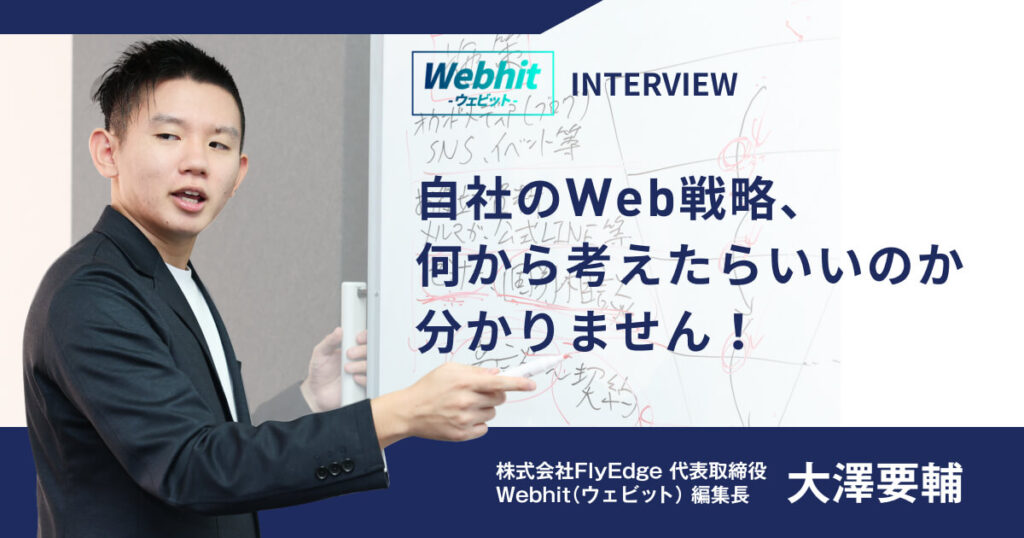Webhit 編集部
Webhit 編集部今回は、「マーケティングの内省化はなぜ難しいのか?」というテーマでお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。



お願いします。





では早速ですが、マーケティングの内製化はなぜ難しいと言われるのでしょうか?



マーケティングの内製化が難しい理由は、ステークホルダーが非常に
多いからです。
例えば、外注のマーケ支援会社などが広告運用を代行する場合、広告
運用の成否を決めるのはその広告運用会社の運用力や改善提案次第に
なります。
厳密に言えば、事業会社側のサービスの状態やプランなどの話はあり
ますが、実行するのは広告運用代行の会社になるでしょう。



なるほど。マーケティングの内製化が難しい理由は、ステークホルダーが多い点にあるのですね。



そうですね。そのため、内製化するのであれば、担当者がしっかり改善できるのかはもちろん大切です。
そのうえで、担当者に対して適切に指示ができて、現場の改善をさせられる上長がいるのかも肝心です。
そして、最終的に経営者がマーケティングの現場や性質、状態を詳しく理解して、現場担当者のスキルセットレベルを理解し、適切な指示を出せるのかがポイントになります。



なるほど。担当者だけでなく、上長や経営者の理解や適切な指示出しも大きなポイントとなるのですね。



はい。経営者はマーケティングで社内を改善していく際、次々に売上や利益を求めますが、担当者のスキルセットでは現状として難しい場合があります。



しかし、経営者に求められていることを、マネージャーがうやむやに
しながら現場に伝えると現場も担当者も動きにくい状態になります。
さらに、上長が正しくコントロールができず、改善をさせられないにも関わらず、経営者からはずっと数字を詰められるといった状態になると破綻するでしょう。



そうですよね。



先程ステークホルダーが増えると言いましたが、先程の広告運用の件で言うと広告運用会社がどうなのかは、アウトプットを見れば済みます。
しかし、社内で内製化するのであれば、他の営業部との連携や営業部
から言われることを担当者が全て対応する必要があります。
広告の部分だけを外注するのではなく、関係者が非常に多くなるため、非常に前に進みにくいということが、内製化が難しい1つの要因です。



なるほど。関係者が多くなると前に進みにくくなるのですね。
他にもマーケティングの内製化が難しい理由はあるのでしょうか?



もう1つの理由に、内製化が進んでいる実感を得られにくいことが
あります。



施策を行って数値が出たからといって、内製化ができたわけではありません。たまたまヒットしただけかもしれません。数値が悪くなった時に改善方法がわからないと、内製化できたとは言えないでしょう。



改善方法がわからないと再び外注に頼ることになるため、内製化では
なく「内製化したつもり」になります。
これは、内製化にチャレンジした企業に多く起きる現象です。



内製化にチャレンジしても、内製化したつもりになっているだけの企業が多いのですね。



はい。そのため、弊社が支援した会社は、基本的に改善含めて、自分でできる状態にしていきます。
中途半端にそれっぽい知識を入れて勉強して、「プログラムが終わったから内製化できた」というのは、なんの意味もありません。



弊社の場合、6ヶ月かけて、 結果を一緒に出していきます。しかし、内製化支援をする会社の都合でもありますが、 半内製化として前半や1/3ほどの初期段階を支援会社がやってしまうことがあります。



一番経験する必要がある、一番難しい最初の立ち上がりを、自社では
なく支援会社がやるメリットは、数字が出やすく成功確率が上がる
からです。
しかし、本質的にその企業のことを考えるならば、失敗するならそのタイミングで失敗させた方がいいと思っています。



なるほど。支援会社がやってしまいがちな一番難しい部分を、自社で行わないと知識もスキルも培われないということでしょうか?



おっしゃるとおりです。本質的に一番ハードで大変な部分が経験でき
ないのは、費用のかけ損になると思います。
それなら広告代理店に頼んで、数ヶ月運用してもらってそのアカウントを譲り受け、基本知識を入れて運用する方が都合がよいと思います。



たしかに、そうですよね。



内製化を支援するということは、担当者の方が、企業のマーケターと
して社内で提案をしたり、決済を通したり、企画を立てて戦略を改善し、数字も分析して改善策を実行できるようにすることが重要です。



しかし、支援会社が半内製化といって戦略部分を代行することで、前に進んでいる実感が得にくくなります。
そして、自分自身で改善できるようになったかどうかが非常に分かり
にくい状態になります。



実感を得られにくいため、支援会社に言われたことをやっているだけ
ではないかと思うこともあるでしょう。



実感を得られないと、ただ言われていることをやっているような感覚になりますよね。



そうです。そのため、弊社の場合、「こうやって直して、こうやって改善してください」といった指示型ではなく、基本のレクチャーやフィードバックがあったうえで、どう改善したらいいかというコーチング型で
支援します。



つまり、担当者が自分で考えた方法でアウトプットしてもらい、
それに対してフィードバックをします。



工数は非常にかかり泥臭いですが、それをやってもらうため、担当者の方は強制的にマーケティングの分析を自分でやって、強制的にアウトプットを出さざるを得なくなります。



そのため、弊社の内製化支援プロジェクトでは、その辛い部分の改善をやる必要があります。アカウントの設定1つ取っても、自分で実際に触ってみて欲しいので、絶対に実務代行をしません。



非常に泥臭い作業でも、自分自身の手で実際に行っていくことが肝心だということですね。



はい。楽をしてると思われるかもしれませんが、実は正直それが一番楽ではないのです。
自分でやったほうが100万倍楽ですが、「絶対に内製化させきる」という想いで支援しているため、全ての取り組みを内製化できるような支援をします。



自分で操作方法を探して見つけるというスキルも必要です。
正解にたどり着くまでに時間がかかっても、自分でアウトプットして
もらい、自分で探してもらいます。



どちらも大変ですね……。



そうです。非常に手間がかかり、大変です。 そのため、内製化したら
コスト削減されるといった単純なことではないのです。





ありがとうございます。
マーケティングを内製化するにあたって、一番大変な部分はどこに
なるでしょうか?



強制的にアウトプットを出させるところです。
最初のうちは担当者も分からないと逃げたくなると思います。



企業の中で担当者がマーケターとして内製化していく際に、経営者や
上長はマーケティングに詳しくないことがほとんどです。
しかし、担当者が白旗を揚げてしまったら、みんな分からなくなり
ます。
そのため、自分が最後の砦だと思って、諦めずにアウトプットし続け
られるかどうかが極めて重要で難しい部分です。



なるほど。分かりました。
内製化が難しいことは前提として、内製化をする際に失敗しないためにやっておいた方がいいことはありますか?



内製化をする前の準備は特に必要ありません。楽をすることを、思考の最初に持ってこないことが大切です。
しかし、近年では、生成AIをマーケティングに活用する取り組みが盛んになってきています。生成AIを使って、効率化することに対しては賛同しますが、経験や理解がないのに、最初から効率化はできません。



例えば、マーケティングのことを分かっていない人や実務レベルの
スキルがない人が、なんとなく理解したプロンプトを生成AIに流し込んでマーケティング戦略を作っても、適切にフィードバックできる能力がないため、品質がいいかどうかの判断もできません。



そうすると、内製化ではなく、単純に生成AIの言いなりになって振り回される人材ができあがるだけで、マーケターとは言えないでしょう。
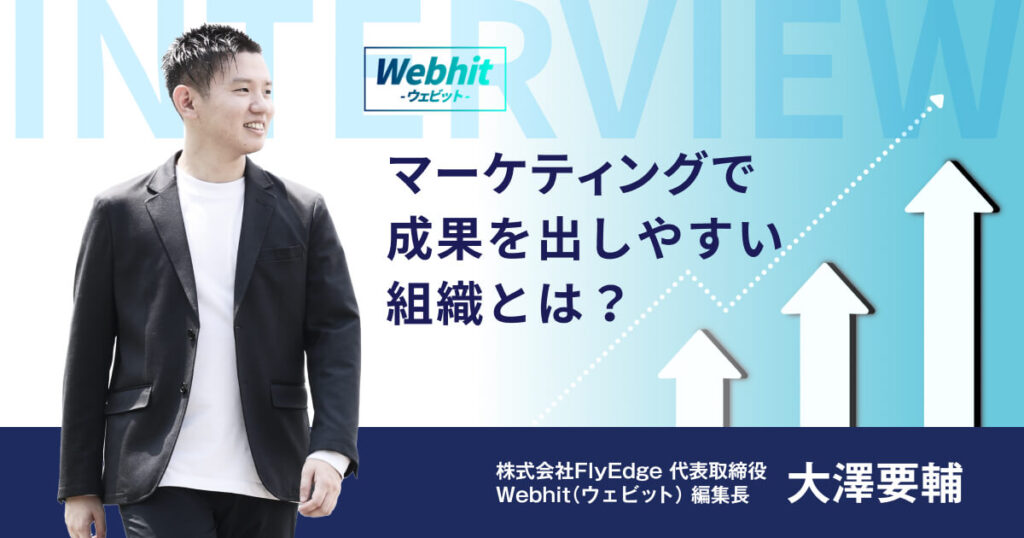
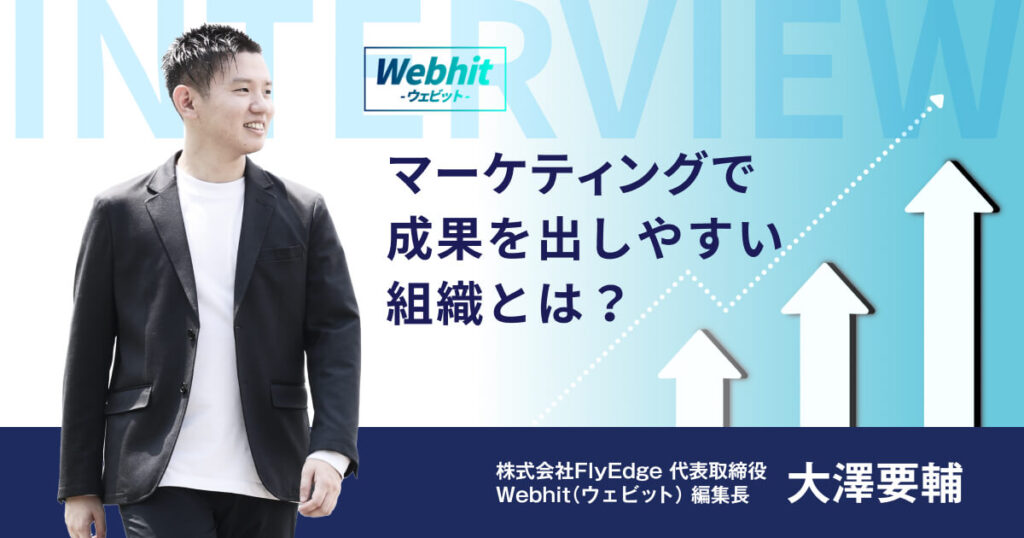



そうですよね。経験や理解がない段階で楽をしようとしても、結果的に品質の悪いものができることになってしまうと思います。



そうです。そのため、戦略を作るには、さまざまな文献に当たる、人に話を聞きに行く、お客様の声やアンケートを全部確認するといった地道なことを全部やる必要があります。
経験や理解がない人間が、いきなり生成AIを使って上手くいくのであれば、全世界の企業マーケティングは大成功しているでしょう。
しかし、実際はそうではありません。



そのため、とにかく楽にやろう、手間をなくそうという思考を最前列に持ってくるのではなく、まず企業として、自分がマーケティング担当者および責任者としてやっていくのであれば、あえて辛い道を選んでください。



なるほど。あえて辛い道を選ぶことが大切なのですね。



はい、内製化に関しては泥臭くやっていかないと絶対に長続きしないので、その道が辛ければ辛いほどいいと思います。



ありがとうございます。
難しいと言われるマーケティングの内製化に中小企業が取り組む価値というのは、どんなことがあるのでしょうか?



そうですね、まず、外注にかかるコストを減らせます。
既存の社員を教育することでスキルが増えて結果が出て、役職や報酬、給料が上がることがあるにしても、新卒採用や中途採用に比べて固定費は大幅に増えません。



そして、外注費を最小化できる状態になります。中小企業にとってそのコストを減らせるということは、自分たちの施策に回せるお金が増えるということになります。
そうすると、問い合わせの獲得を含めた事業拡大のための具体的なマーケティング施策に対して、投下できる予算が増えるということにつながります。



なるほど。外注コストが削減できると、自分たちの施策にお金をかけられるようになるのは大きなメリットですね。



はい。それに加え、社内にマーケティング視点で考えられる担当者が
いるということも大きな価値になるでしょう。
今までになかった改善提案が議題にのぼりやすくなるのは、メリットと言えます。



内製化は一部だけ外注するなどではなく、完全に内製化した方がいいのでしょうか?
それとも、外注と内製のバランスを取った方がいいのでしょうか?



結論としては、バランスを取った方がいいです。
自分たちがやるべきことと、やるべきでないことを切り分けて、自分
たちがやるべきことは内製化するべきです。
そうでないものは、外注した方がいいと思います。



外注と内製のバランスを取った方がいいのですね。



はい。例えば、動画編集のトレンドが分からない状態で、動画編集を
内製化しようと思ったら、動画編集のトレンドを自らキャッチアップ
していく必要があります。さらに、常に進化する編集技術を全部キャッチアップすることも必要です。



そのため、自分たちが動画編集やトレンドのキャッチアップにもリソースを割けるのか、もっと重要なことはなかったかといったことを考え、重要なものが他にあるのであれば、外注した方がいいと思います。



しかし、自分たちが時間、手間をかけたとしても、自分たちでやっていくべきだと判断するのであれば、内製化を進めればいいと思います。
社内のリソースは有限であるため、そのリソースの中でできるのかどうかを考えたうえで、内製・外注のバランスを取ってコントロールした方がいいでしょう。



ありがとうございます。
社内のリソースをどのように活用していくかを考えながら、外注との
バランスを取って内製化に取り組んでいくことが大切だということが
分かりました。
では、最後にこの記事を見てくださっている経営者の方や、マーケ担当の方に一言お願いします。



とにかく言いたいのは、「マーケティングの内製化を甘く見ないでください」ということです。



経営者は、「いいマーケターになってくれたらな」「自律的に動いてくれたらな」とさらっと言うことが多くありますが、そんなに簡単なことではありません。



自分たちの工数が3倍、5倍、10倍になったとしても、マーケターが社内に欲しいか自問自答していただきたいと思います。



弊社の中にもマーケターはいますが、マーケターの一人ひとりが私と
全く同じことができるわけではないので、私が一切フィードバックを
しなくていいというわけではありません。



私がフィードバックを一人ひとりに出すのは、社内でやるべきこと
だからです。私がやるべきことは私がやり、反対に社外に出すべき
ことは全部出しています。



やるならやるで、甘美な部分だけを知るのではなく、ちゃんと苦しいことを分かった状態でやっていただきたいと思います。
また、企業から全く未知の業務にチャレンジしてくれというオーダーを受け、大変な思いをして一番辛いのは担当者だと思います。
そのため、マーケティングの担当者に指名する方に最大限の敬意を持って接してあげてほしいと思います。



ありがとうございました。