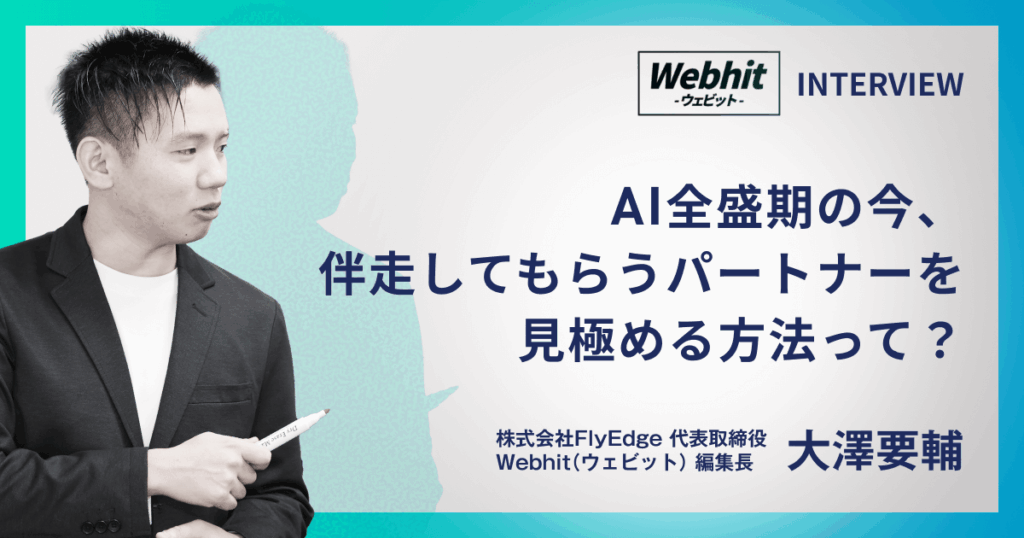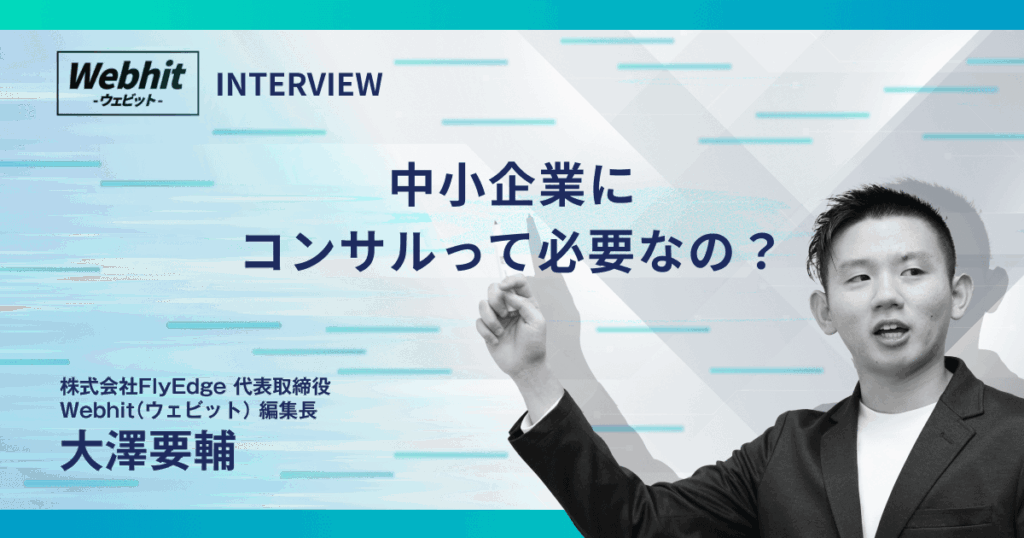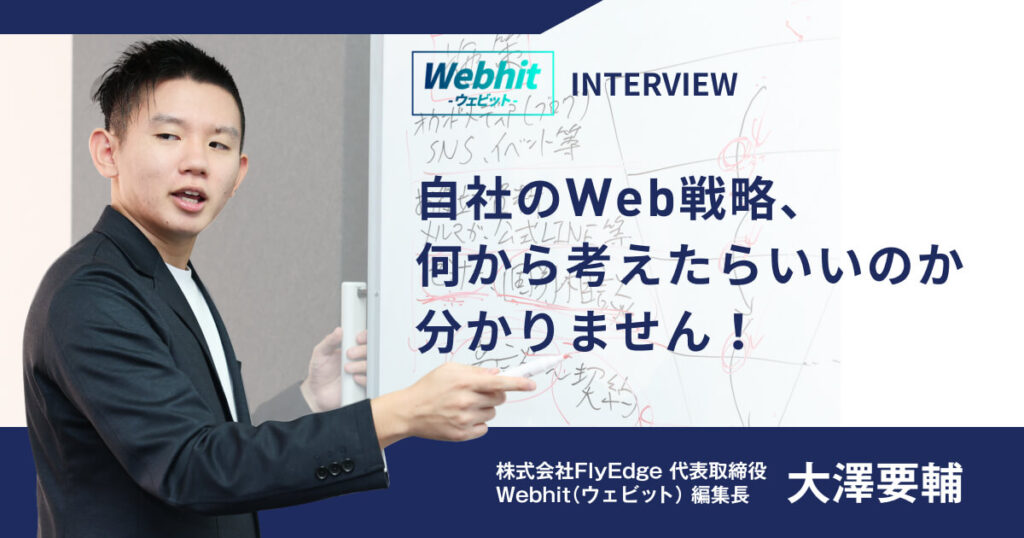Webhit 編集部
Webhit 編集部アンケートをとって商品やサービスの改善をしているはずなのに、
なぜか売れない。原因は何でしょうか?



仮に、ある飲食店がアンケートをとっていて、お客様に指摘された内容に対して改善しているとしましょう。それでもうまくいかないということを前提とします。


アンケート結果を信じすぎる落とし穴



例えば、「お客様アンケート」ってよく見かけますよね。
「お味はどうでしたか」という質問に対して意見を書く場所があって、味がちょっと濃いかなっていう人たちが全体の3割いたとします。
その3割の人たちが濃いって言っているから、「うちは味が濃いのかな」と思って薄くするとします。それでも売れなかった場合、売り上げが
変わらない、または下がったっていうことですよね。



そもそも味が濃いと言った3割の人たちが、
・何回も来てくれている常連さんみたいな人たちなのか
・初めて食べに来た人たちが書いた案件なのか
これによってイメージが全然違うんですよ。



初めて食べに来た人たちで、単純に味の好みが合わなかっただけかもしれない。逆に、3回目4回目に来店してくれている常連さんは、味が濃いけれども来てくれてるわけじゃないですか。別に味が濃いから行かなくなるわけじゃない、ですよね?
そうすると、決して味を薄くしたら売り上げが上がるっていうロジックはどこにもないんですよ。



例えば、「濃いからもう来るのをやめます」っていう人たちが大勢いて、実際に来店が2回目以降の相手にそのパターンがあって。
それは、味が濃いことが原因で2回目の来店を考えられないからやめますっていう可能性もありますよね。
改善すべき声と流してよい声の違い



2回目、3回目以降の常連さんで、少し濃いかなって言っている程度なのであれば、それは流してもかまいません。
もちろん、対応をゼロにするよりは何かやった方がいいので、味が濃いっていう人たちに味の調整ができるようにメニューの仕組みを変えて
あげるとかですね。



ラーメン屋さんによりますけれども、味の濃い薄いのようなところを
選べるお店と選べないお店がありますよね。
選べないお店で「味が濃い」という意見がたくさん出ていて、それによって初回来店でお客様に逃げられてしまっている、ということなのであれば、ラーメンを注文する際に、薄味、普通、濃いめ、というのを明確に選べるようにしてあげると、オペレーション改善によって味に対する不満の声が出なくなる可能性が高いです。



常連の人が「味は濃いかもしれないけれど、ここのラーメンが好きだよ」と言って来てくれている人たちは別にそれはそれでいいかと。
例えば、ちょっと薄味のものを季節に合わせて試験的に出してみるとか、もしお客様が気に入ってくれるのであれば、今後そのメニューを
固定化すればいいわけです。
ですので、必ずしもお客様の声はすぐ対策しないと売り上げに影響してしまうものではないということに気付いたほうが良いかなと思います。


売れない原因は設問設計にある



ただ、気付くためにはそもそもアンケートの設問設計をしっかり考えておかないといけないんですよ。
「お味はどうでしたか?」だけだと「濃かった」「薄い」「美味しい」
といった答えしか出ないんですよね。



より具体的に改善したい部分を聞きたいのであれば、「当店の料理に対して、ここをもう少し直してくれたら嬉しいなと思うポイントはありますか」のような質問にすると、「麺がちょっと伸びていた気がする」と具体的に返してくれますよね。
あと、初回来店なのか2回目、3回目以降なのか、お客様の来店が何回目なのかというところで、どういう属性のお客様かがわかりますよね。



どういう質問を準備するのか、どういう言葉で準備するのかによっても回答ってある程度変わっちゃうんですよ。
ですので、比較的正しくお客様の声を得られるように、しっかりアンケートがとれているのであれば、その売上改善に繋がるような施策を
打てるかなと思います。


自由記入と選択式の正しい使い分



なるほど、より効果的に扱うためには、そういった質問や設問を工夫しないといけない、ということですね。
例えば、アンケートの質問が多いと、回答する側は答える気がしなく
なると思うんです。その辺のバランスはありますか?



例えば、アンケートの設問の一つ一つを自由記入とかにしてしまうと、回答側は何を書くか考えなきゃいけません。
もちろん、具体的な内容を書いてもらえる可能性は高いですが、ただ
面倒くさいから書きたくない、書くのに不安感があるなどのケースも
あるので、設問の出し方を工夫しなきゃいけません。



例えば、「当店には、どういうサイトを見て来られましたか」というのを自由記入にさせてしまうと「あれって何だっけな…まあいっか…」と
いった状態になりかねませんよね。
その点、Google検索やGoogleマップ、インスタグラム、TikTok、Twitterなどが選択肢として書いてあれば、その中から丸やチェックを付けるだけでいいわけです。
そうなると回答負荷は下がるんです。



その分、細かい経路を教えてもらえる確率は低くなってしまいますが、回答負荷が減るので、お客様の声が集まる数が増えるわけですよ。
ですので、そういった回答の難易度や欲しい回答の粒度の細かさをバランスよく配置するのが一番いいかなと思います。



もちろん、細かい経路を教えてもらえれば理想的ですけど、それよりは今何を見て来てくれている人たちが多いのかを知ることのほうが大事
なので。だったら選択肢方式がいいですよね。



一方で、お店の味や接客に対して改善してほしいポイントがあるかどうかを知りたいときに、選択肢方式にしてしまうと、「選択肢の中から1個しか選べないので当てはまらない、意見が言えない」といった可能性があります。
そういうところは自由記入にして記入例とかを添えてあげると、自分
たちの本当に欲しい結果に繋がるかもしれないですね。



そういうことですね。



アンケートによってどういう回答を得たいのか、それを聞いてどう分析するのか、それによって設問の出し方が変わるっていう感じですね。