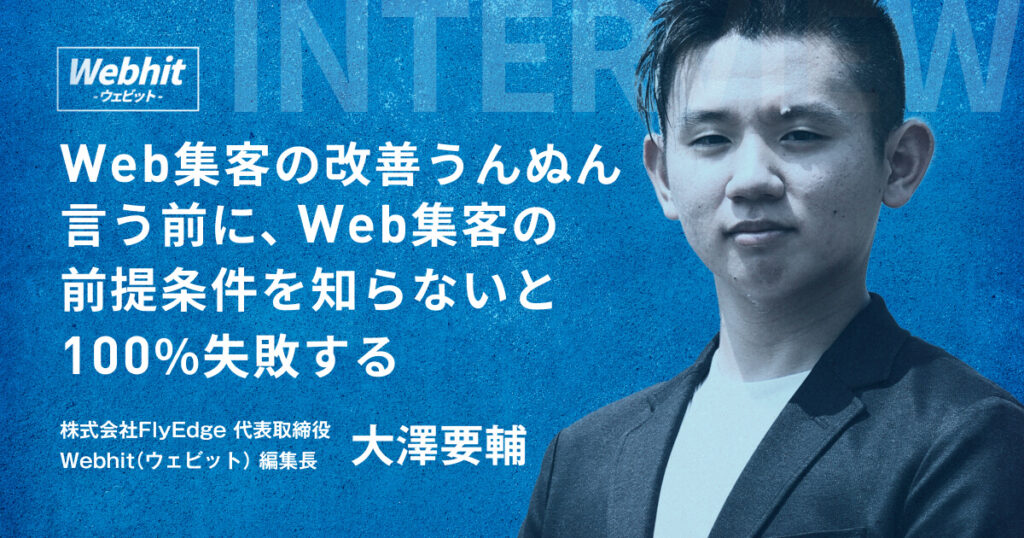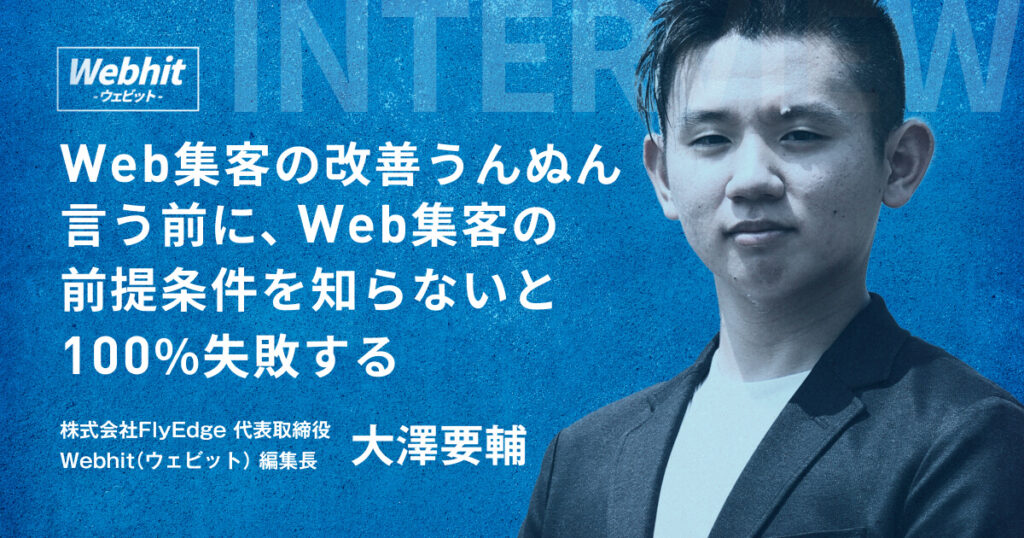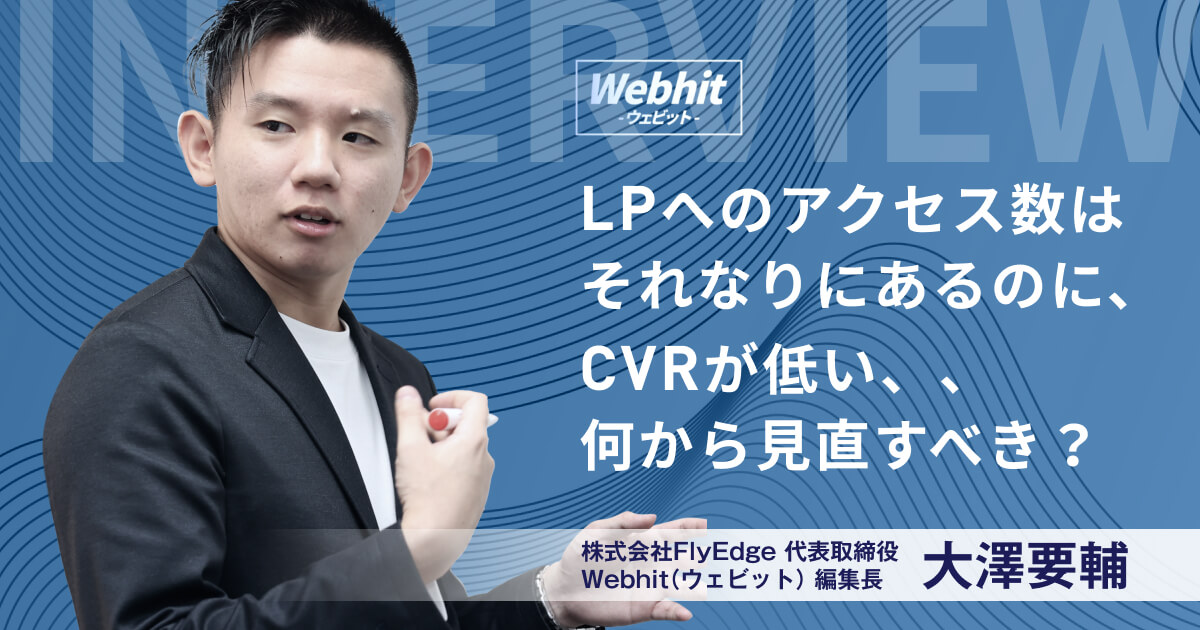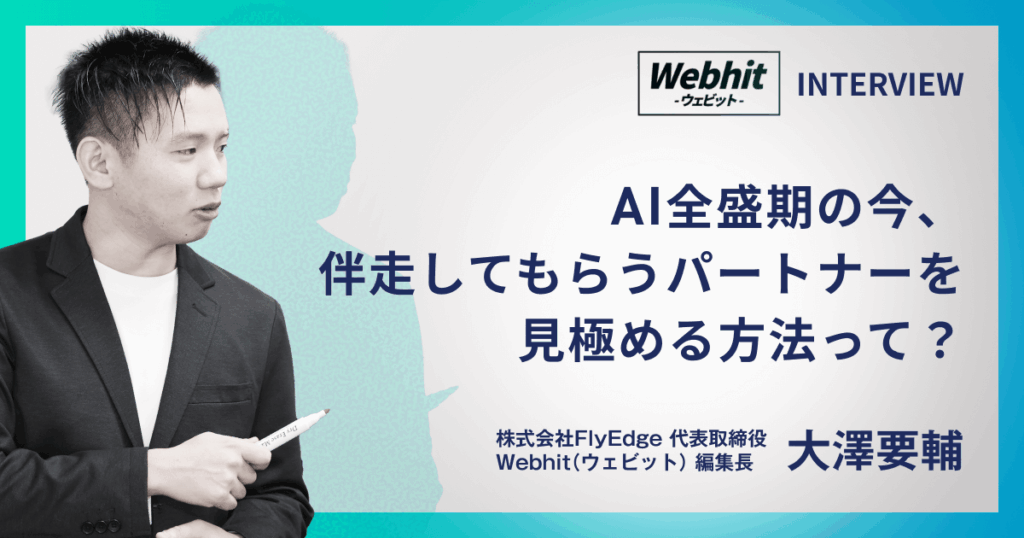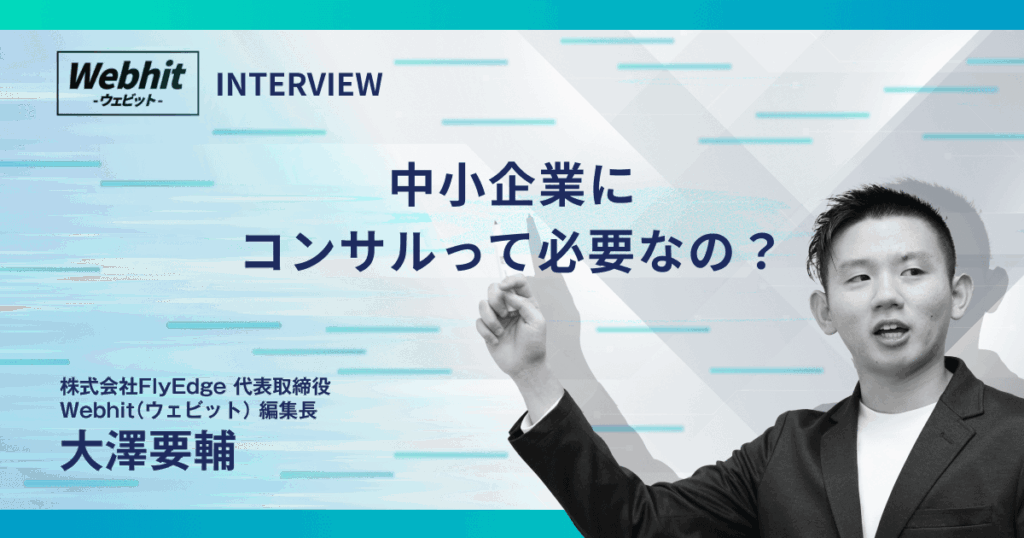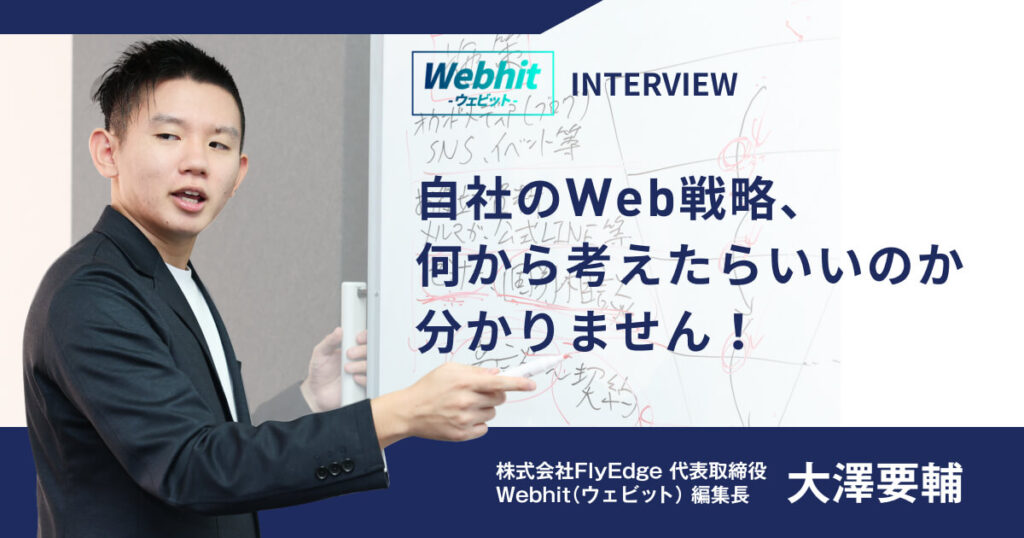Webhit 編集部
Webhit 編集部LPを運用していて、アクセス数はそれなりに入ってきているのにCVRが低いといった場合、どこに原因があって何から見直すべきなのかを教えてください。



はい、よろしくお願いします。


アクセスはあるのにCVRが低い…何から見直すべき?



実際にはどこから見直したらいいでしょうか?



CVRが低いというのは相対的な評価なので、だいたいの基準をどこまで設定しているのかにもよりますが、例えば、CVR1%を目標としていて、現状実績が0.5~0.7%になっているといった場合を前提でお話しますね。
CVR低下の原因は「流入の質」と「LPの訴求力」



このときの原因は大きく分けて二つあります。
一つは、そもそもLPに入ってきているユーザーの品質ですね。要は集客チャネルからの送客品質に課題があるケースです。
もう一つは、LPの構成やメッセージの訴求が流入しているユーザーに合っていないケースです。



なるほど。流入してきた時点で、すでにズレが生じている場合もあるんですね。



この2つの原因が両方あるケースもあります。入ってきている送客品質がよくない、さらに送客品質に対してメッセージの訴求もあっていないといった状態ですね。
ですので、まずは流入の大元から見ていく必要があります。
例えば、LPを必死に直しても、送客されてきたユーザーの品質に問題があるとうまくいきません。



LPへの流入というプロセスは、よく水道とバケツの関係に例えられ
ます。
ここでの「水道」はユーザーがLPに流入する経路を指し、「バケツ」はLP自体を示します。
この比喩では、水道からバケツに水を入れる行為がユーザーをLPに導く
ことに相当します。



しかし、たとえバケツ(LP)が完璧に設計されていたとしても、水道から流れてくる水(流入するトラフィック)の質が悪ければ、バケツがその機能を果たすことはできません。これは、流入するトラフィックの質がLPのコンバージョン率に直接影響を及ぼすことを意味します。



従って、LPの成果を最大化するためには、まず流入するトラフィックの質、すなわち「水の状態」を確認し、改善することが必要です。



流入経路の見直しも、広告や集客チャネルごとにチェックすべきってことですね。
広告とLPで訴求がズレていないか?流入の質をチェック



流入の品質でよくあるのが、LPのメッセージと広告側で全く違うことをいってしまっているケースですね。
例えば、アロマブリューといったコーヒーは他のコーヒーと比べて香りが広がるのを魅力としています。ですが、広告側ではこのコーヒーは豆にこだわっていてとか、ブルーマウンテンの豆が何%入っていて…といったことを広告で出していると。



ブルーマウンテンの豆が何%入っているということに惹かれて入ってきたユーザーが、香り高いと謳ったLPを見るんですよ。
ブルーマウンテンの豆に魅力を感じているユーザーにとって、不一致が起きてしまい、離脱してしまうことがあります。



それだと「思ってたのと違う」と感じてしまいそうですね。



なので、広告とLPで言っていることが違うといったケースによって流入の品質がおかしくなっていないか、を見極める必要があります。


広告とLPが連携していないと、コンバージョンは下がる



連携していないことなんてあるんですか?



何故こういったことが起きてしまうのかというと、LPを作っている会社と広告を運用している会社が別の場合です。
そこを分けているから、いわゆる制作時の意図とか、製作時のメッセージのラインと、広告のところが連携されてないので、そういう訴求違いみたいなことが起きてしまいます。



なるほど!



よくあるのが、同じ会社でやっていても、違う会社でやっていても、そもそもLPを作るときに、「こういうふうなメッセージでいきましょう、こういう訴求でいきましょう」っていう流れとか、メッセージの意図とかをすり合わせてないケースもあります。



なので、まずその流入の品質っていうところでいくと、「広告とLPで全く言っていることが違うよね」みたいな話が起きているその原因は、そもそも広告とLPの制作会社が別だったり、もともとLPを作るときにそういうふうな訴求だったりなど、すり合わせがされてないっていうことが
多いです。


ファーストビューの離脱率をチェック



流入に問題がない場合はどこに問題がありますか?



流入の質が問題ない場合、LPの方の訴求力に問題があるということになります。



その中でどこから見るのかですが、基本的に、最初はファーストビューをチェックします。
ファーストビューっていうのは、要は基本的にLPを表示したときに一番最初に出る部分の範囲のことです。
それはパソコンでもスマホでも同じです。



なのですが、そのファーストビューの部分、結局お客さんが入ってきて、ユーザーが入ってきて、大体そこで6、7割ぐらい普通に離脱します。ある程度のものを作っても6割ぐらい普通に離脱します。
そこでまず、ファーストビューのところの離脱率が、例えば80%とか90%という高い値になってないか、みたいなことを確認するのが1番目かと思います。



離脱率が80%を超えてる場合って、具体的にどんな問題が多いんでしょうか?



もしそれがすごい高い数字になってしまっているのだったら、そもそも入ってきている流入に対して、
・期待外れのファーストビューになってしまっていないか
・広告側が言っていること、広告主が言っていることより弱い内容になっていないか
・そもそもそのキャッチコピーが引き付けられる内容になっていないか
をまずファーストビューでは確認する必要があります。
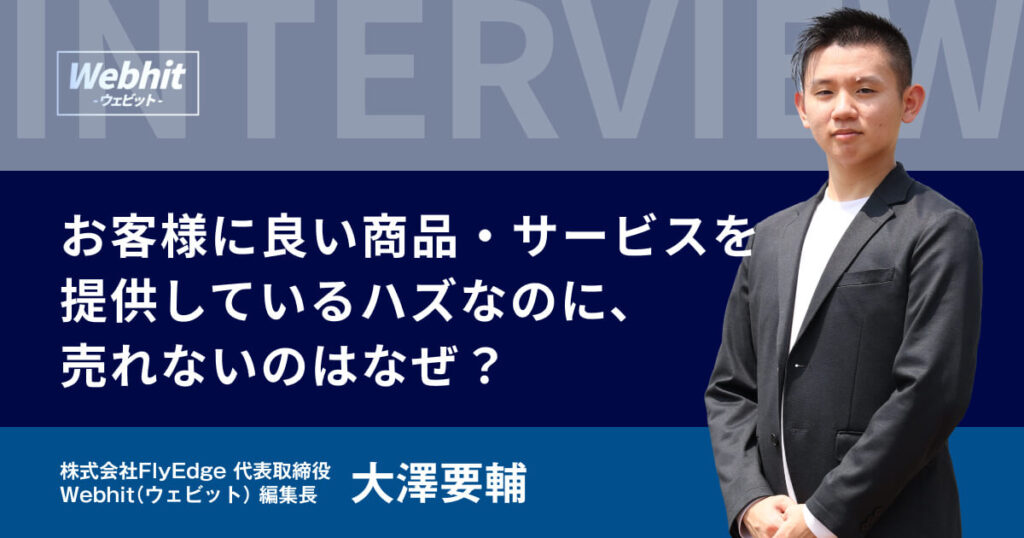
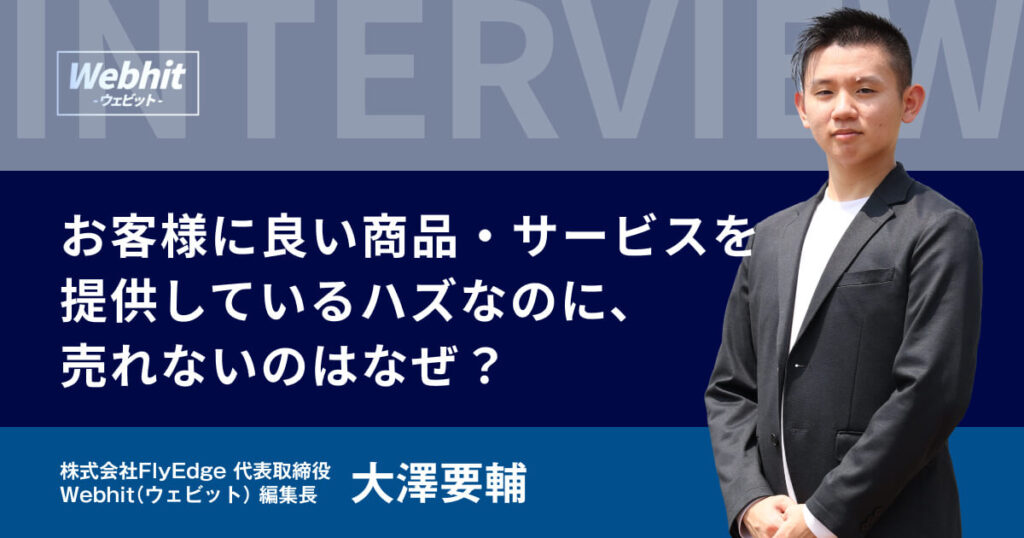
ユーザー思考に合ったLPの構成が、成約率を左右する



大きな範囲ではもう一つあって、それが「LP全体の流れ」ですね。
例えば、20代後半向けの化粧水とかの場合。



化粧水のLPでは、”しっとり感”を重要な売りにしているとして、ファーストビューでは、”しっとり感”、製品の価格、商品名、そして購入を促すボタンが強調されます。これにより、お客様は製品に対する興味を
持ち、詳細を知りたくなります。



お客様がLPを下にスクロールすると、化粧水が1日経っても、あるいは
7日経っても肌をしっとりと保つ理由が説明されています。
しかし、ユーザーはインターネット上の情報を簡単に信じないため、
製品の信頼性を高めるような、著名人やインフルエンサーの推薦、雑誌掲載などで情報の信ぴょう性が増します。



たしかに、根拠や第三者の評価があるほうが安心します。



さらに、ユーザーが自分の肌の悩みに合った製品であるかどうかを確認できるよう、特定の肌の悩みに対する製品の有効性を強調しなければなりません。
製品の効果の背後にある成分や、肌への安全性についての情報を伝えることで、ユーザーは安心と信頼をもって商品を購入します。



しかし、LPのどこかでユーザーの期待と実際のコンテンツが一致しない場合、例えばその成分がそもそも刺さってない、要はターゲットを変えた方がいいかもしれないっていうケースもあります。



でも、どこで刺さっていないのか、見極めが難しそうです。



LPを直すだけでどうにかなるものに関しては、そこの該当部分を直すだとか、お客さんの思考の順番がそもそもこうじゃないよねとなれば、
それを入れ替えるようなことをやっていく。
これをやる時に、Webのデータだけでこれの順番が正しいかとか、
お客さんの悩みを拾えているかをきっちり改善しきるのはすごく難しい
です。


数字だけでは限界。ユーザーの声を反映した改善が鍵



結局、出せるのはせいぜいLPの長さを割合で分けて、ここの割合までで、どのぐらいで離脱してるといったことを表す数字ですね。
でも、お客さんがそこで何を思ったかってわかんないわけです。



そのため、ユーザーインタビューなどを通じて、実際の訪問者の反応やニーズを把握し、LPの内容を調整することが効果的です。
直接的なフィードバックを取り入れることで、より多くのお客様を購入に導くことが可能になります。



ユーザーの不安や疑問に応えて寄り添うのが重要ということですね。


まとめ



では最後に、今回のテーマについて簡単にまとめていただけますでしょうか。



LPへのアクセス数はそれなりにあるのに、CVRが低い時、一番はLPに入ってくるアクセスに、そもそも流入品質の問題があるケースです。
それに対して広告とLPがしっかり連動したメッセージになっているのか、そもそもLPを設計するときや広告を設計するときにメッセージ自体の訴求を見直さなきゃいけないよねという話が一つ。



もう一つが、LPの流れやファーストビューですね。
まず入ってすぐのところが、広告に対して訴求負けしてないか、お客様に刺さるものになってるのか、みたいなところですね。
そこが大体6から70%ぐらいの離脱率であれば適正ではあると思うので、90%とか80%後半とか、異常な離脱率になっていないかの見直しをする。



最後はLPの中の流れですね。
全体の流れの中で、入ってきたお客様の感情や思考の状態の部分です。
それに合わせて、回答を次から次へとしっかり出すことができているのか。
回答がお客様にフィットしていないというケースがあれば、その構成の中で一部調整をしなきゃいけないでしょうし、順番を入れ替えることも必要になる可能性があります。



ただ、それをWebのデータだけでやるのはすごく難しいことなので、
ユーザーインタビュー等で地道に改善を行うということが必要かと思います。