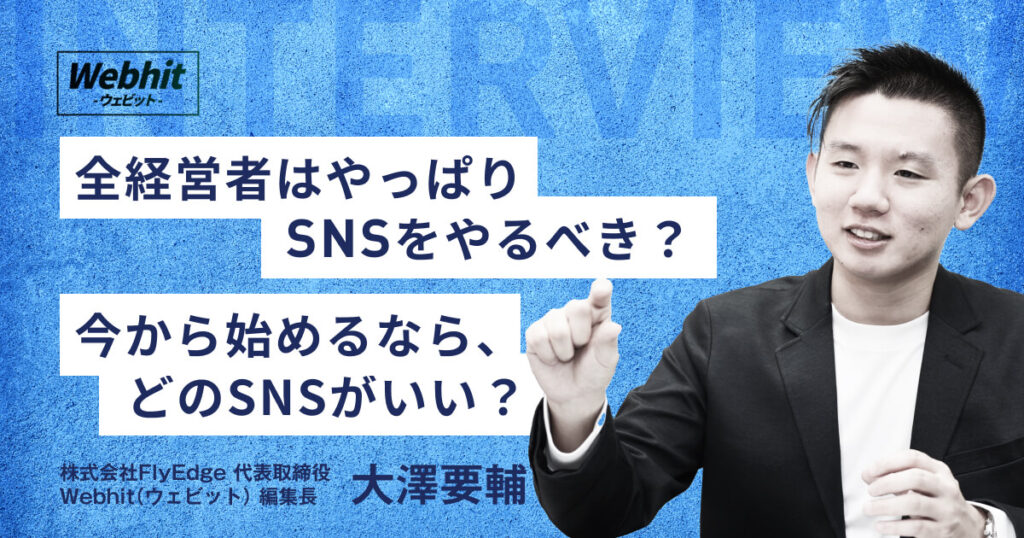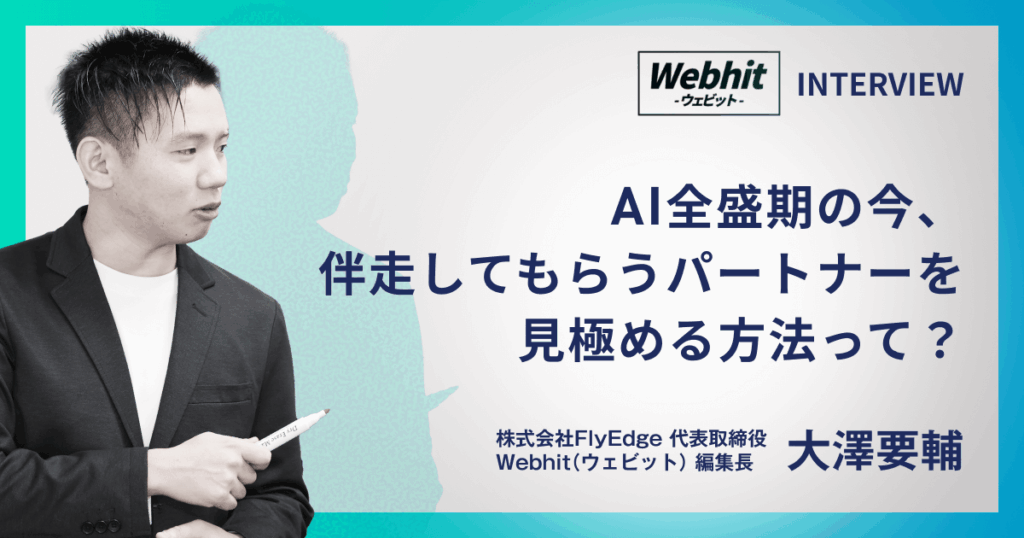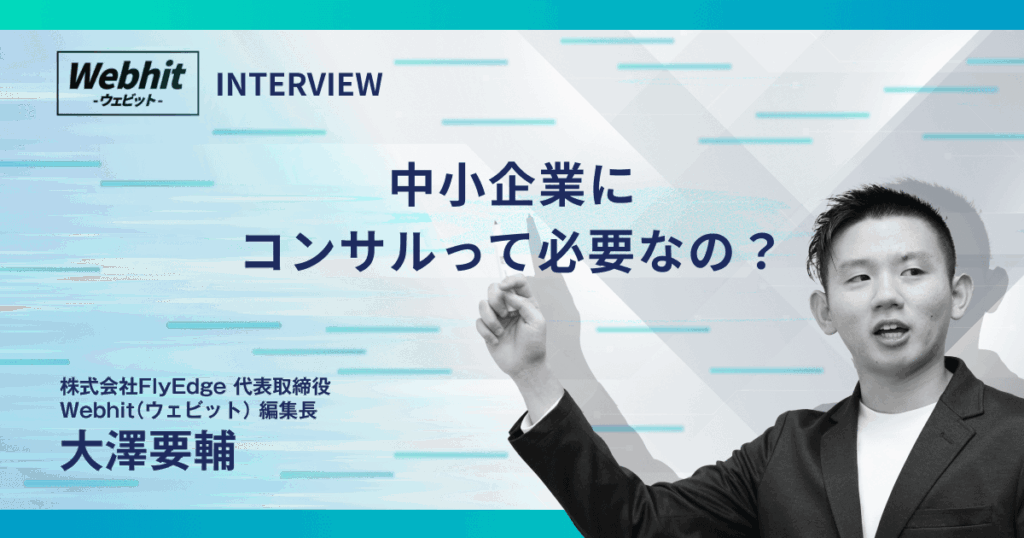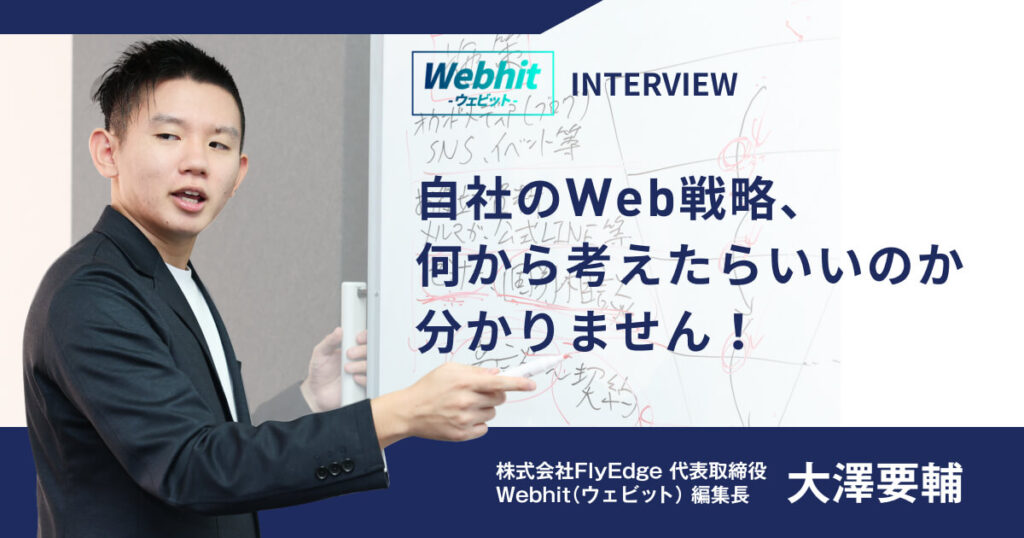Webhit 編集部
Webhit 編集部マーケティングで調査をやった、戦略も立てて分析もしたのにもかかわらず、集客ができなかったり売れなかったりといったお悩みについて、その原因はなんでしょうか。



調査・戦略・分析。ここに欠けているものがあります。
それは「お客様」なんですよね。


お客様が見えていない?マーケティングで見落とされがちな本質



例えば、
・インターネット上でこういった商品が出ている
・アンケート調査をした結果、何十代の方がこのエリアに集中している
・競合他社はこれくらいの数がいて、こういうことをやっているので、自社はこういった戦略でいこう
のような分析をした結果、数字が出てくるわけですよね。



ですが、そこに「お客様」が抜けているんです。
変に丸めた戦略や数字にしてしまっていて、「お客様の声」が聞けて
いないから売れないんです。



たしかに…数字ばかりを見ていると、個別の「生の声」って見落としがちですよね。
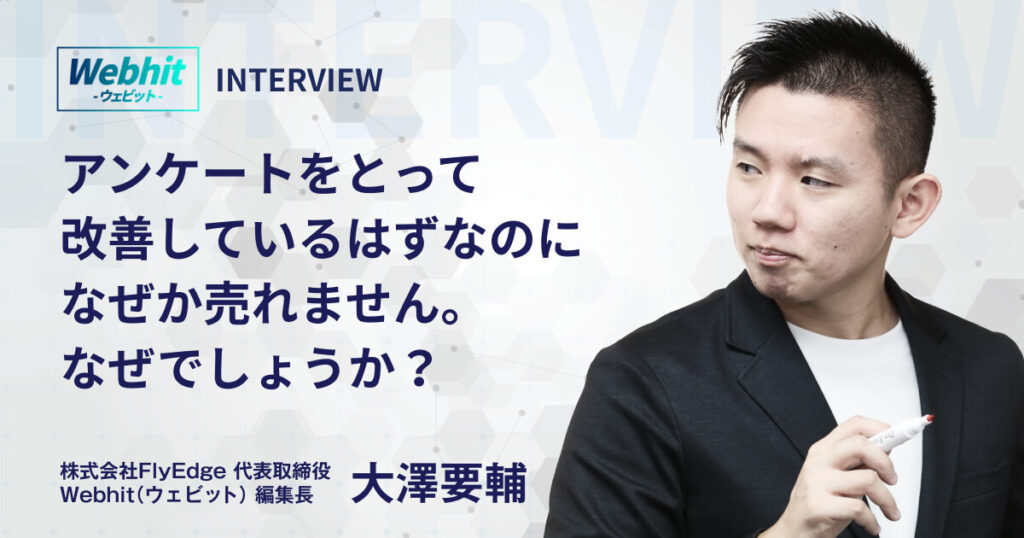
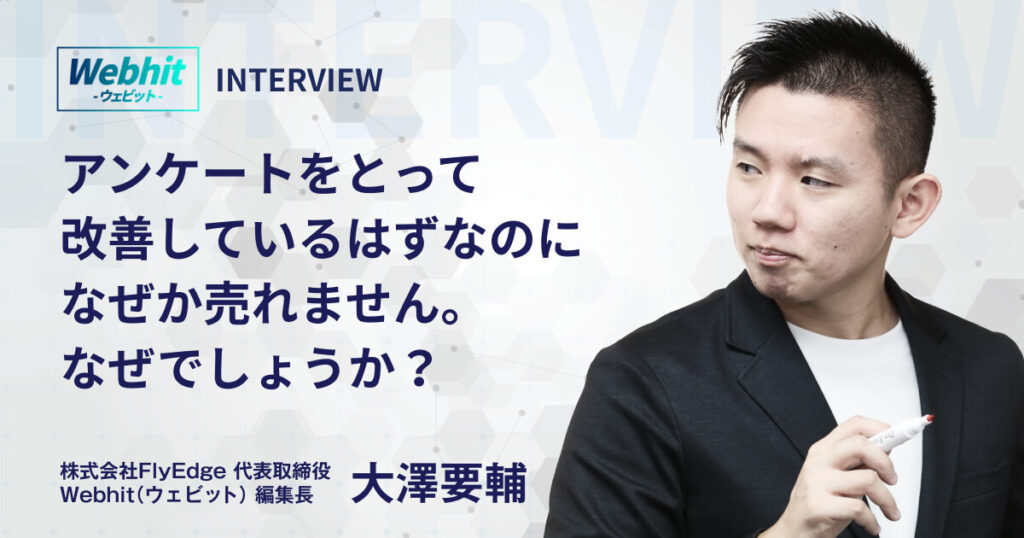



例えば、整体系だとお客様の悩みって肩こりや腰痛がありますよね。
でも、肩こりや腰痛という言葉だけで捉えていませんか?ということ
なんですよね。



主婦の方であれば、スーパーで重い荷物を持った後にジワジワと肩に痛みが出てきたとか、腰痛の人であれば、長時間座りっぱなしの生活を
していたことで腰に痛みが出てきたとか。



なるほど…!そうした「日常の背景」まで拾えているかがカギなんですね。単なる肩こりで片付けてはいけない、と。



そうです。
要は、背景を全部捨ててしまっているんですよね。お客様の悩みはそれぞれいろんなパターンがあって、背景が必ずあるわけじゃないですか。



なので、お客様がいない状態での調査・戦略・分析は空虚なものになってしまうんですね。
お客様がいないので、もちろん売れないし集客もできないわけです。



お客様が整体院に通うことを決めましたとなったときに、なぜ整体院に通うことを決めたんですか?と。
病院に通ったり薬局で薬を買ったり、整体院ではなくマッサージやエステでもいいわけじゃないですか。



そういうことを聞きながら、お客様が実際に何を考えているのかまでを聞かないとだめです。
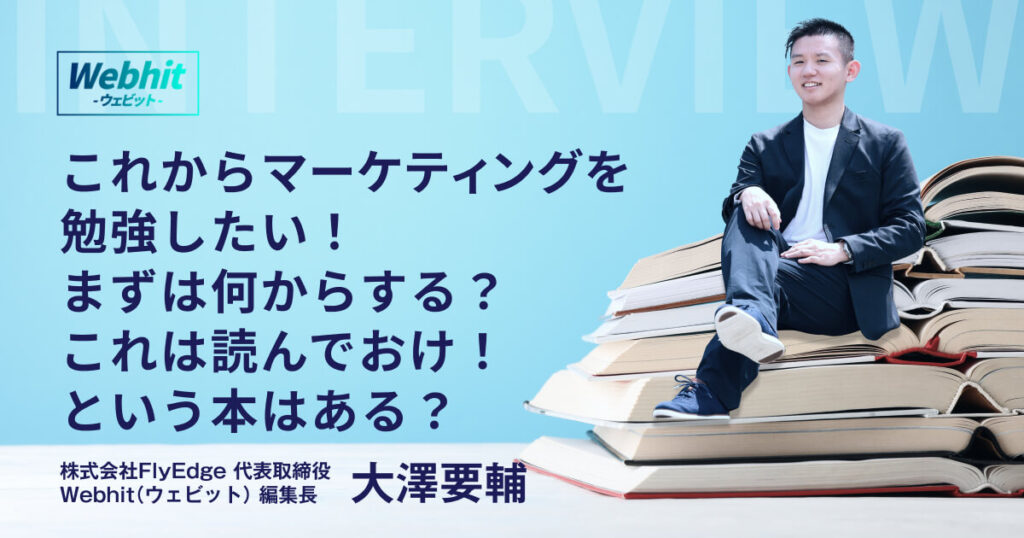
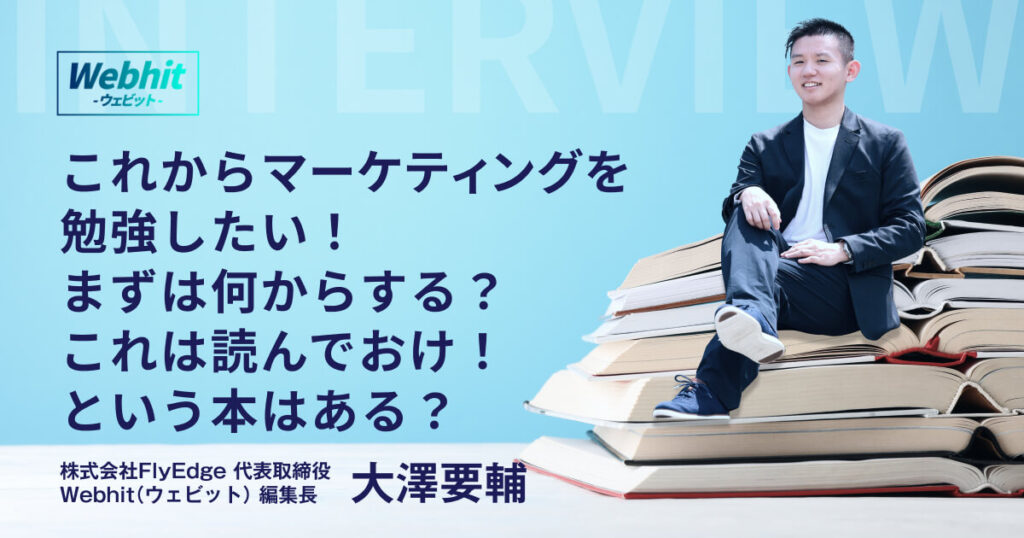
「数字を読む」だけでは不十分?Webマーケティングの落とし穴



ありがとうございます。
Webマーケって、数字だけを見ている印象なんですが…。



数字ももちろん大事。
結果は全て数字分析が大事なのでそれはやるんですけど、ただ、数字は全部お客様なんですよね。



「1」という数字をとっても、広告の表示1回分は、どこかの誰かが1回見てくれたということでもあります。
その数字をお客様だと思えないような分析をしたり、いいように当てはめちゃったりしている可能性があります。
「これはこのぐらいのクリック率なんで」、「調査でこうやって出てるんで」のようなことです。
楽をしていると言えばそうですし、マーケティングには向き合っていないですよね。



マーケティングっていう仕事の見え方が、キラキラしていて華々しい
感じというか、お客様がドーンと成功させている華やかな印象がある
らしいんですけど、全くもってそんなことはありません。
スーパー泥臭いんです。



華やかな成果の裏側には、地道なヒアリングや観察といった「泥臭い努力」があるわけですね。



そういうところの認識の違いなのかなとは思います。
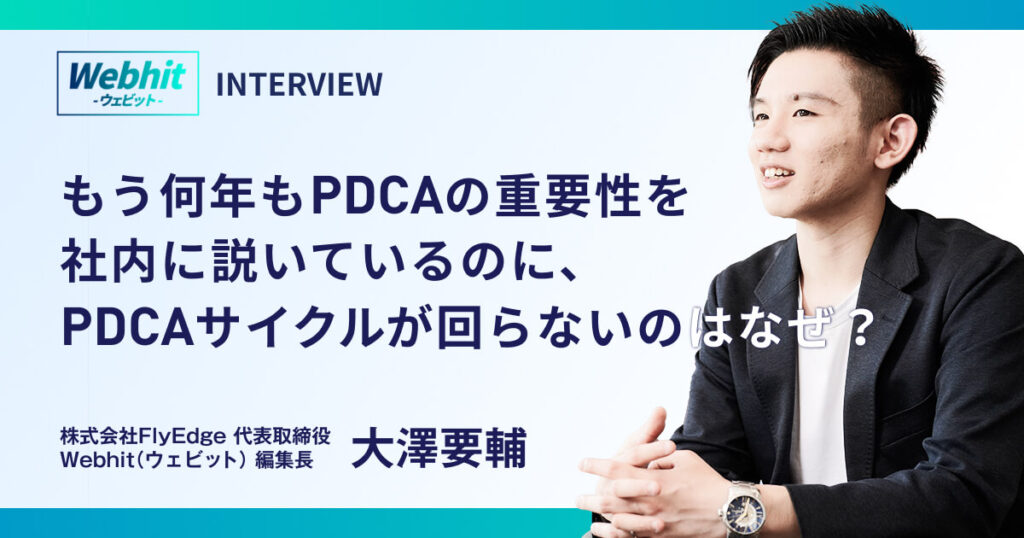
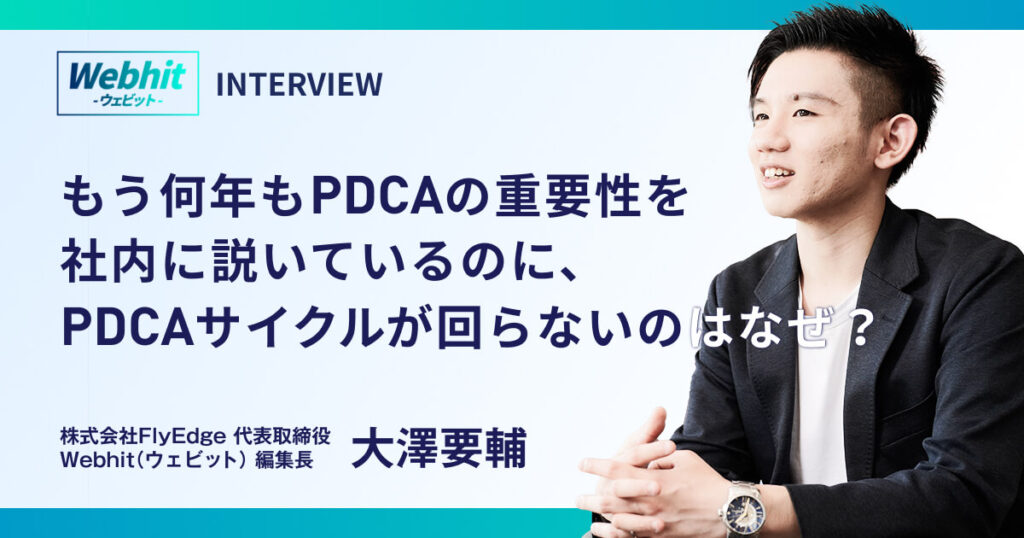


売れない本当の原因は「お客様を無視した戦略」



なるほど…。
お客様への向き合い方が足りないということでしょうか。



お客様を軽視してると思いますね。



「戦略やったし調査もやったし、分析もやって、でも集客できない、売れない、なんで?」っていう時は、大体お客様を無視してるんですよ。
なので、何をやるよりもまず先に、時間をかけられるんだったら、
かけられなくてもまずお客様に一言でも意見をもらうことが一番早い。



各数字やデータポイントが実際には一人一人の顧客であり、その背後にはそれぞれの物語が存在することを忘れてはなりません。
デジタルマーケティングの成功は、数字を顧客の声としてどう解釈し、対応策をどう講じるかにかかっています。


リアルな接客体験に学ぶ、お客様視点の重要性とは



よくある例では、飲食店さんです。
僕も、4年間の飲食店の経験があるのでわかりますけど、営業時間中は
やっぱりすごく忙しいわけですよ。
もう、余裕がないときは本当に余裕がないんです。
なので、それは僕もすごくわかるんです。



ただ、僕は当時キッチンをやってたんですよね。
和食の会席料理店だったんですけど、ホールさんが足りないときがあるんですよ。



ホールさんが足りないときに僕が何をするかっていうと、当然ながら
キッチンの格好ではあるけど、そのままお皿を持って、要はサービングの提供をやるんですよ。それでお客さんに説明したりしてたんです。
鍋会席の専門だったので、野菜の説明とかいろいろしてたんですけど、それをやるときも、どういうことを言うとお客さんが笑顔になってくれるのかとか、逆に言えば、こういう説明だとお客さんは全然何とも思ってくれないとか。



例えば、そこで一言「今日は、どういう食べ方をされたいなどはありますか?」とか「しゃぶしゃぶが好みで今日は来てくださったんですか?」とか。



「今日はちょっとさっぱりめで食べたいんですよね」ということが聞けたら、「だったら、レタスとこの野菜を一緒に茹でて、そこに豚を巻きつけて食べるとさっぱり食べれるので美味しいですよ」と。
そういうことを説明すると、「それは知らなかったよ」と反応が返ってきて、そこで商品が売れるわけですよ。
「今日はさっぱりした気持ちで食べたい」っていうお客様の声を聞かなかったら、いつも通りの標準的な説明をして終わりなんですよ。



標準的な説明をしてはいつも通りに食べて、お客様は「もっとさっぱりしたのが食べたかったな」と思いながら帰るわけです。
結局満足に繋がらないので、継続して来てくれないとなると、結果的に売れないんですよ。



僕がサーブを出したときに、お客様へ一言聞いて、返ってきた返事に対して一個回答を出して、「そんな食べ方もあったんだ。ここの食べ方は確かにさっぱり食べれるね、美味しかったらまた来ようね」になるわけですよ。それが”売れる”になるんです。



本当にちっちゃい話ですよ。本当にちっちゃい話ですけど、一言お客様に聞いて、それを「返ってきたものに対してちゃんと答えていく」っていうことに置き換えられれば、少しずつ売れるんですよ。



でも売れないのは、そういうお客様の声を無視したり、「自分たちにとってはこれが効率的だから、これを駄目だと思ってはいけない」みたいな考え方をしてるんで、いつまでも売れないんでしょうね。



確かに「マニュアル通り」って、飲食店にはよくありますよね。



マニュアルが大事なのはわかりますけど、使い方次第ですよね。
誰がやっても60点から80点ぐらいを出せるっていうのはすごい大事なことなので。
日本的な美的感覚にもちょっと近いですよね。
誰に聞いても親切だし、誰に聞いてもしっかりやってくれる。
すごく日本的な考え方だと思います。
ただ、それ自体はすごく大事なことだなと思うので、そこでもう一歩
お客様側に寄れるかどうかですね。


「お客様の気持ち」に寄り添えるかどうか



どんなに忙しくても、例えばそれがチェーン店でも、「今日は、他に何かこういうものが食べたいと思って来たんですか」みたいなことを一つ切り出せるかどうかですよね。そこを面倒くさがると売れなくなります。
お客様って、大体嫌なときって言ってくれないので、例えば「美味しかったよ」とは言うかもしれないですけど、あんまりだなと思ったら普通に帰ってしまいます。意外と言わないんですよ。
面と向かって人にクレーム言わないじゃないですか。



例えば、友達とご飯を食べに行っても、友達の前でいきなりクレームになるのかなっていうのありますし、誰かにご馳走になっているときにも結局その人の顔を立てなきゃいけないから変に言えないし。



だからこそ、こちらから積極的に聞きに行く必要があるんですね。



そう、お客様の声ってどんどん後ろに隠れていくんですよ。
自分から行かないとお客様の声は取れないんです。



よく分かりました。
ありがとうございました!