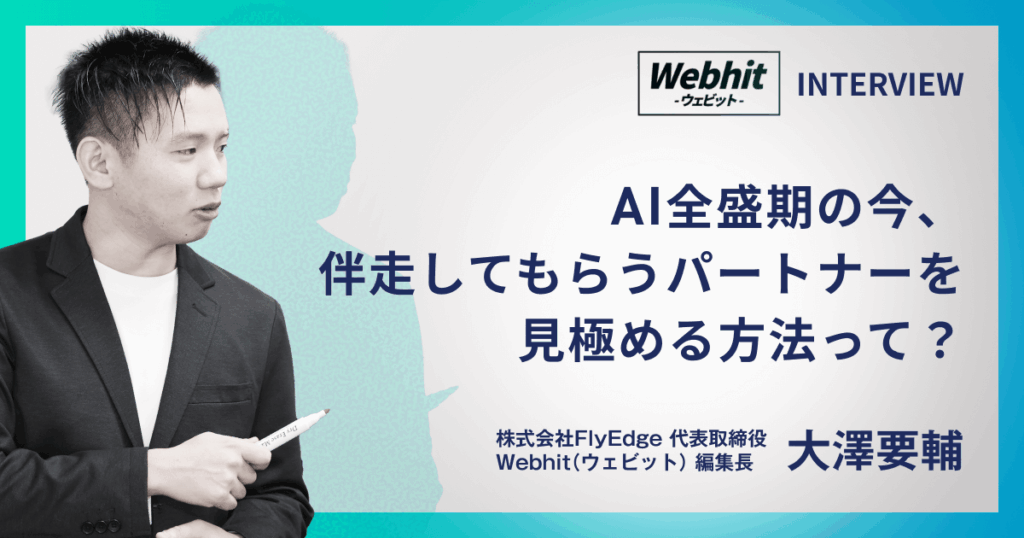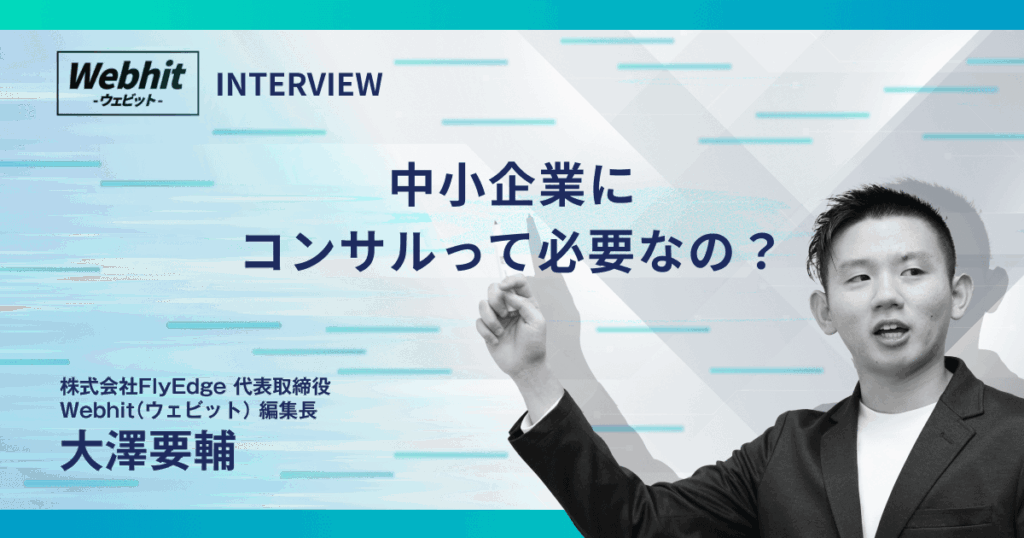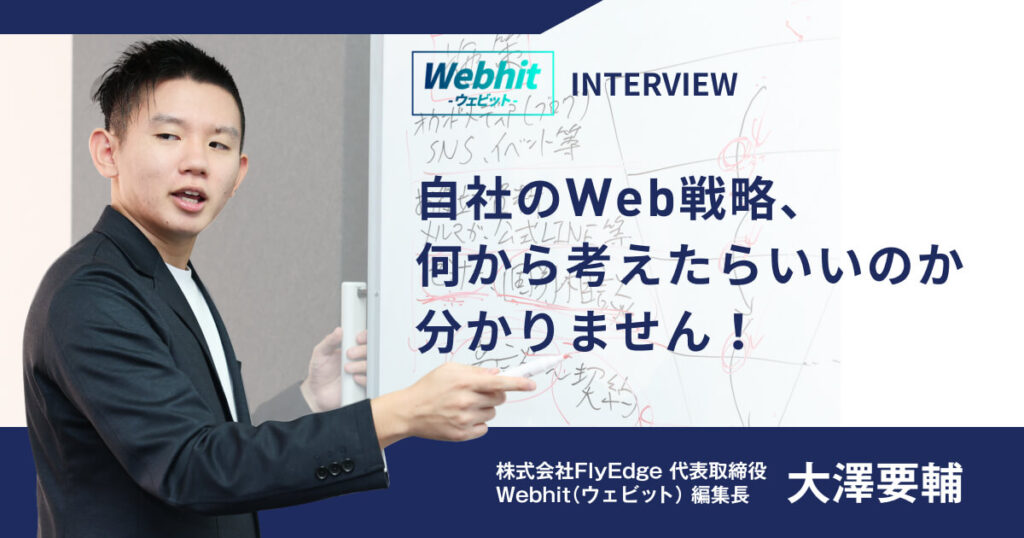Webhit 編集部
Webhit 編集部今回は「マーケティングで成果を出しやすい組織とは?」について
お話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。



はい、よろしくお願いします。



早速ですが、マーケティングで成果を出しやすい組織について、
共通点はあるのでしょうか?



はい、あります。
成果を出しやすい組織は共通して、届ける商品やサービスはもちろん、どんなメッセージを発信するのが、お客様のためになるのか考え抜かれている組織です。





なるほど。
その考え抜かれている組織というのは、考え抜かれていない組織と
何が違うのですか?



例えば、社内のマーケティング改善会議を行った際、成果が出にくい
組織では、
「数字がどうなったのか」
「次はどうやってその数字を取るのか」
「どうやったら売上が上がるのか」
といったことだけが話し合われていることがほとんどです。



これは自社都合でしかなく、お客様の都合は全く考えられていません。お客様不在でマーケティングの改善会議を行っている状態です。



お客様ではなく、数字を見ているということでしょうか。



そうです。
反対に成果が出やすい組織の場合は、
「自分たちが出しているメッセージがお客様に届いているか」
「お客様から受け入れてもらえているか」
といったお客様目線を軸に話し合っています。



もちろん、その売上の動向や主要な指標に関する話もしますが、
仮に受け入れてもらえていないとすれば、どの部分が受け入れられて
いないのかを分析します。
そして、表現や言葉、伝え方の改善などをメインに話し合っている
組織は、成果が出やすい組織になるでしょう。





なるほど。
現状、成果が出にくい組織になってしまっている場合、どのように
組織を改善すると、成果が出やすい組織になるのでしょうか?



そうですね。 結局、どんな商品もサービスも売れなければ意味がありません。
「売れる」ということは、まずお客様に知ってもらい、理解、納得してもらって、買うという行動につなげるものです。
そのため、社内会議では、認知・理解・納得といった各ポイントから議論を始める癖をつけることが、最初に取り組むことだと思います。



そうは言っても、企業側が人の意識を変えようとするのは傲慢な話だと思っています。人の意識は、行動でしか変わりません。



ダイエットで例えると、いきなり「ご飯を食べないようにしよう」
という意識に変えるのは難しいですよね。



そうですね、辛いですね。



しかし、自炊をしている人の場合、スーパーに行った際に、油分や糖分が多いものを買わないという行動から変えられます。
「買っていいものを何個までにする」というのも、具体的な行動です。



突然「ランニングしよう」「 できるだけ運動をしよう」といった意識に改革することは難しいと思います。
そのため、「1日10分、家の周りを散歩する」「何時から何時までやる」とカレンダーに入れて、疲れていようが何だろうが必ずやる!というように行動していけば、意識は変わっていくでしょう。



マーケティング組織においても、「お客様のことを考えよう」と突然
言っても、何を考えたらいいのかわからないため、意識は変わらないと思います。



そのため、会議の中でお客様のことを考えるポイントを最初から議題のベースに入れておくことから始めましょう。



まずは何から始めたらいいのかわからないケースも多いと思うので、ダイエットの具体例はとてもわかりやすかったです。
組織の話でいうと、組織自体は少人数でも問題ないのでしょうか?



少人数でも問題ありません。社長と社員数名しかいない中小規模の会社であっても、問題なくマーケティング組織として機能できるため、少人数でも問題ないでしょう。



大人数でも問題ないのでしょうか?



もちろん、大人数でも問題ありません。
しかし、その場合、関係する人数が多くなるため、1人ひとりのターゲットへの理解度やペルソナの言語化レベルの違いが発生しやすいです。



そのため、大きなマーケティング組織では、ターゲットやペルソナ、
商品・サービスで訴求すべきポイントの共通認識を持っておくことが
重要なポイントです。
これができていないと、知らず知らずのうちに施策やメッセージに
「ズレ」が生じることになります。



ある程度大きな組織であれば、商品・サービスにブランドがあるケースの方が多くなるかと思います。
そういった観点を考えると、商品・サービスのブランドイメージが崩れることに繋がりかねません。
そのため、認識の平準化は必ず行う必要があります。





そうすると、少数組織の方がやりやすいのではないかと感じましたが、いかがでしょうか?



そうですね……。
何をもって「やりやすい」とするかは、会社や関わる人によって
解釈が変わると思います。
小回りが利くという観点で言えば、小さいマーケティング組織の方が
やりやすいかもしれません。



少人数の組織であると、大きな意思決定ができる人間とマーケティングの施策を運用する人間が、比較的近い距離にいることが多いため、認識のズレが起こりにくく、小回りが利きやすいと思います。



組織の大きさはあまり関係なく、認識のズレを起こさないようにして
いくことがポイントという感じでしょうか?



そうですね。人数という観点で言うより、認識のズレを起こさないようにしていくことがポイントとなります。



人数が多くなればなるほど、マーケティング組織の中の一部を管轄するマネージャーやリーダーのような役職が必要になってきます。
組織的な成功には、マネージャーやリーダーのディレクション能力が
どの程度かというのも大きく関係してきます。



そのため、組織が大きな規模になってくると、マーケティング能力とは直接的に関係ないマネジメント能力や、ディレクション能力も問われる場面が増えてくると思います。



そうすると、規模によって違ってくるかと思いますが、経営者は
マーケティングをどこまで社員に任せるべきなのでしょうか?



任せられるのであれば全部です。
そうは言っても、現実的な話として、全部を任せられないことの方が
多いのではないかと思います。



特に中小企業だと、経営者や役員などの経営陣と現場スタッフ間で、
商品・サービスに対する理解や戦略の構築・実行能力に、大きな差が
開いていることが多いのが現状です。
そのため、現実的には任せたいけれど、任せられないことが多くなる
のだと思います。





そうですよね。経営者は社員に任せられるのなら全部任せて、別のこともやりたいですよね。
では、これまでコンサルティングで、さまざまな会社をサポートされてきたと思いますが、経営者と現場スタッフのバランスはどのようにすれば取れるのでしょうか?



弊社ではこれまで、中小企業に特化する形で30業種以上のコンサルティングをやってきましたが、どの業種においても、経営者が舞台を整えたうえで、担当者が舞う状態を作るのがいいと感じています。



中小企業規模の会社の場合、知識がなく、
「マーケティング業務や改善をどう進めていいかわからない」
「次に何をやればいいのかわからない」
と手が止まることがほとんどです。



そのため、経営者はマーケティングの戦略を描き、次に担当者が具体的に何をすればいいのか、タスクレベルまで落とし込む必要があります。





タスクレベルまで落とし込むのですか?



はい。売り上げを上げたいケースでお話しすると、新規開拓で戦略を
作る場合、営業活動分野で新規開拓の戦略を立てて進めていきます。
しかし、経営者が担当者に「よし、お前ら新規開拓してこい」と
言っても、何をどのぐらいやればいいかわかりませんよね。



そうですね。何をどうしたらいいのかわからず動けないと思います。



そうですよね。
例えば、新規の売り上げが毎月プラス100万円必要で、自分たちの商材の販売単価が10万円だったとしましょう。



この場合、10件の新規受注を取る必要があります。
商談からの成約率が20%だとすると、50件の商談が必要になります。



そうですね。



アポイントで約束してもドタキャンする人もいるため、50件の商談に
するためには、アポイント獲得数は70件は必要です。



アポイント獲得をアポ率が1%のテレアポで行う場合、70件の商談を
毎月取ろうと思ったら、7000件の架電が必要になります。



月の営業日が20日だとすると、7000件架電するのであれば、1日当たり350件の家電が必要になるでしょう。



はい、そうなりますね。



そして、担当者がABCの3人いたとします。
Aさんはテレアポ経験があって、比較的慣れており、BさんとCさんが
慣れていない場合、



「Aさんは1日に150件架電をして、BさんとCさんは1日に100件架電を
してください。
月の売り上げが100万円必要で、これまでの実績で見るとこういう割合になるため、商談アポイントが70件必要なんです。
アポ率は1%なので、100〜150件お願いします」



「アポ率が1%から1.5%になったらもう少し皆さんが楽になると思うので、アポ率を上げるための改善もやってください。
週次MTGで、30分でやりましょう」
といったところまでセットされると動けるようになります。



そうですね。具体的にどうすればいいのかわかります。



リストが準備されていれば、リストにかけていけばいい。明日から
やることが明確になって、初めて担当者は動けるようになります。



例えば「1日350件の家電が必要なので、やってください」 という指示
だけだと、350件を誰が何件担当するか考える必要があるため、手が
止まると思います。



この程度であれば、1〜2日すると動き出すかもしれませんが、わざわざ止まる時間を作る必要はないと思います。



そのため、経営者がルールやマニュアルを作って舞台を整え、その通りに回せることが、特に小規模のマーケティング組織では、重要なこと
だと思います。



経営者がいかに舞台を整えるかが肝心なのですね。



はい。そうは言っても、「優秀な人を雇えばそんなことをしなくていい
のではないか」という議論は当然、巻き起こると思います。



しかし、非常に優秀な人が、一般的な事業会社の1人マーケターになる
ことはほとんどありません。



よほどいい条件を出さないと、少なくとも正社員では入ってきません。
起業時などの最初からチームにいる状態ではなく、 途中から中途採用で取ればいいという発想は正直なところ難しいと思います。



業務委託で、全体の落とし込みができる人を頼もうとすると、最低でも月30万円から50万円程かかると思います。



そのため、外部の人に入ってもらい、戦略を立ててもらったり、分解をしてもらったりするコストをかけられないならば、経営者がやるしかありません。



どうしても経営者ができないのであれば、お金を使って外注するのも方法としては有効だと思います。



非常に細部まで整えてあげないと動けないんだということが
よくわかりました。



経営者は、「これぐらいなら日々言っているから、わかってくれている
でしょう」と言いますが、経営者の思いを大事にしている担当者は、
あまり多くありません。
「ずっと口うるさいことを言われている」という印象の方が強いかも
しれません。



そもそも、経営者と担当者は視座が違います。
経営者は自分の会社のためにお金を出して、万が一何かあれば、自分が全責任を取らなければいけません。
自分の子供のような扱いをしている方もいると思います。



しかし、担当者は正社員もそうですが、決められた時間で働く労働者
なんです。定時が決まっていれば、定時で帰ります。



はい。そうですよね。



そして、残業が発生したら「残業代をください」となります。
しかし、担当者は、あくまで設定された労働時間の範囲内で労働力を
提供する雇用契約になっていると思います。



そのため、会社側で仕組みを整えてあげないと満足な労働はしません。自発的に気がついたり、素晴らしい戦力を作ってくれたりすることは
ないと思った方がいいでしょう。



もし、それをやってくれる人がいるのだとしたら、本当に恵まれているので、感謝した方がいいと思います。



視点がズレていないかもチェックしつつ、土台をしっかり整えてあげることが、うまくいくコツだということがわかりました。
最後に、この記事を見てくださっている方に、一言お願いします。



はい、ありがとうございます。
マーケティングで成果を出しやすい組織にしようと思ったら、まず
お客さんを必ず議論の中心に置いている組織にする必要があります。
マーケティングに対して売上を求めるのは当然ですが、「お客様は
満足してくれているか」「いい提案ができているか」という点は、
営業活動でも気にするポイントだと思います。



そのため、お客様が満足していないにも関わらず、「お客様にこの見積書で必ず押し通せ」といった指示や、満足な提案もできていないのに、
「とにかく契約を取ってこい」という指示は通用しません。
これは、営業をやったことがある人ならば、絶対にわかると思います。



しかし、マーケティングになると、それを忘れてしまう方が結構います。
マーケティングはインプレッション数やCV数などの数字を見ながら
やっていきますが、Webマーケティングでもオフラインマーケティングでも、広告1枚の先では当然人が見ている状態になります。



そのため、お客様が認知してくれているのか、理解、納得してくれて
いるのかを、まず押さえていない限り、どんな広告やSNS、その他の
施策をやってもうまくいきません。



短期的にうまくいったとしても、すぐに頭打ちがくると思います。そのため、前提として、お客様のことを中心に据えられている組織であることが重要です。



経営者の、「本当は担当者に全部任せたい」という気持ちはよくわかり
ます。
しかし、基本的に中小企業で、現実的に組織を回そうと思うと、マーケティングの施策を担当者がすぐに行動できるレベルまで落とし込む必要があります。



そこのところを履き違えて、「優秀な人がいてくれれば」「彼らがもう少し勉強すれば」といったような他力本願、他責志向になると、組織も会社自体もうまくいかなくなるパターンが多くなります。
そのため、履き違えないよう気をつけていただきたいと思います。



ありがとうございます。