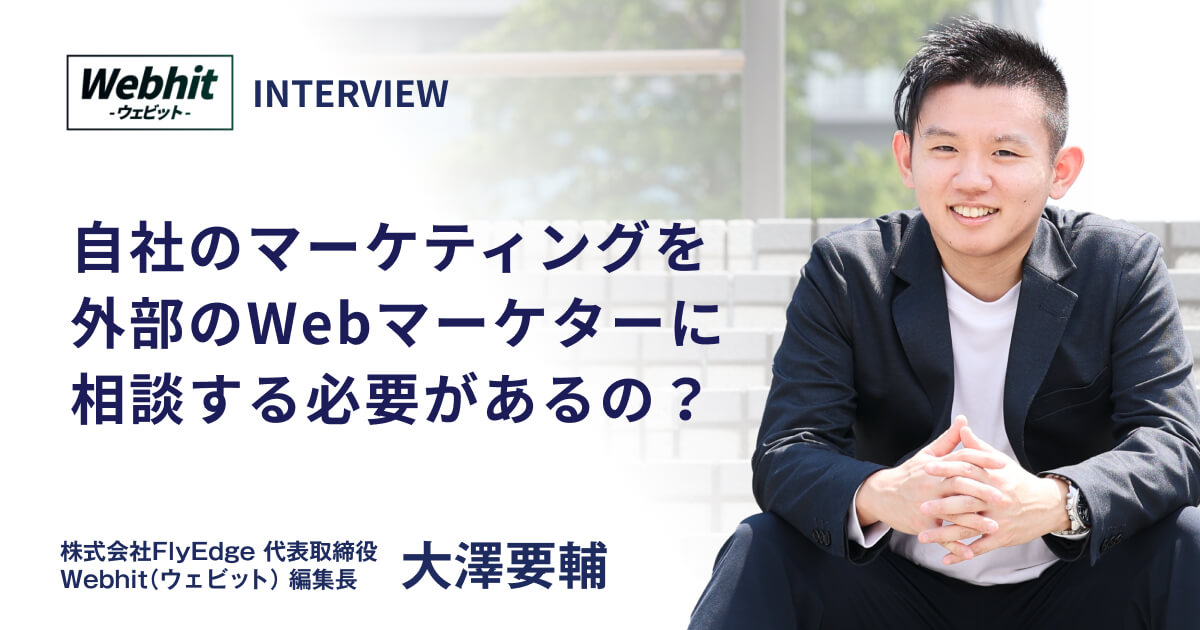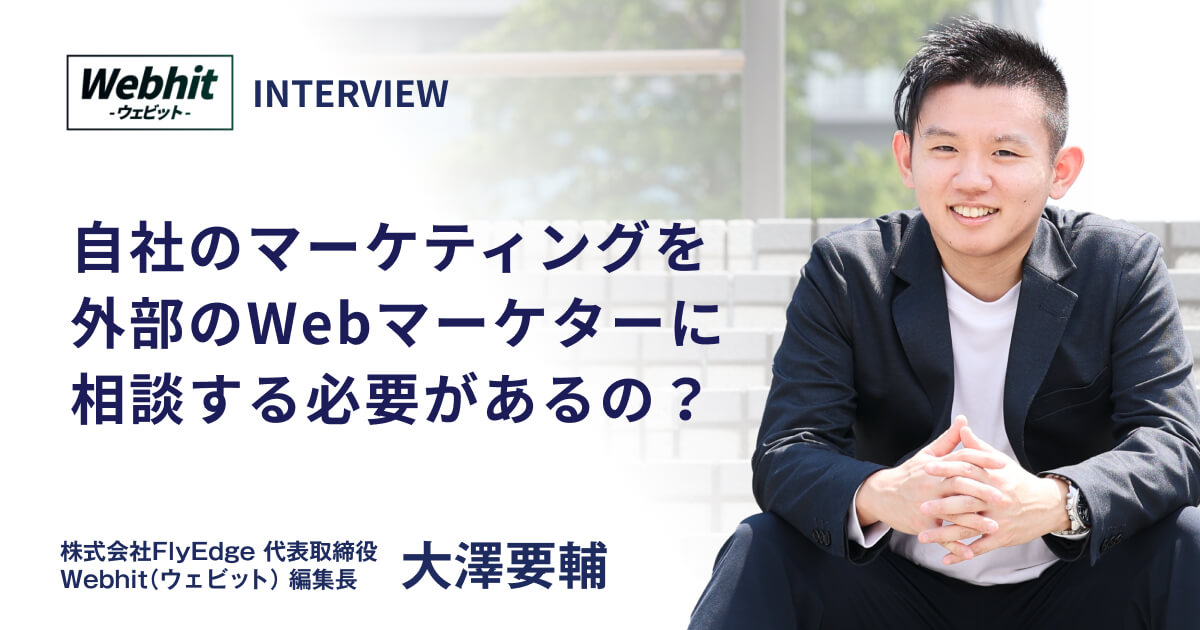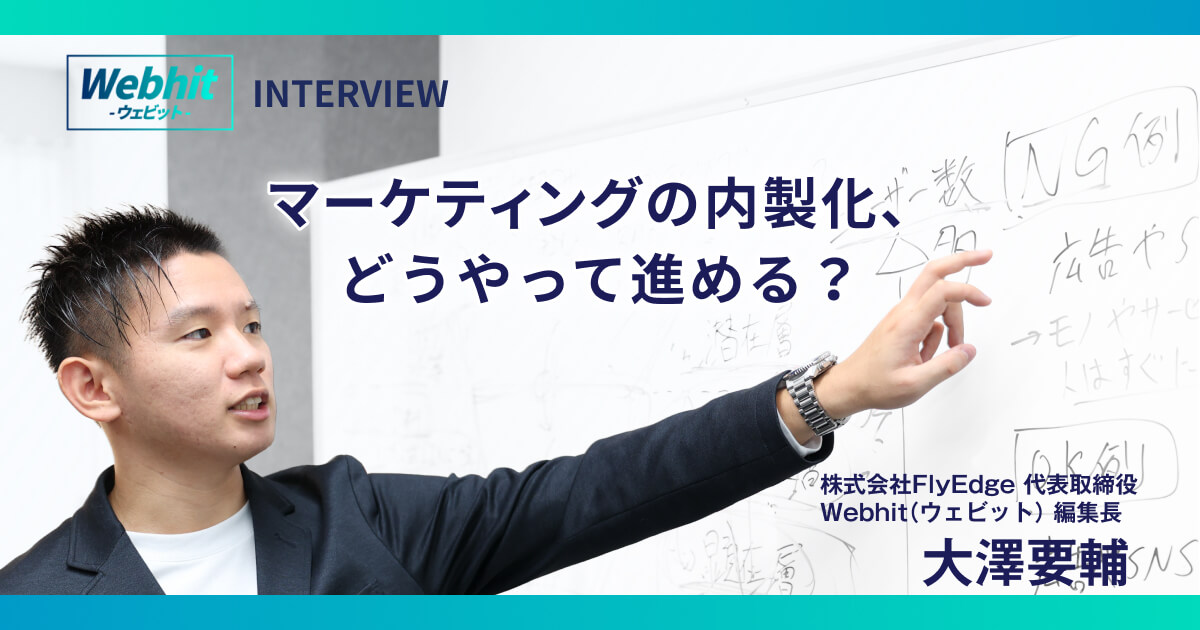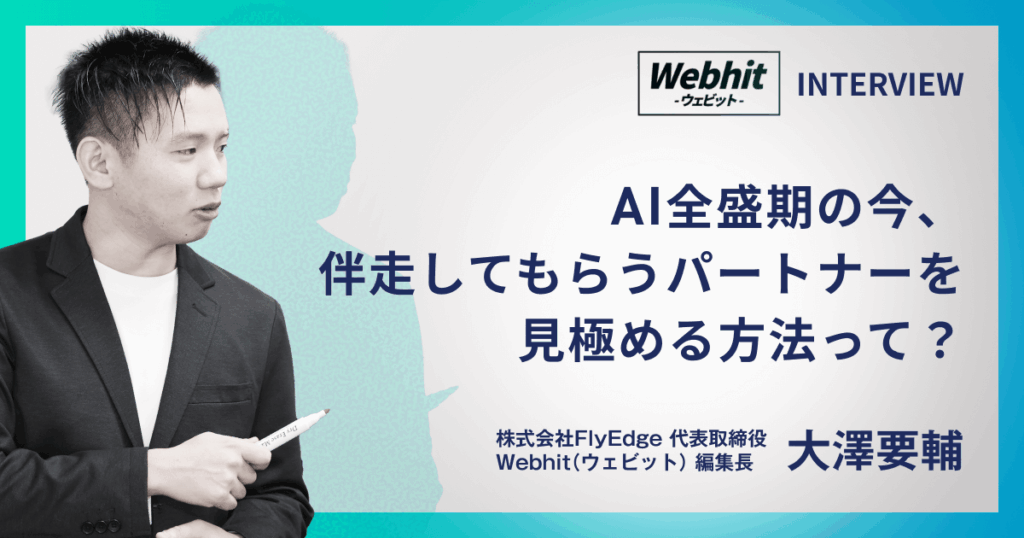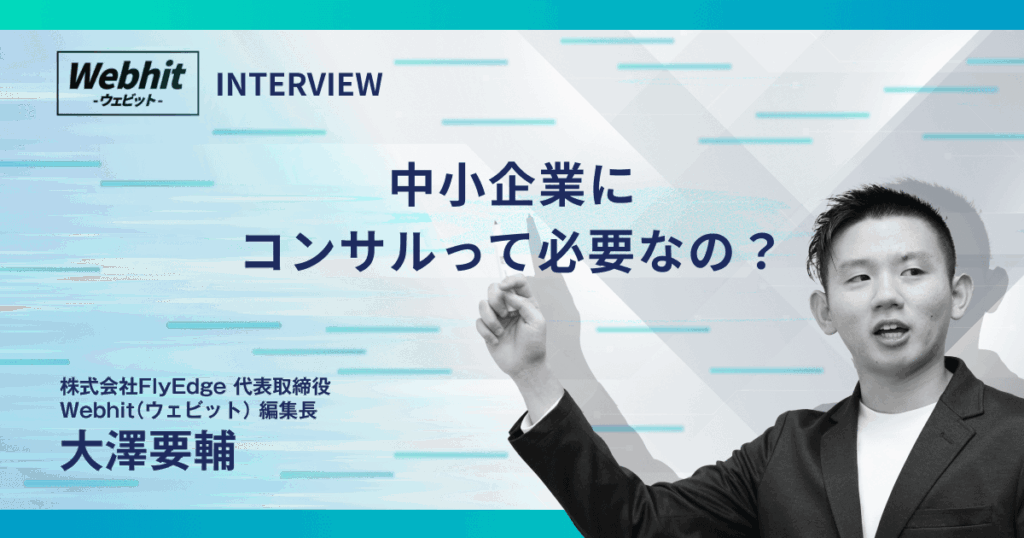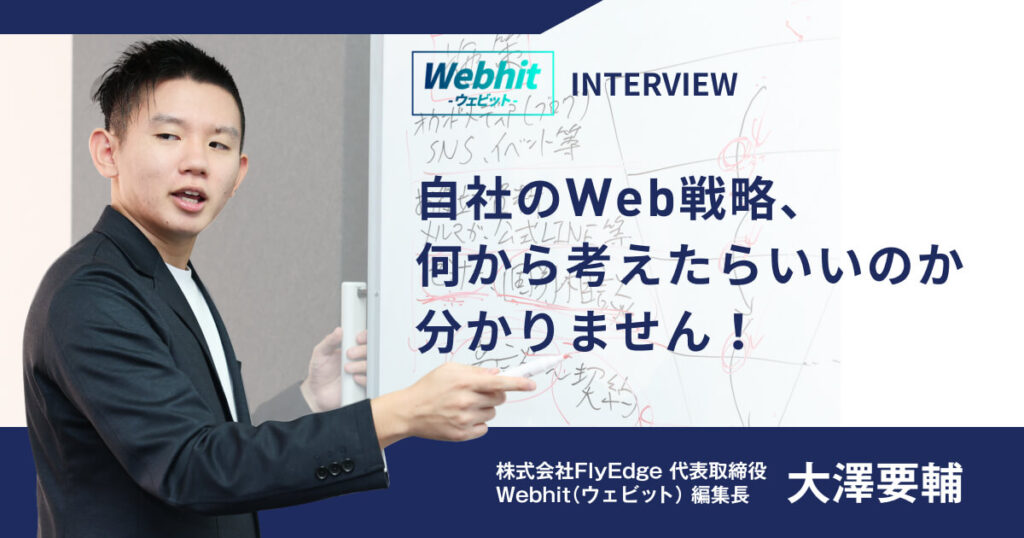Webhit 編集部
Webhit 編集部今回は「マーケティングの内製化、どうやって進める?」というテーマについてお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。



よろしくお願いします。



初めに、マーケティングの内製化というのは、どういうものなのでしょうか?



はい。マーケティングの内製化というのは、自社でマーケティングの戦略立案から、実務の実行、仮説検証、行動改善までを、全部行うこと
です。
そして、内製化というのは、マーケティング業務を外注している場合に検討されます。



ありがとうございます。
では、内製化はどのように進めるといいのでしょうか?



そうですね。まず、内製化を誰が中心になってやっていくのかを決める必要があります。



内製化を検討している場合、社内にマーケティングの戦略を考えられる人や実務を実行できる人がいないというところからスタートすることがほとんどだと思います。



そのため、誰を中心にやっていくのか特定の1人を決めて、今後のマーケ
ティングの旗振りをしていくことが必要です。





まずは、中心となる人物を選定することが必要なのですね。



はい。その上で、中心人物が社内のマーケティングとしてどんな役割を果たし、どんな目標を目指すのかを決める必要があります。
例えば、1年間で問い合わせを何件取るといったような、計測可能で
具体的な目標を立てましょう。



次に、マーケティングの基礎知識をインプットすることが、基本と
る重要なポイントです。
例えば、CPAやCVなどのマーケティング用語や、マーケティングの数字改善の仕方などの基礎知識をインプットしましょう。



広告運用の場合、「この数字が悪くなっている時はここを確認する」と
いった基本的な知識、マーケティングにおける作法のようなものを身に付けます。



英語で例えるとわかりやすいかもしれません。
英語で言うと、先程のマーケティング用語を覚えるのは、アルファベットや単語を覚える段階です。基本的な知識や改善の仕方のようなものは文法に該当します。



なるほど。英語での例えは非常にわかりやすいです。



知識と要望をどう組み合わせて、基本的なセオリーを行っていくのかが重要です。
しかし、多くの企業の場合、未経験の人に対してこの段階ですぐに自社の改善を任せようとしてしまいます。



そうすると、要望も分からなければ、セオリーも分からないので、
まともな改善はできません。



そうですよね。何をどうしたらいいのか分からない状態だと思います。





はい。なぜ面倒な基礎知識を時間をかけてでもインプットする必要があるかというと、そもそも実行自体ができないからです。
知識がないと、マーケティングに関する議論についていけないだけでなく、本を読んでも分からない、ノウハウを調べたくても言葉がわからないため調べ方も分かりません。



単語も文法も分からないと、英語が話せないのと一緒です。
そのため、まずは知識をインプットしないと話になりません。



それから実際に、3C分析とかSTP分析などのマーケティングの戦略を作る作業になります。
しかし、これはやった気になってるだけだと上手くいきません。
経営者やマーケティングの内製化を支援できる会社などに入ってもらい、必ずフィードバックをもらうことが肝心です。



まずは、知識をインプットして、実際にマーケティング戦略を作っていくことが大切だと分かりました。



しかし、未経験からマーケターになる人は、そのフェーズではまだ知識の段階であるため、実際に何が現場で通用するのかが判断できません。



セオリーだけが頭に入っている状態なので、それだけでは上手くいかないのです。
そうは言っても、実際に現場でやっていく際に、こういうことをやらなければならないというのは、人にフィードバックされないと絶対にわかりません。



やってみてうまくいかなくて、それをフィードバックされて、直してといったような泥臭い作業をやることが必要です。



このように、戦略を進めていくなかで、今まで得た基礎知識や基礎用語などを活用して、理解を深めながら、実務の実行に移していきます。



基礎知識や基礎用語などの理解を深めながら、施策を実行し、フィードバックをもらいながら正しい知識ややり方を身に付けていくことが大切なのですね。



はい。インプットしてすぐに実務を進めるということは、表面的な基礎知識しか入ってない状態です。企業としてどういうマーケティングの戦い方をするか理解できていないにもかかわらず、実務に着手するということです。 つまり、一般論だけを自分たちの実務に押し付ける形になるため、うまくいきません。



とりあえずやりたいという企業であれば進めればいいと思いますが、
私は順を追ってやっていくべきだと思っているため、おすすめ
しません。



ミスしてもお金の損失がないエリアで試しながら、戦略を作っていく中で、自社がマーケティングをどこで勝とうとしているのか、どういう訴求であるべきなのかを考え抜いて、実務に落としていく必要があります。



表面的な基礎知識だけでは、上手くいかないことが分かりました。



そうです。実務も同様に、当然ここまでにセオリーも入っているため、Web広告運用やSNSの運用など、一度やってみることも必要だと思い
ます。



しかし、担当者にやらせてやりっぱなしになっている企業が非常に多いのも現状です。
要するに、経営者からのフィードバックがないため、ほとんどの担当者は何がうまくいって、何がうまくいっていないのか分からない状態になります。



そのため、必ず経営者がそのプロジェクトに対して、フィードバックを徹底的に行い、どういう方向性で何をしたいのかを常に言語化することが肝心です。



マーケティングの内製化は非常にハードな、泥臭い改善作業をする必要があるのですが、それができない経営者の方がほとんどです。その場合は、弊社のような内製化を支援する企業が入ってサポートします。



担当者に任せっきりではなく、経営者が適切なフィードバックを行うことが重要なのですね。



おっしゃるとおりです。
そうすると、マーケティングの戦略を作ったり、実行して分析したり
することが可能になります。



そこからさらに広げるのであれば、マーケターの下に誰をつけるのかという、マーケティングのチーム化を社内で行いましょう。



もともと1人の担当者がやるしかなかったことを、マーケティングチームとして多くの人が関わることで実現できる領域が大きくなります。
そうすると、さまざまなマーケティング活動を並行して行えるように
なります。



そもそも、マーケティングの内製化に向いている企業というのは、
どんな特徴があるのでしょうか?



内製化に向いている企業は、中長期での投資的目線がある企業です。



内製化には非常に時間がかかります。少なくとも最低6カ月は必要なうえ、最低6カ月の間は、まともな成果が出ないと思っていただいた方がいいでしょう。



それは支援会社がついたとしてもですか?



はい、ちゃんとした支援会社がつかないと、1年経っても駄目かもしれません。
担当者自体が自力で、プライベートの時間を削ってありとあらゆるスキルアップをしているなどの特殊な事情がない限り、6カ月以内は成果が出ないことがほとんどです。



そうなんですね。



1年、2年、3年とかけて少しずつ、会社のマーケティングを任せていけるような人材に育てあげることを前提として考えるのであれば、内製化は合っていると思います。



反対に、短期で売上をとにかく上げたいという企業には合いません。
それならば、プロに頼んだ方が話が早いでしょう。
未経験の担当者にやらせて、売上もすぐ欲しいといったことは、ないものねだりの極地と言うしかないと思います。



マーケティングの担当者だけではなく、担当者の同僚や上長、経営者
など周りの人間が泥臭い改善を一緒にやるという気概がある企業にはマーケティングの内製化は向いているといえます。
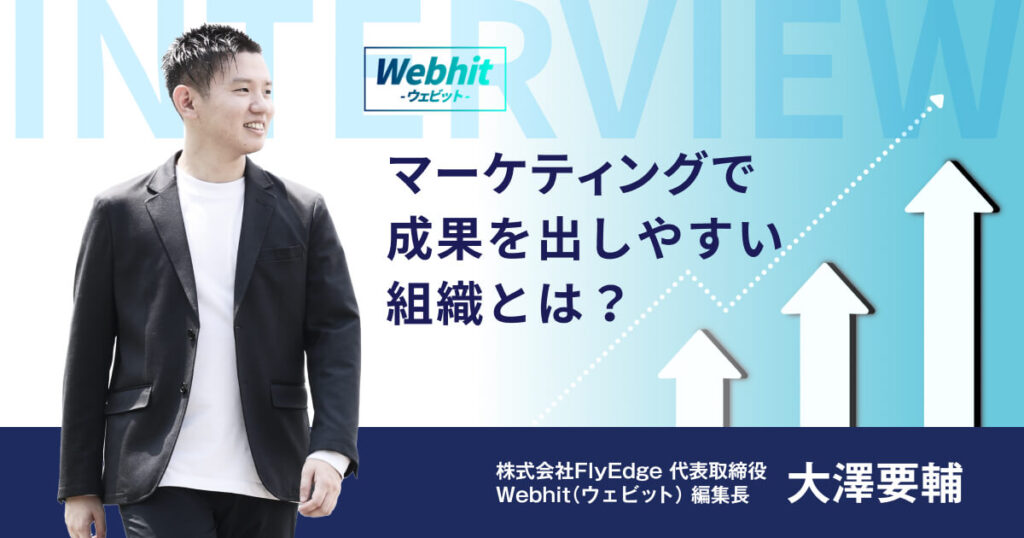
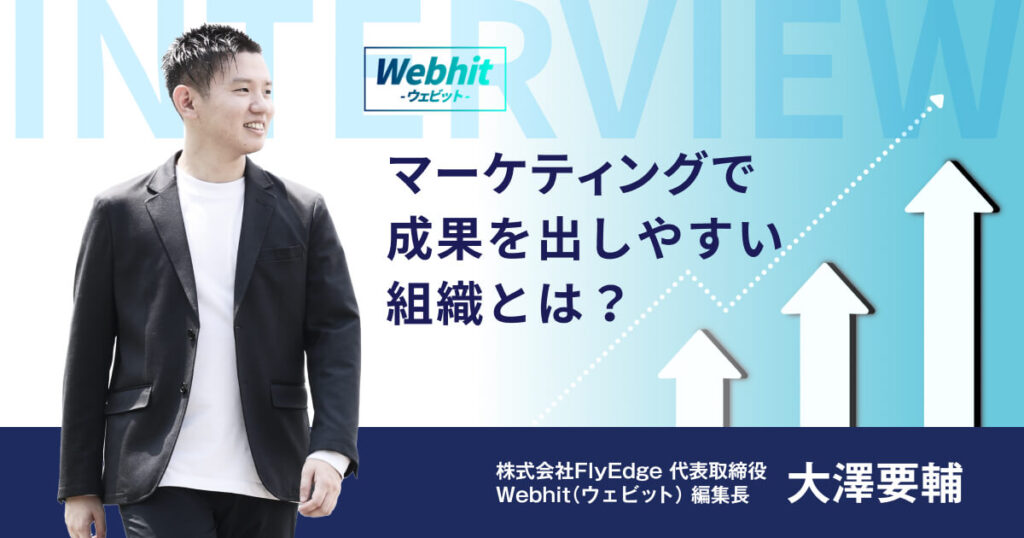



短期で売上をとにかく上げたい企業には、内製化は向いていないの
ですね。



そうですね。そして、担当者にとって新しいことだらけということは、おそらく企業にとっても同様だと思います。
ずっと使われてこなかった知らない用語が飛び交うといった新しいことが非常に多くなるでしょう。



しかし、担当者は新しいことであっても諦めずに自ら切り開いていって、やり切らなければ内製化できる未来はありません。



経営者も「難しい話だから」「自分は分からないから」と逃げずに、
担当者と向き合って、一緒に学びながら、理解を示して一緒にやって
いくということができないと、非常に難しいと思います。



そうですよね。
担当者と上長、経営者が協力して、学びながら一緒になって進めていく必要があるのだと分かりました。



おっしゃるとおりです。
内製化が合わない企業はマーケ担当に丸投げする企業です。



経営者がマーケティングのことを理解して言語化する努力をしないと、担当者だけがずっと浮きっぱなしになり、担当者が社内で立つ瀬が
なくなります。



そうすると、担当者がどれだけ頑張ってくれる人であったとしても、社内の同意が得られないので、プロジェクトが前に進まなくなります。
そのため、経営者や上長が泥臭くやり込めるかどうかが非常に重要
です。



少し戻ってしまうのですが、内製化を進める際に社内でマーケティング担当の人をアサインする場合には、どんな人が向いてるのでしょうか?



そうですね、お客様目線が極めて強い人はマーケティング担当に向いているでしょう。マーケティングの業界は、よくも悪くも数字数字になりやすい傾向にあります。



営業も同様だと思いますが、営業の場合はお客様と直にコミュニケーションを取れます。
そのため、提案書を作ったり、メールをしたりするなかでお客様目線が自然に身に付きます。それを維持するのもそんなに難しくありません。
しかし、マーケティング業界は数字目線になりやすい傾向にあります。



なぜ、マーケティング業界は数字目線になりやすいのでしょうか?



なぜなら、グーグルアナリティクスを開けば、ページビューのセッション、コンバージョンなどのさまざまな指標の数字が所狭しと出てきます。別のツールを開いても、また別の指標でいろんな数字が出てくるでしょう。



そのなかで、「数字を分析しろ」「数字のデータで示せ」「数字を根拠に
提案してくれ」と言われるため、数字目線になりがちになります。



なるほど。数字を改善していくためにはさまざまな指標の数値に触れるため、数字目線になりがちになってしまうのですね。



はい。数字目線になることは、数字をしっかりみれる人間ということ
なので、大事なことです。



しかし、数字だけ見始めたら改善にはつながりません。広告の表示1回も、1人のお客様が見に来てくれたということです。
この数字の結果からお客様はどう感じたのか、お客様の立場に立って
考えることが重要です。



そのため、
・お客様が見たときに伝わらない
・何を言っているか分からない
・自分たちにとっては言いたいことだけど、お客様にとっては必要ない
このようなことが判断できる、お客様視点が極めて強い人が、担当者としては合ってると思います。



なるほど。お客様目線で考えられる人が、担当者に向いていることが
分かりました。



あとは、諦めない人もマーケティング担当者として向いている
でしょう。



マーケティングは、予算や営業人員が無限にあって、コンテンツが無限に作れるというものではありません。



予算はこのぐらいしか使えない、営業が少ない、コンテンツを作る予算が下りないなど、必ず何か制限があって、さまざまな制限のなかで適切な施策を考え、実行していくのが、マーケターの役割です。



しかし、マーケティングの施策を行っていくと、諦めたくなる時が来ます。「もっとこういうのがあれば、こうできるのに」「 もっと予算があれば、これができるのに」という言い訳がでてきます。
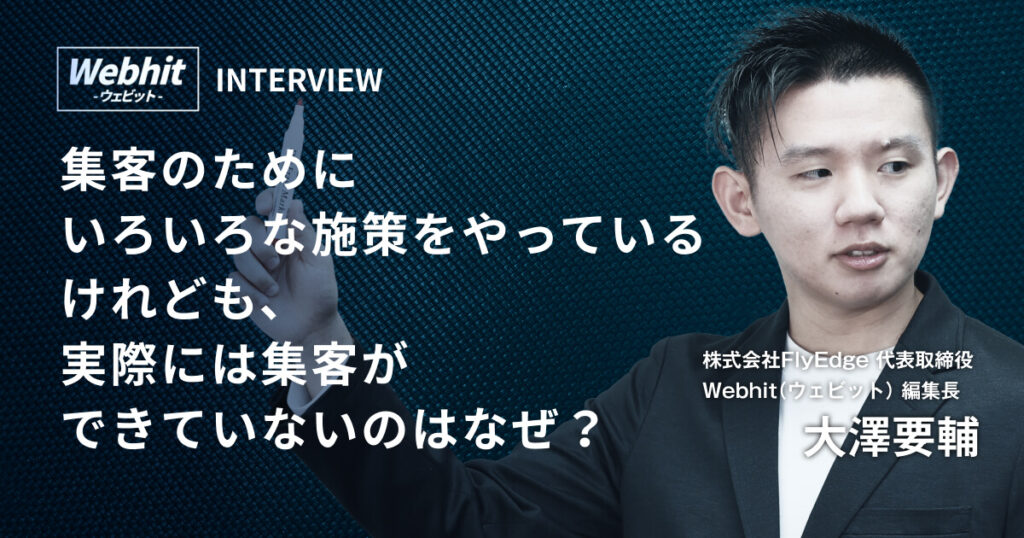
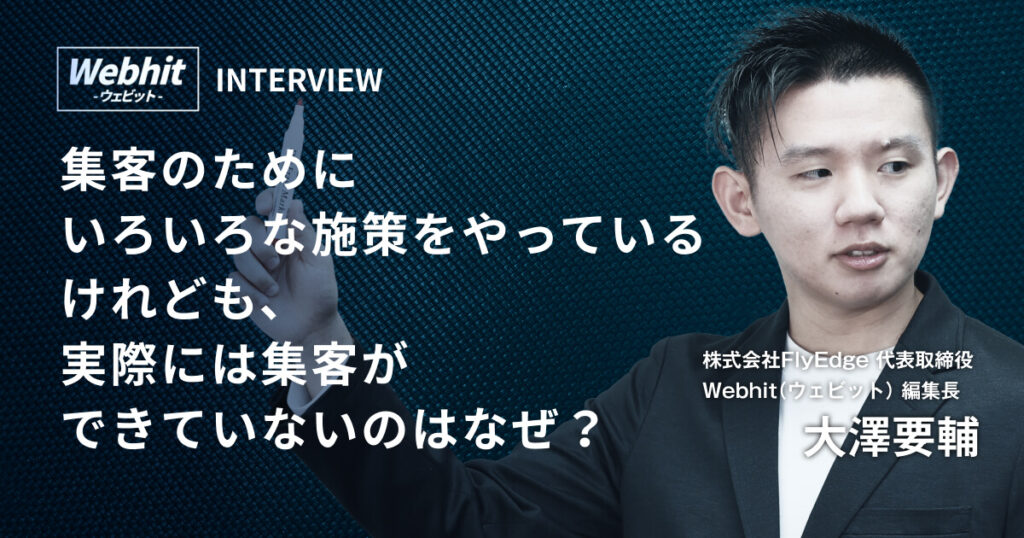



制限が多いなか、諦めずにどうしたらいいか考え続けることが大切なのですね。



はい。言い訳をすること自体は簡単ですが、壁にぶつかった時に諦めない人だけが、社内のマーケティングをやっていけると思います。



あとは、自社の事業解像度が高い人間も、内製化を進める際のマーケティング担当として向いているでしょう。



自社の事業解像度が高い人間とは、どんな人でしょうか?



はい。
そもそも、営業やサービス側、企画開発や経営者が何を指標として
いて、何を目指しているかを理解していない人は、マーケターには
向いていません。
顧客の解像度はもちろん、自分たちの事業解像度、自分たちの事業の全体が見えている人がマーケターになると、全体に適合できるため、適しているといえます。



全体が見えている人だと、全てに適応可能なため向いているということでしょうか?



そうです。
内製化したマーケターでも、支援事業会社のマーケターでも同様に、
結局やる必要があるのは、会社の売り上げを伸ばすことです。
もっと言うと、その先の営業利益を伸ばすことです。



そのため、会社の売り上げや資産を上げていくことに、コミットできる人が向いているでしょう。
そこにコミットできない人は、社内でも事業会社でも、マーケターと
しては向いていません。



コミットしようと思ったら、「広告のCPAが上がりました」と言って
話が終わる人は、向いていないでしょう。



「広告のCPAが上がりました。しかし、マーケティング側で営業側に
新しく商談用のコンテンツを作って渡したことによって成約率が1.5倍になり、最終的なCPOが落ちました 」
「商品設計を変えてプランの見せ方を変えてマーティング資料を作り
営業に提供して、その新料金プランでやったら、LTVがこれだけ伸び
ました」



このように、全体を見れて初めて、事業会社のマーケティング責任者として、非常に有意義な状態になります。
そのため、一部だけやるのであれば、代行してもらった方がいいと
思います。
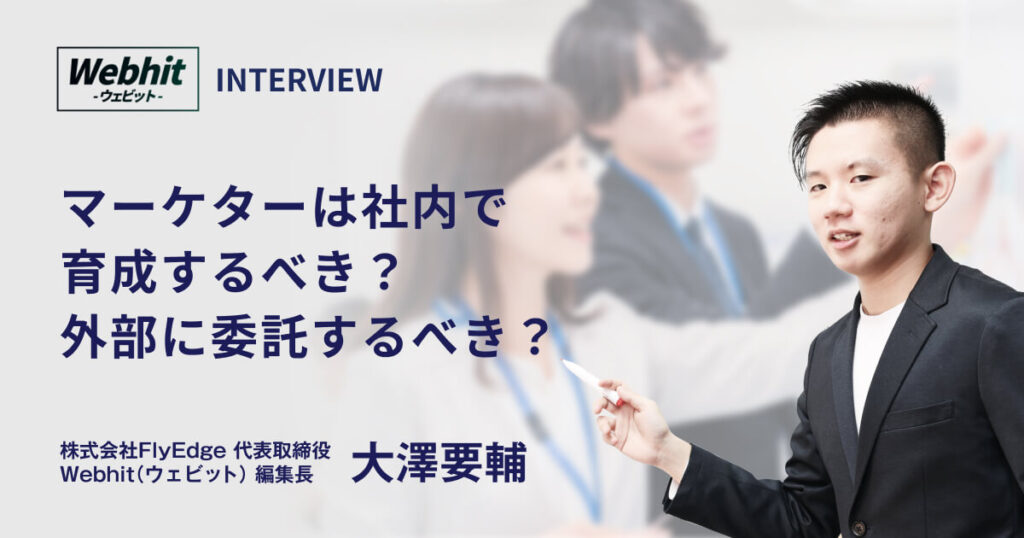
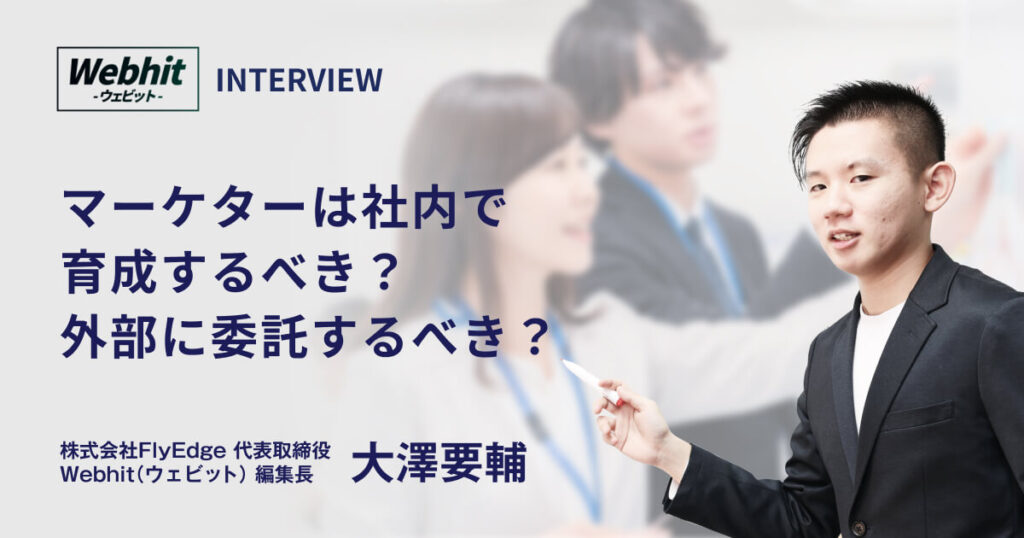



ありがとうございます。 最後にこの記事を読んでいる経営者の方や、
マーケ担当の方に一言お願いします。



内製化は、マーケティングのさまざまなプロジェクトの中でも、
割と難易度が高いプロジェクトになります。



経営者がまず「内製化をして、中長期でマーケティングに関する教育をしよう」という意思決定ができるかというところも重要です。
さらに、アサインされた担当者が最後まで、諦めずにやりきれるのかというところも大切な要素になります。



それを踏まえて、さらに最終的な施策が伴っているかどうかを含める
必要があるため、非常に大変なプロジェクトになります。
非常に簡単な気持ちで内製化をしようという人が多くいますが、マーケティングの内製化は簡単なものではありません。



内製化のメリットとして、
・外注に払う報酬がなくなる
・広告の運用手数料を払わなくていい
などのコスト削減を、非常に安直に考える企業もあります。
しかし、内製化をしたらマネジメントするべき対象は数十倍にもなり
ます。中途半端にやるぐらいならやめた方がいいでしょう。



マーケティングの内製化は、企業として自社のマーケティング力を根底から高めたい場合には、ベストな選択肢だと思います。



その場合は、一定の覚悟を持ってやっていただきたいと思います。
必要な場合は、弊社も全力でコミットいたします。
内製化を検討している場合は遠慮なくご相談いただけたらと思います。



ありがとうございました。