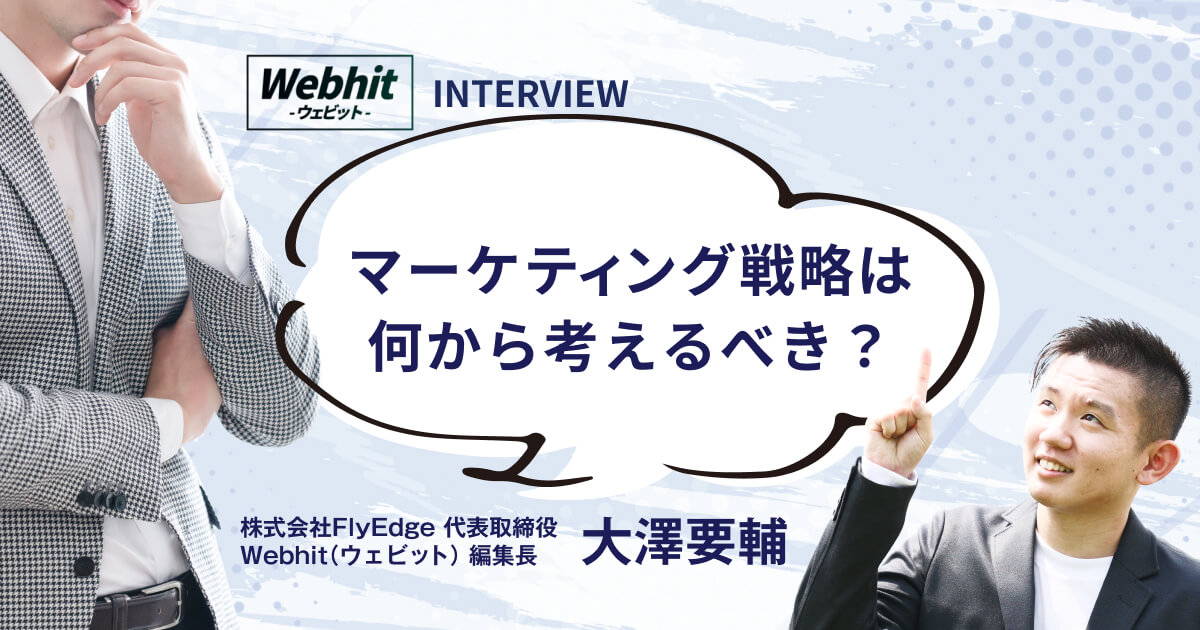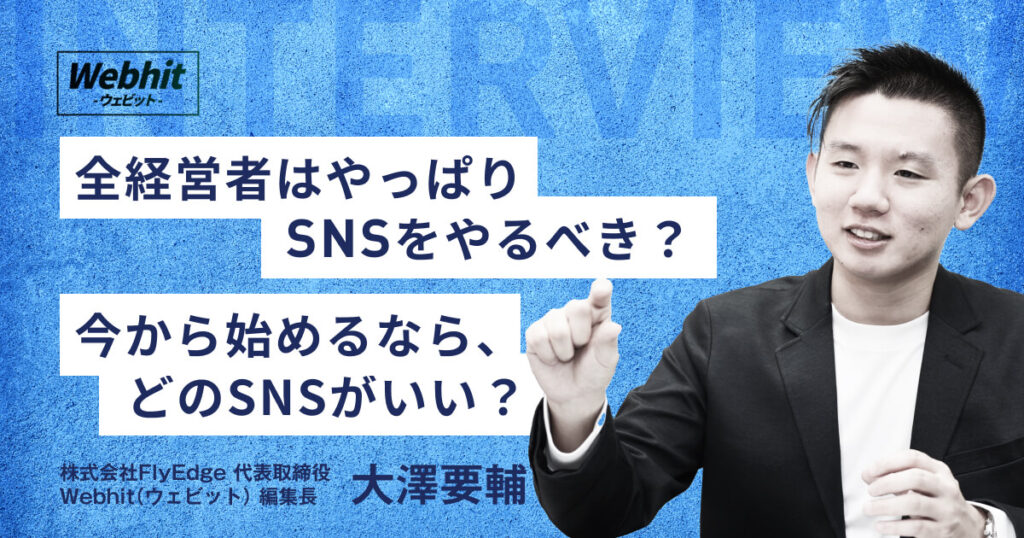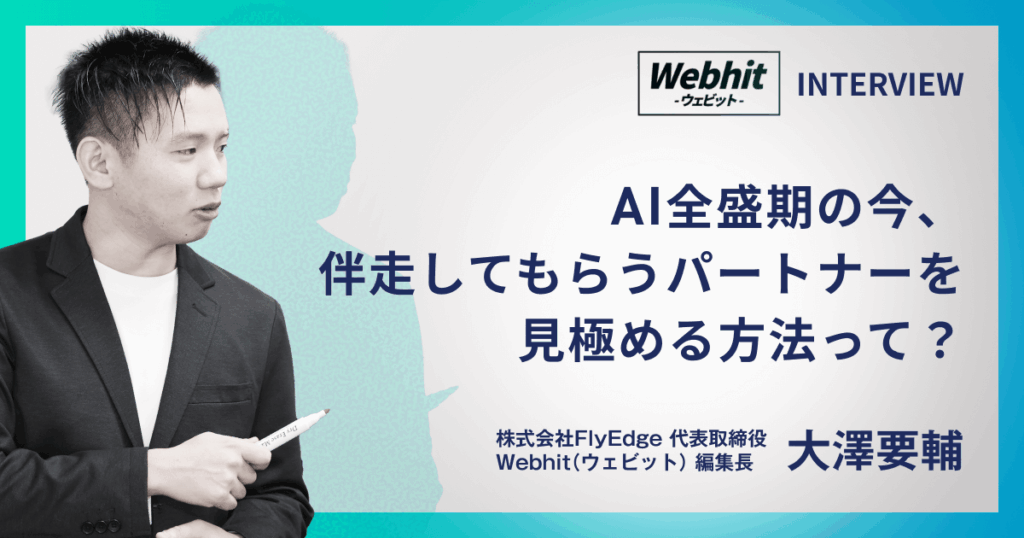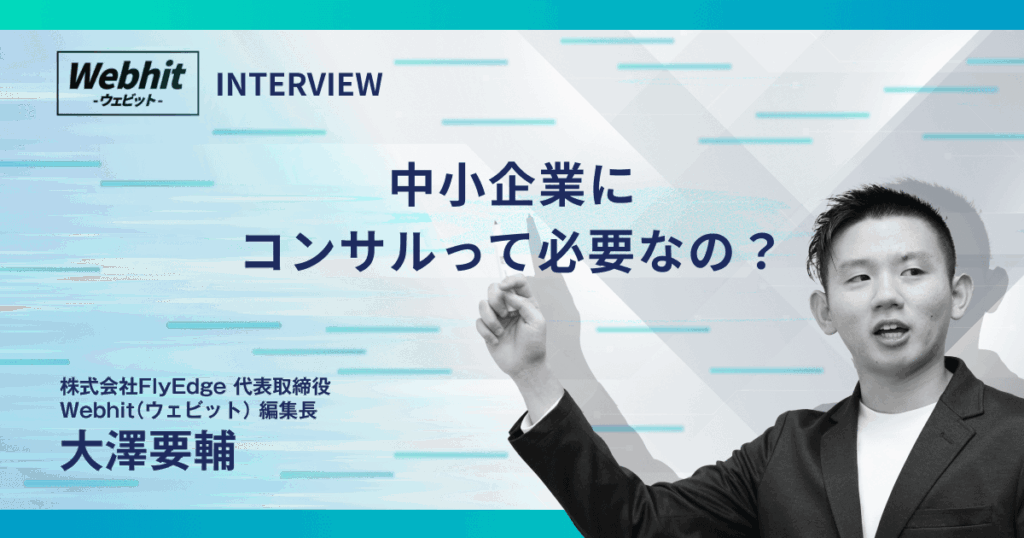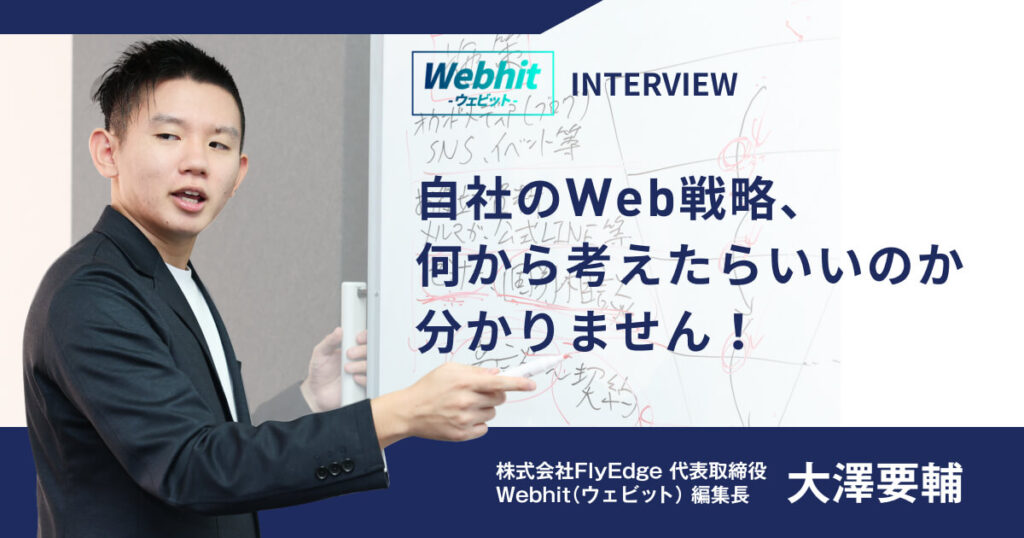Webhit 編集部
Webhit 編集部今回は、「マーケティング戦略は何から考えるべき?」についてお話し
いただきたいと思います。よろしくお願いします。



お願いします。



早速ですが、社内でマーケティングの戦略を進めていこうとする場合、何から考え始めるとよいのでしょうか。



そうですね。
市場の中で自分たちのポジションがどこかを把握するところからです。



結局、差別化をしたり強みを活かしたりするために、どんな広告を出したらいいか、どんなSNSをやるべきかというのは、自分の立ち位置が
分かってないと何をやっても当てずっぽうになります。



例えば、業界のシェアを多く持っている企業や、地方マーケであってもそのエリアの中でもトップクラスのシェアを取っている企業と、業界の中でのシェアが全然なく後発で、地方でやるにしても、そのエリアの
中での知名度が低い企業では、全然やり方が違ってきます。



そうですよね。



業界リーダーのような企業が、まだ認知されてない企業と同じやり方をすることは、まずないでしょう。逆もしかりです。



そのため、まず何から考えればいいの? という質問の回答は、
「まずは自分たちの立ち位置、ポジションを明らかにする」
というところになります。
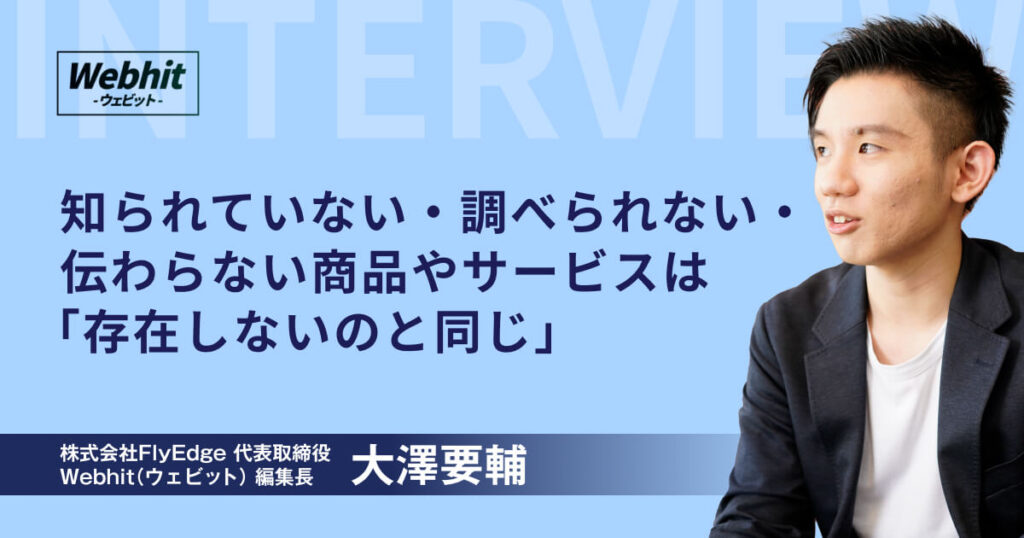
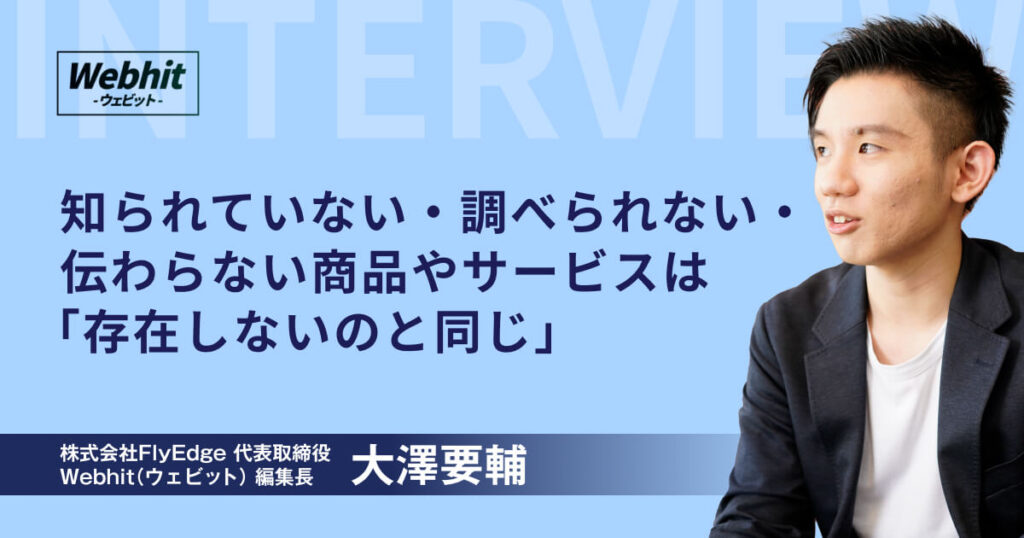



ありがとうございます。
マーケティング戦略は何から考え始めるといいか?ということより前に押さえておくべきポイントはあるのでしょうか?



それはマーケティング初心者でも変わらないです。
結局、自社が今市場の中でどこにいるのかを把握することが先です。



例えば、パン屋さんがあるとします。そのパン屋さんに来てくれる
人たちは、基本的にはそれほど商圏が広くない範囲です。



結構おいしいところでも、よほど何か強みがないとお客様は来ない
ので、来てくれる人はそんなに多くないと思います。
足を運んで行ったとしても、一駅ぐらいの範囲でしょうか。



その中で、パンを買うという目的に対して、直接的に競合するところと、間接的に競合するところがあります。



例えば、直接的に競合するのは、同じようなパン屋さんや、パン自体を
売っているスーパーやコンビニなどです。



そして前提から考えても、パンは朝ご飯に食べたり、お昼ご飯に食べたりする人が多いですよね。
夜ご飯にパンだけ食べる人はあまりいないと思います。



確かにそうですね。



そうすると、朝ご飯や昼ご飯としてパンを食べるという、もう一つ
粒度の高い目的として、パンは選ばれる選択肢の一つになるでしょう。



パン以外だと、お米も競合になります。
ご飯は自宅での自炊の他に、コメダコーヒーなどが朝に提供している
モーニングも競合にあたります。



なるほど。



自分たちが置かれているその市場の環境の中には、自分たちと同じく
お客様のパイを奪い合う対象として「直接競合」と「間接競合」が
います。



そのため、まずは直接競合・間接競合に、どういうところがあるのかということを見る必要があります。



競合を押さえておくことが大切なのですね。



そうです。同時にもう一つ、お客様の方を見る必要があります。
今そのエリアに住んでいるお客様にとって、どういうものが流行って
いるかを知る必要があります。



どのエリアでも大なり小なり、「最近あの店が流行っている」「あのお店は人気らしい」「SNSで話題らしい」などの情報があると思います。



そういった、
・今はどういうものにみんなが興味を持ちやすいのか
・どういうところにみんなが行きたいと思うのか
ということを、まず押さえることが大切です。



つまり、「どんなお客様に囲まれて自分たちが存在しているのかをまず
把握しましょう」ということです。



そうすることで初めて、今自分たちがどんなお客様のマーケットの中で戦っていて、シェアを奪い合っている会社や店舗にはどのようなところがあるのかという全体が可視化されます。



全体を可視化することが大切なのですね。



はい。
まずそこをやっていないと、その後の戦略云々の話ができません。



前提情報があって初めて戦略というのが成り立つので、それをやらないのは、戦争で言えば「相手の配置も地形も、ミッションの目的もあまり
わかっていない状態で、どうやって攻めようかという話をする」のと
同じなので、それは不可能です。



よくわかりました。ありがとうございます。
では、どんなお客様に囲まれて自分たちが存在しているのかを把握した後、中小企業ならではのマーケティング戦略の立案で大切なポイントはありますか?



そうですね。 もちろん、やることは言い出せばキリがなくなります。



しかし、中小企業は当然予算も、人的リソースも潤沢ではありません。その中で何をどれだけ重視するかが肝心です。



リソースや予算を割く必要があるため、どれも中途半端になるよりは一点突き抜けた方がいいです。
そのために、「お客様に選ばれる理由を意図的に作る、仕込む」という
ことになります。



意図的にお客様に選ばれる理由を作るとはどういうことでしょうか。



選ばれる理由はさまざまですが、先程のパン屋さんの例で言うと、
自分たちのメロンパンに自信があるとしましょう。



しかし、メロンパンには派閥があります。
外がカリッとサクっとしているのがいい人もいれば、ふわっとしているのがいい人もいます。
メロン果汁を使ったクリームが入っている方がいい人もいるでしょう。



その中でお客様に選ばれる理由を作るのであれば、最低限そのどれか
一つに属さなければ、選ばれる理由にはなりません。



メロン果汁も使ってないし、外側がふわふわなわけでもない普通のパンで、外はカリカリなわけでもないメロンパンというのは、何の特徴もないですよね。
それならコンビニのパンでよくなるわけです。
「もしかすると、コンビニのパンのほうが美味しいのでは?」という
話になるかもしれません。



たしかにそうですよね。決め手がないですね。



はい。お客様が選ぶ基準は商品ごとにあります。



例えばパソコンだったら、
・スペック
・画面のきれいさ
・持ち運び時の軽さ
などが大事という人もいます。



その人の意思決定の基準のどこかに属する必要があるということです。人の意思決定の基準のポイントは、ニーズの一部またはすべてに当たるため、そのニーズがどこにあるのかを把握することが重要です。



ニーズを把握して、そのニーズのどこかに属することで選ばれるようになるのですね。



はい。例えば、自分たちのパン屋さんには一駅分前後の商圏があったとしましょう。しかし、その商圏で「メロンパンが食べたい」と思った人の中に、メロンパンの好みのタイプが均等にあるわけではありません。



そのため、「どういう人が多そうなのか」という、ターゲットとなる人がどれぐらいいるのかということを考慮しながら、自分たちがそのターゲットの意思決定の基準に直接的に絡みにいくことが必要です。



なるほど。



問題なのは、この程度はみんなやってくるということです。
しかし、その商品の単体の情報以外にも、選ぶ基準は多くあります。



例えば、フォロワーが何万人というママインフルエンサーの人が、
自分の店舗のメロンパンを食べてくれて、「今、ここのメロンパンが
美味しい」「子供にも食べさせたい」などと情報発信してくれたと
しましょう。



そうすると、
・このインフルエンサーがどんな人か
・どのぐらいフォロワーがいるのか
・どんなファンを持っているのか
などによってももちろん変わりますが、「インフルエンサーが食べに来てくれる店」だと言えるようになります。



そうすると「そんなにいいなら、私も行きたい」と、お客様がお店に行く理由になるんです。
有名人が食べてるものだったら、1回食べてみたいという感情を起こさせることができます。



もう1つ例を挙げると、「メロンパン大賞」みたいな賞を取って実績をつくるのもポイントです。有名なのはモンドセレクションでしょうか。



あとは、比較的手軽にできるのは、「自称世界一」を作ってしまうこと
です。 なんでもそうですが、なにかの一番というのはみんな気になる
ものです。



例えば、「世界一、外の皮が硬いメロンパン」と言われたら気になりませんか? 食べられるかどうかは別として、一回買ってみたくないですか?



確かに。買ってみたいですね。



そうですよね。購入してSNSに上げてもらったり、その硬いメロンパンをどうにかして食べる方法という投稿などが出てきたりします。
そういった投稿が増えてくれれば万々歳だと思います。



そのため、意図的に「自称世界一」を作ってしまうのも1つの手です。



今いくつか挙げたのはただのアイデアですけども、結局やる必要があるのは、お客様が選ぶ理由や選びたくなる仕掛けを施すことです。まずは人の意思決定をするときの基準に入り、それに絡むことが必要です。



もう1つはその基準以外のところで、信頼性や権威性など、人が選ぶ理由になり得るものを付加的に足してあげることが全体として重要なことになります。



はい、ありがとうございます。「世界一」というのは「ギネス記録を
持っています」というものでもいいのでしょうか?



いいと思います。例えばトンカツ屋さんをやっているのなら、
全然メインのトンカツとは関係ないけど「キャベツの千切りの早さ」のギネス記録を持っていますとかでもいいと思います。
キャベツの千切りのギネス記録を持っている人のとんかつ、少し食べてみたくないですか?



気になりますね。話題作りをするということも、戦略を作るポイントの
一つということでしょうか?



そうですね。



こうした戦略や戦術などは、マーケ担当が決めることもあると思いますが、経営者が握る部分もあると思います。
その場合、経営者はマーケティングの戦略や戦術について、どこまで
決めてあげるべきなんでしょうか?



・担当者がいるのか
・担当者は優秀な人か
・担当者は視座が高い人か
などにも左右されますが、基本的には中小企業の場合は経営者が全部
関わった方がいいです。



なるほど。全部関わった方がいいんですね。



はい。なぜなら、今まで30業種以上見てきたなかで、経営者が担当者にマーケの戦略・戦術を丸投げして、うまくいっているケースを見たことがないからです。





それなら、今後も丸投げしてうまくいく企業は出てこなそうですね。では、どんなバランスで関わっているといいんでしょうか?



中小企業の場合は、基本的に「トップダウンアプローチ」で落として
いく方がいいです。なぜなら、社長と担当者はマーケティング戦略を
対等に話せないからです。



つまり、社長の場合は、もちろん今期も大事ですけど、今期だけで
なく、3年後、5年後も考えてマーケ戦略を考えます。



一方で、担当者がマーケ戦略を何年間にもわたって先を見据えて考えて作ることはできないので、議論もできないと思います。
そのため、そこは経営者が作るべきです。



座組は組んであげて、「ここまでやってください」と落としたほうがいいということですか?



そうです。作り方や作る流れは経営者側が決めて、担当者の人には情報収集や競合調査、自社の調査、情報の発掘などの作業的なことをどんどん任せるといいと思います。



ただし、戦略自体は経営者が作る、または、経営者と対等に話ができる
外部の人間と一緒に作るべきです。



外部の専門の方と一緒にということですか?



はい、そうですね。
外部に相談するときは、広告代理店やウェブ制作会社などの一部領域
のみを担当する会社や人には相談しない方が無難です。



それはなぜでしょうか?



なぜなら、彼らはあくまで一部領域の最適化、いわゆる「グロース
ハック」だからです。
一部を固定し、一部の施策の結果を出すというところのアルゴリズムや仕組みを把握しながら、より最適解を出していくお仕事だからです。



そのため、マーケティングについて相談したとしても、広告文脈に落とされれたり、「ウェブサイトであったらこう」みたいな話に落とされると
思います。



しかし、経営者は「クライアントやお客様、マーケットとどういうふうにコミュニケーションを取るか」ということを考えなければいけない
ので、視座が全然違うんです。



そのため、施策をやっている人に対して、マーケティング全体の戦略の相談をするのは、完全に筋違いです。
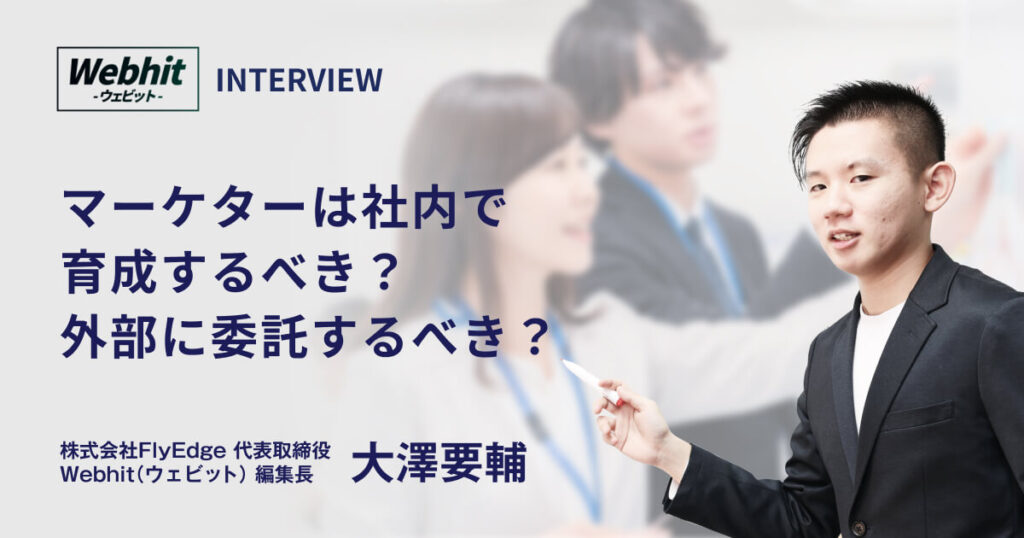
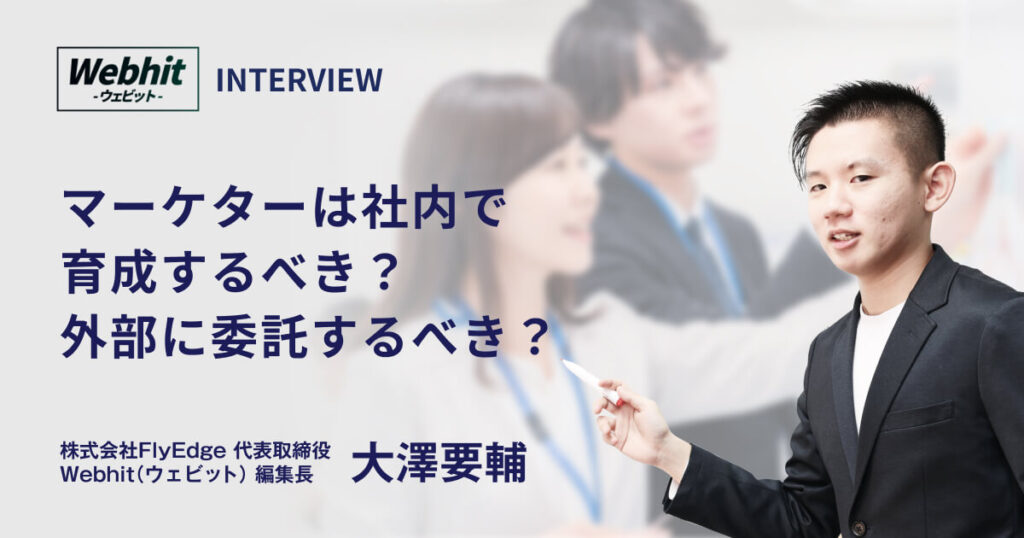



そうなんですね。では、経営者の方たちというのは、マーケティングの戦略を、どれぐらいの頻度で見直していくとよいのでしょう?



そうですね。 月一回見直すのがいいと思います。
戦略は、立てたものをずっと変えずにビシッとはまり続けることは、
まずありえません。それでいけるのであれば苦労しないでしょう。



大変なのは、戦略を作った後、それを実際進めてみて、うまくいった
時にうまくいったら、どうやって伸ばすのかとか、うまくいかなかった場合にどうやってピボットしていくのかを機動的にやれるかどうかです。結局、そこで成功か失敗かに分かれます。



機動的に改善するというのは、結果が自分たちの立てた仮説とフィットしているかどうかを見ていかないとできないことです。



そのためにも、少なくとも月一回程度の頻度で、見た方がいいと思い
ます。



そして、施策ごとの仮説とのズレの改善は週一でやった方がいいです。実際の施策の運用まで自分でやるなら、毎日やった方がいいです。



実際やるとすると、運用は社員に任せて、週に一回ミーティングして
チェックする感じでしょうか?



そうですね。



ありがとうございます。考えた戦略が絵に描いた餅にならないように
するために、大切なことは何でしょうか?



まず、作った時点では絵に描いた餅でしかありません。
そのため、絵に描いた餅をどうやって現実の餅にしていくのかが重要
です。



戦略は1年、3年先を見て仕込んで作っていきます。「こうなったらいい、こういうふうにやっていきたい」「こういうふうに勝ち筋をつかんでいきたい」というふうに目標を立てて、「そのためにこういうことができそう」とやっていきます。



そのため、やってみて思った結果は得られないし、それ以上売れないし、違うとなることもあり得ます。
その場合、そこでピボットができるかどうかで変わります。



そのピボットを正しく繰り返していくと、やればやっただけさまざまなものが見えてきて、現実味を帯びて最終的には、絵に描いた餅が徐々に現実の餅になっていくでしょう。



そのため、絵に描いた餅にしないようにするというよりは、絵に描いた餅をどうやってリアルな餅にしていくかを考えてもらった方が、間違いないと思います。



初めから絵に描いた餅ではないものが作れるんだったら、その人は多分預言者ですね。



ありがとうございます。
最後に、この記事を見てくださっている読者の方に一言お願いします。



はい。
マーケティング戦略というと、基本的には非常に難しいことのような
ニュアンスを持たれる方が、比較的多いと思っています。



しかし、難しいからやらなくていいわけではなく、やらなくては
いけないのがマーケティング戦略です。



営業戦略を立てない会社はないと思いますが、なぜかマーケティング
戦略が立っていない会社は多くあります。



マーケティング戦略は別に難しいことではありません。マーケティング
戦略を立てないのであれば、何をやるのかも不明瞭になります。



非常に大変なことは、お客様にどれだけ向き合うかということです。
そのため、今、お客様はどういう人たちがいるのか、お客様が選びそうな直接競合や間接競合はどこなのかを把握することが大切です。



ツールで数字やグラフを見て、こういう傾向があるとか、統計学の
ようなデータを想像されている方が非常に多くいます。



しかし、正解はお客様が持っているので、どこまで行ってもデータは
何も教えてくれません。今、この辺りで何が流行っているかは、駅前で
直接お客様に聞くような、非常に地味で泥臭い作業が必要なのです。



大手のように数字で細かく作るのなら、大手並みの報酬を誰かに
払って、大手並の動きをしてもらうしかありません。



しかし、中小企業のお仕事はそうではないことがほとんどです。
もちろん数字も大事ですが、「データが全て」「データが取れないんだったら……」といったことを言っている場合ではありません。
お客様に聞いて分かることなら、お客様に聞けばいいのです。



自分たちの周りにどういう競合がいるか分からないなら、街を歩いた方がいいです。
商圏が決まっているのであれば、ウェブで叩けばいいのです。
そういうことを本当に地道に繰り返して作っていくのが、マーケティング戦略です。



最初は絵に描いた餅でしかないので、どうやってリアルの餅にしていくかという話になります。
そこを勘違いしないようにやっていただけるといいと思います。



ありがとうございます。