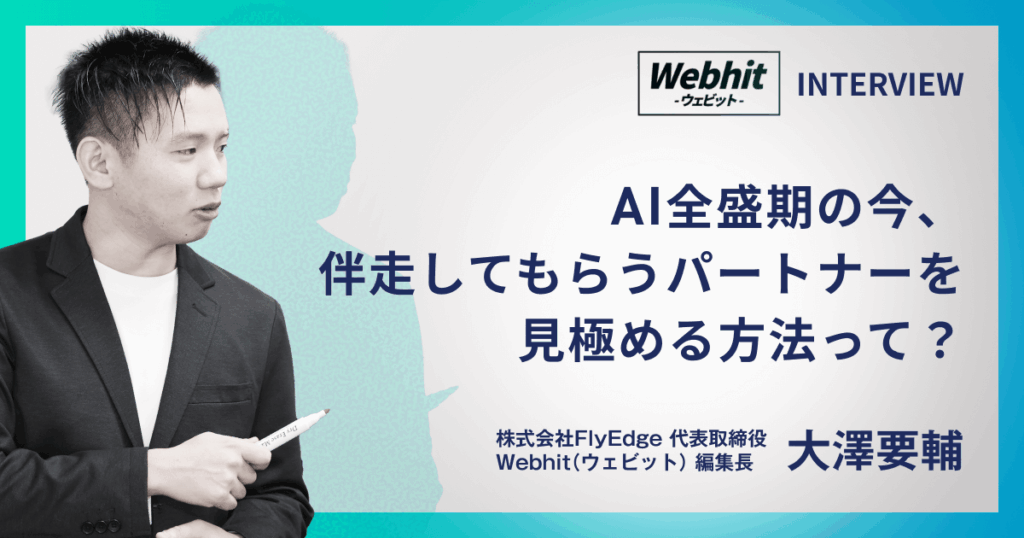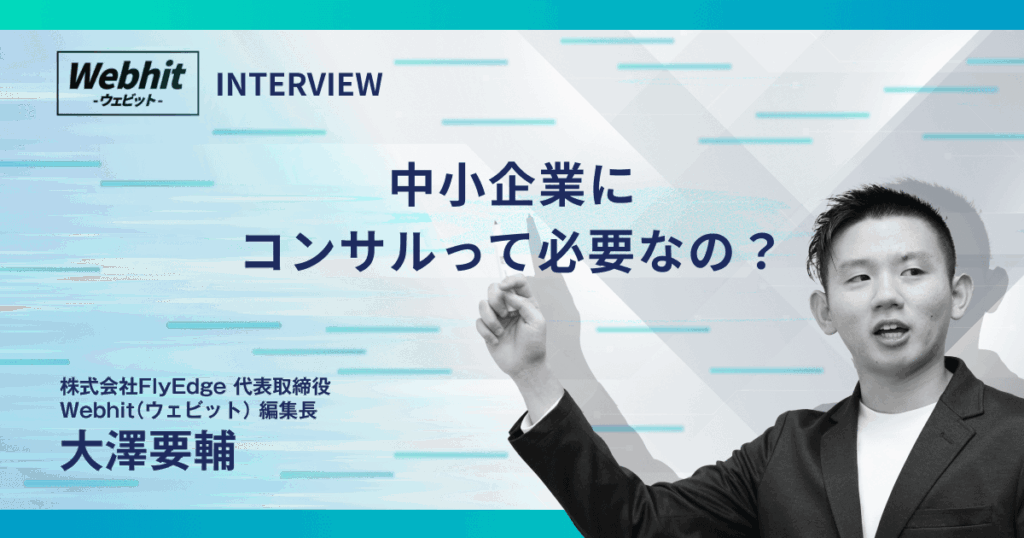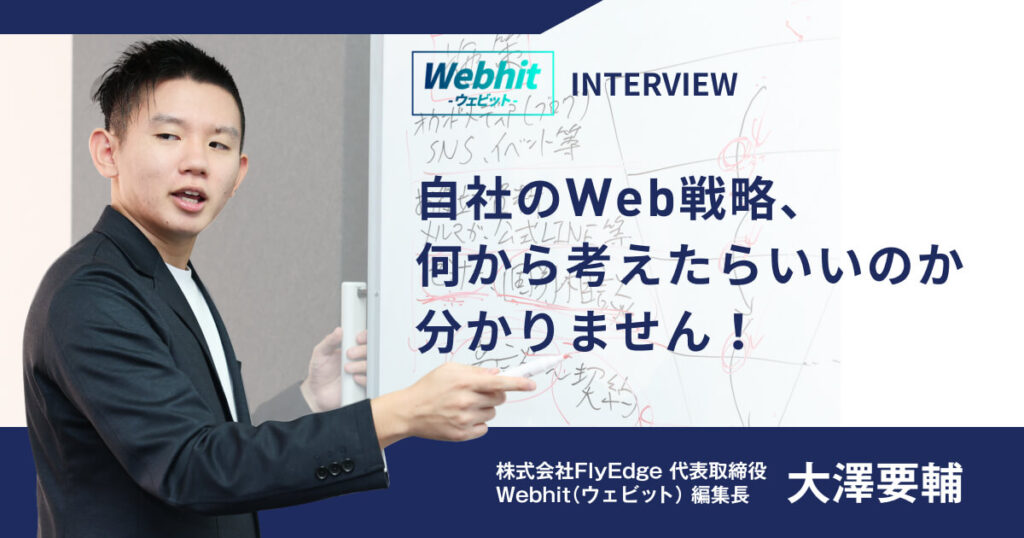Webhit 編集部
Webhit 編集部今回は「失敗しないホームページのリニューアルの具体的手順とは?」についてお話いただきたいと思います。よろしくお願いします。



はい、よろしくお願いします。



結論としては、どのようにリニューアルしていくのが良いのでしょうか?



はい、結論から言いますと、まずリニューアルの目的とリニューアル後の目標の定義をした上で、現状分析とユーザー調査を行ってから始めるのが失敗しないホームページのリニューアルの一番重要なポイントになります。



ありがとうございます。
てっきり、リニューアルの1から10みたいなことを教えてもらえるのかと思っていたのですが、その前の準備段階が大事ということですね。
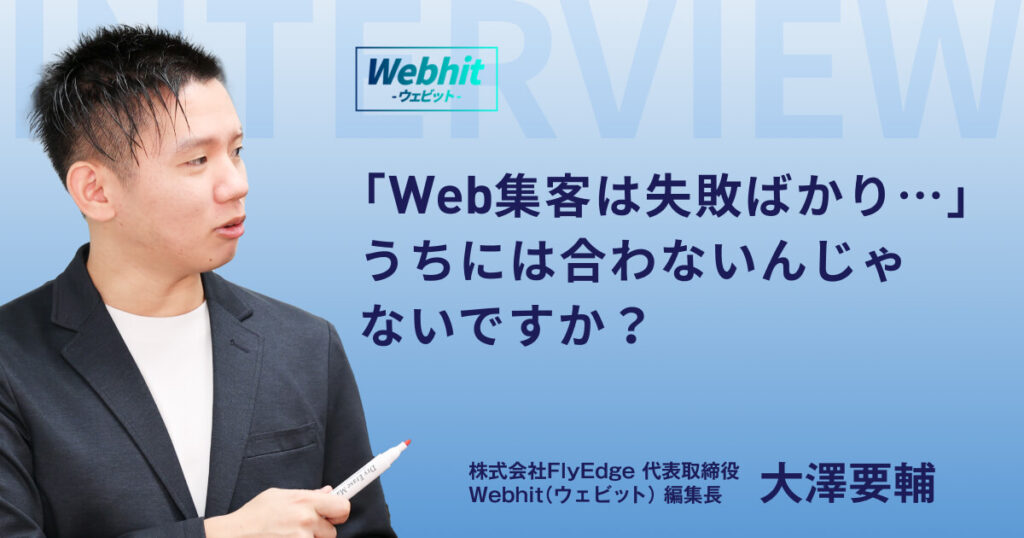
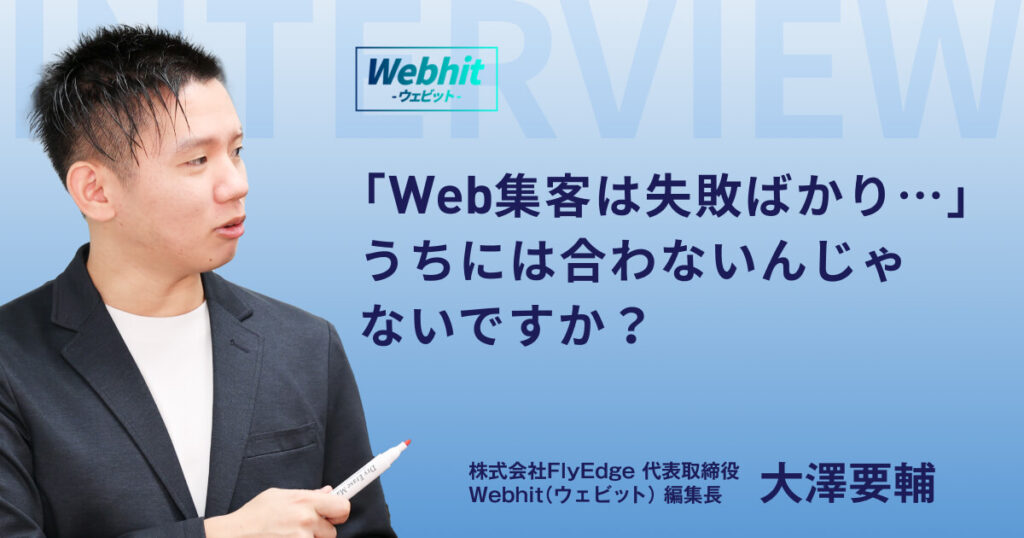



そうですね。
リニューアルする際に、多くの会社が競合大手会社のホームページに近い感じにしたり、競合でなくても自分たちのいいと思ったデザインなどを見つけて近づけたりして、リニューアルと言っていることがほとんどです。



しかし、このようなリニューアルの仕方をしていると、基本的に失敗
します。



そうなんですね。
しかし、大体は自分たちに近い競合の会社をリサーチして、こんなふうにするのがいい感じなんだと考えると思うのですが、最初は何をした
方が良いのでしょうか?



リニューアルの理由や目的は、会社によってさまざまだと思います。



例えば、わかりやすいもので言うと、
・ブランドイメージを新しくしたい
・ホームページからの問い合わせ数が少ないため、問い合わせ数を増やしたい
また、場合によっては
・採用を強化したい
ということが目的として出てくると思います。



そのため、何を主目的にしたいのかをまず決めないと、その後が大きくずれてしまいます。



なるほど。
逆に、何となくリニューアルしようとしている会社が多いということ
ですか?



はい、もう9割以上がそうですね。



そうすると、ブランドイメージを新しくしようなどという考えは、
どのタイミングでもありそうな気がするのですが、リニューアルすると決めるタイミングはどのようにしたら良いのでしょうか?



リニューアルをするときに「リニューアルって1回公式ホームページを作ったら何年おきにやった方がいいですか?」という質問をよくもらう
ことがありますが、正直その発想自体あまり意味がありません。



なぜなら、例えば「ホームページを5年前に作ったから新しくしたい」という場合、5年前に作っていたとしても、今まで問い合わせが取れてる、今でも採用ができてるなどと成果が出ているのであれば、別にリニューアルをする必要はありません。



反対に、非常に極端な話をすると、1ヶ月前にホームページを作ったけれど、その1ヶ月後にミッションビジョンバリュー(MVV)をリニューアルしたため、今のホームページのテイストが全く合わなくなってしまったという場合は、そのタイミングで直した方が良いと思います。



たしかにそうですね。



結局何を目的にするのかもそうですし、どういう状況なのかによってもリニューアルするタイミングは変わります。
「何年おきに定期的に必ず変えましょう」というタイプのものではないため、目的がしっかりあるならば、別にいつリニューアルしても良いと思います。



リニューアルは理由も目的もなく、期間が経ったから何となくする必要はありません。



わかりました。では、リニューアルの目的とは何かということと、もしそのリニューアルの目的がしっかり定まっていた場合、リニューアル後の目標はどのように立てると失敗しないのでしょうか?



リニューアル後の目標は、ほとんどの会社が良くなることばかり考える傾向にあります 。 そのため、リニューアル後に数字が少し悪くなった
だけでリニューアルが失敗したと思ってしまいます。



しかし、リニューアルの仕方はさまざまです。
例えば、「企業理念」というページが既にあるとしましょう。その企業
理念というページ自体は残るけれども、中身が切り替わるというケースもあれば、今まであったサービスページを削除して、新しいサービスのページを入れるというケースもあります。



はい。



例えば前者の場合、企業理念というページは同じだけれども、中身の原稿が変わったり、SEO上のコーディングが変わったりするのであれば、そこのページの評価が変わることはもちろんあり得るでしょう。



後者の、既存のページを削除して新しいページを作るのであれば、既存のページがSEO上一定の評価を得ていてアクセスを取っていた場合、
そのページがなくなるため、その分のアクセスは全て抜けることになります。つまり、新しいページが評価されるかされないかによって、数字が変わります。



そのため、必ずしもリニューアルしたら数字が上がるということはありません。



リニューアル後の目標は、
①楽観目標 ②妥当目標 ③悲観目標 の3種類を作る必要があります。



3種類の目標を立てていると、目標の中にある程度振れ幅が出てきます。例えばアクセス数が月間5,000PVのサイトがあったとすると、
妥当に進んで5,500程度になるであるとか、楽観目標だと5,000~7,000PVあるサイトが8,000~10,000PVになるというようなものですね。
悲観的な目標としては、反対に4,000~3,000PV程度に1回落ちるといったことです。



要するに、そこまで考慮に入れることで目標に幅が出ます。
そのため、悲観目標も立てておくことで、数字が少し下がったとしても
想定の範囲内となります。



前提として、目標を3つ立てておくと、リニューアルした後に、すぐに
良くなる方向ばかりを考えることによって、安易に失敗だという判断を
しないようになります。



しかし、その目標それぞれが、どこかで例えば悲観目標になったとして、 その結果、「悲観目標だから、想定の範囲だからそれでいいよね」というふうに放置するわけではもちろんないですね。



・悲観目標であれば、どのようにアクセス数の回復を図るのか
・妥当目標であれば楽観目標に近づけるためにどんな施策をするのか
・楽観目標であれば、更なる成長を目指すためにどんな施策をしていくのか
など、それぞれの目標ごとにやる施策をまとめておく必要があります。



つまり、目標を3種類立てて、その各目標それぞれに対して対応策を事前に決めておくと、当初の目標を達成しやすいと思います。



なるほど、わかりました。本当に事前準備が多くかかるのですね。



そうですね。



目的とその後の目標とを定義した後に、現状分析とユーザー調査をしてから始めましょうということだったと思いますが、これはどのように
すれば良いのでしょうか?



はい。現状分析に関しては、基本的に自社サイト内の情報と、競合の
サイトの状態を把握することです。



これは一部ツールなどを使う必要があります。
例えば、自社サイトに関して言うと、
・Googleアナリティクス
・GFO
・Googleのサーチコンソールなどの比較的使いやすいツール
をメインで使います。



・現状で検索結果からどのぐらいアクセスが来ていてどんな推移なのか
・どのキーワードからどういう数字が出ているのか
・ページの中でどのページがアクセスが多く、かつ滞在率が高く、滞在時間が長いのか
などを含めて分析しましょう。



競合の分析で使う有名なツールは、エイチレフスですね。
例えばそういったツールを使い、競合はどういうキーワードでアクセスを獲得しているのか、自社と競合で特定のキーワードに対してどちらが今上位なのかなどを確認をすることで、競合と自社の関係性をまず整理をする必要があります。



「なぜ自社と競合の分析をやる必要があるのか」ということに関しては、そもそもここをやらないと、妥当な目標にならないからです。



自分たちのアクセス数もわかってない、自分たちのどのページが今アクセスが取れて、競合に対して自分たちが強くいられる部分と弱い部分とを把握していない状況にあると、目標も作れない状態になってしまい
ます。



そのため、目的や目標の設定時に、この現状分析のデータを基に精度を上げるということになります。



ありがとうございます。
ユーザー調査はどのように行うのでしょうか?



ユーザー調査は、例えば既存のお客様や、自社の従業員、知り合いの
経営者など誰でも良いので、実際自社のサイトを触ってみてもらうと良いです。



理想を言えば、Zoomなどで30分から1時間程度あればいいですね。
1人あたりそのぐらいお時間をいただいて、大体5人から10人ぐらいやると良いと思います。
実際に目の前でサイトを触ってみてもらって、「わかりやすい、使いやすい」などの良いと思う部分と、反対に「ここがわかりにくい、使いにくい」などというものを、一式出してもらいます。



そうすることで、実際にユーザーがサイトを見に来たときに、どのように見て、どういうポイントを使いやすい・使いにくいと思ってくれて
いるのかという洗い出しができます。



その要素を盛り込む形でリニューアルしていくと、綺麗なだけのサイトや、ただ原稿を差し替えただけのリニューアルにはならなくなります。より効果的な改善ができるため、このようなやり方がいいと考えています。



ありがとうございます。
実際にZoomで見て目の前で触ってもらうところまでやっている会社は
少ないと思いますが、いかがでしょうか?



そうですね、あまりないですね。



そうですよね。



はい。
「そこまでやるんですか?」とたまに聞かれます。
時間はかかるので急ぎの場合とかは別ですが、そこまでやった方が
もちろん良いと思います。



ここまでやってみて初めて、リニューアルの意味を持つサイトになるということですよね。



そうですね。公式サイトリニューアルというと、見た目だけのリニューアルと捉える人が非常に多いですが、ユーザー導線のリニューアルももちろん含まれます。



そのため、リニューアルを表面的に捉えるのではなく、デザインや
原稿、ユーザー導線もあれば、コンテンツもあればという形で、多層的に捉える方がより効果的なリニューアルができると思います。



ありがとうございます。 それを踏まえてよくある失敗や、「ここを押さえておかないと全部失敗する」みたいな部分は他にありますか?



そうですね。サイトの中で、最終的にユーザーをどこに持っていきたいのかを、リニューアルのプロジェクトに関係する人間全員で共通認識を持っていないと少し危ないと思います。



結局、共通認識がないとどのページも、とりあえず言われた原稿やデザインを作ったら「なんか良さそう、綺麗になった」といって終わって流れてしまうことが非常に多くあります。



例えば、最終的なWeb上での落としどころである、コンバージョンポイントに「お問い合わせ」しかないのであれば、比較的シンプルだと言えます。
しかし、「お問い合わせ」もあれば「お役立ち情報」もある、さらにセミナーやイベント紹介などさまざまなページがあった場合、Webサイト内の全ページを、全てコンバージョンポイントに持っていくのは無理なんですよ。



各ページがコンバージョンポイントに対するリンクばかりになり、非常にセールス感が強いサイトになります。そういうサイトになると、もちろんユーザーにとっても非常に使いにくく、結果も出ないサイトになってしまいます。



そのため、このページの場合はどこのコンバージョンポイントに持っていくのがいいか、どこまで何を見せるべきかなどを、そのプロジェクト関係者全員が共通認識を持った上で議論ができる状態になっていると、より効果的なリニューアルに繋がると思います。



最終的にユーザーをどこに持ってきたいのか議論していない状態だと、誰もそのコンバージョンポイントを意識しないままリニューアルが進んでいきます。
その結果、綺麗にリニューアルしたのに、なぜか問い合わせまで繋がらないため、見直したら動線がないといったようなことが多くあります。



ありがとうございます。
ホームページに関わる関係者が集まると、「自分の部署にコンバージョンしたい!」と誰もが譲らなくなってしまうことはないのでしょうか?



各部署それぞれ自社で自分の部門とか部署のKPIを持ってるため、当然ありますね。
そのため、ウェブサイトのリニューアル全体を取り仕切るディレクターが整理する必要があります。
正直、ディレクターの腕次第になってしまう傾向にありますね。



もちろん全部のコンバージョンポイントの数字が上がればいいのですが、世の中そんな甘くはないので、コンバージョンの中でどこに優先順位を置くのかが重要です。



例えばtoBの場合だとお問い合わせがもちろん一番重くなることが多いのですが、次に重たいのは、セミナーやお役立ち情報、または資料請求だとかですね。



さまざまなものがありますが、優先順位を落とし込んだ上で、ディレクターが「このページに関しては、これを優先します」というのを整理して主導できるかどうかが肝心です。



ディレクターになりうる人材が社内にいないという場合には、社外のディレクターに依頼をしてでも、整理したほうが良いと思います。



そうですよね。ありがとうございます。
まとめ



では、最後に記事を見ている方に今日のまとめと一言をお願いします!



はい。ホームページリニューアルというと大体の人たちが原稿を少し変える、一番多いのはデザインを新しいデザインにして今っぽい感じにしたいなどの理由でリニューアルを始めることが多い傾向にあります。



しかし、それをやっていて、「リニューアル成功しました」という会社はあまり見たことがありません。
どちらかというと、
・綺麗になったけどアクセス数が増えない、または減った
・雇用数が増えない、または減った
などという話をよく聞きます。



もちろんどんな原稿を作って、どういうデザインにするのか、どんなコンテンツを入れるのかはもちろん大事です。しかし、それよりももっと前の段階で、そもそもリニューアルはなぜ、何のためにやるのかというところが抜けてしまうと、何も結果は出ません。



プロジェクト関係者も、ゴールがわからない状態でやらなくてはいけないので、大体失敗します。



目標に関しても「結局リニューアルしたらうまくいくだろう」と非常に楽観的な目標を作る会社が多いです。



もちろん楽観目標は必要です。
しかし、通常通りこのまま伸びていった場合の妥当目標や、反対にリニューアルしたことによって一部アクセスが取れなくなってしまうという悲観目標など、全部で3シナリオぐらい目標を作っておくと良いでしょう。



そうすることで、リニューアル直後の細かい数字だけ見て、安直に失敗したと判断してしまうことがなくなると思います。



精緻に根拠を持ってホームページを作るためにも、一定の現状分析や、なかなか数字に表れてこないユーザーが実際にどう思っているのかの評価が重要です。



このサイトを実際にどう感じるかという部分を明らかにするためにも、ユーザーに対して実際にインタビューするような形で調査を行っていくというのも重要なポイントです。



関係者全員でこのサイトの中でユーザーをどう動かしていきたいのか、どこに着地させたいのかという議論を皆同じ目線で行いながら、サイトリニューアルを進められれば、基本的に効果的なリニューアルができると思います。



このようにリニューアルをしているケースは、ほとんどの場合あまり失敗しません。そのため、この記事を見た方にもぜひこの手順を心がけていただきたいと思います。



ありがとうございました。