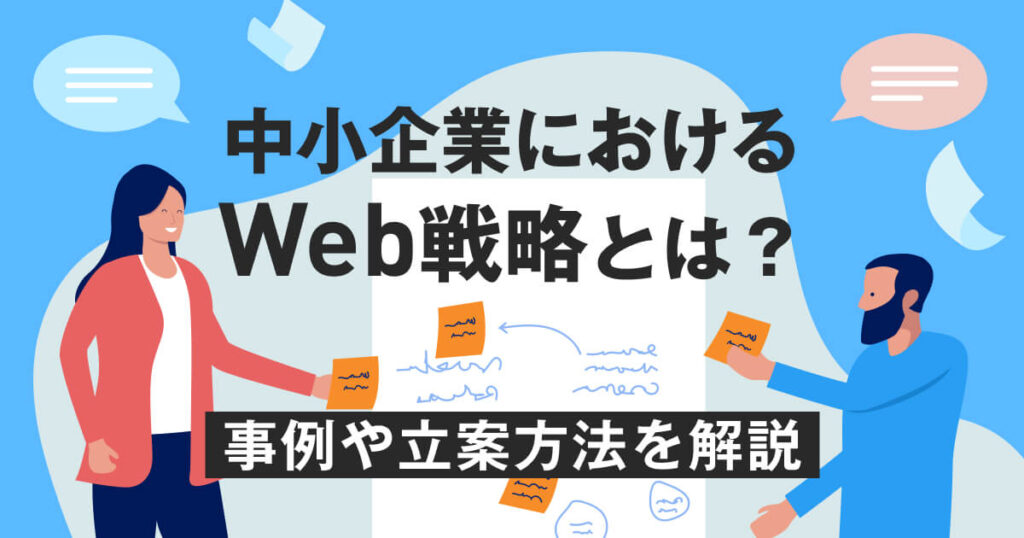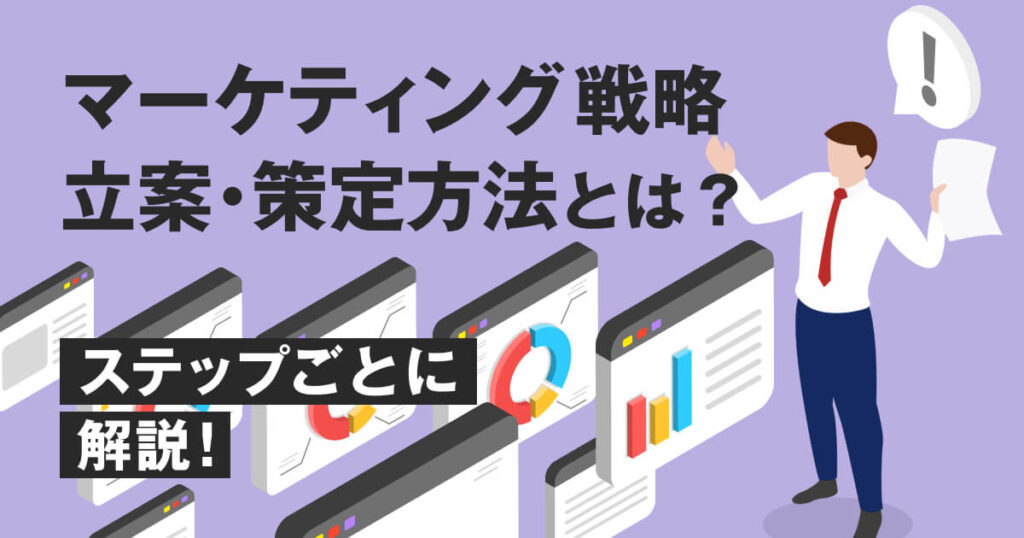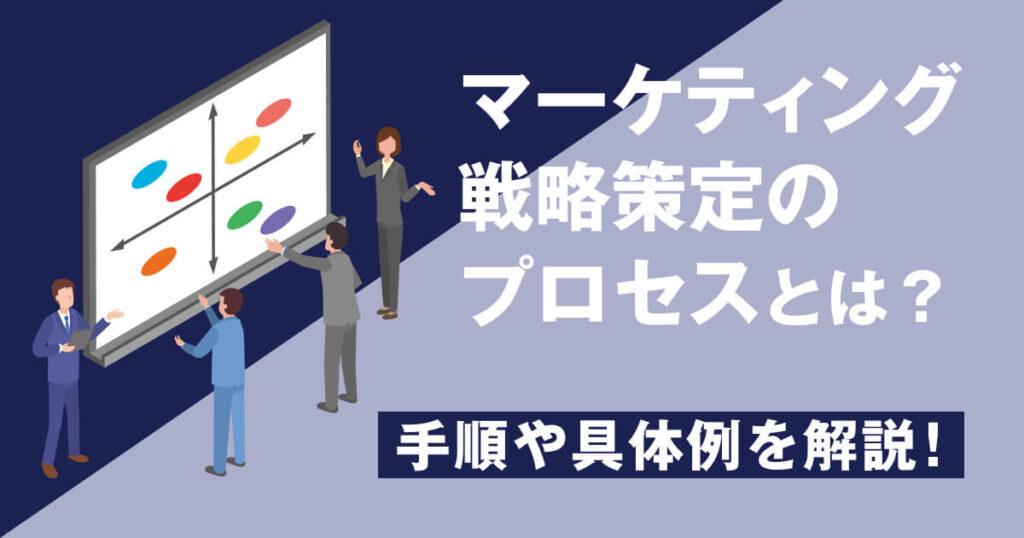BtoBにおけるコンテンツマーケティングのキーワード選定は、BtoCと同じ点もあれば、異なる点もあります。その違いや選定のノウハウを理解することで、的確なキーワードを選べるようになり、CVにつなげられるスキルになるでしょう。
本記事では、BtoBにおけるキーワード選定の手順や注意点などを解説し、成果につなげるヒントをお伝えします。基礎知識からBtoB企業ならではの知識とノウハウも紹介しますので参考にしてください。
SEOとコンテンツマーケティングでのキーワード選定の違い
キーワード選定とは、検索エンジンやユーザーが興味を持つワードを選び出し、それを基にコンテンツやWebページを最適化するためのプロセスです。ここでは、SEOとコンテンツマーケティングにおける、キーワード選定の違いについて解説します。
SEOにおけるキーワードの選定
SEOキーワードとは、検索エンジンに上位表示させる対策「SEO」を考える際に用いられるワードやフレーズです。つまり、SEOにおけるキーワード選定では、サイトを見つけてもらうために行う作業です。メインとなるキーワード次第で対策の仕方やコストは変わるため、社内でよく吟味する必要があります。
コンテンツマーケティングにおけるキーワードの選定
コンテンツマーケティングでのキーワードとは、ユーザーを自社商品やサービスに導くためのワードです。つまり、コンテンツマーケティングにおけるキーワード選定とは、商品やサービスとユーザーをつなげるための作業です。
例えば、在庫管理の効率化を考えている企業は「在庫管理ツール おすすめ」や「在庫管理ツール 安い」といった言葉が、コンテンツマーケティングで用いると良いキーワードとなります。
キーワード選定が不可欠な理由
SEO・コンテンツマーケティングにおいて、キーワード選定は成果に直結するため重要な工程といえます。キーワード選定が不可欠な理由は、以下の2つです。
- 単語で検索する仕組みのため
- 同じカテゴリーの商品やサービスが溢れているため
インターネットは、単語で検索して答えを教えてもらう仕組みです。そのため、選ぶキーワードを間違えると検索意図が変わり、ターゲットに自社商品やサービスが届かなくなってしまいます。
また、同じカテゴリーの商品やサービスが世の中には溢れています。そのため、ターゲット企業に認知してもらうにはキーワードの難易度を把握して適切な単語やフレーズを選ばなければなりません。難易度が高いキーワードを選ぶと自社商品やサービスが埋もれてしまいます。成果を上げるためには、細かいキーワード分析が必要です。
キーワードを選定する上で把握しておきたい種類と分類
キーワードは、主に以下の種類に分けられます。
- 検索意図
- ユーザーニーズ
- 検索ボリューム
それぞれのキーワードを以下の頁で解説します。
検索意図による種類
キーワードの種類は検索意図によって以下4つに分けられます。
- 関連キーワード
- サジェストキーワード
- 再検索キーワード
- 共起語
関連キーワードとは検索したキーワードに関連するワードで、GoogleやYahoo!の検索結果の下に表示されます。ほかにも知りたい内容があり検索されたワードになるため、コンテンツ内容に盛り込めばユーザーが知りたい内容を網羅できます。
サジェストキーワードとは、GoogleやYahoo!にキーワードを入力するとリスト表示される複数のワードです。実際に検索されているワードが多いものをピックアップし表示されているため、検索意図を知る手がかりになります。
再検索キーワードは、検索後に再び調べられた異なるキーワードです。把握しておくことで、Webサイトからの離脱を防止できる、充実したコンテンツ作成のヒントになります。
共起語は、キーワードの内容に出てきやすいワードです。文中によく使用される内容を盛り込めば、より内容を充実させられます。ただし、コンテンツ内容と無関係な内容は混乱するため、何を使用するかの見極めが肝心です。
ユーザーニーズによる分類
ユーザーのニーズは以下4つのクエリに分類できます。
| クエリ | 検索意図 | 用途 |
| Doクエリ | 「したい」の意図がある 例:SEO 対策 | 問い合わせや資料請求のCV向上 |
| Knowクエリ | 「知りたい」の意図がある 例:コンテンツマーケティングとは | 自社商品・サービスの認知度向上 |
| Goクエリ | 「行きたい」の意図がある 例:旅行 奄美大島 | 特定地域の店舗の集客の向上 |
| Buyクエリ | 「買いたい」の意図がある 例:昇降デスク かっこいい | LPや購入ページで購入促進 |
ニーズの解像度を高められるため、クエリも考えてみましょう。なお、効果を発揮させるためには、目的に応じた使い分けが必要です。
検索ボリュームによる分類
SEOキーワードは、検索ボリュームによってビッグ・ミドル・スモールに分類できます。
| 種類 | 定義 |
| ビッグキーワード | 月間における検索数が10,000を超えるもの。1ワード程度で検索される。 例)在庫管理ツール |
| ミドルキーワード | 月間における検索数が1,000〜10,000あるもの。2ワード程度で検索される。 例)在庫管理ツール おすすめ |
| スモールキーワード(ロングテール) | 月間検索数が1,000以下の少ないもの。3ワード以上で検索される。 例)在庫管理ツール おすすめ 無料 |
なお、単語の構成数が多いほどライバルが少ないため、検索順位上位を取りやすい傾向にあります。
成果につながるキーワード選定の手順
キーワード選定は以下の手順で行います。
- メインになるキーワードを決定する
- 関連性のあるキーワードを調査する
- ニーズやカテゴリーで分類する
- 検索ボリュームからキーワードをチェックする
- ライバルサイトを分析して難易度を測る
- SEOキーワードを選ぶ
選定手順を1つずつ解説するとともに、選定のコツも紹介します。
1.メインになるキーワードを決定する
はじめに、メインキーワードを決めます。どのようなコンテンツを作成したいかを考え、それに該当するキーワードを考えましょう。BtoBの場合は、自社商品やサービスに関連するキーワードを検討します。
2.関連性のあるキーワードを調査する
次に、関連・サジェストキーワードを調査し、内容を絞り込みます。「商品+安い」「サービス+おすすめ」のように、メインキーワードの内容を膨らませましょう。目星をつけた各関連・サジェストキーワードは、スプレッドシートなどに貼り付けておくと、次の工程に取り組みやすくなります。
この工程に取り組むと同時に、検索クエリも調査します。検索クエリの言葉に近づけることで検索に引っかかりやすくなります。
3.ニーズやカテゴリーで分類する
目星となるキーワードが見つかったら、次はニーズやカテゴリーで関連・サジェストキーワードを分ける作業です。グループに分けてリスト化すると、使われた単語がどのような内容を知りたくて検索されているかが一目でわかります。
例えば、メインキーワードで「SEO」と検索するとサジェストに以下のワードが表示されます。
- キーワード
- 対策
- ツール など
これらを区分し、それぞれに該当する関連キーワードやサジェストキーワードを分類します。
4.検索ボリュームからキーワードをチェックする
次に、検索ボリュームを調査してCVが狙えそうなものをピックアップします。ゼロに近いほどニーズがないため、仮に上位表示されても流入は見込めません。したがって、検索ボリュームで需要のあるキーワードを整理し、ニーズが高いキーワードをピックアップする必要があります。
5.ライバルサイトを分析して難易度を測る
次に、ライバルサイトの分析を行いましょう。検索ボリュームが多いほどニーズは高くなりますが、レッドオーシャンのため上位表示は困難です。ビッグキーワードのみだとユーザーが商品やサービスにたどりつけません。
ミドルキーワードやスモールキーワードも用いてライバルを減らしたり、ターゲットを絞り込んだりしましょう。自社商品やサービスへのニーズが高いターゲットに認知されやすくなるためにも、必要な工程といえます。
6.SEOキーワードを選ぶ
SEOキーワードをさらに絞り込みます。ほかのコンテンツにしたほうが良いものと、一緒に盛り込んでも問題のないものを分けて考えるとキーワードは選びやすくなります。
すでにコンテンツがある場合は、掲載済みのコンテンツに近いキーワードから作成しましょう。関連記事として掲載し内部リンクでつなげるとサイトの回遊率が上がり、上位表示されやすいWebサイトに育成できます。
BtoBでキーワードを選定するときに把握しておきたいこと
BtoB企業においてキーワード選定をする場合に、把握しておきたいことが3つあります。
- BtoCと比べると検索ボリュームが少ない
- CVしやすいキーワード(スモール)から対策する
- BtoBは「課題解決型」を積極的に選ぶ
それぞれを解説します。
1.BtoCと比べると検索ボリュームが少ない
BtoCに向けたキーワードと比べて、BtoBは検索ボリュームが少ない傾向にあります。BtoCのように考えていると、無理な目標につながったり、選定する際にどれを選ぶべきかわからなくなったりします。
なお、BtoBの場合は検索ボリュームが10〜100程度あれば十分です。一般的には1,000〜10,000程度とされているため、最低ラインは10〜100、最高ラインは1,000〜10,000で考えておきましょう。
2.CVしやすいキーワード(スモール)から対策する
CVしやすいキーワードから対策すると成果につながりやすくなります。なかでもスモールキーワードは効率的にCVを向上できる手法の1つです。ただし、この方法が有効なのはBtoBに限ります。
BtoBの場合は少ないボリューム数でもニーズがあるため、傾向的にはどのキーワードでも狙いやすい状態です。スモールキーワードはターゲットの絞り込みが強く、検索ボリュームが小さくなるため、BtoBのCV事情と相性が良いといえます。
3.BtoBは「課題解決型」を積極的に選ぶ
「課題解決型」とは、企業が抱えている問題の解決につながるキーワードです。企業が商品やサービスを求めているのは、社内の問題解決のためです。
カフェの経営者の場合、「お客様に美味しいコーヒーを淹れたいけど、ドリップは時間がかかるしインスタントは忍びない」といった問題を解決したいと考えられます。このようなニーズを汲み取ったキーワードを選ぶと、CVにつながりやすくなります。
結果に結びつけるための事前準備
選定したキーワードを効果に結びつけるには、事前準備が大切です。結果を出すための事前準備は以下の4つです。
- カスタマージャーニーマップを応用する
- サイトの目的を明確化しておく
- ペルソナ設計をしておく
- キーワードの検索意図を理解しておく
それぞれを社内で話し合い、戦略を固めましょう。
1.カスタマージャーニーマップを応用する
CVに直結するキーワードだけではWebサイトの育成は難しいため、さまざまな企業に流入してもらえるようにする導線を組むのがベストです。そのためには、フェーズごとに企業の状況やニーズなどがわかる「カスタマージャーニーマップ」を応用しましょう。
情報収集のフェーズ、購入のフェーズなど状況に合わせてキーワードを選定しコンテンツを作れば、見込み客から購入したい客層まで範囲を広げられます。結果的に、見込み客から購入につながる可能性があります。

2.Webサイトの目的を明確化しておく
Webサイトの運用目的を明確にしておくと、キーワードの絞り込みが効率良く行えます。加えて、自社商品やサービスのターゲットに沿ったコンテンツや、狙っているCVに沿ったコンテンツの作成も可能です。
例えば、「在庫管理や棚卸しに関する役立つコンテンツ」「総務・人事・経理に向けた役立つコンテンツ」などです。SEO効果を高め、上位表示されやすいWebサイトに育成できるメリットもあるため、キーワードを選定する前に目的を明確化しましょう。
3.ペルソナ設計をしておく
ペルソナ設計で具体的なターゲットを絞り込むと、そのターゲットの心をつかむコンテンツを作成できます。具体性が上がるほど記事を読んだ際に「自分のことだ」と共感してもらいやすくなるためです。
年商・企業規模・地域・業態など企業像を細かく検討し、悩みに寄り添えるコンテンツを作成しましょう。ペルソナ設計は、想像でも実際に身近にいる会社員を思い浮かべて作っても構いません。また、知恵袋などの質問サイトを使用するのも手段の1つです。

4.検索意図を理解する
検索されたキーワードにどのような意図があるかを知らなければ、ターゲットが興味を引くコンテンツを作成できません。自分の悩みを解決できるWebサイトではないと感じ、離脱につながります。そのため、問い合わせや購入に結びつきません。
検索意図の理解はどの施策においても大切ですが、キーワード選定においてはベースとなるため重要です。したがって、時間をかけてでも調査と分析を行う必要があります。なお、検索意図は先ほど紹介した「検索クエリ」の種類、知恵袋、上位記事のリード文から探れます。
キーワードを選定する上での注意点
キーワード選定をする上で、以下2つのポイントに注意が必要です。
- カニバリゼーションを避ける
- 1記事にKWを複数入れるなら検索意図と関連性を整理する
カニバリゼーションとは、コンテンツ内容の重複を指します。カニバリゼーションがあると、SEO評価が下がって上位表示が難しくなります。Webサイト内のコンテンツが増えるほどカニバリゼーションを特定するのは困難なため、以下のツールを使用するとよいでしょう。
- GRC
- site:コマンド
- Googleサーチコンソール
- Ahrefs
- SEMRush
また、1記事に入れるメインキーワードは1つが理想的ですが、複数入れたい場合は検索意図との関連性を必ず整理しましょう。検索意図がズレるキーワードや無関係なキーワードを入れると、内容の軸がズレて混乱を招きます。伝えたいことがユーザーに伝わるコンテンツにするためにも、盛り込む情報の整理は必要です。
まとめ
キーワード選定は奥が深く、調査と分析を怠ると成果につながりません。検索している企業が持つ問題や悩みを考え深掘りし、その答えに沿ったキーワードの使用により、自社商品やサービスの魅力が伝わりCVにつながります。
なお、リサーチはツールの使用がおすすめです。ラッコツールやウーバーサジェストなどを利用すると、関連・サジェストキーワード、検索ボリュームが一目でわかります。今回紹介したノウハウや方法を実践し、多くの企業に自社商品・サービスの魅力が伝わるコンテンツを作成しましょう。
ウェビットでは主に中小企業がWebマーケティング、Web集客を行ううえでのお悩みを解決するような情報を発信しております。気になられた方はぜひ、ほかの記事もご一読ください。