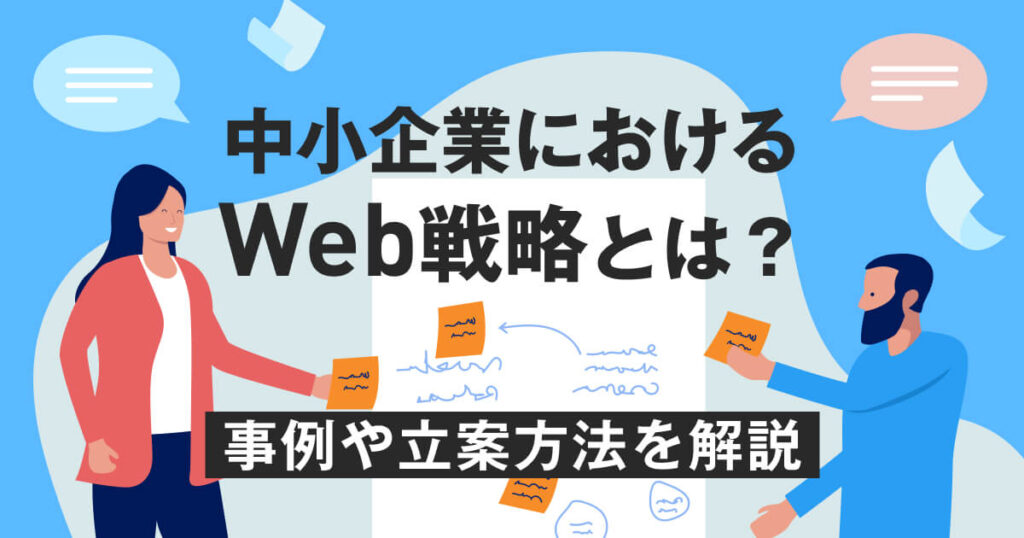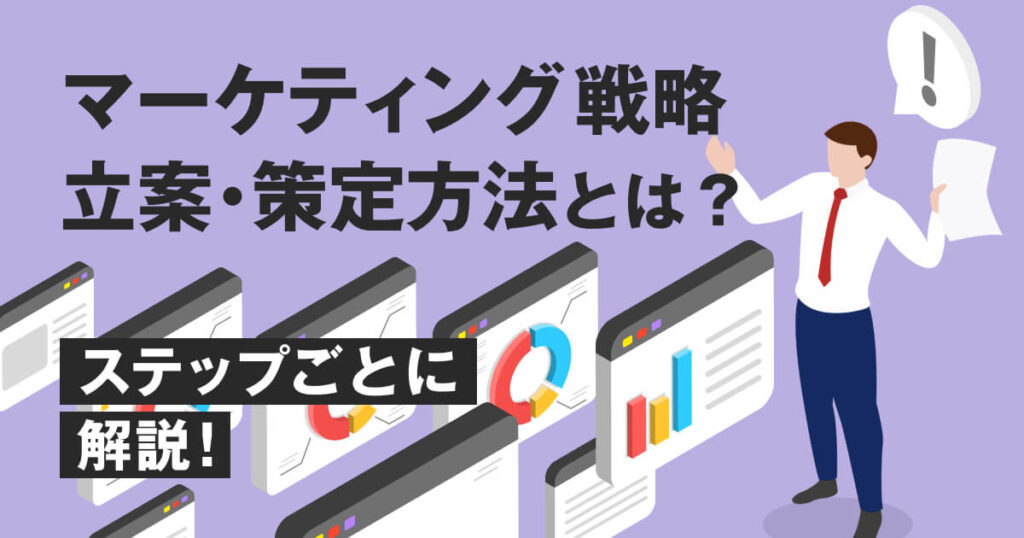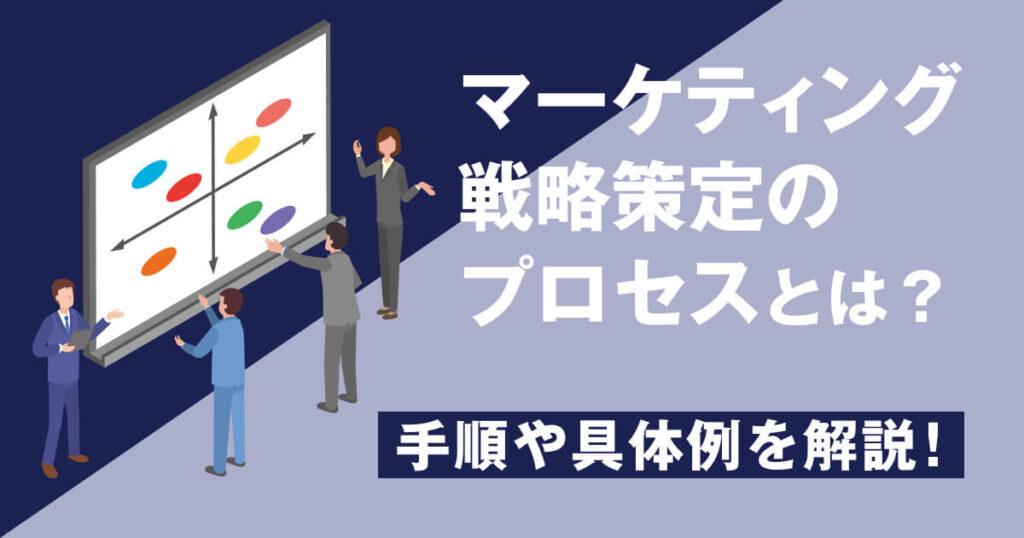近年、マーケティング手法の1つとして「共感マーケティング」が注目を集めています。ユーザーの信頼を獲得して企業ブランドや商品のファンを増やすための手法ですが、やみくもに共感を得られればよいわけではありません。
本記事では、共感マーケティングの基本や成功事例、メリット・デメリットを紹介します。また、共感マーケティングの始め方と成功させるためのポイント、実施する際の注意点も併せて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
共感マーケティングの概要
まずは、共感マーケティングの基本的な概念を解説します。併せて、近年注目を集めている背景や、類似するアプローチ手法であるエモーショナルマーケティングとの違いも紹介します。
ユーザーの心を動かして「ファン化」させるマーケティング手法
共感マーケティングとは、ユーザーとの感情的なつながりを築き、企業や商品の「ファン」を増やすことで、ブランド認知の拡大や売上向上を目指す戦略です。
ユーザーに共感を呼び起こし、忠実なファン層を形成するための施策を展開します。また、ブランドの価値を高めるために、口コミやインフルエンサーの発信を活用することも、共感マーケティングにおける主要なアプローチの1つです。
共感マーケティングが注目されている背景
技術の進歩やインターネットの普及により、現代は商品やサービスの選択が膨大に増えています。その結果、消費者は「何を選ぶべきかわからない」という状況にあるのが実情です。
さらに、アフィリエイト広告の普及により、従来の広告やインターネット上の情報の信頼性は低下傾向にあります。このような背景から、信頼できる個人の口コミやリアルな体験談が消費者の購買行動を左右する重要な要素であると考えられます。
エモーショナルマーケティングとの違い
エモーショナルマーケティングとは、感情マーケティングとも呼ばれ、共感マーケティングと同様にユーザーの感情に訴えかけるマーケティング手法です。
両者には明確な違いがあり、エモーショナルマーケティングはユーザーの「ニーズ」よりも強い感情、つまり「欲しい」「今すぐ手に入れたい」といった衝動を刺激し、強い購買意欲を喚起することが目的です。
一方、共感マーケティングは共感を通じてブランドや商品に対する信頼や親近感を育て、長期的なファンを獲得することに重点を置いています。どちらも効果的な手法として注目されていますが、目的やアプローチにおいて異なる特徴を持っています。
共感マーケティングを取り入れている企業事例
共感マーケティングを取り入れている企業の事例を3つ紹介します。
- 土屋鞄製造所
- サウナイキタイ
- 「AND PLANTS」
それぞれの企業がどのようにユーザーからの「共感」を得ているのか、事例を通して学びましょう。
土屋鞄製造所
土屋鞄製造所は、皮革商品の製造と販売をしている企業です。土屋鞄製造所はFacebookやInstagramなどのSNSやWebサイトを活用して急激に売上を向上させています。
SNSやWebサイトなど複数の媒体を運用していると、ブランドの世界観にズレが生じてしまいがちです。しかし、土屋鞄製造所ではこのような世界観のズレを生じさせないよう、特定部署の主要メンバーがコンテンツやクリエイティブの内容をすべてチェックしています。
どの媒体でも安定した「土屋鞄の世界観」の発信は、ユーザーに安心感を与えています。ブランドコンセプトに共感したユーザーからの支持が、売上に直結したと考えられる事例です。
サウナイキタイ
サウナ検索サイト「サウナイキタイ」の公式Instagramでは、若者の間で高まっているサウナブームにフォーカスした投稿を発信しています。特に、サウナとノスタルジックな要素を組み合わせることで、ファンのニーズに応え、人気を集めているのが特徴です。
さらに、グッズ展開においてもサウナイキタイは注目を集めています。Instagramのフィード投稿やストーリーズを活用し、グッズの販売情報を効果的に発信して、ファンの購買意欲を高めています。
AND PLANTS
AND PLANTSは、観葉植物とインテリアを展開するブランドです。公式Instagramでは、観葉植物のレイアウト方法を学べる投稿や、新たなお気に入りの植物を発見できるコンテンツを発信し人気を集めています。
ユーザーが求める情報を提供しつつ、自社商品の魅力を自然に伝えている点が特徴です。ユーザーのライフスタイルや価値観に寄り添うことで共感を生み出し、ファン化を促進した事例です。
共感マーケティングの実践方法
ユーザーからの「共感」を得るマーケティングは、以下の流れで実践していきます。
- 自社のビジョンを明確にする
- ペルソナ設計・ニーズ分析を行う
- 共感が得られるコンセプトを考える
- 商品のストーリーを投稿する
- UGCを得るための仕組みを作る
それぞれを詳しく説明します。
1.自社のビジョンを明確にする
ユーザーに共感してもらうためには、企業が実現したいビジョンを明確に掲げることが重要です。ビジョンが不透明なまま発信してしまうと、企業の目指す未来がユーザーに伝わらないため興味を引けません。
その結果、ユーザーからの共感を得ることは難しくなるでしょう。ユーザーが応援したくなるような魅力的なビジョンを掲げ、共感マーケティングを実践していきます。
2.ペルソナ設計・ニーズ分析を行う
商品を売りたいターゲットを絞り込みます。ターゲットを選定する際は、実在する人物のように詳細にペルソナを設計することで、より深い理解とつながりを築けます。ペルソナ設計では、以下のような要素を詳細に検討してください。
- 年齢
- 性別
- 居住地
- 職業
- 収入
- 趣味
- 嗜好 など
ペルソナ設計が完了したら、ペルソナのニーズを分析し、共感を得られるコンセプトを考えます。ペルソナの日常で発生する具体的なニーズを洗い出すことが重要です。

3.共感が得られるコンセプトを考える
ペルソナのニーズに合わせて、共感を得られる商品コンセプトを検討します。この際、自社の分析も行い、自社の強みや共感ポイントを洗い出すのも重要です。例えば、以下のような強みや共感ポイントがコンセプトに挙げられます。
- ミニマリストに選ばれた
- シンプル
- 現役ママスタッフが選んだ など
ユーザーへのアンケートやインタビューなどもコンセプトを決めるのに役立ちます。
4.商品のストーリーを投稿する
商品やコンセプトが決まったら、商品のストーリーを発信していきます。発信内容には、以下が挙げられます。
- 商品完成までの課題や苦労
- 実際に商品を利用した顧客の変容
- 自社の熱意 など
ストーリーに共感する人の熱量が高いほど、拡散力が向上する傾向にあります。
5.UGCを得るための仕組みを作る
共感してくれるファンが集まったあとは、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を生み出す仕組み作りが重要です。熱量の高いファンはSNSで投稿して拡散してくれますが、より多くのUGCを獲得するためには、企業側の仕組み作りが不可欠です。
抽選やシェアキャンペーンなどを積極的に活用し、UGCを得るための仕組みを構築しましょう。ユーザー参加型のキャンペーンは、ユーザーとの絆を強め、ファンを増やすことにもつながります。
共感マーケティングを取り入れるメリット
共感マーケティングを取り入れるメリットは、以下の通りです。
- 顧客ロイヤリティの向上につながる
- シェアやUGCによる認知拡大が見込める
- 改善につながるフィードバックを獲得できる
- 新規顧客の獲得につながる
それぞれのメリットを詳しく解説します。
顧客ロイヤリティの向上につながる
共感マーケティングにより企業やブランドに共感したユーザーは、親近感や信頼感を抱きやすいため熱量の高いファンとなる可能性があります。
自社ブランドに信頼や愛着を持った熱量の高いユーザーは、競合に流されず、商品やサービスを積極的に紹介してくれるロイヤリティの高い顧客に変わります。共感を生み出すことで顧客ロイヤリティが向上し、その結果、売上向上の効果が期待できるでしょう。
シェアやUGCによる認知拡大が見込める
ユーザーから共感を得られれば、シェアやUGCが生まれ、効率的にブランドの認知拡大が狙えます。共感したユーザーは「良い商品を広めたい」という感情が湧くため、SNSでは「いいね」や「リポスト」といった行動を起こします。
これにより、共感が共感を呼ぶ連鎖が生まれ、ブランドの認知度が自然に広がる効果が期待できます。
改善につながるフィードバックを獲得できる
共感マーケティングでは、熱心なユーザーが情報を発信するといった特徴があります。そのため、質の高いフィードバックを獲得できるでしょう。
商品やサービスを利用したあとの口コミには、自社では気づいていなかった改善点が記載されている場合があります。得たフィードバックを活かして品質向上に努めれば、顧客満足度や信頼を獲得でき、結果として売上向上につながります。
新規顧客の獲得につながる
共感が増えるほど、ファン化や顧客ロイヤリティが向上します。その結果、熱量の高いファンが自社を応援してくれるようになり、リピートや宣伝活動を通じて新たな顧客獲得につながります。
ただし、ファンの獲得は簡単ではありません。共感を得られるストーリーを構築し、継続的な情報発信を行い、長期的に運用していく必要があります。
共感マーケティングのデメリット
共感マーケティングはメリットばかりではなく、以下のようなデメリットもあります。
- 共感が得られない場合がある
- 成果が出るには時間がかかる
共感マーケティングを実施しても、すべての人から共感を得られるわけではありません。共感を得ようとするあまり過度に刺激的なコンテンツを配信すると、批判を受ける可能性もあります。
さらに、ユーザーの共感を獲得するためには、試行錯誤を重ねながら運用を続ける必要があります。成果が出るまでには時間と根気が求められるでしょう。
共感マーケティングを成功させるポイント
共感マーケティングを成功に導くポイントは、以下の通りです。
- 企業らしさを感じさせない発信を心がける
- ユーザーにとってためになる情報を発信する
- コミュニティやイベントなど交流の場を提供する
それぞれのポイントを詳しく解説します。
企業らしさを感じさせない発信を心がける
共感マーケティングを成功させるには、ユーザーからの信頼を得ることが重要です。そのためには、企業らしさを感じさせない情報発信を継続する必要があります。売りたいという意図が強く読み取れる発信は、ユーザーに不信感を与える可能性があるため、過度に押し出した内容は控えるべきです。
商品を購入するかどうかの決め手の1つには、「この企業は信頼できる存在だ」とユーザーに感じてもらうことです。販売意欲が前面に出る発信は避け、まずはユーザーに寄り添う姿勢を大切にしながら、信頼関係を構築していきましょう。
ユーザーにとってためになる情報を発信する
SNSでの投稿は「有益な情報」が拡散されやすく、注目を集める傾向があります。そのため、商売色を抑え、SNSはユーザーにファンになってもらう場として活用するという視点が重要です。
ユーザーにとって価値のある情報を提供し、「いいね」や「保存」「シェア」を促進することを目標にしましょう。こうした積み重ねが信頼関係の構築とブランド認知の拡大につながります。
コミュニティやイベントなど交流の場を提供する
コミュニティやイベントなどで、ユーザー同士が交流できる場を作ったり、ファンのつながりを作ったりするのも共感マーケティングを成功に導くポイントです。
特に、リアルな場でのコミュニティは、より強固なファンのつながりが構築できるため、ファンの熱量が上昇していきます。イベントに同席した友人や知り合いなど、新たな顧客の獲得にもつながるでしょう。
共感マーケティングを実施する際の注意点
共感マーケティングを実施する際は、以下の点に注意が必要です。
- トラブルにつながる内容を避ける
- 宣伝感を全面に押し出さない
- ブランドイメージと商品のコンセプトに一貫性をもたせる
- BtoBマーケティングには向いていない
- インフルエンサー選びは慎重に行う
それぞれの注意点を把握し、共感マーケティングに取り組みましょう。
トラブルにつながる内容を避ける
人の心を動かすためには、時に強い言葉や価値観に影響を与える表現が必要になる場合もあります。しかし、その一方で、反発を招くリスクも十分に理解し、リスク管理を前提とした発信が求められます。
特に、明らかに炎上につながる可能性のある表現や失言は避けるべきです。投稿前には必ず内容を見直してトラブルを未然に防ぎましょう。
宣伝感を全面に押し出さない
商売欲や宣伝感を押し出した内容だと、ユーザーの気持ちは冷めてしまうため注意が必要です。共感マーケティングはファンの熱量を高める施策であり、結果として売上向上につながるという認識を持つことが大切です。ファンとのコミュニケーションを最優先に進めるようにしましょう。
ブランドイメージと商品のコンセプトに一貫性をもたせる
企業のブランドイメージと商品のコンセプトに一貫性をもたせることは、共感マーケティングにおいて重要な要素です。一貫性が欠けていると、ユーザーに違和感を与えてしまい、共感を得ることが難しくなる可能性があります。
ブランドイメージと商品コンセプトがかけ離れてしまわないよう、企業の理念やビジョンを反映したコンセプト設計が求められます。
BtoBマーケティングには向いていない
共感マーケティングは感情に訴えかける手法であるため、BtoBマーケティングには必ずしも適しているとはいえません。BtoBの場合、価格や機能性、導入後の効果といった論理的な要素が重視される傾向にあります。
また、BtoBでは意思決定に複数の関係者が関わることが多く、感情的なアプローチだけでは十分な成果を得られない場合もあります。そのため、共感マーケティングを補完する形で、データや実績に基づく説得力のある施策も組み合わせることが重要です。
インフルエンサー選びは慎重に行う
インフルエンサーの起用は、拡散力が高く、大きな影響を与えるメリットがあります。しかし、インフルエンサー自身の不祥事や炎上によって、自社のサービスや商品にネガティブな影響を及ぼすリスクも伴います。
そのため、インフルエンサーを選定する際はフォロワー数だけでなく、普段の投稿内容や価値観、過去の発言履歴なども慎重に確認しなければなりません。ブランドイメージと親和性の高いインフルエンサーを選ぶことで、共感を得られる効果を最大化できるでしょう。

まとめ
共感マーケティングとは、ユーザーの信頼や共感を得て、自社のブランドや商品のファンを増やすための手法であり、成功すれば認知拡大や売上向上につながります。近年、消費者の購買行動は変化しており、口コミを参考に信頼できる企業から購入する方が増えています。
そのため、共感マーケティングに注目している企業も多いでしょう。しかし、共感を得ればよいわけではなく、明確なビジョンを持って、ペルソナのニーズに合わせた共感ポイントを伝える必要があります。
共感マーケティングを成功させるポイントとしては、企業らしさや販売欲を抑えて、ユーザーに有益な情報を提供することが大切になるでしょう。
ウェビットでは主に中小企業がWebマーケティング、Web集客を行ううえでのお悩みを解決するような情報を発信しております。気になられた方はぜひ、ほかの記事もご一読ください。