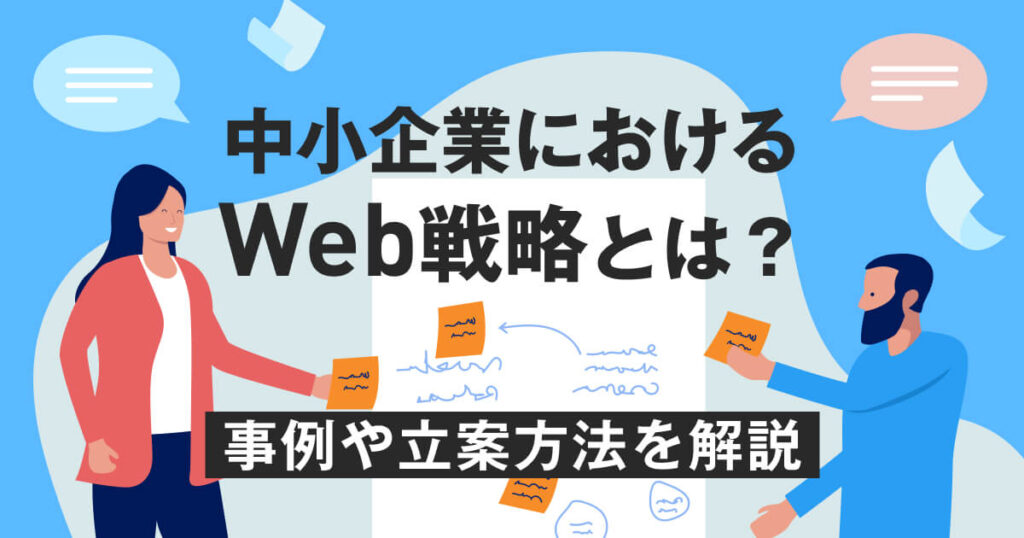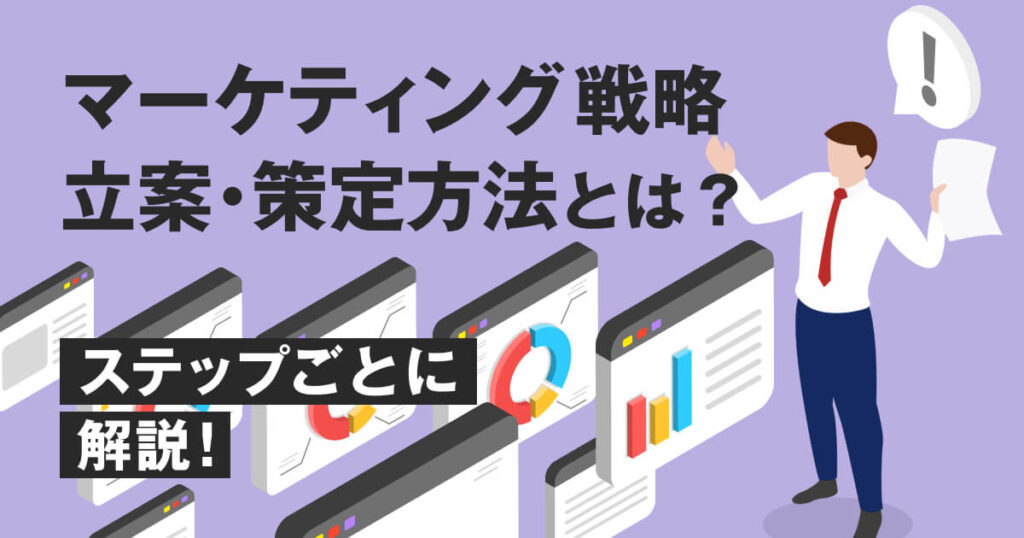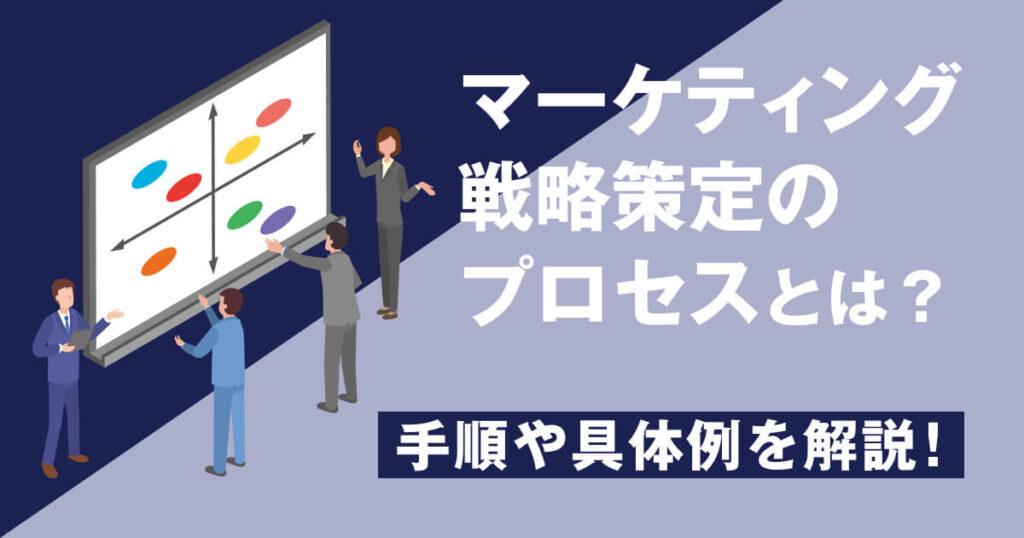顧客心理の理解は、ビジネスを成長させる上で欠かせません。顧客心理を無視した事業は、失敗に終わるでしょう。
しかし、顧客心理とはどのようなものなのかわからず、「〇〇だろうな」と予測を立てて終わりにしている方もいるかもしれません。顧客心理は共通しているところもあり、ある程度理解した上で戦略を立てることで、効果的にアプローチをかけられるようになります。
そこで本記事では、顧客心理の重要性から共通する顧客心理の理解と活かし方について解説します。今後事業を発展させたい方は、顧客心理を理解しておくことをお勧めします。
顧客心理とは
顧客心理とは、消費者が商品やサービスを選択し、購買行動を起こす際に影響を与える、心の中に存在するさまざまな思考や感情のプロセスを指します。つまり、お客様の気持ちです。
顧客心理の理解は、消費者のニーズや欲求、行動の背後にある動機、選択基準などを解明し、それに基づいて効果的な戦略を展開するためにも大切です。
顧客心理の重要性
顧客心理を理解することで、よりターゲットに向けた効果的な広告やコンテンツを制作し、消費者の購買意欲を高められます。また、顧客のニーズに合った商品やサービスを提供できれば、顧客満足度を向上させ、長期的な顧客ロイヤルティを構築することも可能です。
顧客心理を理解することの重要性は、大きく7つあります。
- 顧客心理を理解することで、ターゲット市場のニーズや欲求を正確に把握でき、それに基づいて製品やサービスの特長を強調し、効果的な訴求ができる。
- 消費者の感情や価値観に訴えるコンテンツや広告を提供でき、関心を引くことで顧客とコミュニケーションを図れるようになる。
- 顧客の要望や不満を特定できれば、商品やサービス改善に役立つ。
- 顧客心理を理解して顧客満足度を高められれば、競合他社との差別化ができ独自の価値が提供しやすくなる。
- 顧客心理を考慮したアプローチによって、顧客はより高い関心を示し、ブランドへの愛着を高められる。
- 市場の需要にマッチした商品開発ができる。
- 顧客心理を理解した上での適切な戦略は、リピーターを生み、新たな顧客を引き寄せるためビジネスの発展につながる。
顧客心理を理解せずして、ビジネスの発展はありえません。
顧客の共通する気持ちを理解する6つの心理
顧客の心理はさまざまですが、根本的には共通した心理が働くことがあります。戦略的なアプローチをするためにも、まずは顧客の深層心理にはたらく思考や感情のプロセスを整理しておきましょう。
歓迎期待の心理
歓迎されたい、気持ちよく受け入れてほしいという顧客の気持ちです。店舗に訪れたりWebサイトを閲覧したり、サービスを利用する際に、自分が大切にされ、歓迎されていると感じることを望んでいます。この心理的な要求が満たされると、顧客はポジティブな印象を持ち、満足度が高まります。
人はサービスを受けるときに、無意識にその場の空気や対応するスタッフの表情・口調から敏感に状況を捉え心地よさを測るものです。例えば、お店に入るときに店員の方が「いらっしゃいませ」と作業しながら、定型文のような言葉を投げかけていたらどうでしょう。決して歓迎されている気持ちは感じないはずです。目を見て、一人一人に合った言葉を伝えて初めて気持ちが伝わります。
さらには、顧客に親切な接客や丁寧な対応を行うだけでなく、ウェルカムメッセージや特別な待遇などのように歓迎の気持ちを形にし、提供することも大切です。顧客は自分が大切にされていると感じやすくなり、顧客満足度の向上や顧客のロイヤルティの構築につながります。
自分本位の心理
顧客はまず、自分のニーズや欲求を優先して考えます。意思決定や行動をする際に、まず自分の利益や満足を最優先に考えるのが「自分本位の心理」です。
顧客は何かを購入する際に、その商品やサービスが自分自身にとってどれだけ役立つか、自分のニーズや欲求をどれだけ満たすかを重要視しています。価格やコストパフォーマンスと商品を手にすることで得られる効果が合致するかどうかなどが判断基準です。
マーケティングにおいては、「自分本位の心理」を理解することが重要です。顧客が商品やサービスを選ぶ際に、自分の利益や欲求を満たすことを重視していることを把握し、それに合わせたアプローチやメッセージを提供することで、顧客の興味を引きつけられます。また、商品やサービスの利点を明確に伝え、自分本位の心理に合致する価値提供を行うことで、購買意欲を高められるでしょう。
優越感を感じたい心理
ほかの人よりも優れていると感じたいという心理的な欲求や要因を指します。自分がほかの人よりも特別であると感じることで、自己評価を高め、自己満足感を得たいと望む傾向があるのです。
この心理的な要因は、消費者行動や社会的な関係に影響を及ぼすことがあります。例えば、特別な体験や高級品を求めるのは、ほかの人に対して優越感を持ちたいという心理が働くからです。また、ソーシャルメディアの投稿やシェアも、自分の生活や成果を見せつけ、優越感を得たいという感情の一部でもあります。
マーケティングにおいて、高品質な商品や特別な体験、エクスクルーシブなアクセスなどを提供することで、顧客が優越感を感じられる環境を提供できます。また、ブランドのイメージや広告メッセージを通じて、顧客が他の人よりも特別な存在であると感じる要素を強調することも効果的です。
真似をしたい心理
ほかの人が行っている行動や選択に影響されて、同じような行動や選択をしたいという心理的な傾向です。人は周囲の人々の行動や意見に影響を受けやすく、自分も同じような体験や成功をしたいと感じます。
この心理的な要因は、ソーシャルプルーフ(社会的な影響による行動の模倣)の一例です。ほかの人がよいと評価した商品やサービスを選ぶことで、成功や満足感を共有しようとします。また、流行やトレンドもこの心理に影響されて広まることがあります。
顧客へのアプローチとしては、ほかの人が商品やサービスを選ぶ理由や成功体験のシェアが有効です。同じ選択をしようと考える可能性が高まります。実際の顧客の声やレビューを活用したマーケティング戦略や、ソーシャルメディアでの積極的な顧客の共有などが、この心理を利用したアプローチです。
独り占めしたい心理
特定の商品や体験に対して、ほかの人と共有せずに自分だけが楽しみたいという欲求です。人は時に特別な体験やユニークなものを、自分だけのものとして楽しみたいと考えることがあります。
この心理的な要因は、個人のプライバシーや特別感への欲求に関連しています。特に限定商品や限定サービス、プライベートな体験などに対して、独占的な感覚を求めがちです。
顧客の満足度やロイヤルティを高めるためには、「独り占めしたい心理」をうまく活用することが大切です。限定商品やプレミアムな体験を提供することで、顧客はほかの人と共有せずに特別なものを楽しむことができ、独自の価値を感じられます。また、VIP会員制度や特別な特典なども、独占感を提供する手段の一つです。
損をしたくない心理
顧客が購買や取引において、損をすることを避けたいという心理的な欲求や要因です。プロスペクト理論ともいいます。人は自分の資源や時間を最大限に活用し、無駄なコストや損失を避けたいと考えがちです。
この心理的な要因は、消費者行動において価格やコスト、リスクに対する敏感さを反映しています。顧客は価格の競争力やコストパフォーマンスを重視し、選択肢の中で最大の利益を得たいと無意識のうちに感じているのです。
購入を後押しするには、「損をしたくない心理」を考慮し、不安を解消させることが大切です。価格設定やコスト面での透明性を提供することで、顧客は自分の資源を無駄にしない選択をしやすくなります。
また、リスクヘッジの提供や保証制度を設けることで、顧客が損失を最小限に抑えることができる環境を提供することも効果的です。消費者が自分の投資を守り、最大のリターンを得られると感じることで、信頼感や満足度を向上させることができます。
顧客心理を理解するための方法
顧客心理を知る方法として一番手っ取り早い方法が、自分自身が顧客になる点です。経営者である自分が顧客になって、ほかのお店のサービスを利用したり、商品を購入したりすれば顧客が何を求めているのかがわかります。
さらには、これから紹介する方法を組み合わせれば、顧客心理をより深く理解でき、顧客満足度を高めるサービスや商品を提供できるようになるでしょう。
エンパシー(共感)
エンパシーとは、ほかの人の状況や感情を認識し、理解する能力です。顧客の立場に立ち、消費者が商品やサービスを選ぶ際の心理的な要因や動機、ニーズや欲求を深く理解すれば、顧客心理を深く理解できます。
より難易度の高い方法として、エスノグラフィ(訪問観察調)があります。エスノグラフィとは、顧客と同じ生活環境に一定期間身を置き、顧客の考えを深く理解し、新たなニーズや課題などを探る方法です。
インタビューやアンケートなどでも顧客のニーズを確認できますが、生活をともにすれば、よりリアリティのある情報に多く出会えるため、消費者行動を深く理解できます。
マーケティングリサーチ
マーケティングリサーチとは、アンケート調査やフィードバックの収集、インタビューなどを通じて、顧客の意見や要望などを直接聞き取る方法です。
リサーチ方法には、定量調査と定性調査の2種類あります。定量調査とは、人数や金額など明確な数字で傾向を調べ、その結果を基に市場の実態を調査する方法です。定性調査とは、使い勝手や印象など数字にできない情報を分析し、その結果を基に感覚的な情報や価値観、ライフスタイルなどを調査する方法です。
SNS分析(ソーシャルリスニング)
ソーシャルリスニングとは、Twitter・Instagram・FacebookなどのSNSや、口コミ・レビューサイト・ブログなどで発信された情報を収集して、分析するマーケティング手法です。
SNSは、個人の考えが自由に発信されている場となります。その個人の意見は、消費者のリアルな声となるため、その情報を拾えば顧客ニーズがわかり、そのニーズに合わせて改善を行なえば、顧客満足度の向上へとつながります。
顧客のインサイトを把握しより訴求性の高いアプローチを
顧客のインサイトとは、マーケティング領域において顧客の本質的な欲求や、深層心理にある本音や動機などです。
潜在ニーズとの違いは、自覚できる欲求か無意識の欲求かの違いです。潜在ニーズは無意識に感じている欲求だとしても、質問を通して本人に気づかせられます。一方、顧客インサイトは、潜在ニーズよりもより深い領域で、本人も気づいていない無意識の欲求であり、行動のスイッチとなっているものです。
顧客の無意識の欲求が叶えば、体験価値が高まり顧客満足度も高められます。それぞれのインサイトを見ていきましょう。
自律性
顧客が自分自身のニーズや欲求を理解し、自己の判断や選択に基づいて行動する能力や傾向を指します。つまり、顧客が自分の内面的な気持ちや価値観に従って、自分に最適な選択をしたいという欲求です。
自律性が高いと、広告やマーケティングメッセージに影響されるだけでなく、自分自身の考えや感情を大切にしながら、購買行動や意思決定を行います。一般的なトレンドや社会的な影響に流されることなく、自分自身に忠実に行動しているのです。
自律性の高い顧客に対して、それぞれのニーズや価値観を尊重し、それに基づいて選択をすることを尊重するアプローチが求められます。また、彼らが自分自身の意思決定を尊重する環境を提供することが大切です。
反対に、周囲の情報に過度に影響を受けやすい顧客に対しては、アプローチを変える必要があります。
関係性
顧客は単に商品やサービスを購入するだけではなく、企業やブランドとの信頼関係や良好なコミュニケーションを求めています。期待している関係性として5つのポイントがあります。
- 顧客は自分の大切な情報を預ける際に信頼性を求めます。信頼関係が築かれることで、顧客は安心して取引を進められます。
- 顧客は自分の個別のニーズや要望に合わせた対応を望んでいます。
- 顧客は自分の立場や感情を理解してくれる企業を求めています。共感的なコミュニケーションやサービス提供によって、顧客は自分が大切にされていると感じられます。
- 顧客は単なる一回の取引だけでなく、持続的な価値を受けたいと考えています
- 顧客は自分の意見や要望を伝え、フィードバックを提供したいと思っています。良好な関係性があれば、顧客は積極的にコミュニケーションを取ろうとするでしょう。
関係性の築き方や顧客対応が、ビジネスの成功に大きく影響を与えることがあります。関係性を大切にすることで、顧客の満足度やロイヤルティが向上し、エンドユーザーにつながります。
まとめ
この記事では、共通する顧客心理の解説とアプローチへの活かし方を解説しました。顧客の考えはさまざまに見えますが、実は大元を辿れば共通する欲求があります。顧客から選ばれる企業になるには、顧客の心理を理解した上でマーケティングの戦略を立てなければなりません。顧客自身も気づいていない欲求をくすぐり、セールスをかけ続けなくとも選ばれる会社を目指していきましょう。
Webhit(ウェビット)では主に中小企業がWebマーケティング、Web集客を行う上でのお悩みを解決する情報を発信しています。この記事が気に入った方は、ぜひ他の記事もご一読ください。