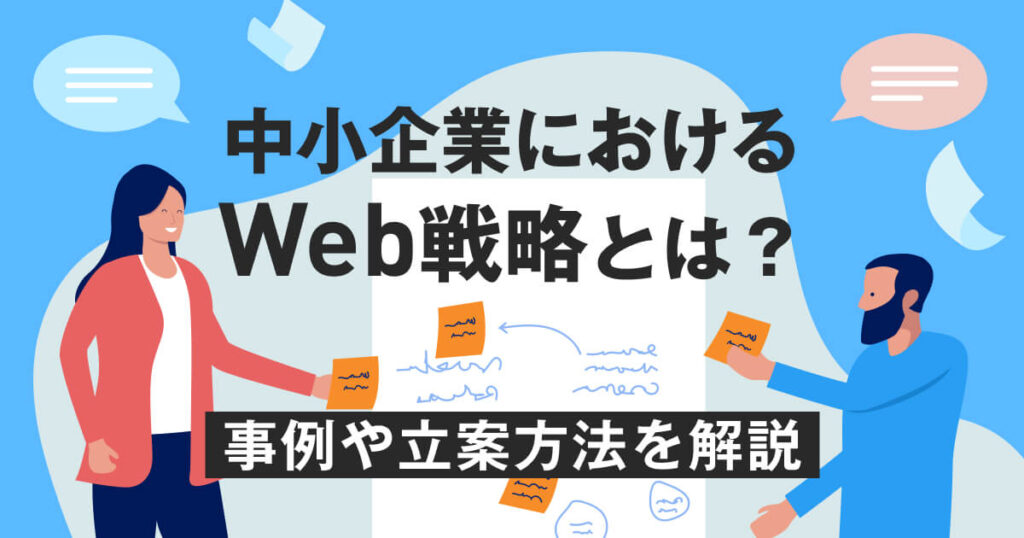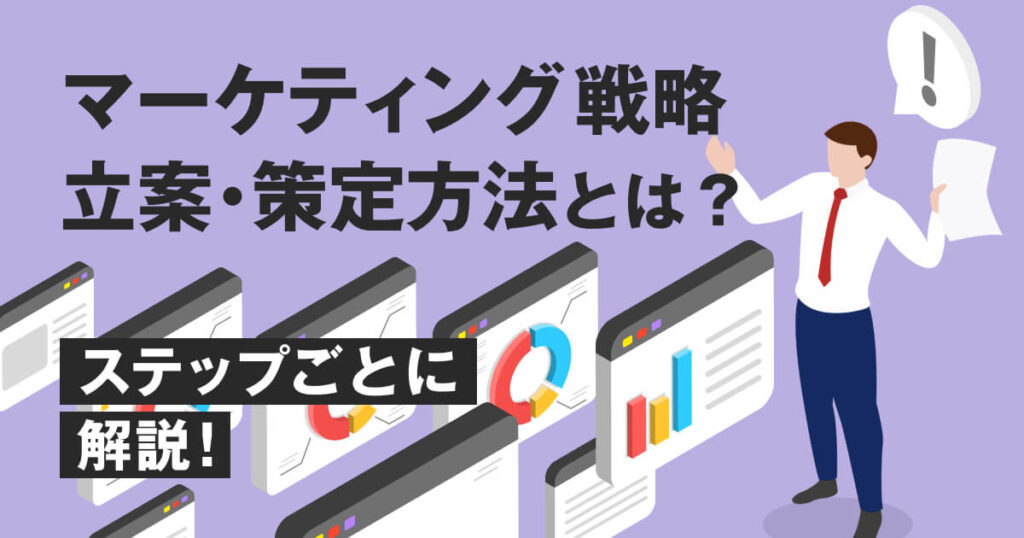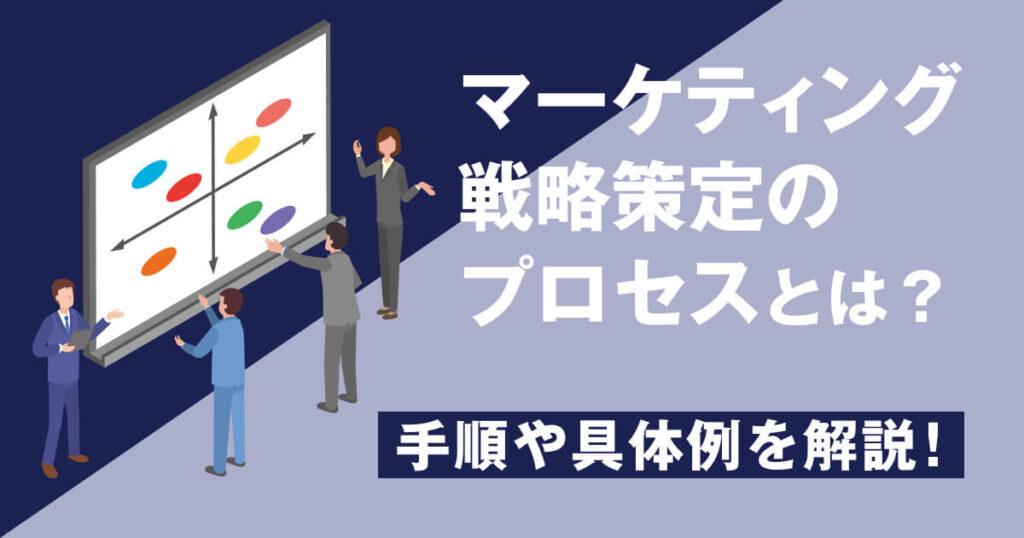ハロー効果とは心理効果の一種です。消費者は、企業の1つの特性や印象に基づいて全体的な評価を下す傾向があります。そこでハロー効果をマーケティングに活用すれば、企業や製品のイメージの向上を狙えるかもしれません。ただし、過度に依存し過ぎると、消費者に誤解を与えたり、信頼を失ったりするリスクもあります。
本記事では、ハロー効果の概要やマーケティングへの活用方法に加え、ハロー効果を活用する際の注意点を解説します。消費者の心理効果を理解し、企業イメージやブランドイメージの向上を狙うマーケティング担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
心理学におけるハロー効果の概念
心理学におけるハロー効果とは、第一印象や第三者からの口コミなど一部から受ける印象で、人や物全体の評価をしてしまう心理効果です。
例えば、高学歴や大企業勤務と聞くと、実際の能力や人柄を確認する前からエリートだと思い込んでしまう事例が該当します。また、第一印象が悪いと、その後も最初の印象を引きずり、印象が好転しない場合もハロー効果の一種です。
このように、プラスに働くこともあればマイナスに働くケースもあります。
ハロー効果は、無意識のうちに誰もが経験する一般的な心理効果です。ビジネスにおいて、人事領域やマーケティングで盛んに活用されています。
ハロー効果の具体例
この項では、ハロー効果の具体例を以下の3点から解説します。
- 面接での例
- 人事評価での例
- 日常生活での例
まずは、ハロー効果が発揮される具体例を確認し、無意識に働く心理効果を認識しましょう。
面接での例
面接は限られた時間と情報で判断が必要なため、ハロー効果が評価に影響を与えやすい傾向です。例えば、国立大学や有名私立大学に通っている学生の方が、知名度の低い大学に通っている学生より優秀と判断されやすいのもハロー効果が働いています。
また、自分や同僚・上司の母校に通っている学生に親近感を抱き、高評価をつけるケースもあります。このほか、綺麗にアイロンがけしたスーツを着用し、清潔感のある髪型をしている学生に好印象を持つ場合もあるでしょう。
一方、第一印象が悪かった場合は短時間の面接では挽回できず、評価に影響を与えかねません。そのため、学生は面接官に好感を与えるような髪型、服装を意識し、高い評価を狙った無難な受け答えになることもあります。
人事評価での例
人事評価で現れるハロー効果の事例として、資格やスキルが評価に影響を与える点が挙げられます。英検1級を持っている、TOEICの成績がよいといった従業員には、たとえ業務と無関係の資格やスキルであっても「優秀な人」と無意識のうちにフィルターをかけてしまうことがあります。知名度が高く難関な資格ほどその傾向は強めです。
このように一部の評価が高いと、マイナス点が目に入らず全体的に高い評価を下しやすい反面、一部の評価が低いと、成果が高くても全体的に低い評価を下す傾向もあります。この現象もハロー効果の一種です。
日常生活での例
日常生活におけるハロー効果の例としては、好感度や知名度の高い有名人がCMをしている商品に好感を抱くことが挙げられます。また、身だしなみが整った格好をして、かつ礼儀正しい振る舞いをしている人に「家柄がよさそう」「能力が高そう」など好印象を抱くのもよく見られる事例です。
反対に、口調が乱暴だったり服装がラフだったりする人に、無意識のうちに悪い印象を抱くケースもあります。
人間関係において、第一印象がよかったことで歩み寄ってみたものの、感じていた印象と性格がマッチせず、距離をおいてしまった経験がある方もいるでしょう。これも、身近におけるハロー効果の影響です。
心理学におけるハロー効果の種類
ハロー効果には、ポジティブハロー効果とネガティブハロー効果の2種類があります。ここでは、2つのハロー効果の特徴や類似している心理効果を紹介します。
ポジティブハロー効果
ポジティブハロー効果とは、一部のよい印象に引っ張られて、それ以外の要素もプラスの方向にバイアスがかかる心理効果です。例えば、人気女優がCMしている化粧品は効果が高いように思えてしまう、親切な行為が目に留まると人柄がよい人に見えるなどが挙げられます。TVCMなどの広告はポジティブハロー効果を効果的に取り入れている好例です。
ポジティブハロー効果の類似効果にピグマリオン効果が挙げられます。ピグマリオン効果とは、他者から期待されると、期待に沿った成果を出す傾向にあるという心理効果です。ポジティブハロー効果で好印象を持たれた人が、ピグマリオン効果によって印象通りに振る舞うようになるケースもあります。
ネガティブハロー効果
ネガティブハロー効果とは、一部の悪い印象に引きずられて全体をマイナスに評価してしまう心理効果です。例えば、自分がスーツで仕事相手が私服だった場合、「仕事に身が入っていないのではないか」「自分が軽く見られているのではないか」といったネガティブな想像が働くケースが挙げられます。
一度不祥事を起こした企業や人物の評価が落ち、ささいな失敗でも厳しく糾弾されるようになるのもネガティブハロー効果の一例です。
ネガティブハロー効果と同様の心理効果がホーン効果です。これは、第一印象や第三者からの口コミなどが悪いと、それに引きずられて全体の評価がマイナスに傾いてしまう心理効果です。
仕事の面接をはじめとするビジネスシーンで身だしなみを整えるのは、ネガティブハロー効果を防ぐためといえます。
心理学におけるハロー効果のメリット・デメリット
ハロー効果にはメリット・デメリットの両方があります。ハロー効果を効果的に使うためにも、メリット・デメリットを理解しておくことが重要です。
メリット:高評価になりやすい
ハロー効果のメリットとして、第一印象で優れているところが1つでもあれば、高評価を受けやすく信頼されやすい点が挙げられます。
例えば好印象を与える広告を作成し「性能や品質が高い商品やサービスである」と消費者に印象づけられれば、仮にマイナスポイントがあったとしてもプラスの要因にバイアスがかかり、顧客からの信頼は崩れにくくなります。
デメリット:不当な評価を受ける場合がある
ハロー効果は、第一印象が悪いと不当な評価を受ける恐れがある点が大きなデメリットです。例えば、優秀で仕事の実績もある人でも、重要な会議に遅刻したり場にそぐわない服装をしてきたりすれば「仕事ができない人」「いいかげんな人」といったマイナスの評価を受ける可能性があります。
特に、インターネット上で誤った印象が広まってしまうと払拭するのが困難です。中でもSNSは拡散力が高く、商品を買ったりサービスを利用したりしたことがない人にも悪印象を抱かれる恐れがあります。
マーケティングでハロー効果を活用する方法
ハロー効果は、マーケティングにも盛んに活用されています。費用をかけて広告を作るのもハロー効果を狙ってのことです。ここでは、ハロー効果をマーケティングに活用する具体例を紹介します。
ブランディングする
ブランドイメージを高めて消費者によい印象を与えることは、ポジティブハロー効果が見込めます。ハイブランドとして世界中で知名度があり、高くても購入者が絶えないメーカーは、会社のブランディングにおける成功例です。
また、お菓子ならばおいしそうなお菓子の写真を載せる、化粧品ならば美しくデザイン性に富んだパッケージにするなど、パッケージに工夫を凝らしてブランディングを高める方法もあります。加えて、手に取った人に強い印象を残す独自のロゴやマークなどをつけるのも効果的です。
ロゴやキャラクターと会社・商品がプラスの印象で結びつけば、ハロー効果により製品全体が高品質であると認識され、信頼できるブランドのポジションを獲得できます。

数値データを活用する
「98%の方が満足しました」「100万部突破」など、具体的な数値や研究データなどをCMや広告に取り入れると説得力が増し、ハロー効果が得られやすくなります。学者や医師など、権威性を持つ人が具体的な数値を挙げて説明すると、さらに高い効果が得られるでしょう。また、受賞歴などの実績を取り入れることでもハロー効果が期待できます。
このほか、「創業×年」などの歴史を強調するのも数値データを活用する方法の1つです。「長く続いているならば信頼できる」と好印象を与えられるでしょう。
有名人や実績のある人を広告に起用する
有名人や人気者を起用したCM・広告作成は、ポジティブハロー効果を見込める宣伝方法です。例えば女優を化粧品のCMに起用すれば、ファンはもちろん「これを使ったら女優のように綺麗になれるかも」と期待を抱き購入する方も一定数います。近年はインフルエンサーを起用してネット広告を出し、製品やサービスをより身近に感じてもらう宣伝方法も行われています。
ただし、あまり商品やサービスとかけ離れた人を起用すると、ポジティブな印象につながらない可能性があるので、人選は慎重に行いましょう。
マーケティングでハロー効果を利用する際の注意点
ハロー効果をマーケティングに利用すると高い効果が見込まれる一方で、注意点もあります。また、ハロー効果でもネガティブハロー効果が発揮されると逆効果です。ここではマーケティングでハロー効果を利用する際の注意点を3つ紹介します。
持続力がない
ハロー効果のデメリットとして、持続力がない点です。例えば、面接時に「この学生はすごい」と思って採用しても、実際の勤務状況が不真面目だとわかれば、最初に抱いたプラスの印象は消えてしまう可能性があります。
マーケティングでポジティブハロー効果を持続させるには、戦略が大切です。例えば、特定の商品で成功したブランドをベースに、ラインナップ全体や会社自体をブランド化します。すると、たとえ展開している特定の製品の印象がマイナスに傾いても、成功した商品がブランドイメージを牽引しマイナス面をカバーできる可能性もあります。
悪い影響が出る場合がある
商品やサービスに抱く印象は小さなきっかけで180℃変わる可能性もあります。例えば、CMや広告に起用した俳優やタレントが不祥事を起こせば、製品の印象まで悪くなる恐れがあります。
また、ポジティブな言葉でも、受け取る人によってはネガティブな意味に捉えてしまう場合があり、思わぬ一言で悪印象を与える恐れがある点もデメリットです。
ハロー効果をマーケティングに活用したい場合、SNSの運用からキャラクターの起用、性格付けなどを入念に行う必要があります。「このくらいなら」といった楽観的な憶測も控えましょう。
虚偽や誇張広告にならないように注意する
広告を掲載する際、虚偽や誇張広告にならないよう注意が必要です。例えば、化粧品や健康食品に「××の効果があります」「100%のご満足をいただきました」といった表現は控えてください。
商品のよいイメージを伝えようとするあまり誇張した表現を使うと、企業や商品の信頼感が失われます。一度信頼を失うと、回復するまでに長い時間が必要です。広告を打つ際は、表現方法にも十分注意して行いましょう。
なお、表記が誇張だと判断された場合、広告表示の停止など措置命令が行われる場合もあるので注意してください。
ハロー効果と共に利用したい心理学効果
最後に、ハロー効果と共に利用することで高い効果が期待できる心理学効果を2つ紹介します。より多くのマーケティングに活用できる心理効果を知りたい方も、参考にしてください。
心理学効果1:ウィンザー効果
ウィンザー効果とは、当事者が発信するより関係のない第三者が発信した情報の方が信憑性が高いように感じられる心理効果です。口コミやレビューなどが該当します。
例えば、ハロー効果で好印象を抱いた製品やサービスを詳しく調べた結果「使ってみてよかった」「効果抜群」といった口コミやレビューを見つけると、より購買意欲が増します。
CMや広告に実際の口コミを追加する、インターネットで商品を説明するページに口コミを書く欄を設ける等の工夫をすれば、自社の商品やサービスの売上にもつながるでしょう。

心理学効果2:アンカリング効果
アンカリング効果とは、最初に提示された印象的な情報が、その後の行動や判断などに影響を及ぼす心理的効果です。例えば「定価10万円です」と説明した後に「しかし、今だけ5万円」と説明すれば、聞いた人にお得感を与えられるでしょう。
また、「この化粧品を使えば美白効果が期待できる」と商品のメリットを説明した上で、「1日125円」と安価な情報を与えれば「効果が出た上にお得」と考えてくれる可能性があります。アンカリング効果は、通信販売のCMなどでよく利用されています。

まとめ
ハロー効果はマーケティングやビジネスなどで幅広く活用されている心理効果です。第一印象で好印象を抱かせ、それが続くように戦略を打てば商品やサービスの売上を大きく伸ばせるでしょう。ほかの心理学効果と合わせれば、さまざまな角度からプロモーションを打てます。
ただし、ネガティブハロー効果にならないように十分な注意が必要です。ハロー効果を利用する場合は、入念に計画を立てて行いましょう。必要ならば、専門家のサポートも視野に入れてください。
ウェビットでは主に中小企業がWebマーケティング、Web集客を行う上でのお悩みを解決するような情報を発信しております。気になられた方はぜひ、ほかの記事もご一読ください。