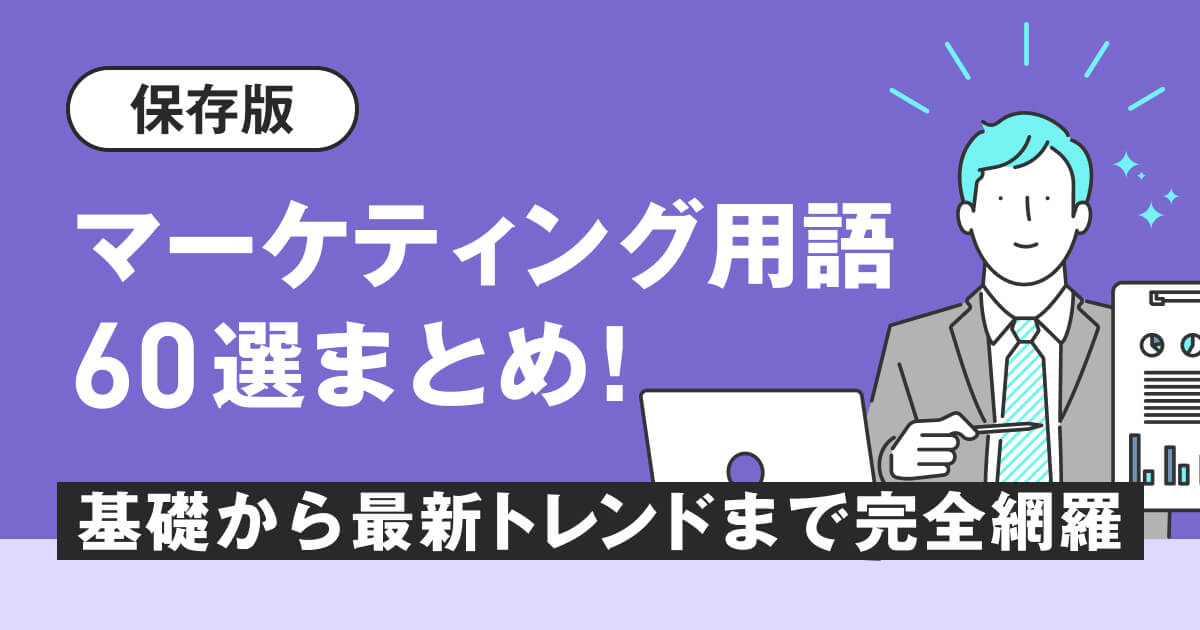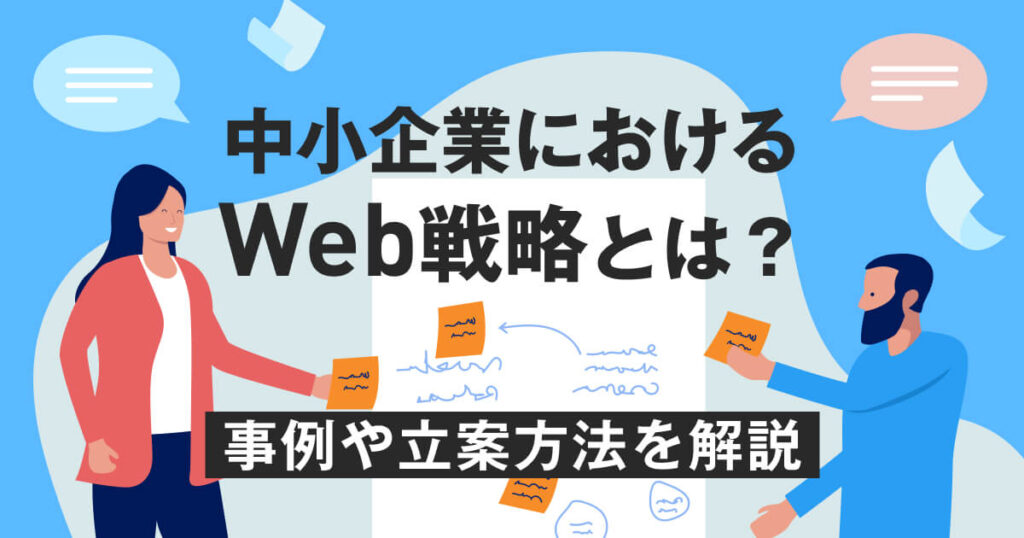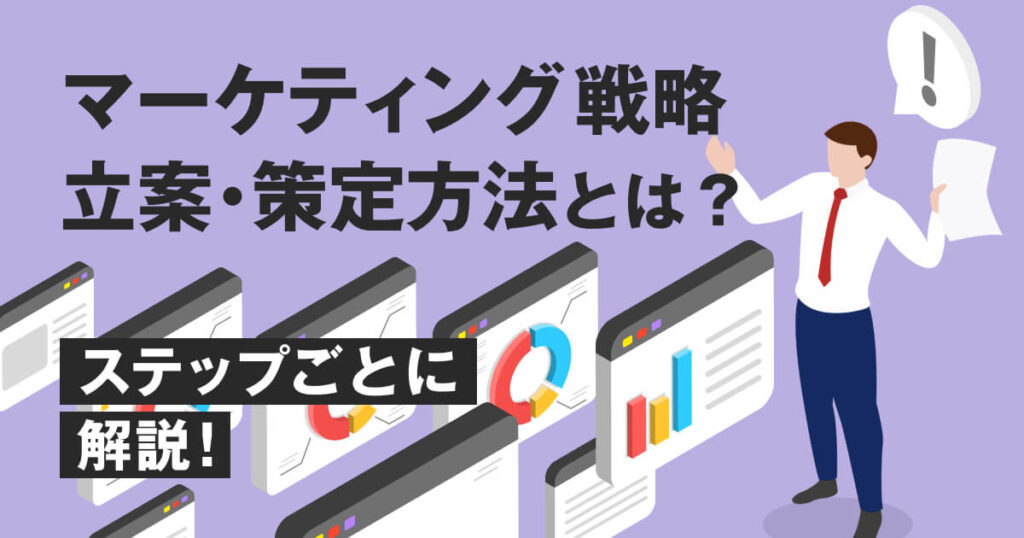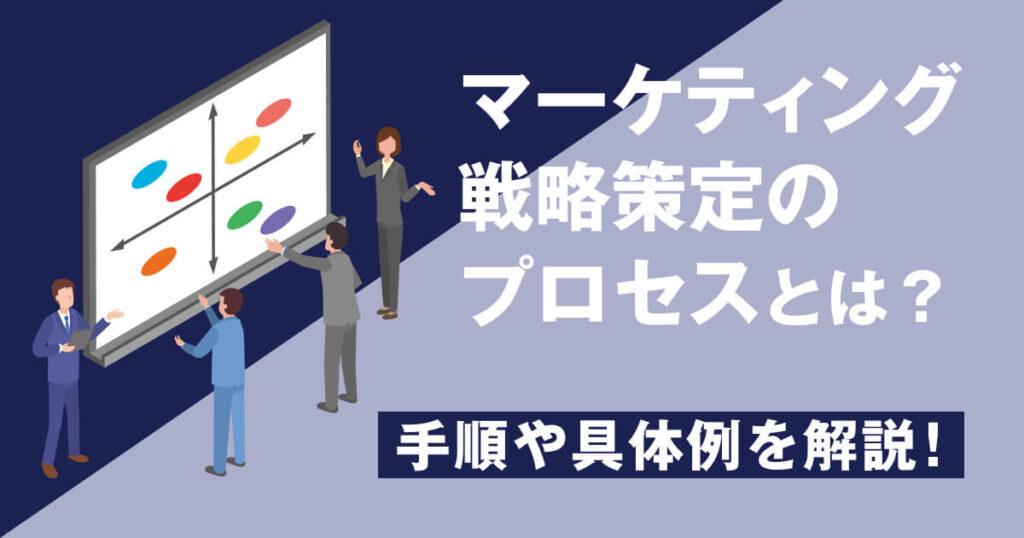マーケティングの世界には、専門用語がたくさんあります。会議や資料で知らない言葉が出てきて、戸惑った経験はありませんか。この記事では、マーケティングの基本から最新トレンドまで、重要な用語を網羅的にまとめました。
高校生や初心者の方でも理解しやすいように、一つひとつの言葉を丁寧に解説します。実務で成果を出すために必要な知識が身につく内容です。用語の意味を調べるだけでなく、効率的な覚え方や学習ツールも紹介します。
もし「マーケティングが難しくてうまくいかない」と悩んでいるなら株式会社FlyEdgeにご相談ください。3,000回以上のコンサルティングで構築した、中小企業の勝ちパターンを活用したい方はぜひお問い合わせください。
マーケティング用語 一覧【50音早見表&ダウンロード】
この記事で紹介するマーケティング用語を、目的の言葉をすぐに見つけられるように50音順の早見表としてまとめました。各用語に解説も記載していますので、辞書のようにご活用ください。
マーケティング用語 一覧【基礎編|高校生・初心者向け20語】
フレームワーク基礎
マーケティング活動の全体像を捉え、戦略を立てるための骨組みとなる考え方を紹介します。複雑な市場や顧客の状況を整理し、進むべき方向を見定めるのに役立ちます。これから解説する用語は、マーケティングの計画を立てる上で基本となるものです。
- 4P
- 3C
- SWOT
- STP
- PEST
- PLC
4P
4Pとは、マーケティング戦略を考える上で基本となる4つの要素の頭文字を取ったものです。具体的には
- 製品(Product)
- 価格(Price)
- 流通(Place)
- 販促(Promotion)
を指します。企業側の視点で、どのような製品を、いくらで、どこで、どうやって売るかを計画するための考え方です。新商品を開発したり、既存商品の販売戦略を見直したりする際に用いられます。この4つのバランスを考えることが重要です。
3C
3C分析は、自社の事業を取り巻く環境を理解するためのフレームワークです。
- 顧客(Customer)
- 競合(Competitor)
- 自社(Company)
の3つの要素を分析します。市場や顧客が何を求めているのか、競合他社はどのような動きをしているのか、そして自社の強みや弱みは何かを明らかにします。この分析によって、事業が成功する可能性のある領域を見つけ出すことが目的です。客観的な視点で各要素を調べることが求められます。
SWOT
SWOT分析は、企業の内部環境と外部環境を整理し、戦略立案に役立てる手法です。
- 強み(Strength)
- 弱み(Weakness)
- 機会(Opportunity)
- 脅威(Threat)
の4つの項目で分析を行います。自社の持つ長所や短所を把握し、市場にあるチャンスやリスクを明らかにします。これらの要素を掛け合わせることで、自社の強みを活かして機会を掴む戦略や、弱みを克服して脅威に備える戦略を具体的に検討できます。
STP
STP分析は、市場の中から自社が狙うべき顧客層を定め、製品の価値を明確に伝えるための手法です。
- 市場を細分化するセグメンテーション(Segmentation)
- 狙う市場を決めるターゲティング(Targeting)
- 市場における自社の立ち位置を明確にするポジショニング(Positioning)
の3段階で構成されます。誰に対して、どのような価値を提供するかをはっきりさせることで、効果的なマーケティング活動につなげることが可能です。
PEST
PEST分析は、企業を取り巻く外部環境の中でも、特に自社ではコントロールが難しい大きな要因を分析する手法です。
- 政治(Politics)
- 経済(Economy)
- 社会(Society)
- 技術(Technology)
の4つの側面から、世の中の動向を捉えます。法律の改正や景気の変動、流行の変化や新しい技術の登場などが、自社の事業にどのような影響を与えるかを予測することが目的です。長期的な視点で事業戦略を立てる際に役立ちます。
PLC
PLCは、製品ライフサイクルの略で、製品が市場に登場してから姿を消すまでの流れを示したモデルです。導入期、成長期、成熟期、衰退期の4つの段階に分かれます。それぞれの段階で売上や利益、競合の数が変化するため、時期に応じたマーケティング戦略を立てることが重要です。例えば、導入期は製品の認知度向上に努め、成熟期には他社製品との差別化を図るなど、適切な対応を考えるための指針となります。
顧客理解の基本
マーケティングの成功は、顧客をどれだけ深く理解できるかにかかっています。ここでは、顧客が誰で、何を考え、何を求めているのかを明らかにするための基本的な用語を解説します。顧客のニーズを正確に捉えることで、心に響く商品やサービスを提供できるようになります。
- ターゲティング
- セグメンテーション
- ペルソナ
- ポジショニング
- カスタマーインサイト
- ペインポイント
- バリュープロポジション
ターゲティング
ターゲティングとは、市場の中から自社が商品やサービスを提供する対象として、特定の顧客層に狙いを定めることです。すべての顧客を満足させるのは難しいため、自社の強みが最も活かせるグループを選びます。年齢や性別、興味関心などの基準で絞り込むのが一般的です。ターゲットを明確にすることで、広告やメッセージがより効果的に届き、限られた資源を集中して使うことができます。
セグメンテーション
セグメンテーションは、市場や顧客を同じような性質やニーズを持つ小さなグループに分けるプロセスを指します。市場細分化とも呼ばれます。地理的な条件、年齢や性別といった人口動態、価値観やライフスタイルなどで分類します。この作業によって、市場の全体像が理解しやすくなります。また、それぞれのグループの特徴を把握することで、どの顧客層を狙うべきかの判断材料になります。ターゲティングの前段階として行われる重要な作業です。
ペルソナ
ペルソナとは、商品やサービスの典型的な顧客像を、具体的な一人の人物のように詳細に設定したものです。年齢、職業、趣味、家族構成、価値観などを細かく描きます。架空の人物ですが、実在するかのように設定することで、関係者間で顧客のイメージを共有しやすくなります。この人物が「何を考え、どう行動するか」を基準に企画や開発を進めることで、顧客のニーズからずれない一貫した意思決定が可能になります。
ポジショニング
ポジショニングとは、ターゲットとする顧客の心の中で、競合製品と比べて自社製品をどのように位置づけるかを決める活動です。価格の安さ、品質の高さ、デザインの良さなど、独自の強みを明確にしてアピールします。顧客が商品を選ぶ際に「この製品は他とは違う」と認識してもらうことが目的です。市場における自社のユニークな立ち位置を築くことで、競争を有利に進めることができます。
カスタマーインサイト
カスタマーインサイトとは、顧客自身も気づいていないような、行動の裏にある本音や隠れた動機のことです。アンケートの回答や購入データといった表面的な情報だけでは分かりません。顧客の言動を深く観察し、「なぜそうするのか」を追求することで発見できます。この本音を突く商品やサービスを開発できれば、顧客の心を強く掴み、大ヒットにつながる可能性があります。
ペインポイント
ペインポイントとは、顧客が日常生活や業務の中で感じている悩み、不満、ストレスなどの「痛み」を指します。解決したいけれど、まだ満たされていない課題のことです。例えば、「手続きが面倒」「時間がかかる」「費用が高い」といったものが挙げられます。この「痛み」を解消する商品やサービスを提供することは、ビジネスの大きなチャンスです。顧客が何に困っているかを正確に把握することが、マーケティングの第一歩となります。
バリュープロポジション
バリュープロポジションとは、企業が顧客に提供する独自の価値のことです。競合他社には真似のできない、自社ならではの強みを指します。顧客が抱える課題を解決し、ニーズを満たすことができると約束するものです。「なぜ、あなたの商品を顧客は選ぶべきなのか」という問いに対する明確な答えとも言えます。この価値提案が魅力的であるほど、顧客から選ばれやすくなり、事業の成功につながります。
ブランド構築・CX基礎
顧客に自社の商品やサービスを選び続けてもらうためには、良い関係を築くことが不可欠です。ここでは、企業のファンを作り、顧客に最高の体験を提供するための用語を説明します。価格競争から抜け出し、長期的に愛される存在になるための考え方です。これから解説する用語は、顧客との絆を深めるマーケティング活動に役立ちます。
- ブランディング
- カスタマージャーニー
- エンゲージメント
- タッチポイント
- ブランドエクイティ
- NPS
- ファンマーケティング
ブランディング
ブランディングとは、顧客に対して、企業や商品に対する共通の「良いイメージ」を作り上げる活動全般を指します。ロゴのデザインや広告だけでなく、店舗での接客や商品の品質など、顧客とのあらゆる接点が関係します。「この会社なら安心できる」「この商品はおしゃれだ」といった特定のイメージを持ってもらうことが目的です。良いブランドイメージが定着すると、信頼性が高まり、価格が高くても選ばれやすくなります。
カスタマージャーニー
カスタマージャーニーとは、顧客が商品を認知してから購入し、その後のファンになるまでの一連の体験を「旅」に例えたものです。顧客がそれぞれの段階で何を考え、どう行動し、何を感じるかを時系列で可視化します。この旅の地図を作ることで、企業は顧客との接点ごとに、どのような情報やサービスを提供すれば満足度が高まるかを検討できます。一貫性のある顧客体験を提供するための重要な考え方です。
エンゲージメント
エンゲージメントとは、企業と顧客との間の「絆」や「愛着」の深さを示す言葉です。単に商品を購入するだけでなく、SNSで企業の投稿に「いいね」をしたり、レビューを投稿したりするような、顧客の積極的な関与を指します。この結びつきが強いほど、顧客は繰り返し商品を購入してくれます。また、知人におすすめしてくれる可能性も高まります。顧客との良好な関係性を測る指標として重要視されています。
タッチポイント
タッチポイントとは、顧客と企業やブランドとのあらゆる接点を指します。例えば、テレビCM、ウェブサイト、店舗、商品のパッケージ、コールセンターの対応など、顧客がブランドに触れるすべての機会が含まれます。顧客は、さまざまな接点での体験を通じてブランドのイメージを形成します。そのため、一つひとつのタッチポイントで質の高い体験を提供し、良い印象を与え続けることがブランド構築において重要です。
ブランドエクイティ
ブランドエクイティとは、ブランドが持つ資産価値のことです。ロゴや名称などが持つ無形の価値を指します。例えば、同じ品質のTシャツでも、有名なブランドのロゴが付いているだけで高く売れるのは、そのブランドに資産価値があるからです。高いブランドエクイティを持つ企業は、顧客からの信頼が厚く、価格競争に巻き込まれにくくなります。また、新しい商品を展開する際にも有利に働きます。
NPS
NPSは「ネット・プロモーター・スコア」の略で、顧客ロイヤルティ、つまり企業やブランドに対する愛着や信頼の度合いを測る指標です。「この商品を友人にどのくらいすすめたいですか」という質問への回答を0から10の11段階で評価してもらい、算出します。点数によって顧客を「推奨者」「中立者」「批判者」に分類し、推奨者の割合から批判者の割合を引いた数値がNPSです。顧客の満足度を客観的な数値で把握するために用いられます。
ファンマーケティング
ファンマーケティングとは、自社のブランドや商品を熱心に応援してくれる「ファン」を大切にし、ファンとの関係性を深めることを中心としたマーケティング手法です。ファンを特別な存在として扱い、限定イベントへの招待や意見交換の場を設けるなどの活動を行います。熱量の高いファンは、商品を繰り返し購入してくれるだけでなく、SNSなどを通じて自発的に商品の魅力を広めてくれます。新規顧客の獲得にもつながる効果的な手法です。
マーケティング用語 一覧【デジタルマーケティング最新トレンド15語】
検索・生成AI関連
インターネット上での情報発信が当たり前になった現代において、検索エンジンやAI技術の活用は欠かせません。ここでは、ウェブサイトへの集客や最新技術に対応するための重要な用語を解説します。これらの技術は日々進化しているため、基本的な考え方を理解しておくことが重要です。デジタル時代のマーケティングを勝ち抜くための知識を身につけましょう。
- SEO
- SEM
- SGE
- GA4
SEO
SEOは「検索エンジン最適化」を意味します。Googleなどの検索エンジンで、特定のキーワードが検索された際に、自社のウェブサイトが上位に表示されるように行うさまざまな施策のことです。サイトの構成を分かりやすくしたり、ユーザーの求める質の高い情報を提供したりすることが基本となります。広告費をかけずに、自社の商品やサービスに関心のある人をウェブサイトに集めることができるため、非常に重要な施策です。
SEM
SEMは「検索エンジンマーケティング」の略です。検索エンジンを活用して行われるマーケティング活動全体のことを指します。具体的には、お金を払って検索結果の上位に広告を表示させる「リスティング広告」と、前述の「SEO」の二つが主な手法です。SEOが中長期的な施策であるのに対し、リスティング広告は即効性が高いという特徴があります。目的に応じて、これらの手法を使い分けることが重要です。
SGE
SGEは「生成AIによる検索体験」を意味します。従来の検索結果に加えて、AIがユーザーの質問に対して要約した回答を自動で生成し、表示する新しい検索機能のことです。ユーザーは、複数のウェブサイトを訪問しなくても、検索結果画面だけで素早く答えを得られるようになります。この変化により、企業はこれまで以上に、質の高い独自の情報を発信することが求められるようになると考えられています。
GA4
GA4は「Google アナリティクス 4 プロパティ」の略で、Googleが提供するウェブサイトのアクセス解析ツールです。サイトを訪れた人が「どこから来たのか」「どのページをどれくらいの時間見たのか」などを詳しく分析できます。ウェブサイトだけでなく、スマートフォンのアプリをまたいだユーザーの行動も分析できる点が特徴です。データに基づいてサイトの改善点を見つけ出し、成果を高めるために不可欠なツールです。
コンテンツ&メディア
現代のマーケティングでは、企業が自ら有益な情報を発信し、顧客に見つけてもらうことが重要です。ここでは、情報発信の拠点となるメディアの考え方や、その中身となるコンテンツに関する用語を説明します。広告に頼るだけでなく、顧客との信頼関係を築きながら自社のファンを増やすための手法です。どのような形で情報を届けるかを考える上で役立ちます。
- コンテンツマーケ
- インバウンド
- トリプルメディア
コンテンツマーケ
コンテンツマーケティングとは、ブログ記事や動画、SNSの投稿といった、顧客にとって価値のある情報(コンテンツ)を発信し続けることで、見込み客を引きつけ、最終的にファンとして育成していく手法です。売り込みたいという気持ちを前面に出さず、まず顧客の悩みや課題を解決する情報を提供します。それにより信頼関係を築き、自社の商品やサービスに興味を持ってもらうことを目指す、中長期的な取り組みです。
インバウンド
インバウンドマーケティングは、顧客にとって有益な情報を発信することで、自社を見つけてもらい、顧客側から自発的にアプローチしてくるように促す手法です。前述のコンテンツマーケティングやSEOなどが代表的な例です。テレビCMや電話営業のように、企業側から積極的に働きかける「アウトバウンド」とは対照的な考え方です。顧客の興味に基づいて自然な形で関係を築くため、受け入れられやすいのが特徴です。
トリプルメディア
トリプルメディアとは、企業が利用するメディアを3種類に分類した考え方です。自社で運営するウェブサイトやブログなどの「オウンドメディア」、広告費を払って掲載する「ペイドメディア」、そしてSNSの口コミやニュース記事など第三者が発信する「アーンドメディア」を指します。それぞれのメディアの特性を理解し、これらを連携させて活用することで、マーケティング効果を最大化できると考えられています。
ツール・自動化
マーケティング活動は多岐にわたり、手作業だけでは限界があります。ここでは、煩雑な業務を効率化し、より高度な分析を可能にするためのツールに関する用語を解説します。これらのツールを導入することで、担当者はより創造的な仕事に時間を使えるようになります。データに基づいた的確な判断を下すためにも、ツールの役割を理解しておくことが大切です。
- MA
- SFA
- CRM
- CDP
MA
MAは「マーケティングオートメーション」の略です。見込み客の情報を一元管理し、メール配信やウェブサイト上でのアプローチといった、マーケティング活動の一部を自動化するツールのことです。例えば、資料をダウンロードした人に対して、自動で関連情報をメールで送る、といった設定ができます。これにより、個々の見込み客の興味関心に合わせた、きめ細やかな対応を効率的に行うことが可能になります。
SFA
SFAは「セールスフォースオートメーション」の略で、営業支援システムと訳されます。営業担当者の活動を効率化するためのツールです。顧客情報、商談の進捗状況、日々の営業報告などをデータとして管理します。これにより、営業チーム全体で情報を共有しやすくなり、担当者が変わってもスムーズな引き継ぎが可能です。また、蓄積されたデータを分析することで、成功しやすい営業パターンを見つけ出すことにも役立ちます。
CRM
CRMは「カスタマーリレーションシップマネジメント」の略で、顧客関係管理と訳されます。顧客の氏名や連絡先といった基本情報に加えて、購入履歴や問い合わせ内容などを一元管理し、顧客との良好な関係を築くためのツールや手法を指します。顧客一人ひとりの情報を詳細に把握することで、それぞれのニーズに合ったきめ細やかなサービスを提供できます。顧客満足度を高め、長期的なファンになってもらうことを目指します。
CDP
CDPは「カスタマーデータプラットフォーム」の略です。ウェブサイトの閲覧履歴、店舗での購入データ、問い合わせ内容など、社内外に散らばっている顧客に関するあらゆるデータを収集・統合するための基盤です。統合されたデータを分析することで、顧客一人ひとりをより深く理解し、MAやCRMといった他のツールと連携させて、最適なアプローチを行うことが可能になります。顧客データを活用する上での中心的な役割を担います。
広告運用・SNS
インターネット広告やSNSは、ターゲット顧客に直接アプローチできる強力な手段です。ここでは、デジタル広告の代表的な手法や、SNSを活用したマーケティングに関する用語を解説します。これらのプラットフォームは利用者が多く、効果測定がしやすいという利点があります。正しく理解して活用することで、商品やサービスの認知度を飛躍的に高めることが可能です。
- リターゲティング
- ウェビナー
- SNSマーケティング
- TikTok広告
リターゲティング
リターゲティングとは、一度自社のウェブサイトを訪れたことがある人に対して、別のサイトを見ているときに自社の広告を表示させる追跡型の広告手法です。自社の商品やサービスに既に関心を持っている人に再度アプローチするため、高い効果が期待できます。例えば、ショッピングサイトで商品をカートに入れたものの購入しなかった人に対し、その商品の広告を表示させるといった活用法があります。
ウェビナー
ウェビナーは、ウェブとセミナーを組み合わせた造語です。インターネットを通じてオンラインで行われるセミナーや講演会を指します。場所を選ばずにどこからでも参加できるため、多くの見込み客を集めやすいのが特徴です。商品やサービスの紹介だけでなく、参加者の役に立つ情報を提供することで、見込み客の育成や信頼関係の構築に役立ちます。参加者の質問にその場で答えることも可能です。
SNSマーケティング
SNSマーケティングとは、
- X
といったソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を活用して行うマーケティング活動のことです。企業の公式アカウントで情報を発信したり、SNS広告を配信したりします。また、利用者の口コミ(UGC)が生まれやすいのもSNSの特徴です。顧客と直接コミュニケーションを取ることで、ファンの育成やブランドイメージの向上につなげることができます。
TikTok広告
TikTok広告とは、短い動画が人気のプラットフォーム「TikTok」に出稿する広告のことです。若年層を中心に多くの利用者を抱えており、音楽やエフェクトを使ったクリエイティブな動画でアプローチできるのが特徴です。広告らしくない自然な形で商品やサービスをアピールすることができ、ユーザーによる拡散も期待できます。特に若い世代をターゲットとする場合に、非常に効果的な広告手法の一つです。
マーケティング用語 一覧【略語・フレームワーク解説10選】
数字×アルファベット系
マーケティングの世界では、特定の考え方や指標がアルファベットの略語で表現されることが頻繁にあります。特に、数字とアルファベットを組み合わせた用語は、戦略を立てたり効果を測定したりする上で重要な役割を果たします。ここでは、実務でよく使われる略語をいくつか取り上げて解説します。これらの意味を理解することで、より深い議論や分析が可能になるでしょう。
- CPR
- 4C
- 5A
- AARRR
CPR
CPRは「コスト・パー・レスポンス」の略で、日本語では「反響単価」と訳されます。広告やキャンペーンによって、1件の反響(レスポンス)を得るためにかかった費用のことです。ここでの反響とは、資料請求や問い合わせ、サンプル申し込みなどを指します。計算式は「かかった費用 ÷ 獲得した反響数」です。この数値が低いほど、効率よく反響を得られたことを示します。広告の効果を測る指標の一つとして用いられます。
4C
4Cは、顧客の視点からマーケティング戦略を考えるためのフレームワークです。
- 顧客にとっての価値(Customer Value)
- 顧客が負担するコスト(Cost)
- 入手の容易性(Convenience)
- 顧客との対話(Communication)
の4つの要素から成ります。企業視点の「4P」と対比して使われることが多いです。顧客が何を感じ、何を求めているかを考えることで、より顧客に寄り添った商品やサービスを提供できるようになります。
5A
5Aは、現代の顧客が商品やサービスを認知してから、最終的に他者へ推奨するまでのプロセスを示したモデルです。
- 認知(Aware)
- 訴求(Appeal)
- 調査(Ask)
- 行動(Act)
- 推奨(Advocate)
の5つの段階で構成されます。特徴的なのは、顧客が他者の意見を調べたり(調査)、購入後にSNSなどで推奨したり(推奨)する、インターネット時代ならではの行動が含まれている点です。顧客との長期的な関係性を重視する考え方です。
AARRR
AARRR(アー)は、特にウェブサービスやアプリの成長段階を測るためのフレームワークです。
- 顧客獲得(Acquisition)
- 利用活性化(Activation)
- 継続(Retention)
- 紹介(Referral)
- 収益化(Revenue)
という5つの指標の頭文字を取ったものです。サービスがどの段階に課題を抱えているのかを明確にし、改善策を立てるのに役立ちます。データに基づいたサービス改善を行う上で非常に重要な考え方です。
購買行動モデル
顧客が商品を知ってから購入に至るまでには、特定の心理的なプロセスがあります。ここでは、そのプロセスをモデル化した「購買行動モデル」と呼ばれる考え方を解説します。これらのモデルを理解することで、顧客がどの段階にいるのかを把握し、それぞれの段階に合わせた適切なアプローチが可能になります。時代とともにモデルは変化しており、その変遷を知ることも重要です。
- AIDMA
- AISAS
- カスタマーファネル
AIDMA
AIDMA(アイドマ)は、伝統的な購買行動モデルの一つです。顧客が商品を認知してから購入に至るまでの心理的なプロセスを
- 注意(Attention)
- 興味(Interest)
- 欲求(Desire)
- 記憶(Memory)
- 行動(Action)
の5段階で示します。テレビCMや雑誌広告が主流だった時代の、比較的ゆっくりとした購買決定プロセスを表しています。マーケティングの古典的な考え方として、今でも基本とされています。
AISAS
AISAS(アイサス)は、インターネットが普及した現代の購買行動モデルです。
- 注意(Attention)
- 興味(Interest)
- 検索(Search)
- 行動(Action)
- 共有(Share)
商品に興味を持った顧客は、まずインターネットで情報を調べ、購入後にはSNSなどで感想を共有します。このモデルは、現代のマーケティングにおいて、ウェブ検索や口コミの重要性を示しています。
カスタマーファネル
カスタマーファネルは、顧客が商品を認知してから購入に至るまでの人数が、段階を追うごとに減っていく様子を「漏斗(ファネル)」の形で表したものです。例えば、1000人が広告を見ても、興味を持つのは100人、実際に購入するのは10人というように、数が絞られていくイメージです。各段階でどれくらいの人が離脱しているのかを可視化することで、マーケティング活動のどこに課題があるのかを発見しやすくなります。
戦略系キーワード
市場で競争に勝ち抜くためには、他社とは違う独自の戦略が必要です。ここでは、自社の強みを明確にし、競合との差別化を図るための戦略的な考え方に関するキーワードを解説します。これらの概念を理解し活用することで、価格競争に陥ることなく、自社が輝ける市場を見つけ出すヒントが得られます。事業の方向性を決定する上で重要な視点です。
- USP
- ブルーオーシャン
- キャズム理論
USP
USPは「ユニーク・セリング・プロポジション」の略で、自社の商品やサービスが持つ「独自の強み」を意味します。競合他社にはない、顧客にとって魅力的な提案のことです。「この商品でなければならない理由」を明確に打ち出すことで、顧客に選ばれる存在になることを目指します。例えば、「30分以内にお届けするピザ」というような、具体的で分かりやすい約束がUSPにあたります。
ブルーオーシャン
ブルーオーシャンとは、競争相手のいない、未開拓の市場領域のことです。多くの企業がひしめき合い、血みどろの価格競争が繰り広げられる既存市場(レッドオーシャン)とは対照的な概念です。新しい価値を創造することで、競争のない穏やかな市場(ブルーオーシャン)を自ら作り出すという戦略です。他社と同じ土俵で戦うのではなく、新しい市場を発見し、先行者としての利益を狙います。
キャズム理論
キャズム理論は、新しい技術や商品が市場に普及していく過程で、初期の熱心な顧客層と、その後の一般的な顧客層との間に「深い溝(キャズム)」が存在するという考え方です。革新的な製品でも、この溝を越えられないと、一部のマニアに受け入れられるだけで普及せずに終わってしまいます。この溝を越えるためには、初期の顧客とは異なる、実用性や安心感を重視する一般層に向けたマーケティング戦略が必要になります。
マーケティング用語 一覧【主要指標・KPI15語】
コンバージョン系指標
ウェブサイトや広告の効果を具体的に測定するためには、数値的な指標が欠かせません。ここでは、マーケティング活動の最終的な成果である「コンバージョン」に関連する主要な指標を解説します。これらの指標を正しく理解し、分析することで、施策がうまくいっているのか、どこを改善すべきなのかを客観的に判断できるようになります。データに基づいた意思決定の基本となる用語です。
- CV
- CVR
- CPA
- CPC
- CPM
- CTR
CV
CVは「コンバージョン」の略で、ウェブサイト上で獲得できる最終的な成果を指します。具体的に何を成果とするかは目的によって異なりますが、ECサイトであれば「商品購入」、情報サイトであれば「会員登録」や「資料請求」などが一般的です。マーケティング活動の目標そのものであり、このCVの数を最大化することが多くの施策の目的となります。ウェブサイトの成果を測る上で最も重要な用語の一つです。
CVR
CVRは「コンバージョンレート」の略で、日本語では「成約率」などと訳されます。ウェブサイトへのアクセス数のうち、どれくらいの割合がコンバージョンに至ったかを示す指標です。計算式は「コンバージョン数 ÷ サイトの訪問者数 × 100」となります。この数値が高いほど、効率よく成果を生み出しているサイトと言えます。サイトのデザインや情報の内容を改善することで、CVRを高めることができます。
CPA
CPAは「コスト・パー・アクイジション」または「コスト・パー・アクション」の略で、1件のコンバージョンを獲得するためにかかった広告費用のことです。「顧客獲得単価」とも呼ばれます。計算式は「かかった広告費用 ÷ コンバージョン数」です。この数値が低いほど、費用対効果の高い広告運用ができていることを示します。広告の成果を測る上で非常に重要な指標であり、事業の採算性を判断する基準にもなります。
CPC
CPCは「コスト・パー・クリック」の略で、「クリック単価」を意味します。インターネット広告が1回クリックされるたびにかかる費用のことです。主に、リスティング広告やSNS広告など、クリック課金型の広告で用いられる指標です。広告の出稿単価を評価する際に使われ、このCPCが低いほど、効率的にウェブサイトへユーザーを誘導できていると判断できます。業界やキーワードによって単価は大きく変動します。
CPM
CPMは「コスト・パー・ミル」の略で、広告が1,000回表示されるごとにかかる費用を指します。「インプレッション単価」とも呼ばれます。Milleはラテン語で1,000を意味します。広告のクリック数ではなく、表示回数に基づいて費用が決まる課金方式で用いられる指標です。商品の認知度を高めたい場合など、とにかく多くの人の目に触れさせたい場合に有効な広告手法の成果を測るために使われます。
CTR
CTRは「クリック・スルー・レート」の略で、「クリック率」を意味します。広告が表示された回数のうち、実際にクリックされた回数の割合を示す指標です。計算式は「クリック数 ÷ 広告の表示回数 × 100」となります。この数値が高いほど、ユーザーの興味を引く魅力的な広告であると判断できます。広告のタイトルや画像、説明文などを改善することで、CTRを高めることが可能です。
ビジネス成果指標
マーケティング活動は、最終的に事業全体の成長に貢献しなければなりません。ここでは、個別の施策の効果だけでなく、より大きな視点でビジネスの成功度合いを測るための指標を解説します。これらの指標は、経営層への報告や、事業全体の目標設定において重要な役割を果たします。マーケティングがどれだけ売上や利益に貢献しているかを示すための言葉です。
- KPI
- KGI
- ROI
- ROAS
- LTV
KPI
KPIは「重要業績評価指標」と訳されます。最終的な目標(KGI)を達成するための中間的な目標を、具体的な数値で示したものです。例えば、最終目標が「売上1,000万円」であれば、そのためのKPIとして「ウェブサイトの訪問者数5万人」や「問い合わせ件数100件」などを設定します。日々の活動が順調に進んでいるかを判断するための道しるべとなり、チームの進捗管理に役立ちます。
KGI
KGIは「重要目標達成指標」と訳されます。事業やプロジェクトにおける、最終的に達成すべき目標を数値で示したものです。例えば、「年度末までに売上高を20%向上させる」といった、具体的で計測可能な目標が設定されます。このKGIを達成するために、より具体的な行動指標であるKPIが設定されます。組織全体の向かうべきゴールを明確にし、関係者全員の目線を合わせる役割を果たします。
ROI
ROIは「投下資本利益率」または「投資対効果」と訳されます。投資した費用に対して、どれだけの利益を生み出せたかを示す指標です。計算式は「(利益額 – 投資額) ÷ 投資額 × 100」です。この数値が高いほど、効率の良い投資であったことを示します。マーケティング施策だけでなく、設備投資など、あらゆるビジネス活動の採算性を評価するために用いられる、非常に重要な経営指標の一つです。
ROAS
ROASは「広告費用対効果」と訳されます。広告にかけた費用に対して、どれだけの売上が得られたかを示す指標です。計算式は「広告による売上 ÷ 広告費 × 100」です。例えば、10万円の広告費で50万円の売上があれば、ROASは500%となります。この数値が高いほど、広告の費用対効果が高いことを意味します。広告キャンペーンが売上にどれだけ貢献したかを測るために使われます。
LTV
LTVは「ライフタイムバリュー」の略で、「顧客生涯価値」と訳されます。一人の顧客が、取引を開始してから終了するまでの間に、自社にもたらしてくれる利益の総額を指します。新規顧客を獲得するコストよりも、既存顧客との関係を維持するコストの方が低いことが多いため、LTVを高めることが安定した事業運営につながります。顧客に満足してもらい、長く付き合い続けることの重要性を示す指標です。
運用・エンゲージメント系
マーケティング施策は、一度実施して終わりではありません。顧客の反応を見ながら、継続的に改善していくことが重要です。ここでは、ウェブサイトやメールマガジンなどの運用状況や、顧客との関係性の深さを測るための指標を解説します。これらの数値を確認することで、顧客がコンテンツに満足しているか、どこに問題があるのかを把握する手がかりが得られます。
- エンゲージメント率
- 開封率
- 離脱率
- NPS
エンゲージメント率
エンゲージメント率とは、SNSの投稿などが、それを見た人からどれくらい反応を得られたかを示す割合です。投稿の表示回数に対して、「いいね」やコメント、シェアなどのアクションがどれくらい行われたかを計算します。この率が高いほど、ユーザーの関心を強く引きつけ、心に響くコンテンツであったと判断できます。コンテンツの質を評価したり、ファンの熱量を測ったりするための重要な指標です。
開封率
開封率とは、配信したメールマガジンが、受信者にどれくらいの割合で開封されたかを示す指標です。計算式は「開封されたメール数 ÷ 配信成功数 × 100」です。この数値は、メールの件名が魅力的であったか、また配信するタイミングが適切であったかを判断する材料になります。開封率が低い場合は、件名を改善するなどの対策が必要です。メールマーケティングの効果を測る基本的な指標の一つです。
離脱率
離脱率とは、ウェブサイトの特定のページを最後に閲覧し、サイトを離れてしまったセッション(訪問)の割合を示す指標です。例えば、あるページの離脱率が80%であれば、そのページを見た訪問のうち8割が、他のページに移動することなくサイトを去ったことを意味します。この率が特に高いページは、ユーザーの期待に応えられていない、あるいは次の行動を促す案内が不十分であるなど、何らかの問題を抱えている可能性があります。
NPS
NPSは「ネット・プロモーター・スコア」の略で、顧客が企業やブランドに対してどれくらいの愛着や信頼を持っているかを示す指標です。「この商品を友人にすすめたいか」という質問を通じて、顧客の推奨度を数値化します。このスコアは、顧客満足度だけでなく、将来的な収益性とも関連が深いとされています。定期的に測定することで、自社の取り組みが顧客ロイヤルティの向上につながっているかを確認できます。
マーケティング用語 一覧の効率的な覚え方・学習ツール
PDF・Excelでの反復学習法
用語を効率的に覚えるには、自分だけの一覧表を作ることが有効です。PDFやExcelを使って、オリジナルの単語帳を作成する方法は、多くの人にとって馴染みやすく、効果的です。特に、繰り返し見返すことで記憶を定着させる反復学習に適しています。自分の理解度に合わせて情報を追加したり、色分けしたりできる点も魅力です。
- 用語、意味、使用例の3列で表を作成する
- 理解度に応じてセルを色分けする(例:未学習は赤、学習中は黄、習得済みは緑)
- 印刷して持ち歩き、すきま時間に確認する
- PDF化してスマートフォンに入れ、いつでも見られるようにする
無料アプリ3選と使い方
スマートフォンアプリを使えば、移動中などのすきま時間で効率的に学習を進められます。自分だけの単語帳を作れる無料アプリが多くありますので、活用するのがおすすめです。ここでは、マーケティング用語の暗記に役立つ代表的なアプリを3つ紹介します。
- Quizlet(クイズレット) 自分で作成した単語カードで学べるだけでなく、テスト形式やゲーム感覚で知識を確認できる多機能なアプリです。学習が楽しくなる工夫がされています。
App Store(iOS)でダウンロード
Google Play(Android)でダウンロード
- Anki(アンキ) 忘れるタイミングで問題を出してくれる「間隔反復」という仕組みが特徴です。効率良く記憶を定着させたい場合に非常に有効なアプリとして知られています。
App Store(iOS)でダウンロード
Google Play(Android)でダウンロード
- WordHolic(ワードホリック) シンプルで直感的に使える単語帳アプリです。手軽に自分だけの用語集を作成でき、カードをめくる動作でサクサク学習を進められます。
App Store(iOS)でダウンロード
Google Play(Android)でダウンロード
フラッシュカード/マインドマップ活用術
デジタルのツールだけでなく、手を使って書くことも記憶を助ける良い方法です。市販の単語カードを使ったフラッシュカードは、古典的ですが非常に有効な学習法です。カードの表に用語、裏に意味や簡単な使用例を書いて、繰り返し確認してみましょう。
また、マインドマップもおすすめです。中心に「フレームワーク」などのテーマを書き、関連する用語を線でつなげていくと、言葉同士の関係性が一目で分かります。知識を体系的に整理できます。
マーケティング用語 一覧【FAQ】──よくある質問と回答
4Pと4Cの違いは?
4Pと4Cの最も大きな違いは、誰の視点に立っているかという点です。4Pは企業側の視点、4Cは顧客側の視点に基づいています。両方の視点から考えることで、より顧客に受け入れられやすいマーケティング戦略を立てることができます。
| 視点 | 項目(4P:企業視点) | 項目(4C:顧客視点) |
|---|---|---|
| 製品・価値 | Product(製品) | Customer Value(顧客価値) |
| 価格・経費 | Price(価格) | Cost(顧客の経費) |
| 流通・利便性 | Place(流通) | Convenience(利便性) |
| 販促・対話 | Promotion(販促) | Communication(対話) |
CPAの平均的な目安は?
CPAの平均的な目安は、業界や取り扱う商材、広告の手法によって大きく異なります。そのため、「平均はいくら」と一概に言うことは非常に困難です。例えば、数百円で購入できる化粧品のサンプルと、数百万円する自動車では、1件の成約にかけられる費用が全く違います。大切なのは、自社の事業が利益を出せる範囲でCPAの目標値を設定することです。
- 目標CPAの考え方: 1件の成約から得られる利益(限界利益)を超えない範囲で設定するのが基本です。
- 情報収集: 類似の商材を扱う企業の事例や、広告代理店が公表しているデータを参考にすることが有効です。
- 継続的な改善: まずは少額の広告費で試してみて、実際のCPAを計測しながら目標値を調整していくことが求められます。
SGEとは何の略?
SGEは「Search Generative Experience」の略称です。日本語に訳すと「検索生成体験」となります。これは、Googleなどの検索エンジンに搭載された、新しい機能のことを指します。ユーザーが何かを検索したときに、AIがその質問に対する答えを文章で自動的に生成し、検索結果の上部に表示する仕組みです。この機能によって、ユーザーは複数のウェブサイトを回らなくても、すぐに要約された情報を得られます。
- S: Search(検索)
- G: Generative(生成する)
- E: Experience(体験)
まとめ──マーケティング用語一覧をアップデートし続けるために
この記事では、マーケティングの基本的な用語から最新のトレンドまで、幅広く解説しました。紹介した用語は、マーケティング活動を進める上での共通言語となります。意味を理解するだけでなく、実際のビジネスシーンでどのように使われるかをイメージすることが重要です。
しかし、マーケティングの世界は常に変化しています。新しいツールや考え方が次々と登場するため、一度覚えただけで満足せず、継続的に学び続ける姿勢が不可欠です。今日得た知識を土台として、これからも情報をアップデートし、実践で活かしていきましょう。
もしマーケティングに関して悩んでいるなら株式会社FlyEdgeにご相談ください。3,000回以上のコンサルティングで構築した、中小企業の勝ちパターンを活用したい方はぜひお問い合わせください。