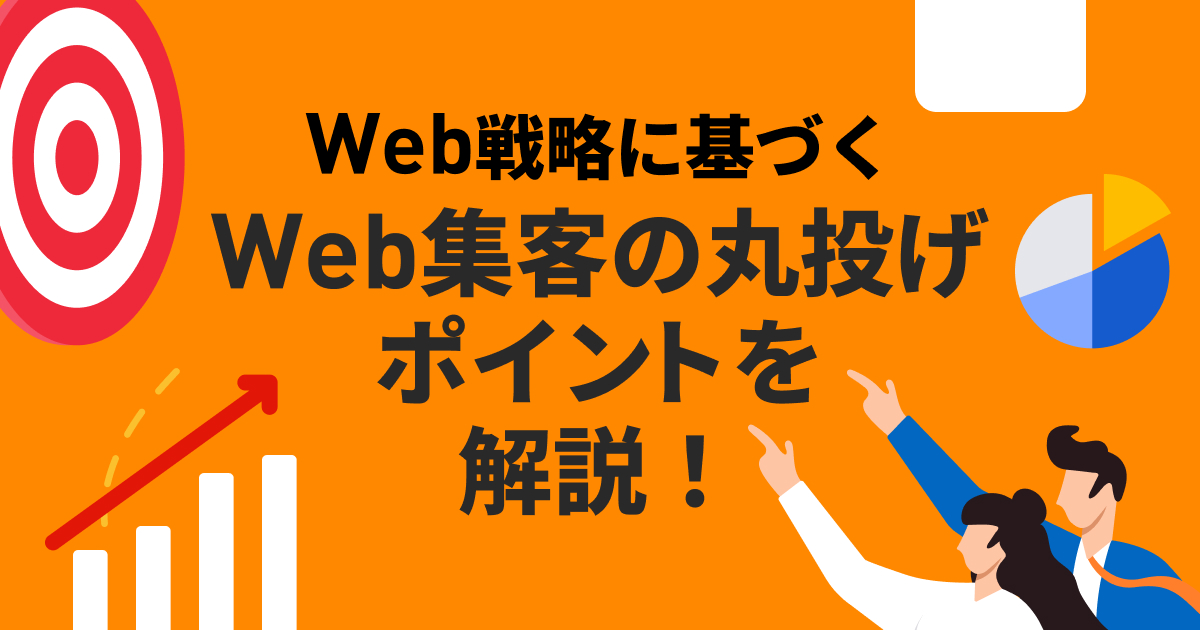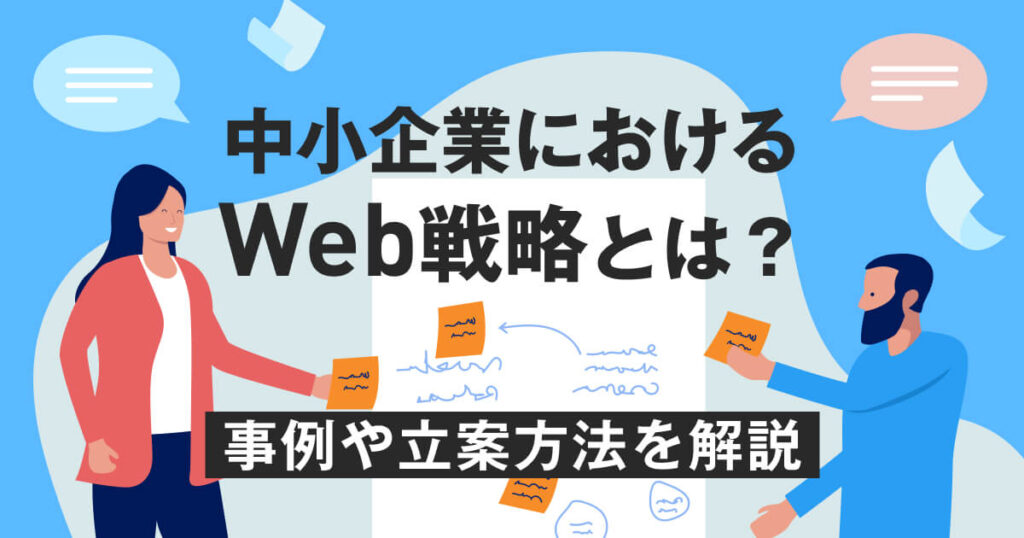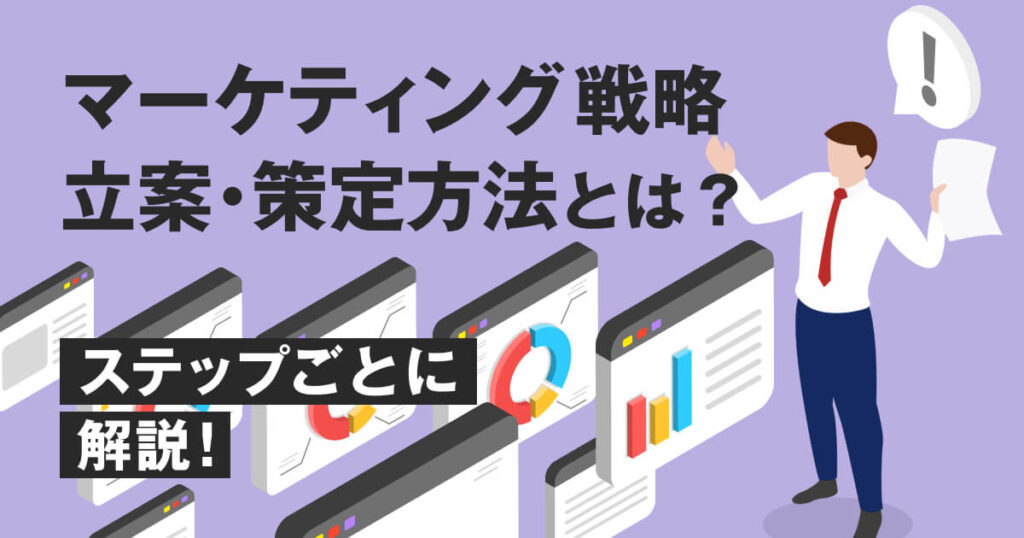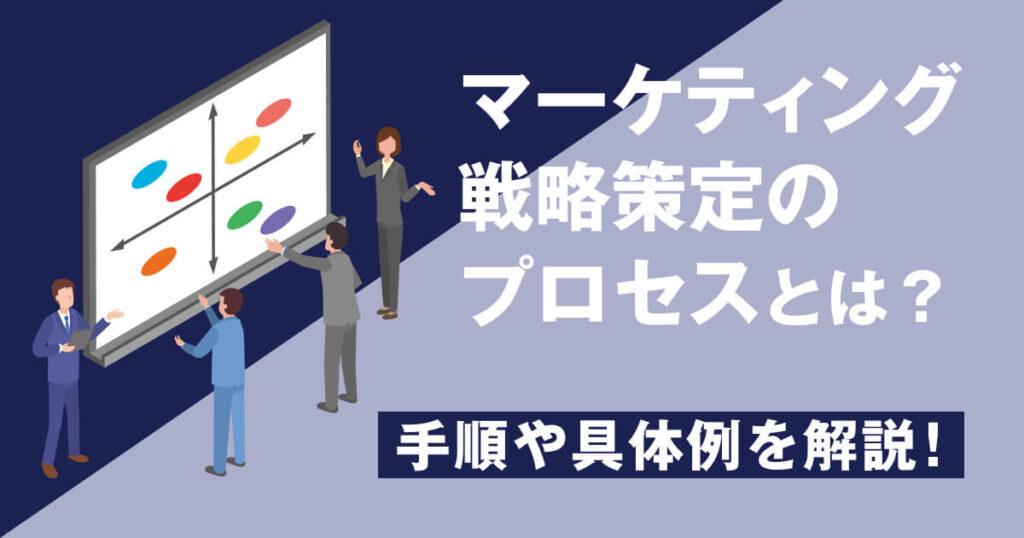Web集客の丸投げを成功させるには、しっかりとしたWeb戦略が欠かせません。戦略がないまま外部に依頼すると、期待する成果が出ないばかりか、時間や費用を無駄にしてしまう恐れがあります。
この記事では、Web集客を丸投げする前に知っておきたい基礎知識から、信頼できる業者の選び方まで、分かりやすく解説します。この記事を読めば、Web集客の丸投げを成功に導くための具体的な手順が分かり、事業成長への大きな一歩を踏み出せるでしょう。
もしWeb戦略についてお悩みなら、株式会社FlyEdgeにご相談ください。3,000回以上のコンサルティングで構築した、中小企業の勝ちパターンを活用したい方はぜひお問い合せください。
Web集客を丸投げする前に押さえるべき基礎知識
Web集客とは何か
Web集客とは、インターネットを使って自社の商品やサービスに関心を持つ可能性のある人々を集める活動全般を指します。
- 重要性:多くの人がインターネットで情報を探す現代では、Web集客は事業の成長に欠かせない活動です。
- 目的:自社の存在や魅力を広く知ってもらい、一人でも多くの人を自社サイトなどに集めることです。
- 具体例:SEO対策、SNSでの情報発信、Webサイト作成、インターネット広告など、多くの方法を用います。
- 位置づけ:Web集客は、人を集めるための具体的な「手段」の一つです。
インターネットで情報を探す人々の行動を活用したWeb上での集客活動は、事業を成長させるための生命線といえるでしょう。
Web戦略とは何か
Web戦略とは、Web集客で成果を上げるための事業全体の計画や設計図のことです。数多くあるWeb集客の手法の中から、どの方法を、どのような順番で、どれくらいの予算をかけて実行するかを定めます。
- 前提:「誰に」「何を」「どう伝えるか」といった、Web集客の大きな方針を明確にします。
- 具体例①:半年で売上を20%伸ばす
- 具体例②:新規顧客獲得を目的としたブランド認知度を30%アップさせる
Web戦略は、市場や競合、自社の強みや弱みを分析し「何を行うか」「何を行わないか」を明確に決定します 。方針を明確にすることでWeb集客という個々の施策に一貫性が生まれ、より効果的な結果へとつながります。
Web戦略の役割は、数ある集客手法の中から最適なものを選ぶことです。
Web集客とWeb戦略の関係性
Web集客とWeb戦略の関係は、家づくりにおける「建築作業」と「設計図」に例えるとしっくりきます。両者は事業を成功させるために、どちらも欠かすことができません。
Web戦略という設計図があって初めて、Web集客という具体的な建築作業が効果を発揮します。
以下に、具体例を挙げます。
| Web戦略(設計図) | Web集客(具体的な作業) | |
|---|---|---|
| 具体例1 | キャンプが趣味の20代男性に新商品のテントを売る | ・キャンプ系動画サイトでの商品を紹介する ・アウトドア専門のメディアへの広告を掲載する |
| 具体例2 | 20~30代の女性に、オーガニック野菜を使った健康的なランチメニューを売る | ・Instagramで料理の写真を投稿する ・グルメブログに広告を掲載する |
| 具体例3 | 中学受験を目指す小学生を持つ保護者に、個別指導の強みを生かした学習サービスを売る | ・中学受験対策の資料をウェブサイトからダウンロードできるようにする ・保護者向けのオンライン説明会をYouTubeで配信する |
Web戦略で全体の方向性を固め、その計画に沿ってWeb集客を実行することが、目標達成への近道です。
Web戦略を立てる6つのステップ
目標を設定する
最初に、Web戦略で最終的に何を達成したいのか、具体的な目標を数字で明確にします。目標があいまいな状態では、どのような施策を打つべきか、またその効果はどうだったのかを正しく判断できません。
Web集客を丸投げする場合、この目標を業者と共有することが成功するために重要です。
以下に、目標設定のポイントを整理しながら具体例を挙げます。
(具体例1)
| 誰が | 営業部が |
|---|---|
| いつまでに | 1年後までに |
| 何を | オンライン上での売上を |
| 達成する | 1.5倍にする |
(具体例2)
| 誰が | マーケティング部が |
|---|---|
| いつまでに | 半年で |
| 何を | 新規の問い合わせ件数を |
| 達成する | 毎月50件増やす |
誰が、いつまでに、何を達成するのかをはっきりさせましょう。明確な目標があることで、社内の関係者や依頼先の業者など、関わる人全員が同じ方向を向いて進めます。
目標設定は、Web戦略全体の土台です。Web集客を外部に依頼する際にも、目標を業者と共有することが成功へと導きます。
ターゲットを選定する
次に、誰に商品やサービスを届けたいのか、ターゲットとなる顧客像を深く考えましょう。ターゲットが曖昧なメッセージは、誰の心にも響かず集客効果が薄れます。
年齢や性別といった基本的な情報だけでなく、どんな悩みや願いを持ち、普段はどんなWebサイトやSNSを見ているか、具体的にイメージできるまで一人の人を描き出すことが重要です。
またターゲットが明確だと、業者に丸投げする際にも要望を伝えやすくなります。
以下に、ターゲットを深掘りするための要素例を挙げます。
| カテゴリー | 項目 | 要素の例 |
|---|---|---|
| 基本的な情報 | 年齢 | 年齢層、年代 |
| 性別 | 男性、女性、その他 | |
| 職業 | 会社員、学生、主婦、自営業など | |
| ライフスタイルと価値観 | 趣味 | スポーツ、読書、旅行、映画鑑賞など |
| 休日の過ごし方 | 自宅で過ごす、外出する、アクティブに活動するなど | |
| 興味・関心 | 美容、健康、教育、テクノロジー、ファッションなど | |
| 消費行動と情報収集 | よく利用するSNS | nstagram、X(Twitter)、Facebook、TikTokなど |
| 情報収集源 | ウェブサイト、YouTube、雑誌、テレビ、友人からの口コミなど | |
| 利用するデバイス | スマートフォン、パソコン、タブレットなど | |
| 悩みと課題 | 仕事上の悩み | キャリアアップ、スキル不足、人間関係、労働時間など |
| プライベートの悩み | 健康、美容、子育て、金銭面、人間関係など | |
| 潜在的なニーズ | 本人がまだ気づいていない、隠れた欲求 |
具体的なターゲット像(ペルソナ)を設定することで、その人の心に突き刺さるメッセージは何か、どんなデザインが好まれるか、どの時間帯に情報発信すれば見てもらいやすいかなど、最適なアプローチ方法を見出せます。
自社の現状を把握する
目標とターゲットが決まったら、次に自社の現在の立ち位置を客観的に把握します。自分たちの強みや弱み、そして競合相手の動きを理解しなければ、勝てる戦い方はできません。
現状を正しく知ることは、業者に丸投げする際に的確な指示を出せます。
以下に、自社の現在地を知るための質問をします。
- Webサイトには毎月何人くらい訪れていますか。
- SNSのフォロワーは現在何人ですか。
- 自社の商品やサービスの強みは何だと思いますか。
- 逆に足りない部分はどこだと思いますか。
- ライバル企業が力を入れているところはどこですか。
- ライバル企業の上手いと思う戦略はなんでしょうか。
自社だけでなく、市場全体を客観的な視点で分析してください。自社の強みを生かし、弱みを補い、競合との違いを打ち出すためのヒントが見つかります。
マーケティングの施策を決める
ここまでの情報をもとに、設定した目標を達成するための具体的な行動、つまりマーケティング施策を決めます。この段階で、どの方法を業者に丸投げするかを具体的に考え始めましょう。
以下に、年齢ごとのマーケティング施策例を挙げます。
| 年齢層 | 特性と情報収集の傾向 | 効果的なマーケティング施策 |
|---|---|---|
| 10代 | ・TikTokやInstagramなどのSNSが情報収集の中心になっている ・視覚的で簡潔なコンテンツを好む ・「映え」よりも「共感」や「リアル」を重視する傾向がある | ・TikTokやInstagramでの短尺動画コンテンツ(リール) ・ユーザーが自由に意見交換できるコミュニティ作り |
| 20代 | ・SNS検索がGoogleなどの検索エンジンを上回ることもある ・YouTubeでのレビュー動画や解説動画をよく見る ・ECサイトでの購買が日常化している | ・SNS広告(特にInstagram、X、YouTube) ・YouTubeでの商品レビューやハウツー動画の作成 ・ソーシャルコマース(SNS上での購買)の強化 |
| 30代 | ・スマートフォンでの情報収集が主流になっている ・効率を重視し、複数のキーワードを組み合わせて検索する傾向が強い ・子育てやキャリアに関する悩みが情報収集の動機になることもある | ・SEOを意識した、具体的なキーワードを盛り込んだブログ記事 ・ターゲットの悩みに寄り添うようなコンテンツマーケティング ・メールマガジンやLINEでの継続的な情報提供 |
| 40代 | ・WebサイトやSNSに加え、テレビや新聞などの従来メディアも利用している ・家族やライフスタイルに合わせた商品やサービスに関心が高い ・健康や老後の生活、資産形成など、将来に向けた情報収集も活発になってくる | ・FacebookやLINEを活用した広告配信 ・テレビCMや新聞広告と連動したキャンペーン ・健康や趣味など、特定のテーマに特化したWebメディアへの広告掲載 |
目標達成のために、SEO対策、SNS運用、広告運用、ブログ記事の作成など、自社の目標とターゲットに合った最適な組み合わせを選びましょう。一つの方法に絞るのではなく、複数の施策を組み合わせることで、より大きな効果が期待できます。
施策の優先度を決める
考えられるマーケティング施策をリストアップしたら、次に実行する施策の優先順位を決めましょう。多くの場合、時間や予算は限られています。全ての施策を同時に始めるのではなく、より効果の高いものから始めるのが賢明です。
以下に「効果の大きさ」と「実行のしやすさ(手間や費用)」を2軸にした施策の例を挙げます。
| 具体的な施策 | 施策の理由 | |
|---|---|---|
| 効果が大きい施策 | テレビCMを打つ | 全国規模で一気に多くの人に見てもらえるため、ブランドの知名度が上がり、多くの顧客獲得につながる可能性がある |
| 人気インフルエンサーに商品のPRを頼む | インフルエンサーのフォロワー全員に商品が知られるため、大きな売上につながることが期待できる | |
| 実行しやすい施策 | 自社のSNSアカウントで商品情報を投稿する | 費用はほとんどかからず、担当者が少しの時間を使えばすぐにできる |
| 無料のブログサービスで記事を書く | お金をかけずに、パソコンと時間があれば始められる |
少ない手間で大きな効果が期待できる施策は、最も優先度を高く設定します。逆に効果は大きいかもしれないけれど、準備に時間や費用がかかる施策は、後回しにするという判断も必要です。
限られた資源を最も効果的に使うために、どこから手をつけるべきかを冷静に見極めましょう。何を業者に丸投げするか決める際にも、この優先順位が役立ちます。
Web戦略を立案する
最後に、これまで決めてきた全ての要素を具体的な行動計画に落とし込み、計画書としてまとめます。「誰が・いつまでに・何を・どのように実行するのか」を明確に記述するのです。
以下に、具体例を挙げます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰が | マーケティングチーム |
| いつまでに | 2026年3月末までに |
| 何を | ウェブサイトへの月間アクセス数を現在の1.5倍に増やす |
| どのように実行するのか | ・潜在顧客が検索するキーワードを分析する ・キーワードに合わせたブログ記事を週に2本公開する ・SNSでブログ記事を拡散する |
「言った、言わない」のトラブルを防ぐためにも全体の流れを文書として残し、社内の関係者全員が共通の認識を持って計画的に行動を進めましょう。
また各施策の達成度を測るための具体的な数値目標(KPI)を設定することで、計画が順調に進んでいるか、どこかに問題がないかを定期的に確認できます。
誰が見ても何をすべきかが一目で分かるように、具体的な行動計画としてWeb戦略を完成させましょう。
Web戦略なきWeb集客の丸投げが招く損失
KPIがブレる
Web戦略がないと、目標達成度を測るための重要な指標(KPI)がぶれてしまいます。KPIとは「重要業績評価指標」のことで、事業全体の最終目標(ゴール)から逆算して設定されます。
Web戦略がない状態で業者へ丸投げしてしまうと、何を基準に進捗を評価すれば良いか、業者は分からなくなります。その結果、その時々の状況や業者の都合で、本来の目的とは関係のない指標を追いかけてしまうかもしれません。
以下に、失敗例と改善策を挙げます。
| 失敗例 | 失敗の理由 | 改善策 |
|---|---|---|
| 「とりあえず売上アップ」が目的 | 最終目標(売上)のみに注目し、具体的なプロセス(KPI)がないため、PDCAサイクルが回らない。 | 事業目標から逆算して、具体的なKPI(セッション数、CVRなど) を設定する。 |
| アクセス解析のみをKPIにする | PV数やセッション数といったアクセスデータのみを追い求め、それがビジネス成果(売上や利益) にどう貢献しているか検証しない。 | Web集客のデータと事業の成果(商談数、契約数など) を紐づけてKPIを評価する。 |
| 競合のKPIをそのまま真似る | 自社の強みや弱みを考慮せず、他社の成功事例を安易に模倣し、自社に合わない目標を設定する。 | 業者と事業目標や顧客像を深く共有し、自社のビジネスに合わせた最適なKPIを設定する。 |
戦略がない状態は、成果を正しく測るための物差しを失っているのと同じです。
投資が無駄になる
明確なWeb戦略がない状態での丸投げは、どの集客方法にどれくらいの予算をかけるべきか、その判断基準を持てません。そのため、大きな投資が無駄になる可能性が高くなります。
以下に、投資を浪費するリスクを挙げます。
- 広告費などの大切なお金が無駄になる
- 費用対効果の高い施策を選べなくなる
- 業者に言われるがまま、自社に合わない方法に資金を注ぎ込むことになる
- ターゲット層と違うSNSに多額の広告費をかけてしまう
- 効果の薄い方法を続け、大きな金額を失う
事業の目標達成という視点が抜けたままでは、大切な投資を浪費してしまうリスクがあることを自覚しましょう。
ブランドが毀損する
Web戦略には、顧客に自社のことをどのように思ってもらいたいかという、ブランドの方向性を決める役割が含まれています。どのようなメッセージを、どのような言葉遣いやデザインで発信するのか、方針を業者と共有する必要があります。
以下に、ブランドが毀損する例を挙げます。
- ターゲット層とのミスマッチ
高級感のあるサステナブルなブランドなのに、価格競争を煽るような安価なイメージの広告が配信される - 不適切な広告クリエイティブの利用
企業のブランドガイドラインを共有しないまま広告クリエイティブの制作を任せたため、過激な表現やセンセーショナルな言葉遣い、不快感を与える画像などが使用された - ステルスマーケティングの実施
集客の成果だけを重視するあまりステルスマーケティング(ステマ) が行われ、広告であることを隠してインフルエンサーに宣伝させたり、偽のレビューを投稿させたりした - ブランドコンセプトにそぐわないメディア掲載
真面目なビジネス向けサービスなのに、信頼性に欠けるゴシップ系サイトに広告が掲載された - 炎上リスクの高い企画の実施
トレンドに乗ることを重視しすぎるあまり、企業の理念や社会的な価値観を考慮しない「炎上商法」のような企画が提案・実行された
一貫性のない情報発信は、顧客に「この会社は一体何がしたいのだろう?」という不信感を与え、時間をかけて築き上げてきたブランドの価値を大きく傷つけます。一度失ってしまった信頼を取り戻すのは、難しいことを覚えておきましょう。
Web集客を丸投げするメリット・デメリットと注意点
Web集客を丸投げするメリット
Web集客には、SEO(検索エンジン最適化)や広告運用、データ分析など、専門的なスキルが求められます。しかしWeb集客スキルを持つ人材を自社で育成したり、採用したりするのは簡単ではありません。
Web集客を丸投げするメリットは、以下のことが考えられます。
- プロの知識や技術をすぐに使える
- 社内にWebに詳しい人材がいなくても、質の高い集客活動をすぐに始められる
- 自社の社員は商品開発や顧客対応など本来の仕事に集中できる
- 会社全体の生産性が上がり、成果も出やすくなる
つまりWeb集客を専門家に任せることで、成果を出しやすくなるだけでなく、社内の資源を使えるようになります。
Web集客を丸投げするデメリット
一方でWeb集客の丸投げには、社内にその知識や経験がたまりにくいという大きなデメリットが存在します。
以下に、Web集客を丸投げすることによるデメリットを挙げます。
- 社内に知識や経験がたまりにくい
- なぜ成功したのか、その理由を社内の誰も理解できなくなる
- 将来、自社で集客しようとしても、知識がないため一から始めることになる
- 業者との契約が終わると、Web集客が完全に止まってしまう
- 外部に頼むため、継続的にお金がかかる
また業者との意思疎通がうまくいかない場合には、自社の強みや魅力が顧客に正しく伝わらず、意図しない方向に進んでしまうことも考えられます。
Web集客を丸投げする際の注意点
Web集客の丸投げを成功させるには、いくつか注意すべき点があります。自社の事業やブランドとの連携が不十分だと、期待通りの成果が得られず、かえって問題を引き起こすこともあります。
以下に、Web集客を丸投げする際の注意点を挙げます。
- 事業目標とKPIを明確にする
「売上を上げたい」という漠然とした目標ではなく、「新規顧客を〇人獲得する」「顧客獲得単価を〇円に抑える」といった具体的な数値を設定し、業者と共有する - 委託先の得意分野と実績を確認する
広告運用、SEO、SNSマーケティングなど、Web集客のさまざまな手法の中で、豊富な実績があるか、過去の成功事例やクライアントからの評価を必ず確認する - 契約内容を細かく確認する
業務範囲、成果物の定義、報告頻度、契約期間、解約条件など、契約書の内容を隅々まで確認し、不明点は解消する - 定期的なミーティングを義務付ける
進捗報告や施策の効果検証を行うために、週次や月次でミーティングの場を設け、対面やオンラインで密にコミュニケーションを取る - レポートの形式と内容を事前に決める
どのような指標(アクセス数、コンバージョン数、費用対効果など)を、どのような形式(グラフ、表、テキスト)で報告してもらうか、事前に合意しておく - 自社内の情報共有体制を整える
委託先にスムーズに情報を提供できるよう、自社の製品情報、ブランドガイドライン、顧客データなどを整理し、担当者がすぐに共有できる体制を整える - 費用対効果(ROI)を常に意識する
単に「費用」だけを見るのではなく、集客にかけたコストに対してどれだけの「利益」が生まれたかを常に計測し、費用対効果を客観的に評価する - 契約解除のリスクを考慮する
万が一、期待した成果が出なかった場合や、契約が継続できなくなった場合に備え、広告アカウントやデータへのアクセス権をどうするかなど、引き継ぎに関するルールも事前に確認する
業者を単なる下請けではなく、事業を共に成長させるパートナーとして捉え、自らが主体的に関わる姿勢こそが信頼関係を築き、成果を最大化することにつながります。
丸投げできるWeb集客の業務
広告運用
Web広告の運用は、専門知識が結果に直結するため、専門業者に丸投げできる代表的な業務の一つです。
GoogleやYahoo!、SNSなどに出す広告は、どのキーワードに、いくらの予算で、どんな広告文を出すか、といった細かい設定の連続です。1円単位での費用対効果の最適化には、深い知識と長年の経験が欠かせません。
プロの業者は膨大なデータから最も効果的な広告の出し方を熟知しています。プロに任せることで、無駄な広告費を抑えながら、効率的に見込み客を集めることが期待できます。
以下に、広告運用の具体例を挙げます。
| 広告の種類 | 具体的な例 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 検索連動型 | ユーザーが検索したキーワードに連動して表示されるテキスト広告。(例:Google広告、Yahoo!広告) | 顕在層へのアプローチ、コンバージョン(購入・申し込み)獲得 |
| ディスプレイ | Webサイトやアプリの広告枠に表示される画像・動画広告。(例:GDN、YDA) | 潜在層へのアプローチ、ブランド認知の拡大 |
| SNS | FacebookやInstagramなどのSNSのタイムラインに表示される広告。 | 詳細なターゲティング、ブランドの認知拡大、エンゲージメントアップ |
| リターゲティング | 過去に自社サイトを訪問したユーザーに、再度広告を表示する手法。 | コンバージョン率のアップ、離脱ユーザーの再獲得 |
| 動画 | YouTubeなどの動画プラットフォームで配信される動画広告。 | ブランドの世界観訴求、商品・サービスの魅力の伝達 |
Webサイト制作・運用
会社の顔となるWebサイトを作り、常に最新の状態に保つ運用も丸投げができる業務です。
人を集められるWebサイトを作るには、見た目のデザインの良さだけでなく、訪問者が情報を探しやすいか(使いやすさ)や、内容が分かりやすいかといった点が重要になります。
以下に、Webサイト制作・運用を丸投げする利点を挙げます。
- プロフェッショナルな品質の確保
デザインの美しさ、使いやすいUI/UX、技術的な安定性、セキュリティ対策など、自社で内製するよりも高品質なサイトを短期間で構築・運用することができる - コア業務への集中
時間と労力がかかるWebサイトの制作や運用を業者に委託することで、自社の社員は本来のコア業務(商品開発、営業、顧客対応など)に集中できる - 最新の技術・トレンドの活用
専門業者は常に最新の動向を把握しており、セキュリティ対策、SEO(検索エンジン最適化)、モバイル対応など、最新の技術や手法を取り入れたサイト制作ができる - 客観的な視点の獲得
業者は、自社のビジネスを客観的な視点から分析し、ユーザーにとって本当に必要な情報や機能、デザインを提案してくれるため、自社では気づかなかった課題や改善点を発見するきっかけになる
プロに依頼すれば、企業の信頼性を高め、訪問者にとって有益な情報を提供できます。最終的には、売上や問い合わせといった成果を生み出し続けるWebサイトを保てます。
SNS運用
XやInstagram、FacebookなどのSNSは、今や企業にとって欠かせない集客ツールとなっており、日々の運用を丸投げするケースが増えています。SNSを通じてファンを増やし、商品やサービスの魅力を伝えるためには、継続的な投稿や、フォロワーとのこまめな交流が必要です。
以下に、SNS運用を丸投げする利点を挙げます。
- 専門的なノウハウと最新トレンドの活用
SNSマーケティングのプロは、各プラットフォーム(Twitter、Instagram、TikTokなど)の特性やアルゴリズム、最新のトレンドを常に把握しているため、ターゲットに響くコンテンツ制作などより効果的な運用と成果の最大化が期待できる - 炎上リスクの回避と危機管理
業者は、過去の事例や経験から炎上リスクを予測して投稿前のチェック体制を構築しており、万が一、炎上が発生した場合でも、迅速かつ適切な対応で被害を最小限に抑えることができる - 継続的かつ安定した運用
継続的な投稿がフォロワーとの関係構築に不可欠なSNS運用を業者へ委託することにより、事前に作成した計画に基づき、安定したペースで投稿を継続することが可能になる - 客観的な視点による改善提案
業者は、自社のブランドやサービスを客観的な視点から分析して改善点を洗い出し、社内だけでは気づきにくい課題や、ユーザーからの率直な意見を基に、より効果的な運用方法や新たな施策の提案を行う
プロの力を借りることで、手間をかけずにSNSアカウントを育て、効果的に企業の知名度や好感度を高めることができるでしょう。
SEO対策
Googleなどの検索エンジンで、自社のWebサイトを特定のキーワードで検索した際に上位に表示させるための「SEO対策」は、専門性が高く、丸投げに適した業務です。
多くの人は、検索結果の1ページ目、特に上位に表示されたサイトをクリックします。つまり上位に表示されるかどうかは、Webサイトへの訪問者数を大きく左右します。
以下に、SEO対策を丸投げする利点を挙げます。
- 専門的な知識と豊富なノウハウの活用
SEO業者は、キーワード選定、内部対策(サイト構造の最適化)、外部対策(被リンク獲得)、コンテンツSEOなど、多岐にわたる専門知識と豊富な実績を持っており、Googleのアルゴリズム変更や技術的な進化にあわせた成果を出せる - 最新のトレンドやアルゴリズム変更への迅速な対応
検索エンジンのアルゴリズムは頻繁にアップデートされるため、SEO業者は常に最新の動向を把握し、サイトに適切な対策を迅速に施すことができる - リスク管理とペナルティ回避
SEOの中には、検索エンジンが禁止している不正な手法(ブラックハットSEO)も存在するため、ガイドラインに沿った安全で健全な手法(ホワイトハットSEO)で対策を進めることができる
専門的な知見を持つ業者に任せることで、自社サイトへの訪問者数を着実に増やしていくことが可能になるのです。
データ分析・レポート
Web集客の活動成果を正しく評価し、次の一手を導き出すためのデータ分析やレポート作成も、専門家に任せたい業務です。
以下に、Web集客のデータ分析・レポートを業者に丸投げした方が良い理由を挙げます。
- 専門的な視点からの深い洞察
Googleアナリティクスや広告データから、ユーザーの行動パターン、コンバージョンの阻害要因、広告の費用対効果などを多角的に分析し、自社だけでは気づけない課題や改善点を発見してくれる - 正確かつ効率的なデータ収集とレポート作成
複数のツール(アナリティクス、広告管理ツール、CRMなど)から得られたデータを統合し、データの収集・整理・可視化を効率的に行い、意思決定に役立正確なレポートを迅速に作成する - 最新の分析手法とツールの活用
業者は常に新しいツールや分析手法などの最新情報をキャッチアップしており、効果的な分析手法を提案してくれる - 客観的な評価と改善提案
第三者である業者に分析を依頼することで、感情や経験則に頼らない、客観的な視点から施策の効果を評価してもらい、次のアクションにつながる具体的な改善提案を得ることができる
業者はデータの中から課題や成功の要因を見つけ出し、次の行動につなげるための具体的な改善策を提案してくれます。感覚ではなく、客観的なデータに基づいた意思決定を繰り返すことで、Web集客の成功確率を飛躍的に高められます。
Web集客を丸投げする業者を選定する際のポイント6つ
求めるサービス内容を提供しているか
自社が依頼したいと考えている業務を、その業者が提供しているか確認しましょう。Web集客の業務は多岐にわたり、業者ごとに得意な分野が異なります。
以下に、具体的なサービス内容を取り上げます。
| サービスの種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| Web広告運用代行 | Google広告、SNS広告、各種ディスプレイ広告などの運用を代行。ターゲティング設定、クリエイティブ作成、入札調整、効果分析、改善提案までを一貫して実施する |
| SEOコンサルティング | 検索エンジンの上位表示を目指し、Webサイトの内部構造最適化、キーワード戦略、質の高いコンテンツ制作、被リンク獲得などを提案・実行する |
| SNS運用代行 | 企業のSNSアカウント(Twitter、Instagramなど)の企画・投稿、コメント返信、フォロワーとの交流、データ分析、キャンペーン実施などを代行する |
| Webサイト制作・改善 | 集客やコンバージョンを目的としたWebサイトやランディングページ(LP)の新規制作・リニューアルを実施。既存サイトの課題分析と改善提案も行う |
| データ分析・アクセス解析 | Googleアナリティクスなどのツールを活用し、Webサイトの訪問者行動、コンバージョン経路、広告効果などを詳細に分析。今後の戦略に活かすレポートや提案を行う |
自社のWeb戦略で定めた施策と、業者の専門分野が合っているかを最初に見極めましょう。
多くの業者はホームページに提供サービスの一覧を掲載しています。依頼したい業者ホームページをよく読み、もし不明な点があれば、問い合わせの段階で聞きたい事項を具体的に質問することが大切です。
実績と具体例があるか
過去の実績は、その業者の実力を判断するための最も分かりやすい指標です。特に自社と同じ業界や、似たような課題を抱えていた企業の支援実績があるかどうかを確かめましょう。
以下に、実績と具体例を調べる方法について挙げます。
| 項目 | 具体的な確認方法 | 確認すべきポイント |
|---|---|---|
| 公式サイト | 導入事例や実績ページ、お客様の声を確認する | ・自社と類似した業界や規模の成功事例があるか ・具体的な成果(数値) が明記されているか。 |
| 直接の質問 | 問い合わせ時や見積もり時に、具体的な実績や事例を直接質問する | ・「CPA(顧客獲得単価)が〇〇円に改善」 のように、具体的な数値を提示できるか。 |
| 第三者メディア | 専門メディアの取材記事やレビューサイト、口コミ情報をチェックする | ・業者に対する客観的な評価や、依頼した企業の生の声が書かれているか |
| ウェビナー/セミナー | 業者が開催するウェビナーやセミナーに参加する | ・専門知識の深さや、得意な分野は何か ・質疑応答の場で個別質問ができるか |
| SNS/ブログ | 業者が運営する公式ブログやSNSアカウントの内容を確認する | ・最新のトレンドを把握しているか。発信内容に専門性と説得力があるか |
信頼できる業者であれば、なぜその施策で成功したのか、その根拠を論理的に説明できるはずです。具体的な成功事例を複数持っている業者ほど、信頼性が高いといえるでしょう。
利用者の口コミ・レビューを参考にしたか
その業者を利用したことのある人の口コミや評判を参考にすることも、良い業者選びにつながります。業者の公式サイトに載っている「お客様の声」だけでなく第三者が運営する口コミサイトや、SNSなどで客観的な意見も探してみましょう。
以下に、利用者の口コミ・レビューを参考にする利点について挙げます。
| 利点 | 具体的な理由 |
|---|---|
| 信頼性の客観的な評価 | 公式サイトにはない、利用者の正直な意見や不満点を知ることができる。これにより、業者を多角的に評価できる |
| 「リアルな声」の把握 | 「担当者の対応が丁寧」「報告がわかりやすい」など、サービス品質や担当者に関する具体的な体験談を得られる |
| 課題解決への適合性判断 | ユーザーの抱える課題と、それに対する業者の解決策が具体的に書かれているため、自社のニーズに合った業者か判断しやすくなる |
| 費用対効果の検証 | 料金に関する言及が含まれている場合があり、提示された見積もりが適正かどうかを判断する材料になる |
| 契約後のミスマッチ回避 | 業者の得意分野や運用スタイルを事前に把握できるため、「想像と違った」という事態を防ぐことができる |
利用した人でなければ分からない、担当者とのコミュニケーションの取りやすさや報告の頻度、返信の速さといった情報も、長く付き合っていくパートナーを選ぶ上で貴重な判断材料となるでしょう。
改善が行われているか
施策を実行して終わりではなく、その結果を分析して、改善を繰り返す仕組みがあるかも必ず確認してください。
Webの世界は変化のスピードが速く、一度成功した方法がこの先も通用するとは限りません。そのため一度決めた計画をただ実行するだけの業者では、いずれ成果は頭打ちになることが予測されます。
以下に、改善が行われているかを確認する理由を挙げます。
| 確認する理由 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 投資対効果(ROI)の最大化 | 市場やトレンドの変化に対応して施策が改善されなければ、費用対効果は低下するため、改善の有無を確認することで、投資が無駄になっていないかを把握できる |
| 市場の変化への対応 | ユーザー行動や競合の動向は日々変化しているため、業者がの変化に気づき、柔軟に対応しているかを確認することで、ビジネスの機会を逃さない |
| PDCAサイクルの確実な実行 | 改善が継続されているかを確認することで、常に最善の施策が実行されているかを確認でき、PDCAサイクルが回っている証拠となる |
| ブラックボックス化の防止 | 業者の施策のブラックボックス化を防止するために、改善の理由や根拠を理解することで、知識を蓄積し、対等な関係を築く |
| 契約継続の判断材料 | その業者が長期的なパートナーとして適切かどうかを判断するために、継続的な改善が行われているかどうかについて、契約の見直しや業者変更を検討する材料とする |
契約前の打ち合わせの段階で「施策の実行後は、どのような流れで改善の提案をいただけますか?」と質問することをお勧めします。
費用対効果に納得できるか
提示された料金が、提供されるサービス内容や期待できる成果に見合っているかを慎重に判断してください。複数の業者から見積もりを取り、料金の金額だけでなく、それぞれのサービス内容やサポート体制を総合的に比較しましょう。
以下に、費用対効果に納得する必要性を挙げます。
| 納得すべき理由 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 投資が事業成長に直結する | Web集客の費用は単なる経費ではなく事業成長のための投資であり、費用対効果が明確でなければ、その投資が本当に利益を生んでいるか判断できない |
| 予算配分の最適化 | 限られた予算を効果的に使うため、無駄な出費を削減し、費用対効果の高い施策に集中投資して予算を最適化できる |
| 目標達成へのコミットメント | 費用対効果に納得することは、「この投資でこれだけの成果を出す」という目標にコミットすることであり、業者との関係がパートナーシップが築ける |
| 社内への説明責任 | 納得できる数値を用いて費用対効果という明確な根拠をもって、経営層や他部署に投資の正当性を説明し、予算承認を得る |
| 将来の戦略立案 | 今回の費用対効果のデータは、次に何に投資すべきか、どの方向へ進むべきかという、次のWeb戦略を立てる上で貴重な資産となる |
金額だけでなく、その費用を投資することでどのような成果を目指せるのか、費用対効果の視点で業者を評価することが重要です。
アフターフォローに対応しているか
契約後のサポート体制が整っているかも忘れずに確認しましょう。
Webサイトの表示に不具合が起きたり、広告の配信でトラブルが発生したりと、予期せぬ問題が起こる可能性はゼロではありません。緊急時に迅速かつ丁寧に対応してくれるサポート体制があるかは、安心して業務を任せる上で重要です。
以下に、アフターフォローが必要な理由を挙げます。
| 確認する理由 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 成果の長期的な維持 | Web集客の効果は時間と共に薄れるため、定期的なメンテナンスや改善提案が必要であり、アフターフォローがあれば、長期にわたって成果を維持・成長させられる |
| 緊急時の対応体制の確保 | システムトラブルや炎上など、予期せぬ事態が発生した際に、迅速に対応してくれる体制が整っているかを確認することは、リスク管理になる |
| PDCAサイクルの継続 | 施策実行後のデータ分析に基づいて改善を続け、常に最善のWeb集客施策を実行し続けられる |
| 技術的な知識の補完 | アフターフォローがあれば、専門家のサポートを継続して受けられる |
| パートナーシップの構築 | 制作・初期運用だけでなく、その後の運用も共に支えてくれる業者は、真のビジネスパートナーという関係を築ける |
契約が終了した後も自社で運用を続けていくためのノウハウを共有してくれたり、簡単な質問に答えてくれたりするような業者であれば、より心強いパートナーといえるでしょう。
契約を結ぶ前に、サポートの範囲や対応してくれる時間帯、追加で費用が発生するかどうかなどを、書面で確かめることをお勧めします。
長期的な視点でサポートしてくれる業者を選びましょう。
まとめ
この記事では、Web戦略に基づいたWeb集客の丸投げについて、基本から具体的な業者の選び方までを解説しました。
Web集客を外部の専門業者に丸投げするとは、自社のリソースを節約し、専門的な知見を活用することです。しかしその成功のためには、依頼する側がしっかりとしたWeb戦略を持つことが重要です。戦略があって初めて、専門業者というパートナーがその力を最大限に発揮できます。
Web集客と戦略の基本を理解し、自社の目標とターゲットを明確にすることから始めましょう。その上で、この記事で紹介したポイントを参考に信頼できる業者を慎重に選び、最高のパートナーを見つけ出してください。
もしWeb戦略についてお悩みなら、株式会社FlyEdgeにご相談ください。3,000回以上のコンサルティングで構築した、中小企業の勝ちパターンを活用したい方はぜひお問い合せください。