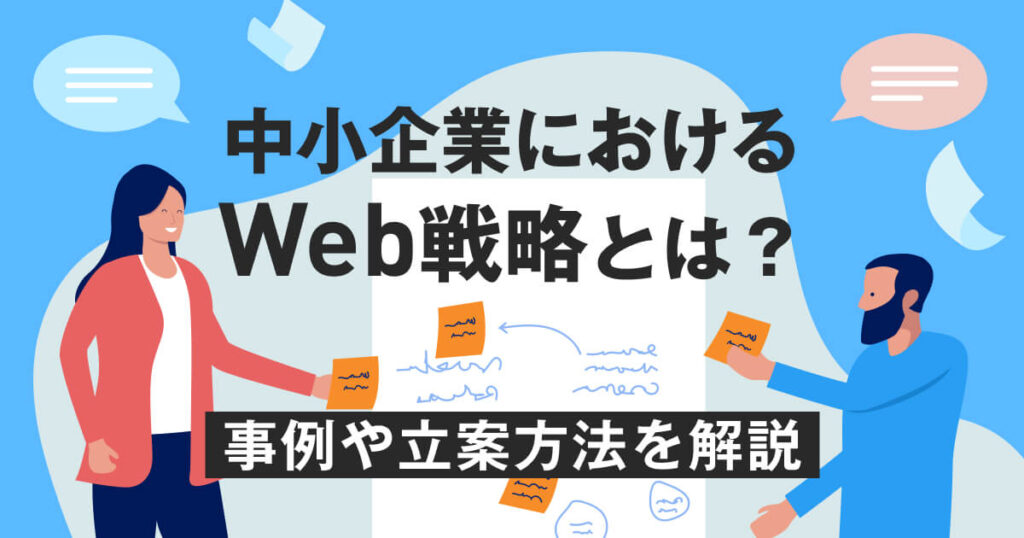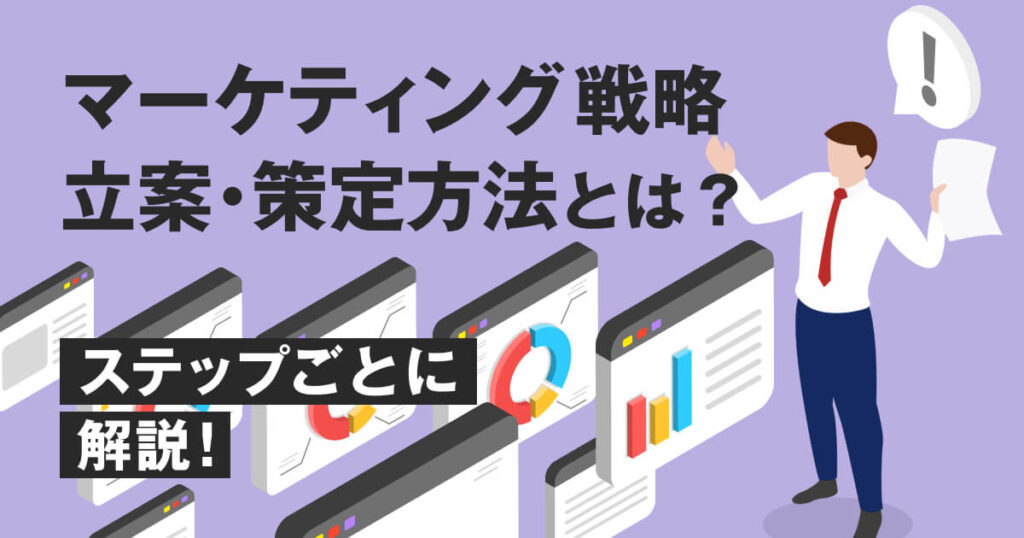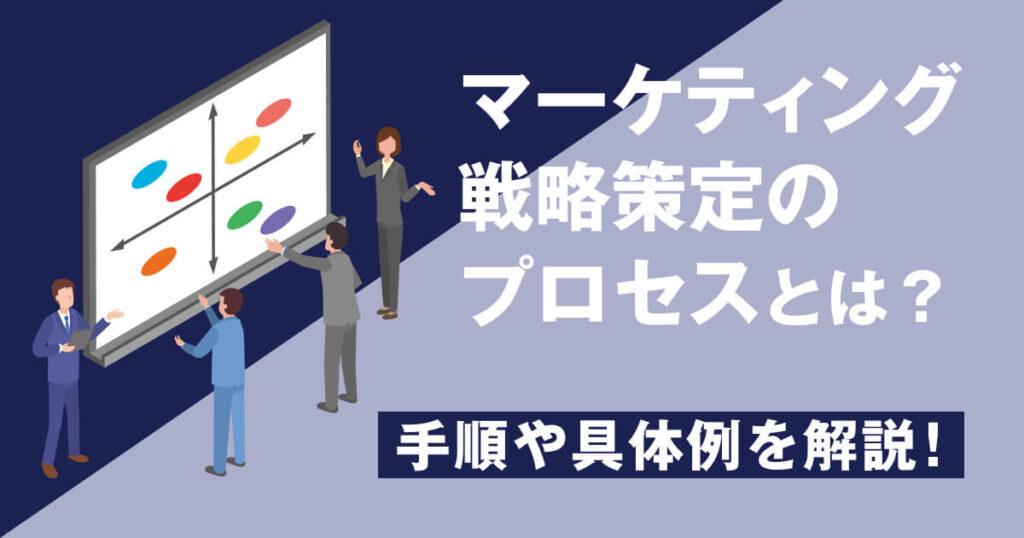営業活動の効率が上がらず、成果に結びつかないと悩んでいませんか。「リードクオリフィケーション」を活用すれば、その悩みを解決できるかもしれません。
リードクオリフィケーションとは、集めた多くの見込み顧客の中から、特に購入意欲が高い層を見つけ出す手法です。有望な顧客に絞ってアプローチするため、営業の生産性を大きく向上させることが可能です。
本記事では、リードクオリフィケーションの基本的な意味から、具体的な進め方、成功させるためのポイントまでを分かりやすく説明します。リードジェネレーションとの違いや、おすすめのツールについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
もし見込み顧客の選別や具体的な方法にお悩みの方は、株式会社FlyEdgeにご相談ください。3,000回以上のコンサルティングで構築した、中小企業の勝ちパターンを活用して貴社のお手伝いいたします。
リードクオリフィケーションとは

リードクオリフィケーションとは、集めた見込み顧客(リード)の中から、購入意欲が特に高い有望な層を選び出すことです。
ここでは、似たような意味で捉えられる言葉と比較して解説します。
リードジェネレーションとの違い
リードクオリフィケーションとリードジェネレーションの最も大きな違いは、目的です。リードジェネレーションは見込み顧客を「集める」段階であり、リードクオリフィケーションは集めた見込み顧客を「選別する」段階を指します。
マーケティング活動は一連の流れで構成されています。まず見込み顧客を獲得し、その後に有望な顧客を見つけ出す必要があるため、二つの活動は明確に区別されるのです。
具体的には、展示会で名刺を交換したり、ウェブサイトに問い合わせフォームを設けたりする活動がリードジェネレーションにあたります。一方、集めた名刺の情報や問い合わせ内容をもとに、企業の規模や予算などを分析し、アプローチすべき顧客を決める作業がリードクオリフィケーションです。
リードジェネレーションで見込み顧客の数を増やし、リードクオリフィケーションでその中から質の高い顧客を見つけ出すという流れになります。
リードナーチャリングとの違い
リードナーチャリングは顧客の購買意欲を「育てる」活動であり、リードクオリフィケーションは育った顧客の購入確度を「見極める」手法です。
多くのコンバージョンを得るためには、すぐには購入に至らない見込み顧客との関係を保ち、関心を高めていく過程が必要です。メールマガジンで有益な情報を定期的に届けたり、セミナーを開いて製品への理解を深めてもらったりする活動がリードナーチャリングにあたります。
顧客の関心が高まったタイミングでその度合いを評価し、営業部門へ引き渡すか判断するのがリードクオリフィケーションの役割です。リードナーチャリングで顧客との関係を築き、リードクオリフィケーションで最適なタイミングを見計らって次の段階へ進める、という連携が重要です。
バリデーションとの違い
リードクオリフィケーションとバリデーションの違いは、確かめる情報の種類にあります。バリデーションは、顧客情報の「正確性」を確かめる作業です。一方、リードクオリフィケーションは、顧客の「購買意欲」を評価する作業を指します。
具体例を挙げると、入力されたメールアドレスが有効か、電話番号が実際に使われているかなどを確認するのがバリデーションです。これはデータの「掃除」と考えると分かりやすいでしょう。リードクオリフィケーションは、その正しい情報をもとに、顧客が自社のサービスにどれだけ関心を持っているかを分析します。
バリデーションで情報の品質を保ち、リードクオリフィケーションでそのデータを使って戦略を立てる、という関係性になります。
リードクオリフィケーションが重要な理由

リードクオリフィケーションを活用することで、少ない労力により高い成果を得るために重要です。
ここでは以下の3つの視点で、リードクオリフィケーションの重要性を解説します。
- コストを削減できる
- 予測の精度を高められる
- LTVを向上できる
コストを削減できる
リードクオリフィケーションを導入すると、営業活動にかかる無駄なコストを大きく減らせます。理由は、購入する可能性が高い見込み顧客に絞ってアプローチできるようになるからです。
例えば、営業担当者が1日に10件の訪問営業を行うとします。リードクオリフィケーションを行わずに訪問すると、成約率は低く、多くの訪問が無駄になる可能性があります。しかし事前に関心度の高い顧客を5件に絞り込めば、移動時間やコストを減らせるでしょう。
さらに1件あたりの商談に集中できるため、成約率の向上も期待できます。結果として、より少ないコストで高い成果を生み出すことが可能になるのです
予測の精度を高められる
リードクオリフィケーションを導入することで、売上予測の精度を上げられます。見込み顧客の質を客観的な基準で評価できるから、という理由が挙げられます。
リードクオリフィケーションでは「スコアリング」という手法がよく使われます。ウェブサイトの閲覧履歴やメールの開封率といった顧客の行動や、企業規模などの属性に応じて点数をつけ、購買意欲を数値化するものです。
仮に「合計80点以上の顧客は3ヶ月以内に70%の確率で成約する」といったデータが蓄積されれば、精度の高い売上予測ができます。データに基づいた客観的な評価を取り入れることで、成約率と売上の見通しをより正確に立てることが可能となるのです。
LTVを向上できる
リードクオリフィケーションは、LTV(顧客生涯価値)の向上にもつながります。自社のサービスと相性の良い顧客を、早い段階で見極められるためです。
LTVを高めるには、一度きりの取引で終わらせず顧客に満足してもらい、長期的な関係を築くことが大切です。顧客が製品やサービスに満足すれば、継続利用や上位プランへの変更、関連製品の購入に結びつきやすくなります。
満足度の高い顧客体験を提供することで、結果的に一人ひとりの顧客が会社にもたらす利益、つまりLTVが向上するのです。
リードクオリフィケーションを活用するメリット

リードクオリフィケーションを活用することで、個々の活動を最適化できます。
ここで紹介するメリットで、自社の成長が期待できるか確認してみてください。
有望リードの発見スピードが向上する
リードクオリフィケーションを導入すると、成約につながりやすい有望な見込み顧客(リード)を素早く見つけ出せます。あらかじめ設定した基準に基づいて、システムが自動で顧客の有望度を判断してくれるからです。
さらにMA(マーケティングオートメーション)ツールを使えば、特定のウェブページを見た、資料をダウンロードした、といった行動をした顧客に自動で高い点数をつけられます。合計点が一定の基準を超えた顧客だけを、営業担当者に通知する仕組みを作ることも可能です。
この仕組みによって、営業担当者は毎日大量のリストに目を通すことなく、今すぐアプローチすべき顧客を即座に把握できるようになります
マーケティングと営業の連携が強化される
マーケティング部門と営業部門において「どのような顧客を営業に引き渡すか」という共通の基準を持つは、認識のずれをなくすために重要です。マーケティング部門は「多くの見込み顧客を集めた」と考えていても、営業部門から見ると「成約につながりにくい顧客ばかりだ」と感じることがあります。
リードクオリフィケーションでは、点数などの客観的な指標を用います。例えば「スコアが80点以上の顧客を営業に引き渡す」というルールを共有すれば、マーケティング部門は80点を目指して顧客を育てます。
営業部門は質の高い顧客リストを受け取れるため、双方の不満が減るでしょう。明確な基準を設けることで、部門間のスムーズな協力体制を築けます。
データドリブンな改善と自動化が可能になる
リードクオリフィケーションを実践すると、データに基づいた改善活動を継続的に行い、多くの作業を自動化できます。どのような行動をとった顧客が成約しやすいか、というデータが蓄積されていくためです。
当初は「価格ページの閲覧」を最も重要な行動として高い点数を設定していたとします。しかしデータを分析した結果、「導入事例ページの閲覧」の方が成約率が高いと判明するかもしれません。この場合、スコアリングの基準を見直すことで、さらに精度を高めることが可能です。
またMAツールを使えば、スコアに応じたメール配信などの作業を自動化できます。客観的なデータに基づいた判断と改善を繰り返すサイクルと、自動化によってマーケティング活動全体の質が向上します。
リードクオリフィケーションを行う手順

リードクオリフィケーションを効果的に行うには、計画的な手順を踏むことが重要です。ここでは、一つひとつの手順を詳しく解説します。
自社に合った精度の高いリード、クオリティケーションを実現するために、段階的なアプローチを心がけましょう。
h3:セグメンテーション
セグメンテーションとは、見込み顧客をグループ分けすることです。すべての顧客を同じ基準で評価するのではなく、顧客の属性や特徴に合わせて適切なアプローチをするために行います。
BtoBビジネスであれば、企業の業種、従業員数、所在地といった情報でグループ分けができます。IT企業と製造業では、求める製品やサービスが違うはずです。また、企業の規模によって予算感や導入までの期間も変わってきます。
顧客をいくつかのグループ(セグメント)に分けることで、それぞれのグループに合ったメッセージを届けたり、評価の基準を調整したりすることが可能になるのです。
カスタマージャーニー/シナリオ設計
次に、顧客が製品やサービスを知ってから購入に至るまでの道のりである「カスタマージャーニー」を設計しましょう。顧客がどの段階にいるのかを把握し、それぞれの段階でどのような情報を提供すれば購買意欲が高まるかを考えられるようになります。
具体的には、ブログ記事で製品の存在を知り、次に比較記事を読み、資料をダウンロードし、最後に問い合わせをするといった一連の流れがカスタマージャーニーです。
それぞれの行動段階に合わせて、「このタイミングでは製品の基本的な情報をメールで送る」「資料をダウンロードした人には事例を紹介する」といった具体的なシナリオを設計します。顧客の気持ちや行動を予測することで、適切なタイミングで適切なアプローチが可能です。
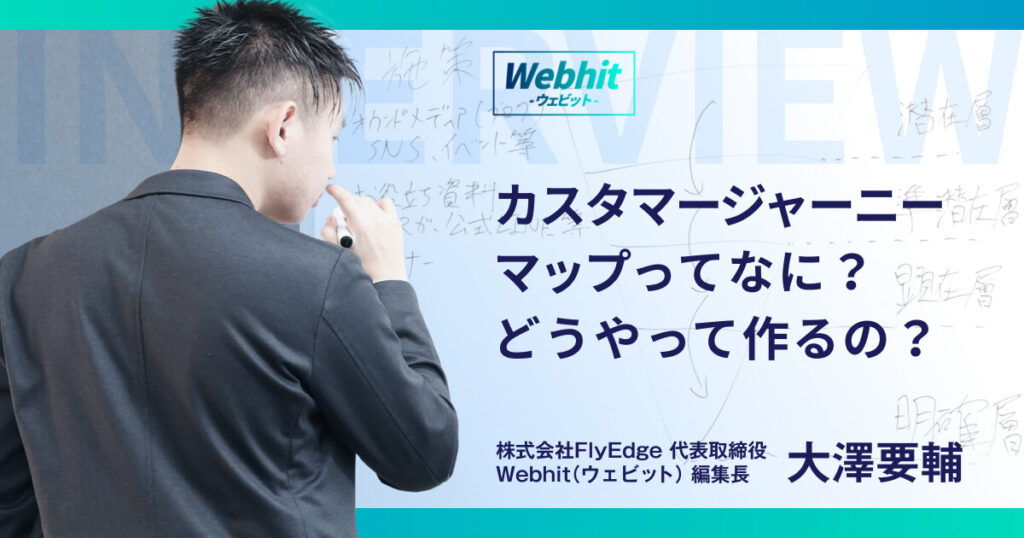
スコアリング設計
スコアリング設計とは、見込み顧客の行動や属性に点数をつけ、購買意欲を数値で評価する仕組みを作ることです。営業担当者がアプローチすべき優先順位を、客観的な基準で判断できるようにするために行います。
例えば、以下のような具体的な点数を設計します。
- 「役職が部長以上なら+10点」
- 「料金ページを見たら+5点」
- 「資料をダウンロードしたら+15点」
点数を設計したら、合計点が一定の基準を超えた顧客を「ホットリード(有望な見込み顧客)」と定義します。この点数設定は、過去の成約顧客のデータを分析し、「どのような属性や行動を持つ顧客が成約しやすいか」を基に行うと、より精度が高まります。
スコアリング設計によって、誰が見ても同じ基準で顧客の有望度を判断できる、公平で効率的な仕組みとなるのです。
スコアリング運用と営業部門へのパス
設計したスコアリングを実際に運用し、基準点に達した見込み顧客を営業部門へ引き渡す段階に進みます。マーケティング活動で高まった顧客の関心を、実際の商談につなげるための重要な連携プロセスです。
具体的には、MAツールなどで顧客の行動を自動で追跡し、スコアを計算します。スコアが設定した基準点に達した顧客の情報は、自動的に営業担当者へ通知する仕組みを整えましょう。
通知の際は、「料金ページを3回閲覧し、導入事例をダウンロードした」といった具体的な行動履歴を共有することで、営業担当者は顧客の関心事を事前に把握できます。
フィードバックループと改善サイクル
最後に最も重要なのが、営業部門からの結果をマーケティング部門に伝え、評価基準を継続的に見直す改善サイクルです。一度決めた基準が、常に最適とは限りません。市場や顧客の変化に対応し、リードクオリフィケーションの精度を維持・向上させましょう。
具体的なほうほうとして、営業部門は引き渡された見込み顧客と実際に商談した結果をマーケティング部門に報告します。マーケティング部門はフィードバックから予測と違った原因を分析し、スコアリング基準の見直しを行います。
このやり取りを繰り返すことで、仕組み全体の精度がどんどん高まっていくのです。リードクオリフィケーションを成功させるには、改善サイクルを回し続けることが必要です。
リードクオリフィケーションにおすすめなMAツールとは

MAツールはマーケティングオートメーションツールの略で、顧客情報の管理からスコアリング、アプローチの自動化までを一貫して行えます。
手作業で膨大な数の見込み顧客の行動を一つひとつ追跡し、点数を計算するのは現実的ではありません。MAツールを使えばウェブサイト上の行動履歴やメールの開封といったデータを自動で収集し、あらかじめ設定したルールに基づいてスコアを付けられます。
有名なMAツールには、以下があります。
- HubSpot
- Marketo Engage
- Salesforce Account Engagement
MAツールを選ぶ際は、自社の規模や予算、必要な機能に合わせて選びましょう。
まとめ
本記事では、リードクオリフィケーションの意味や重要性、具体的な手順について説明してきました。リードクオリフィケーションを導入することで、集めた見込み顧客の中から購入意欲の高い層を選び、限られたリソースを集中投資できます。
そのためコスト削減や売上予測の精度向上、さらにはLTVの向上といった多くのメリットが生まれるのです。
具体的な手順も解説したので、一つひとつステップを踏みながら実践してみてください。もし「リードクオリフィケーションがうまくいかない」と悩んでいるなら株式会社FlyEdgeにご相談ください。3,000回以上のコンサルティングで構築した、中小企業の勝ちパターンを活用したい方はぜひお問い合わせください。