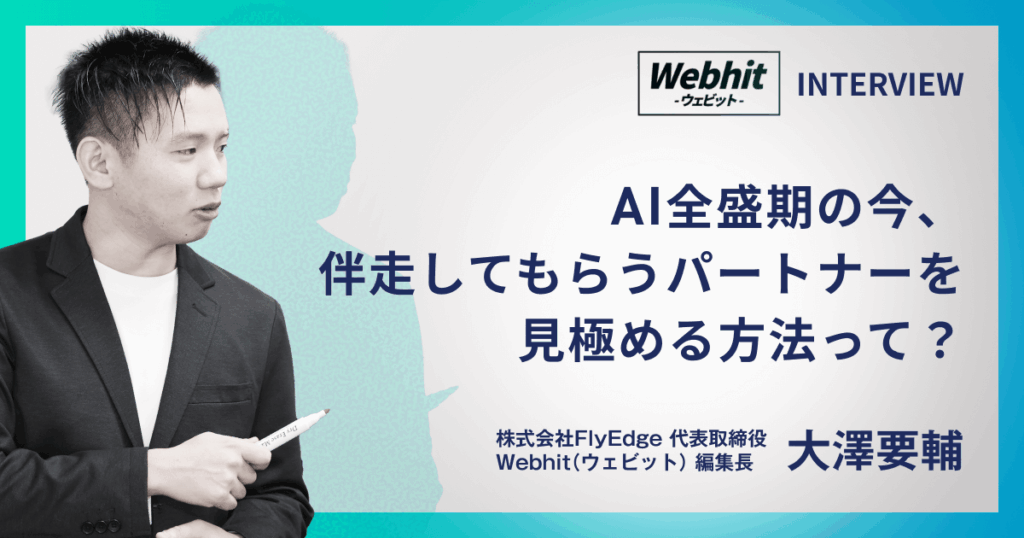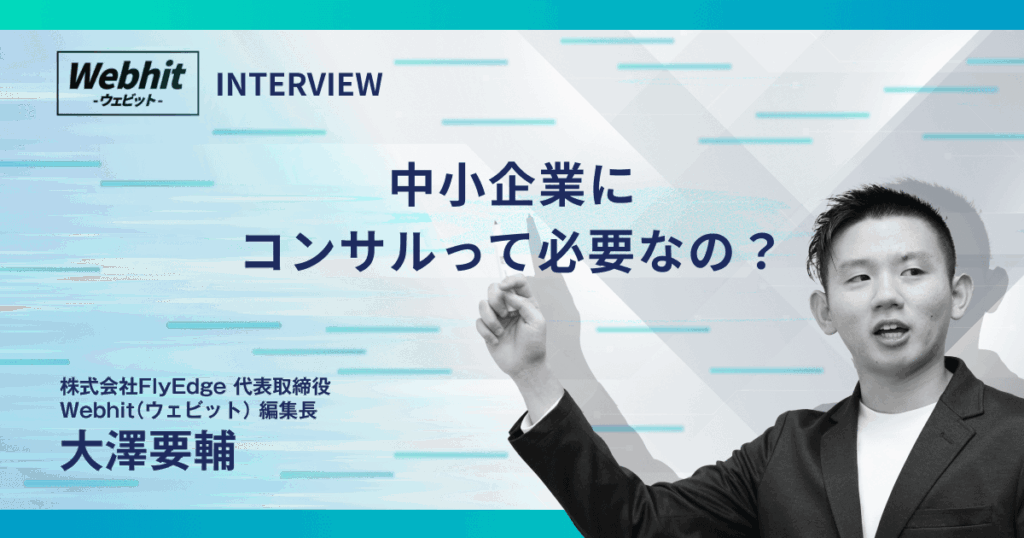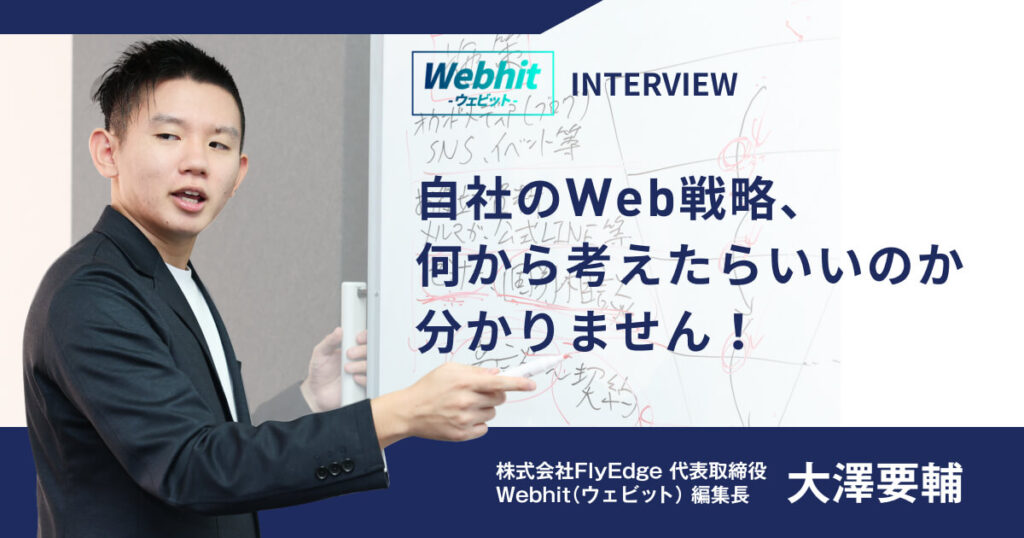Webhit 編集部
Webhit 編集部今回は「中小企業の9割が間違えている「ブランディング」とは?」に
ついてお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。



はい、お願いします。
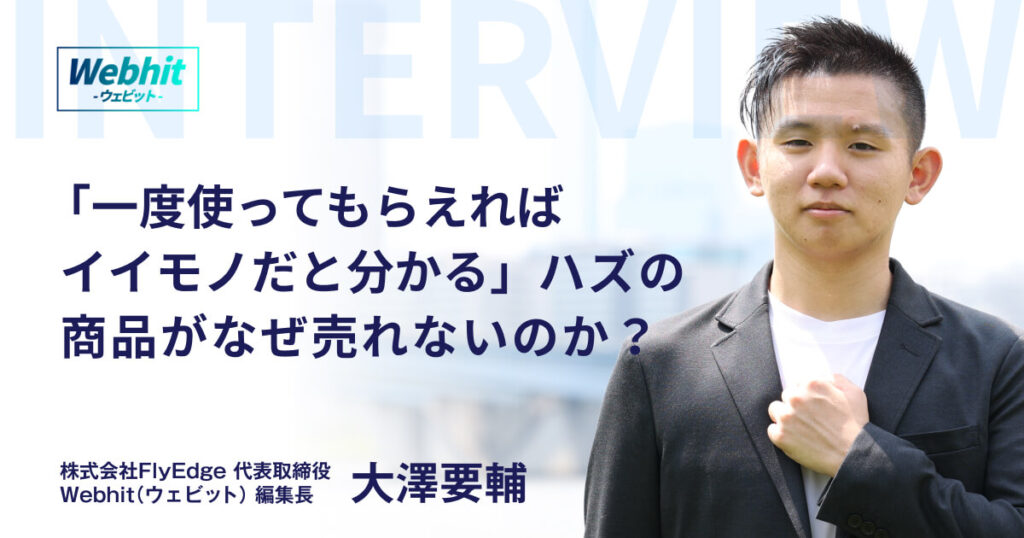
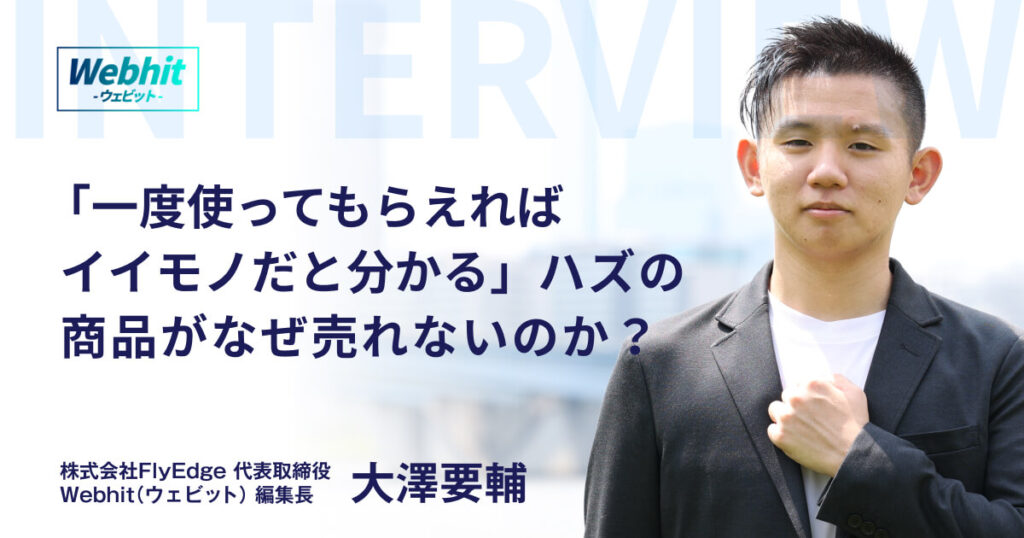
ブランディングの本質とは?中小企業が陥りがちな誤解



まず、9割が間違えている「ブランディング」というのはどういったことを指すのでしょうか?



「ブランド」とは自分たちが思われたい自社・商品・サービスに対する印象、イメージのことです。そして、自分たちが発信しているものとお客様の頭の中にある、自社・商品・サービスに対する印象、イメージを、イコールにしようという作業が「ブランディング」です。



ブランディングをしていくためには、自分たち側から発信をする必要があります。



ユニクロを例に挙げて説明すると、ユニクロはホームページだと結構、ブランドっぽい感じになっていますね。少し小綺麗な感じのサイトにしてクオリティの高いイメージを出しています。



一方で、集客の方において現店舗で配られてるチラシを見ると、どちらかというと電気屋さんなどに近い結構ゴテゴテのチラシを配っています。そこで訴求してるのは、基本的に「安さ」なんですよね。
各商品の金額を大きく強調して安さをアピールしているのですが「ユニクロはとにかく安い!」というイメージがある人はほとんどいないと思います。



どちらかというと、ユニクロは昔に比べてそんなに安くはないかもしれないけれど、それでもまだ他大手よりは安いし、全然普段着れるクオリティという認識でいる方が多いと思います。
このように、企業がイメージとして出したい状態とお客様側の頭の中で認識されてる状態がイコールになってるのが、ブランディングできている状態です。


9割の中小企業が間違えているブランディングの落とし穴



「ブランディング」を中小企業は9割が間違えてるということなのですが、ほとんどの企業が間違えてるということですよね?



はい。どこを間違えているかと言いますと、まずブランディングというとほとんどの中小企業は見た目の部分である「デザイン」を考えるんです。
もちろん、見栄えもブランディングに影響のある範囲のため、非常に重要な部分があるのは事実です。その一方で、ブランディングは見栄えだけで構成されてるわけではありません。



ブランディングは、
・企業やサービス・商品のメッセージ、コンセプト
・誰に向けたものであるのか
・商品やサービスを使うとどんなベネフィットがあるのか
などの要素で構成されています。



そして、それをお客様に届け、かつお客様が自分たちが発信している認識と同じ認識を持ってくれているという状態がブランディングが成立している状態です。



例えば、食料危機にどのように対応していくべきか「食料危機は大変だから、基本的には食料自給率をあげていこう」「我々にもできることがある」とコンサルティングをしている会社があるとします。
そこで、食料自給率を上げようというコンセプトをデザインだけでどうにかしようとしてデザインに起こすと何が起きるかというと「食料自給率なんだから食料がたくさんある感じを出したらいいのでは?」となるんです。



そうすると、ホームページ上に野菜とか果物、魚、肉のような画像がとにかくたくさん使われていたり、アイコンやマウスのカーソルにも食料のデザインが使われたりします。



ホームページの内容は一切検討せず、デザインだけ重視して、会社概要やサービス内容だけが書いてあるシンプルなコーポレートサイトであった場合、何が伝わると思いますか?



・ご飯や食材がたくさん並んでて、なんか楽しそうな会社なのかな
・面白い会社なのかな
・あんまり他に見ない個性的な会社なのかな
などという印象を持たれることが多いと思います。



しかしこれは本来、自分たちがお客様に思ってもらいたかったイメージとイコールか?という話なんです。
この時点で自分たちは食料危機に対応していくんだ、食料自給率を上げなければならないんだというメッセージ性がどこにもないですよね。



このように、デザインができていればブランディングできているという勘違いをしている人たちが非常に多いんです。そのため、デザインももちろん重要な要素ですが、それに加えて中身の部分を作っていくことが大切です。



なるほど。ブランディングで重要なのは見た目だと思っている人は多そうですね。



そうですね。
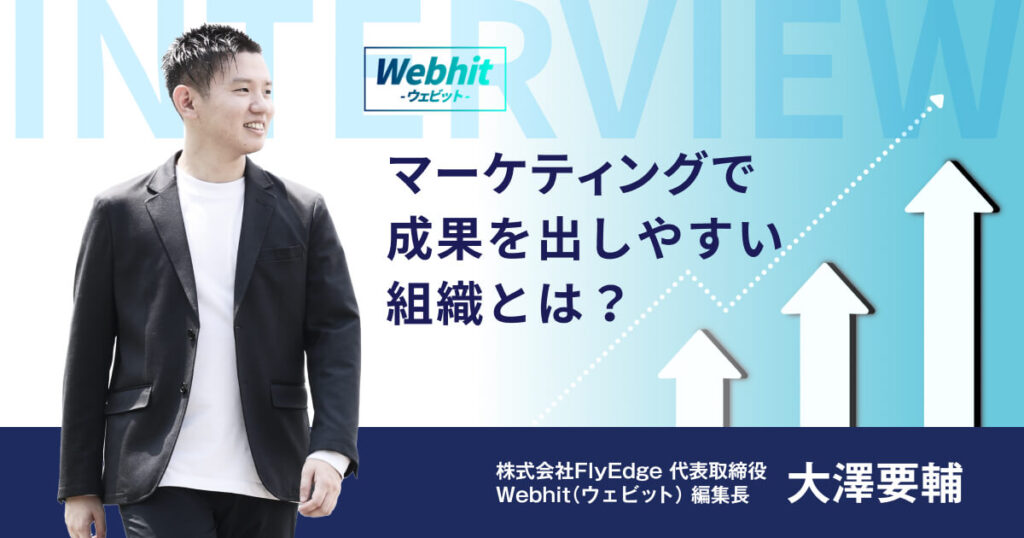
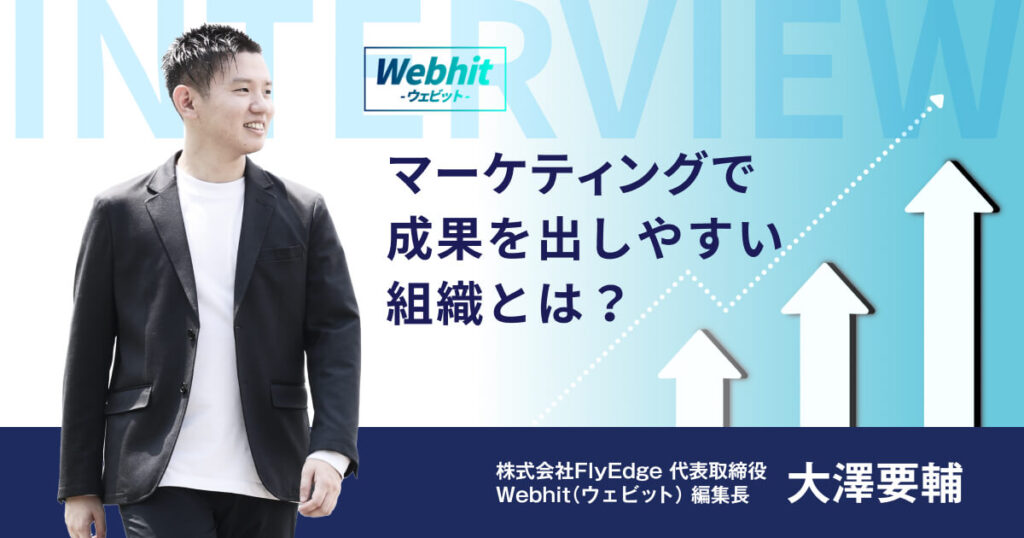
成功するブランディングの作り方



では間違えないために、ブランディングはどのように作っていくのが一番いいんでしょうか?



はい。まずデザインや見せ方の工程については、最後の話になります。



最初にやるのは、
・自分たちが何をどう思われたいのか
・どういうイメージでありたいのか
・どういうサービスだと認識されたいのか
ということを可能な限り全部、具体的な言葉に落とすことです。



そして、言語化したらそれをユーザーの頭の中にも同じことを想起させる必要があります。



自分たちがこう見られたい、こういうふうに認識されたいという要素一つひとつに対して、事前の知識や情報が一切ないユーザーが初めてその情報に触れた場合に、伝えたい印象やイメージ、認識をどうやって伝えるのかをここで初めて検討します。
イメージについては、カラーのフォーマットを決めたりルールを決めたりする必要があります。カラーだけではなく、フォントもそうです。ゴシック体と明朝体では伝わる印象が全然違いますよね。



例えば他にも、デザインは四角とか三角みたいな直線系のイメージに近いのか、丸のイメージのほうが近いみたいなこともそうですね。
イラストや写真を使う場合にはどういうテイストのものを使うべきなのかも、検討する必要があります。さらに、どういうメッセージを実際に訴求すると良いのかなど、フレーズやキーワードも重要な要素になります。



あとは、
・コンセプトとしてこういう言葉で伝える
・プロジェクトだけではなく補足説明文も一緒につける
などのルールも必要です。



ストーリー調にした方がお客様がこちらが伝えたい認識になってくれやすいのであれば、ストーリー調にしましょうというようなルールも決めていきます。



ブランディングの流れをまとめると、まずは自分たちが伝えたいイメージや印象、認識を全て言葉に落とします。
次に、それを今度ユーザーにどう伝えるのか、どうしたら前提情報も知識もないユーザーに、このイメージ、印象、認識が伝わるのかを検討していきましょう。
また、最終的にそれを全てブランディングをするのであれば、自分たちが出すコンテンツや情報などは全て統一しないといけません。



例えば店舗があるお店であれば、
・店舗の内装やお客様に対しての接客
・看板のデザインのテイスト
・ウェブサイトのデザインのテイストやフォント
・お客様に対してのメッセージの出し方、言葉の使い方
などがそうです。



SNSで代表が発信するというのであれば、SNSでどういうふうなメッセージを常に出していくのか、共通するメッセージは何するのかなどを、そのブランドがブランディングを成り立たせるためにどうすればユーザーにこちらの思ってもらいたいイメージ、認識、印象が正しく伝わるのかというのを統一していくという流れが良いと思います。


ブランディングには終わりがない?継続的な改善が必要な理由



ブランディングの流れをさらっとお話いただきましたが、ブランディングというのはどれぐらい検討して熟成されていくものなんでしょうか?



結論として、ブランディングには答えもなければゴールもないです。
また、その期間は必ずこれだけやればいいというものではなく、この
項目だけ埋めれば確実に上手くいくというものでもありません。



どちらかというと、ブランディングにおいては、少なくとも1回イメージを決めることが大切です。そういった意味では、熟成というのは少し違いますが、そぎ落とすイメージに近いと思います。
多分最初は、自分たちが思ってもらいたい印象やイメージを出していくと結構な数になるはずです。その中から、似たようなことを言ってるものをまとめたり、本当に言いたいことや会社として伝えたいことを再検証したりしていくと結構数を削れます。



その結果、結局最終的に言いたかったことがいくつか絞れてきます。
もちろん数が1つのところもあれば、いくつもあるところもありますが、ある程度グルーピングされていくため、集約されたもので一旦全体的にどのように出していくのかを言葉に落として、もう1回まとめて出す必要があると思います。



当然ながら、最初からこちらが思った通りにお客様が認識してくれるわけではないので、お客様にインタビューやアンケートなどの、いわゆるマーケティングリサーチを行いながら、進めれば良いと思います。



そして、ブランドが今どういう認識、認知をされてるのかを調査できる「ブランドリフト調査」を行いながら、自分たちのブランドの浸透度合いおよび浸透のされ方をチェックをしていきましょう。
・この方策は間違っているから変える
・ここの見せ方を少し強化する必要がある
・要素として以前に削ったものの方が出てくるため、どうやれば認識を
変えられるか
という観点で進めていくと良いと思います。



とはいえ、1回で決め切るのではなくて、随時更新されるものと認識してアップデートをし続けなくてはいけません。


まとめ



ありがとうございます。
では、最後に今日のまとめとこの記事を見てくださっている方に一言お願いします。



はい。そもそも「ブランディング」というものの考え方を、中小企業の9割が間違えています。



ブランディングに関しては、中小企業の観点で言えば短期的にすぐに費用対効果が見込めるようなものでもないですし、どちらかというと検討する優先度は非常に低い方だと思います。



そのなかでも、こだわりを持ちたいという会社様がブランディングをやっています。
しかし、そこで残念ながら見栄えのみに目線がいってしまい、うまくいかないケースが多い傾向にあります。
そういう会社のほとんどは基本的に自分たちがどういうふうに見られたいのかを言葉にできていないケースが多く、見た目の雰囲気や、何となくでブランディングしようとする傾向があります。



万が一少しでも「そういうふうにやってたかも……」と思った方がいらっしゃれば、まずは自分たちがどう見られたいのか、どういうイメージを持たれたいのか、どんな認識をされたいのかを具体的な言葉に落とすようにしましょう。



まずそこから始めないと、議論も当然具体的になりません。そこまで来て初めて一旦これで公開しましょうという話ができます。



とはいえ、それだけで終わりではないため、実際にお客様にはどのように伝わっているのかをアンケートやブランドリフト調査などでチェックする必要があります。
そして、状況をチェックしつつ、伝えるべきものがあるのであれば、要素を変える、展開の仕方を変えるなどの改善も必要です。



また、ブランディングは非常に大変なため、しっかりやりきるならばいいと思いますが、やる気がないのであれば、無理に取り組もうとしなくても良いと思います。
取り組むと、自社のポジションがより明確になるので、やるに越したことはありませんが、物事の優先度がある中で、他の優先度が高いものを押しのけてまでやることではないと思っていただければと思います。
以上です。



ありがとうございました。