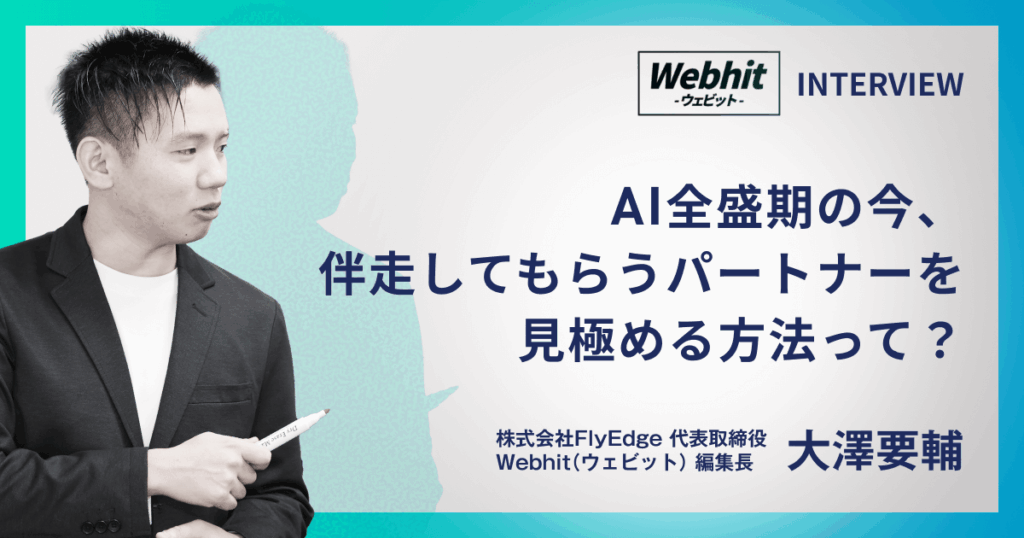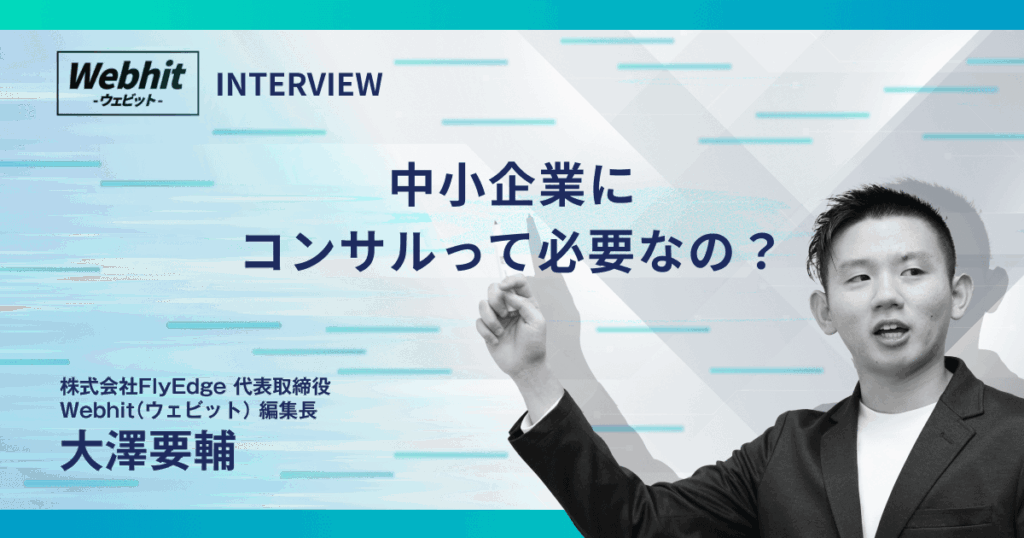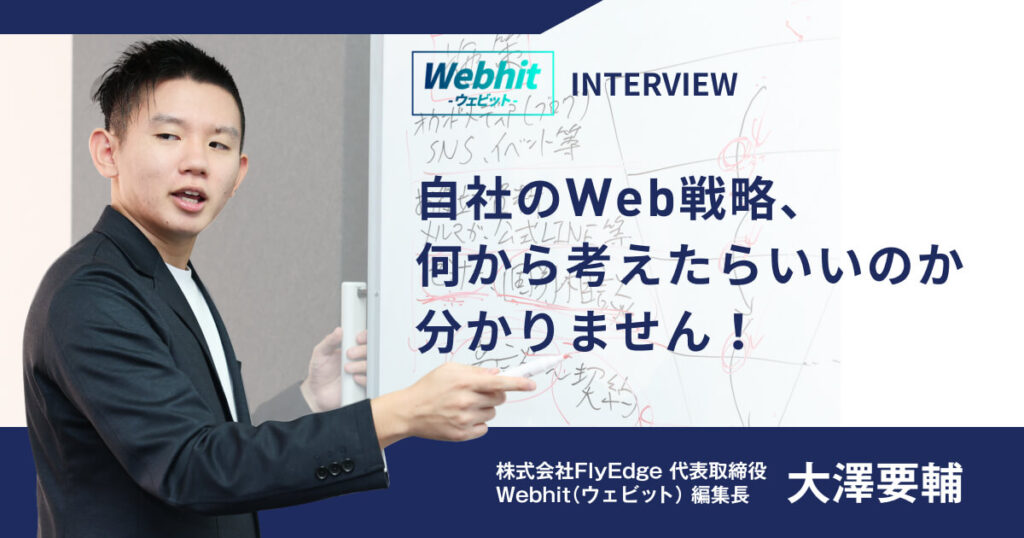Webhit 編集部
Webhit 編集部今回のテーマは「一番Webマーケティングが成功する方法は、とにかく楽しむこと!」というところでお話を伺っていきたいと思います。



よろしくお願いします!


なぜWebマーケティングは「楽しむこと」が成功のカギなのか?



こちらのテーマなのですが、とにかく「楽しむこと」ということに至った背景や理由をお聞かせいただけますか?



まず、Webマーケティングが一番成功する方法は、楽しむことなんですよ。



中小企業さんによくある例として、集客をしなくてはいけないために、問い合わせの件数や、問い合わせの獲得単価などをKPIに立てることがあります。



それ自体は別に間違ってはいないんです。
KPIを設定すること自体は全く間違っていないのですが、ただ、あまりにもそれに囚われてしまう会社さんがとても多いんですよね。



よくあるケースでは、目標の問い合わせ数を10件としていたところ、実際の結果が5件だった時に、「なんで5件なんだ、なんでもう5件取れなかったんだ」のような議論がよく起こるんですよね。



でも、そのことに関して、「なんで?」を突き詰めたところで、特に結果は出ないんですよ。



もちろん、ある程度原因を突き止めて、それに対して改善策を実施することもあるのですが、「なんで出ないんだ」ということばかり言うケースもよくあるんです。



「次回は達成するために何をするのか」を考えるべき時に、原因を突き詰めて、「これはこうじゃないと駄目、あれじゃないと駄目」とか、「これはやりたくない、あれはやりたくない」のようなことを言いながら改善策を出しています。



でも、そうすると、改善案としてはすごく平凡な施策が出来上がるんですよ。そしてほとんどの場合、そういう施策では改善されません。



なるほど。
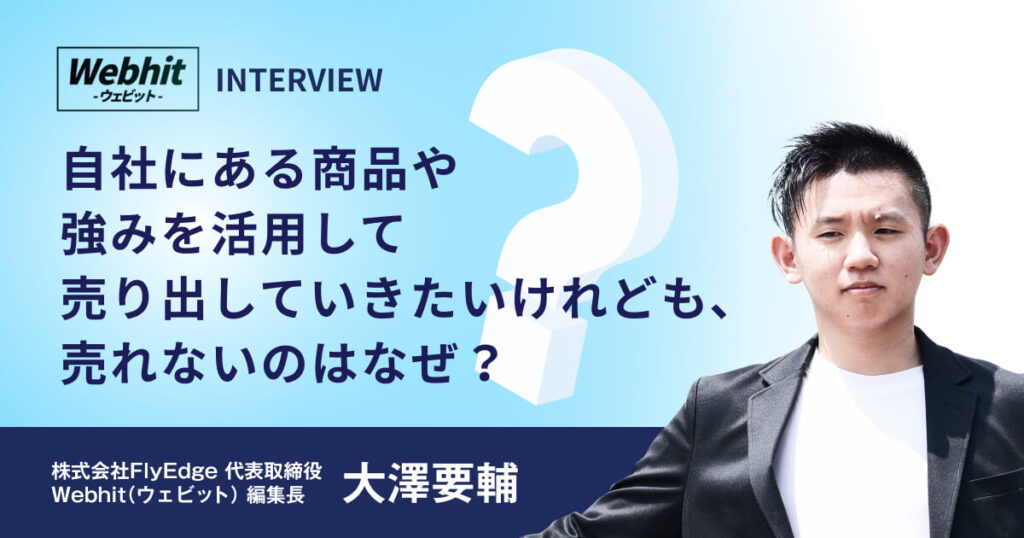
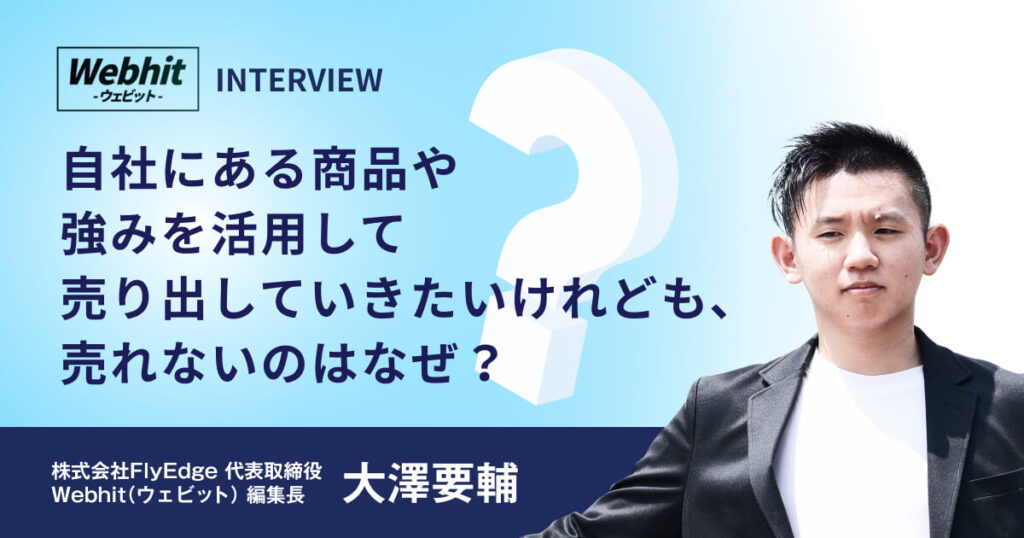
「楽しめないマーケティング」が失敗する理由



どうしてかというと、「これはできない」「あれはできない」と制約条件をたくさんつけたり、思い通りの数字が出なかったからと言って、中小企業の広報や営業の方が、担当者に対して「なんでできないんだ、なんで取れないんだ」みたいなことをゴリゴリ言っても、柔軟な発想は浮かばないからです。



「ああいうことにチャレンジをしてみよう」とか、「次はこういうことをテストしてみよう」、「こういう方法だったら取れるんじゃないか」のような、柔軟な発想になることはまずないんです。
これはすごくシンプルな、人間の真理だと思います。



よく、中小企業さんは間違って、担当者にプレッシャーとストレスをかけようとしてしまいます。プレッシャーやストレスをかければうまくいく改善策を出せるだろうと考えているからなのですが、100%出ないんですよね。



確かにプレッシャーがあると難しい気がします。



やっぱり、お客様が自ら選んでくれる状態を作っていくことがマーケティングなんです。



そう考えた時、先ほどお話ししたように、数字の原因がああだこうだというようなことを理詰めで話して、他の会社がすでに取り入れている普通の改善策が出てきても意味がないんです。



普通のことばかりを普通にやるだけではうまくいくわけがないんですよ。
その方法が成功するのは、一定の規模がある企業や、サービスに大きな強みがある企業などです。



いわゆるナショナルクライアントと呼ばれる大手企業や上場企業、誰もが知っている商品やサービスを扱う店舗や会社は、きちんとしたことをしっかりと行うことによってうまく行くケースがあります。



ただ、中小企業はそもそも商品力・サービス力が弱く、知られてもいないという中で、普通のことをやってもうまくいくわけがないんですよ。



その厳しい市場環境の中で勝てるようにするためには、いろいろなものをどんどん試さなくてはいけないし、柔軟な発想を持たなくてはいけない。



「これは一般的ではないかもしれないけれども、やってみたらうまく行くんじゃないか」ということを、次々に試していかなくてはいけないんです。



ちょっとうまく行かないからと言ってゴリゴリ詰めたりしたところで、柔軟な発想は出てこないので、絶対失敗するんですよ。



そうなると、マーケティングの組織が崩壊して、数字が改善されるどころか、数字がそもそも出せない組織が出来上がってしまいます。そうなるとまた「何でできないんだ」という悪いサイクルに入っていきます。



そのボトルネックは結局何なのかと言うと、マーケティングの施策を実際に実行したり、提案をしたりする立場の人間が、マーケティングを楽しめていないことが原因なんです。



楽しめる環境を準備できない中小企業の経営者さんなどが、いわゆるボトルネックになっているんです。



一番大切なのは、そういうところも楽しめるかどうかなんです。
最も成果を出しやすいのは楽しむことなのですが、従業員にストレスやプレッシャーを与える方法のほうが良いと勘違いしている企業さんがとても多いんですよね。



過去にお仕事でご一緒した中に、そういったマネジメントを実際に行っている会社さんがいて、弊社に対して「何でできないんだ」と言われたことがありました。



そうなると、人間とは面白いもので、提案内容がだんだん保守的になっていきます。「こうしたら反対されないだろう」というような思考になってしまうのが、人間なんですよね。



ですが、それではありふれた企画になってしまうので、何も尖ったところがないんですよね。尖りがない分、ノーとは言われないけれど、やはり「なかなか成果に繋がりにくくて……」という感じになります。



最終的には、そのようなお仕事の環境では弊社のパフォーマンスを十分に発揮できないので、こちらからお断りをしました。



そういった自分の実体験からも、構造的に整理をしても、楽しむことのできる会社さんが一番うまく行っていることがよく分かります。



実際に、Fly Edgeのクライアントでも、マーケティングを一緒になって楽しんでくださるクライアントは、どこもうまく行っていますし、逆にそうではないクライアントは伸び悩んでいるという事実もあります。



このようなことから、やはりマーケティングの成功の第一原則は「楽しむこと」だと思っております。
まずはマーケティングを始めること



「チャレンジしてみよう、何か普通とは違うことをやってみよう」という柔軟な発想になるために、経営者側や施策実行の担当者側にできることはどのようなことがありますか?



まず、経営者側にできることを一言で言えば、厳密に数字を見なければいけないような状況になる前に、マーケティングに手をつけることですね。



なるほど。



経営者にとって、数字は生死に関わることなので、とても大事にするんですよね。



それは当然なのですが、資金の状態が厳しい状態や、売り上げが苦しい状態になったりしてから、いきなりマーケティングを始めようとする会社があるんです。



そうなってしまうと、経営者は従業員に対して厳しく言わなくてはいけなくなります。その状態になってしまったら、時既に遅しなんです。



そうなる前のある程度余裕がある時に、マーケティングに関するテストや仕込みを先に進めて、着実な土台作りができていれば、そもそもあまり厳しく言う必要がないんですよ。



まずは厳しい状況、苦しい状況になる前にマーケティングに着手をすることが、経営者にできることとして挙げられますね。



その他に担当者がすべきことは、まずできるだけ成果を出すという前提を持つことなんです。もう一つは、マーケティングに正解がないという認識を持つことですね。



例えば、マーケティング界隈の人間はみんな、「広告運用は必ずこうするべきだ」とか、「Webサイトは必ず作らなければならない」、「SNSの運用は必ずこういうことをするべきだ」「バズらせなければならない」のようなことを、ポジショントークで言うんです。



けれども、それはあくまでその人が経験してきた業界や状況だったり、アカウントの目的だったりと、誰もが違う背景を持っている中で、一部の経験をもとに言っていることなんですよ。



なので、それが自分の会社に合うのかどうかを考えると、必ずしもイエスやノーの正解があるわけではないんです。



要は、「この会社がすごくうまく行っているから、必ずこの方法を取ればうまく行く」というわけではないということですね。



それを「これだけやれば絶対うまくいく!」と思ってしまうと、大コケするんですよね。



そうではなくて、はっきりとした正解がないので、いろいろなものを参考にしながら、「自分たちはこうしようかな」「これができるかな、あれができるかな」という角度で提案や実施をして、最大限楽しんでいただけると一番良いのかなと思います。
施策のアイディアが出ないときはどうする?



たくさんチャレンジして、最適な方法は何かをどんどん試していくということが大事だとわかりました。
初めて担当になった方は、施策数があまり出てこないのが悩みかなと思うのですが、どうしたらたくさんの施策が出るようになりますか?



まず一番良いのは、SNSとWebサイトとリアルの3つで、とにかくいろいろなコンテンツに触れ続けることですね。



僕はもう習慣にしていますが、例えばSNSだと、TikTokを開いている時に素で楽しむことは実はあまりありません。



TikTokって、スワイプしていくといろいろなものが出てくるのですが、似通ったフォーマットのコンテンツが多いんですよね。



そのなかで、音源だと今はこれがよく使われているなと思うものを保存しておいたり、メモしておいたりするんです。
そのうち、フォーマットや動画の構成が似ているものが増えてくると、今はこのフォーマットが見やすいと思われているのかなということをメモしています。



合間に広告も流れてくるので、この業種では、今はこういう広告の見せ方をしているんだな、これは使えるかもなといった感じで保存をしたりもしていますね。



例えば、Webサイトで自分の業種について調べてみると、いろいろなことが出てくるんですよ。自分たちの業種が住宅リフォームだとしたら、「住宅リフォーム」で検索すると、いろいろな住宅リフォーム会社が出てきますよね。



住宅リフォームそのものについての情報サイトや、会社の比較サイトなどでは、住宅リフォームに関するノウハウみたいなものを知ることができます。リフォームする時に気を付けるべきポイントについてのコラムなどもたくさんありますよ。



そういったものを見ると、住宅リフォームというものに対して、世の中は今このように認知をしていて、それに対してこういうコンテンツが出ているんだということが見えてくるんですよね。



なので、自分たちはそこに対して何を打ち出せるか、世の中のユーザーに対してどのように役に立つことができるかを考えることが大切です。



最後に、僕が電車に乗った時によくしていることとして、電車の中吊り広告をよく見るようにしています。



他には、電車の上の角や、出入口の両サイド、扉の上や取っ手の下、窓の下あたりにあるポールなどにも広告が付いているんですよ。その辺りの広告を見るのがいいかなと思います。



あとは、駅構内ならホームの向かい側が壁になっていて、その壁にはたいてい大きな広告がありますよね。また、駅の構内にもたくさんの看板広告がありますので、そういうものでもいいですね。



他にももちろんたくさんあります。ビルの上にある広告や、お店に展示されているもののレイアウトも参考になりますね。そういった世の中にあるさまざまなコンテンツを、リアルに触れて見ることが良いと思っています。



先ほどの電車の例で言うと、電車の自動ドアの上には細い広告が入っているんです。そして、ほとんどの場合、そこには転職や人材紹介、人材派遣など、人材系の広告が貼ってあるんですよね。



これはどうしてかというと、会社員の人などが満員電車に乗ると、もう何も見ることができなくて、唯一見えるのはドアのところにある駅名表示の電光掲示板のあたりなんです。



しかも、そのドアの近くは一番窮屈に押し込められるところなので、「こういう通勤は嫌だな」とか「仕事が面倒くさいな」と思うタイミングでその付近のスペースが目に入るんですよ。



そうなった時に、他の乗客の頭越しにギリギリ見えるのがその広告なので、「転職しようかな……」と思いやすいということがあります。



そういうふうに、広告の設置場所や、広告の表現方法の理由などを意識して考えると良いと思います。
広告ではなくても、例えばお店のレイアウトであれば、配置場所について考えてみるのもいいですね。



大体どこのスーパーでも、入口付近にあるのは野菜と果物なんですよね。どうしてかというと、それが置いてあることによって購買意欲を高めることができるからなんです。



そういうふうにちょっと考えながら、それが合っているか間違っているかは関係なく、「この店はこういうふうにしたくて、このような配置をしているんだろうな」ということを考えながら日々を過ごすというのが一番良いかなと思います。



これは、経験の有無に関係なく行うことができ、日々の意識づけや、アンテナを高くすることに役立ちます。



そういったアンテナを高めておくと、
「そういえば、あのスーパーはこういうふうにしていたな」とか、
「あのお店は、ここでこういう見せ方をしていたな、うちでも試してみよう」などと考えることができるので、日々の意識付けとして行えるといいですね。



ちなみに大澤さんにとって、マーケティングで一番楽しいことは何ですか?



一番楽しいことですか?全部楽しいんですけど、そうですね……。
一番楽しいのは、何かコンセプトを作っている時ですね。



コンセプトというのは、商品やサービスなどを世の中に出していく時に、「うちの商品サービスのコンセプトはこれです」と発信するものなんですよね。



人によって考え方が違うという前提はありますが、コンセプトについて一言で表すと、会社と世の中、社会との間で接点になるものなんですよ。



なので、コンセプトというものは、社会に対しても意味のあるものでなければいけないし、逆に自社にとっても意味のあるものでなければいけないんです。
ベン図で言うと、一部が重なった「AかつB」が存在する関係性ですね。



この位置がコンセプトを表す部分になるので、自社の方に偏りすぎてもいけないし、逆に社会の方に偏りすぎてもいけないんです。



ここで良いコンセプトが作れると、社会に認められるもの、かつ自社にとってもメリットがあるものが作れます。そういったコンセプトを作る過程が、僕は一番楽しいですね。


まとめ



最後に今日のまとめと、この記事を見てくださっている方に一言お願いします。



つらつらとお話ししましたが、結局マーケティングで一番大事なのは「楽しむこと」です。
「成果、成果」と言ったり、CPAやコンバージョン数のことばかりを言ったりすることも大事ですが、長々と言うことにはあまり意味がありません。



どちらかというと「次はどうしようね」とか、「これはまだ試していないよね、やってみようか」とか、「こういう方向性は考えたことがなかったよね」のように、次々と新しい企画を生み出していろいろなものをどんどん試すことが、特に中小企業におけるマーケティングでは非常に大切です。その過程を存分に楽しんでもらえたら良いと思います。
その過程でうまくいくものが出てくるので、成功したものに対して予算を大きく投入するという方法が一番うまくいくと思います。
マーケティングを今ひとつ楽しめていないという方や、「数字、数字……」という状態になっている方がいたら、ぜひ一度落ち着いて、楽しむことから始めていただけたら一番嬉しいなと思います。



ぜひ、マーケティング担当の方は参考にしていただければと思います!