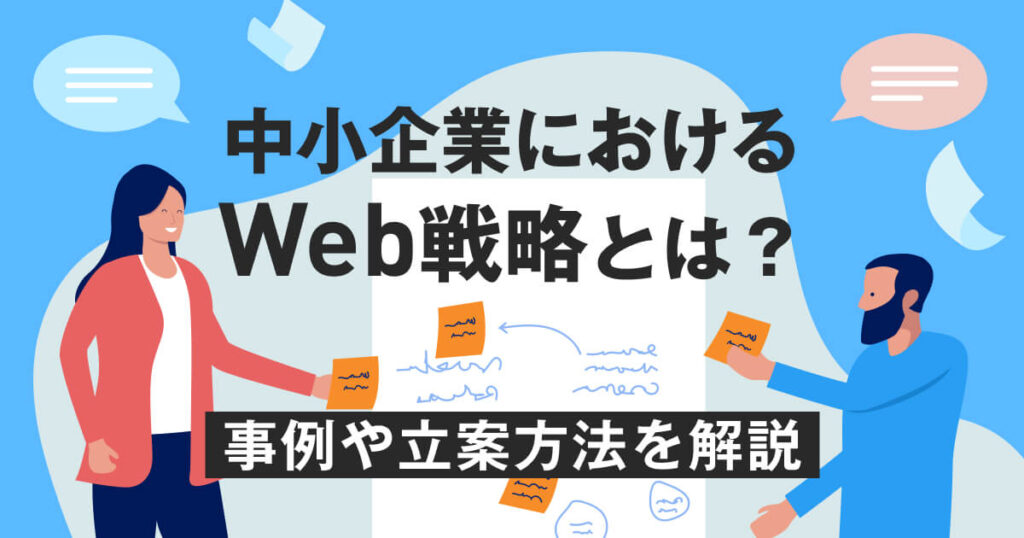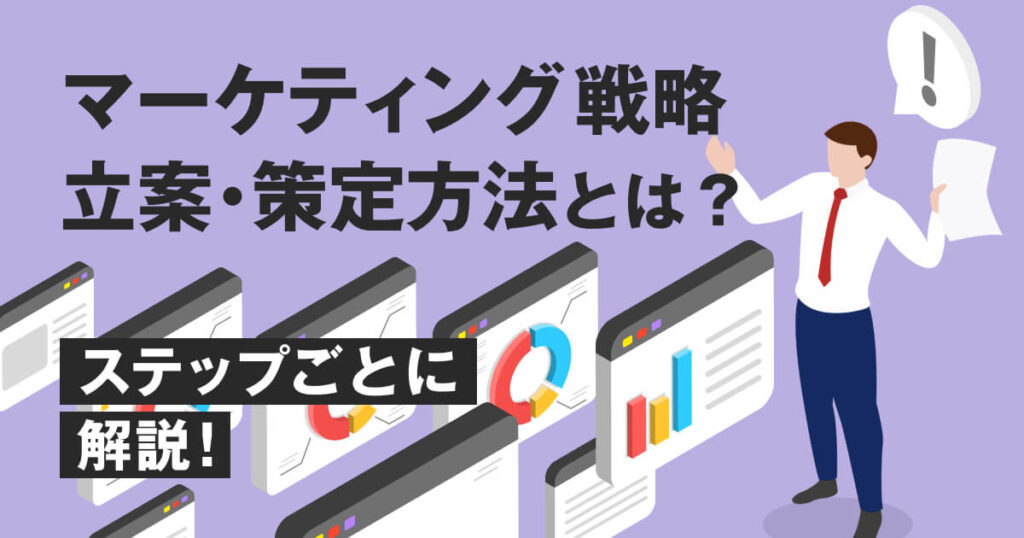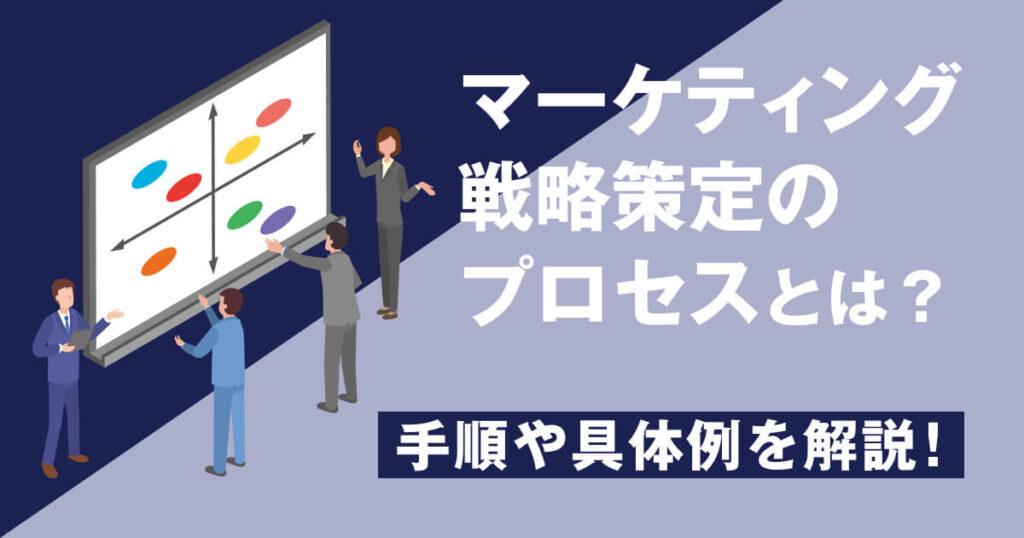「この商品、めっちゃ良かった!」
「〇〇を使い始めて人生が変わった!」
SNSやレビューサイトで、こんな投稿を見たことはありませんか?
でも、その投稿が実は企業から報酬をもらって書かれたものだったら?
近年、企業が広告であることを隠して宣伝する「ステルスマーケティング(ステマ)」が大きな問題となっています。
特に2023年10月からは景品表示法違反にもなり、違反企業には罰則が科される可能性があります。
- そもそもステルスマーケティングって何?
- どこからが違法になるの?
- 知らずにやってしまうリスクは?
そんな疑問に答えるため、本記事ではステルスマーケティングの定義・規制・具体的な事例・企業が取るべき対策を徹底解説します。
この記事を読めば、「知らずに違反してしまった…!」というリスクを回避し、正しいマーケティング戦略を立てられるようになります。
それでは早速、ステルスマーケティングの実態を見ていきましょう!
ステルスマーケティングの基本知識
ステルスマーケティングはステマと呼ばれており、広告であることを隠しながら事業者が商品・サービスを宣伝する手法です。あたかも自然な口コミや推薦であるかのように見せる手法であるため、消費者からは「騙された」という印象を抱かれやすい点が問題視されています。
なりすまし型と利益提供型
ステマの手法には主に2種類、「なりすまし型」と「利益提供型」があります。
なりすまし型は、事業者側が消費者のふりをして自分の商品・サービスを宣伝する手法です。SNSや口コミサイトに自社商品・サービスの肯定的なレビューを投稿し、あたかも一般消費者が実際に評価しているように見せかける特徴があります。
利益提供型は、芸能人やインフルエンサーに対価を提供し、広告であることを伏せた状態で宣伝してもらう手法です。SNSの普及に伴い多く見られるようになっており、消費者に信頼性が高い情報として受け取られやすいため、購入意欲を高める効果が期待できます。
アフィリエイトはステマにならない
ステマとアフィリエイトの違いは、広告であることを消費者へ明確に示しているかどうかです。ステマは、広告である旨を伏せて行われる商品・サービスの宣伝手法です。一方、アフィリエイトは、広告であることを明記した上で紹介する仕組みで、消費者が商品を購入した際に報酬を得ます。
なお、アフィリエイトであっても広告である旨を隠したり、自主的な意見や口コミのように装ったりした場合には、ステマ規制に抵触する可能性がある点には注意が必要です。
問題点と2023年からの法規制
ステマは、消費者が商品・サービスを適切に評価できなくなってしまう点で問題視されています。広告であることが明らかな場合、消費者はある程度の誇張が含まれることを前提に情報を受け取るため、後々トラブルになることは少ないでしょう。
しかしステマでは、消費者が広告であることを認識しづらいため、実際よりも良い印象を抱いてしまう可能性があります。このように、消費者に対して印象操作できてしまうため、2023年10月1日よりステマは不当表示として規制されるようになりました。

ステルスマーケティングに対する法規制
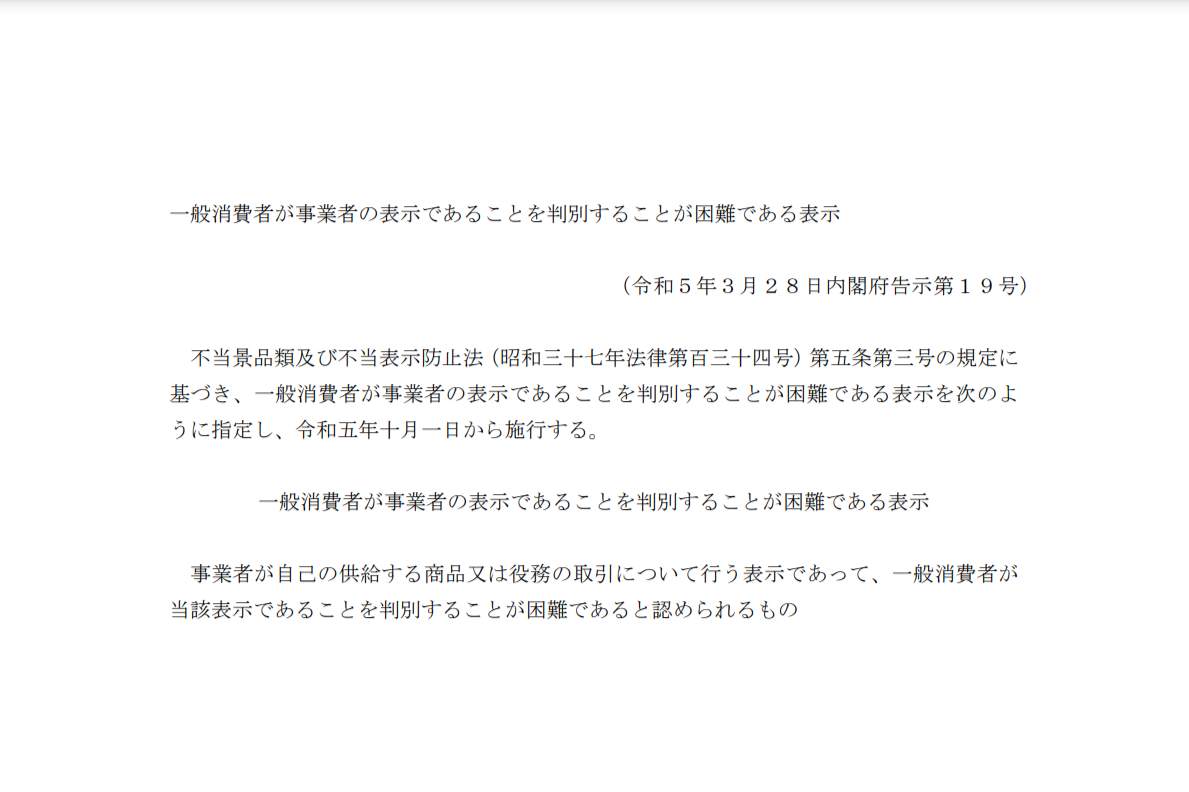
引用:消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」
2023年3月28日に、内閣府がステマの規制に関する告示を発表しました。これは、広告であることを認識しにくい宣伝活動を禁止し、消費者の誤解を招く可能性がある不当表示を取り締まる目的で制定されたものです。
以下で規制対象となる条件や違反した際の罰則を解説します。自身が実施している宣伝活動が規制対象となっていないか確認しましょう。
規制対象となる条件
規制対象となるのは商品やサービスを提供する広告主で、実際に宣伝する人は含まれません。
ただし、広告主の指示のもとで行われた投稿は「事業者の表示」とみなされるため、実際に宣伝する人であっても広告である旨を明記しなかった場合は規制対象となります。
例えば、ハンドメイド作家が自らの作品をSNSなどで紹介するだけなら問題ありません。しかし、宣伝である旨を明記せずに事業者の指示に沿った内容を投稿した場合は、ステマに該当する可能性があるため注意が必要です。
違反した際の罰則
ステマ規制に違反すると、景品表示法7条に基づき消費者庁から措置命令が出されます。違反した事業者は社名の公表などのペナルティが科され、宣伝活動の撤回・不当表示広告類の削除・再発防止策の実施といった対応を行わなければなりません。
なお、措置命令に従わない場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。ステマが発覚した際は、罰則だけでなくブランドイメージの低下や、顧客からの信頼喪失といったリスクも生じるため、規制を遵守した宣伝活動が必要です。
問題視されつつもステマがなくならない3つの理由
問題視されつつもステマがなくならないのは、次の3つの効果が期待できるためです。
- 費用対効果が高い
- 消費者の信頼を得やすい
- 広告だと気づかれにくい
それぞれ以下で詳しく解説します。
費用対効果が高く低コストで広告できる
ステマは一般的な広告費用と比較して、コストを抑えた宣伝が可能です。商品・サービスに関する知識が豊富な企業関係者が第三者を装って口コミやレビューを投稿すれば、低コストで効果的に宣伝できます。
また、高評価の口コミにより消費者の注目を集められるため、長期的な宣伝効果も期待できるでしょう。企画やアイデアを出して一から広告を打ち出すよりも費用対効果が高いため、ステマと知りつつも取り入れる企業もいるようです。
消費者の信頼を得やすく影響力が強い
ステマは宣伝している印象が薄いため、消費者に信頼されやすい点がメリットです。一般的な広告は、消費者から懐疑的な印象を抱かれたり、そもそも興味を持ってもらえなかったりします。
一方、ステマでは第三者が口コミやレビューを投稿するため宣伝と認識されにくく、消費者から好意的に受け入れてもらえる可能性が高いでしょう。
ステマには広告への警戒心を回避し、消費者の意見や行動に対して効果的に影響を与えることが期待できます。したがって、SNSを頻繁に利用する若者層へのアプローチとして効果的です。
広告だと気づかれにくい
インフルエンサーによる宣伝は広告だと気づかれにくい点も、ステマがなくならない理由の一つです。消費者は広告だとわかると見るのをやめてしまうことがありますが、好きなインフルエンサーの紹介なら購買につながる可能性が高まります。
インフルエンサーを起用した施策自体は問題ありませんが、規制に抵触しないよう注意する必要があるでしょう。

企業がステマを行うリスクとは?マーケティング担当者が知るべき注意点
ステマをマーケティング施策に取り入れるリスクは、次の3つです。
- 消費者からの信頼を失う
- 炎上リスクが高い
- 取り締まりを受ける可能性がある
それぞれのリスクについて、以下で詳しく解説します。
消費者からの信頼を失う
ステマが発覚すると、消費者からの信頼を失ってしまいます。消費者に不信感を抱かせることは、ステマで販売した商品だけでなく自社商品すべての売上を落としてしまう可能性もあります。
また、リピート顧客の減少や潜在顧客の喪失にもつながる恐れもあるでしょう。一度失った信頼を取り戻すのは困難なため、ビジネス成長に対して長期的な悪影響をおよぼす可能性もあります。
炎上リスクが高い
ステマが発覚した場合、炎上するリスクが高い点には注意が必要です。ステマは消費者を騙す行為であり、インターネット上ではそのような行為を許さない風潮にあるため、企業や関係者が批判の対象となります。
その結果、ユーザーに事実が掘り下げられて企業名や一連の出来事が拡散されます。一度拡散された情報はインターネット上で残り続けるため、企業名などで検索すれば誰でも認知でき、ビジネス成長に対し長期的な悪影響をおよぼしかねません。
また、商品自体は変わっていなかったとしても、炎上前後で売上が大きく変わってしまう可能性もあります。そのため、炎上しないよう防止するのはもちろん、炎上時の対応や対策も重要です。
取り締まりを受ける可能性がある
ステマ規制に違反した場合、違法行為だとして取り締まりを受ける可能性があります。不当表示に当てはまるものは下表の通りです。
| 優良誤認表示 | 商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際より著しく優良であると消費者に誤認される表示 |
| 有利誤認表示 | 商品やサービスの価格などの取引条件について、実際より著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 |
| その他 | 無果汁の清涼飲料水やおとり広告など、一般消費者に誤認されるおそれがある表示 |
宣伝時には、どのような表示が違反対象となるか把握することが重要です。
ステマを防ぐための3つの対策
ステマを防ぐために実施できる対策は次の3つです。
- 一目で広告だとわかる表示をする
- 誇張表現や虚偽の情報を使用しない
- 第三者との関係性を明記する
ステマ対策を未実施の方は、以下で解説する対策を取り入れるとよいでしょう。
一目で広告だとわかる表示をする
一目見ただけで、消費者が広告だと理解できるような表示をすることが重要です。
消費者が事業者の表示だと判断することが困難な場合、ステマ規制に抵触します。
あいまいな表現であったり、広告である旨を小さく記載したりといった隠微(いんび)な表示ではなく、明瞭な方法で広告表示することが必要です。よくあるSNSの投稿であれば、ハッシュタグを活用すると効果的でしょう。
誇張表現や虚偽の情報を使用しない
消費者の注目を集めるために、誇張表現や虚偽の情報を発信するのは避けましょう。
誇張表現や虚偽の情報は、消費者が商品・サービスに関する正確な情報を得られなくなってしまいます。アンケートやモニタリングなどを活用して実際の顧客の声を集め、正しい情報を発信すれば、ステマ規制に抵触せずに消費者の信頼獲得が可能です。
また、インフルエンサーが「いいね」や視聴回数、フォロワー数を水増しする行為も問題視され始めています。企業・インフルエンサーともに、消費者が誤認しないよう、表現方法に注意して発信することが重要です。
第三者との関係性を明記する
広告である旨だけでなく、事業者と第三者との関係性に関しても明示することが重要です。
例えばインフルエンサーを活用した宣伝では、「#PR」という表記が使われることも多いです。
第三者に対して明確な宣伝依頼をしていなかったとしても、投稿の内容を総合的に判断した際に企業との関係が疑われると、ステマ規制に違反する恐れがあります。そのため、広告主と第三者との関係性が消費者にわかるような表現を使用し、透明性の高い宣伝を行うとよいでしょう。

ステルスマーケティングが問題となった実例
ステルスマーケティングが原因で炎上に発展した実例を紹介します。これらの事例を通じて、現在行っているマーケティング活動がステマに該当しないかどうか参考にしてください。
ペニーオークション|芸能人による虚偽の宣伝
日本のステマ事例で有名なものとして、ペニーオークション事件が挙げられます。ペニーオークションは入札ごとに手数料が発生し、運営会社が入札しても落札できない仕組みです。その仕組みを悪用して、運営会社が入札を繰り返し価格を不当に吊り上げていたことが問題視されました。
また、運営企業は複数の著名人に対して「高額商品を安価で落札できた」とブログ投稿を依頼し、実際に利用しているかのように宣伝しました。その結果、運営企業は詐欺罪で検挙され、宣伝に加担した芸能人も世間から批判を浴び、芸能活動の自粛や休止に追い込まれる事態となっています。
映画「アナと雪の女王2」|SNS投稿によるステマ告知
ディズニー映画「アナと雪の女王2」の宣伝におけるSNS投稿が、ステマとして炎上した実例です。同じ日に複数人のインフルエンサーが当時のTwitter(現:X)へ映画の感想を漫画で投稿したことに対し、多くのユーザーが不審に思ったことからステマ疑惑が生じました。
その結果、インフルエンサーが企業から依頼されて投稿したことを認めて炎上し、最終的にはディズニーが謝罪する騒ぎにまで発展しました。
テレビ局アナウンサー|SNS投稿のステマ疑惑
テレビ局アナウンサーが行ったとされるステマ疑惑の実例です。女性アナウンサー複数名が有名美容院で無料施術を受け、その対価として施術後の写真をSNSに投稿したことが発端です。また、その美容院のSNSに広告として登場したため、ステマの疑惑が持ちあがりました。
アナウンサーの所属テレビ局は「ステマには該当しない」と主張しましたが、世間からは「ステマでなかったとしても倫理的に問題である」と多くの批判が集まる事態となりました。
まとめ
ステルスマーケティングは、企業やインフルエンサーにとって手軽で効果的に見える手法かもしれません。
しかし、その裏には、消費者の信頼を損ねるリスクや、法規制による厳しいペナルティが潜んでいます。特に2023年10月以降、景品表示法の規制が強化され、違反した場合の影響は決して軽くありません。
過去の事例を見ても、ステルスマーケティングが発覚したことでブランドイメージが大きく損なわれたケースは数多くあります。一時的な売上や認知向上のために消費者を欺く手法は、長期的には企業の成長を妨げる要因になりかねません。
だからこそ、広告は透明性を持ち、消費者と正直に向き合う姿勢が求められます。
マーケティングの本質は、顧客との信頼関係を築き、価値を提供することにあります。短期的な成功にとらわれるのではなく、長期的なブランドの信用を大切にする視点を持つことが、これからの時代に求められるマーケティングの在り方ではないでしょうか。
今後も市場の変化に応じて規制は厳しくなり、消費者の目もより一層シビアになっていくでしょう。だからこそ、私たちマーケターは、正しい情報を届け、信頼されるマーケティングを実践していくことが大切です。この記事が、ステルスマーケティングに対する理解を深め、適切なマーケティング戦略を考える一助になれば幸いです。
ウェビットでは主に中小企業がWebマーケティング、Web集客を行ううえでのお悩みを解決するような情報を発信しております。気になられた方はぜひ、ほかの記事もご一読ください。